2010年01月の記事
全70件 (70件中 1-50件目)
-
無縁社会 ~”無縁死” 3万2千人の衝撃~
最初、テレビ番組欄で見た時、よくわからなかった。”無縁死”3万2千人と見て、自殺者を浮かべていた。人数的にも、ほぼ同じ数でもあったからだろう。そして、番組を観た。哀しかったし、切なかった。この国は、いったいどうなってしまったのだろうかと。生涯未婚と言う言葉も初めて知ったし、今後増えていくであろうその割合にも驚いた。男性が3人に1人、女性が4人に1人だと。会社が総てであるような生き方にも、考え直すべき点はたくさんあるのだと思う。幸いにも、今の自分にはネットワークがたくさんある。もちろん、意図して増やしているということもあるが、やはり生まれ育った環境もあるのかもしれない。この番組の中ででてきた地方のうち2ケ所に縁があるので、よけいに思いいれが強くなる。生まれそして暮らしている富山県、そして学生時代を過ごした新潟県。今の自分にできること・・・いろいろあると思う。
2010.01.31
コメント(4)
-

【生きなおす力】柳田邦男著
出だしの1章は、ちょっと気が滅入りそうだった。産院での乳幼児にミルクを与えるお母さん方の光景。我が子を見ないで、ケイタイばかり見て操作している一団。異様だと思う。生きなおす力は、ひとにはあると思う。しかし、確実に退化していっているのかも。装丁の写真を見て、かつて、自分の目でみた彦左衛門という大きなブナを思い出した。大人3,4人でやっと取り囲める大きさ。生命力を感じた。そんなふうにいきたい---------------------------------全国に、30ないうち3軒があります。(和ろうそく)(おかざき匠の会)
2010.01.31
コメント(0)
-

【サイレントボーイ】ロイス・ローリー著
切ない。最後がこれに尽きる。帯に書かれてもいるが、正しいこと、美しいこととはの意味を考えさせられる。サイレントボーイ。サイレント。沈黙・・・いや、実はとても雄弁であるのかなと思った。それは、こちら側の問題で、感じ取れる感性があるのかないのかなのかもしれない。ここ数年、自分の身の回りを考えてみても、とても煩いし騒々しいし、相手や周囲のことを考えていないのではと思う場面がやたらと多くなってきている。一時期はやったジコチューどころではない。周囲に気を配るという感性がないのだろう。人は時々、サイレントになるべき時があるのではないだろうか。
2010.01.30
コメント(2)
-

筑紫さんが選んだ絵本 その1
今朝、読み終えた筑紫哲也さんの本【この「くに」の面影】。その中で、筑紫さんが気に入っている絵本ということで5冊あげられていた。うち、3冊、早速図書館で借りてきて読んだ。 どれも素晴らしい絵本。個人的には、この3冊の中では”よあけ”が一番好き。山歩きをしていた頃の、朝日が昇る一瞬を思い出した。言葉も何も無くて、ただ、見つめるだけ。受けた衝撃の大きさは”アンジュール”が一番。言葉が全く無い、デッサン画だけで、伝わることの何と大きなことか。ほのぼの感は”ルリユールおじさん”が一番。残りの2冊は、後日だ。
2010.01.30
コメント(4)
-

雪の下でも
もう、ほとんど雪がとけたなんか、畑は土竜の跡だらけのような・・・まあ、それはそれとして、雪を掘らなくても野菜がとれる。ただ、葉ものはほとんど無い(ミズナくらいかな)。2010/01/30 収穫 posted by (C)けんとまんそれでも、大蕪と小蕪、赤大根が少しはあった。大根もあるのだが、なんか齧られたようなのがやたらあって、ちょっと残念。でもまあ、雪の下でも野菜たちは頑張っている。玉葱とキャベツ、エンドウマメは冬を越してくれそうで、春になってからの成長が楽しみだ
2010.01.30
コメント(4)
-

【この「くに」の面影】筑紫哲也著
これまで、何度も書いてきたが、運営スタッフをしている森のゆめ市民大学の学長でもある、筑紫哲也さん。もう亡くなられて1年以上たってしまった。そんな筑紫さんに関する本が、ポツポツと出版されている。これもその中の1冊。筑紫さんのこれまでの評論や多事争論の内容などがおさめられていて、読み返すことで、あらためて筑紫さんの凄さを感じた。そのカバーする範囲の広さはもちろん、その視点の確かさだと思う。自分お立ち位置をどこに置くのかこの国を次の世代に渡すためには・・・というのが基本にあるのだと思っている。また、ものの考え方は別として、交友範囲の広さもある。政治的な主張は違っても、お互いに認め合う度量があるかないかだ。さて、つくづく感じたこと。それは、自分の五感・六感を使って、ものごとを見るように努力することだ。もちろん、そんな生易しいものではないが、これからの時代、ますますそれが必要になるのだと思う。ある意味では哀しい・切ないことでもある。しかし、それは今を生きる者のつとめではないかと思う。これを読みながら、筑紫さんの声が聞こえるように思った。市民大学の縁で、何度も、その近くで存在そのものを感じたり、声を聞いたりしたことは、今の自分の大きな財産になっている。-----------------------------------毎年、600万人の子どもが、栄養失調で亡くなっています。(特定非営利活動法人 国境なき医師団日本)
2010.01.30
コメント(4)
-
100号
夜、PTAの広報委員会の編集ミーテイングへ。今日は出稿の日。通算100号という記念すべき号になる今回は、原稿も書いた全8ページの担当毎に、順番にテキパキと印刷屋さんと打合せ。まあまあのできになりそうだ。ここに至るまでは、しんどいこともあったように思うが、やはり、全体として形が見えてくると、やりがいもぐ~んとアップする。何となく、皆さん、やり終えたという安堵感もあるようだ。あとは、校正を残すのみ。楽しみがまた一つ----------------------------------世界では毎年、日本の国土の3分の1の森林が失われています。(特定非営利活動法人 地球緑化センター)
2010.01.29
コメント(0)
-
次期
もう1月も終わる。PTAの次期役員も、だいぶん固まってきたので、ほっと一息。14人前後が執行部の枠組み。キーとなるポジションはそのうち数名分。ほとんど、役目としては変らないのだが、体外的なイメージもあり、それに拘る方もある。おそらく、大抵のPTAがそうなのだと思うが、執行部役員は、人伝手でお願いをし、やってきている。今度は、そのやり方を大きく変えようとしていて、昨年の総会で前振りをしておいた。その点も含め、4月の総会の決議事項となる。その点のアナウンスや、持っていきかたはよく考えないといけない。まだ、今年度は終わっていないが、事務局としていくばくかの役目を果たしてきたと思う。次期も事務局の予定(2年が1サイクルという暗黙の了解がある)。事務局としての役割も、これまで以上に重くなる予定。通常、一般的に言われている事務局としての役割に近くなっていく。いろいろ思いはあるので、形にしていきたい。------------------------------Be Prepared=そなえよつねに。(社団法人 ガールスカウト日本連盟)
2010.01.28
コメント(4)
-

【働く幸せ】大山泰弘著
働く幸せ、働くことができる幸せと言ったほうがいいのかもしれない。サラリーマンでありながら、田圃や畑も少しやっていて、幸せというか充実感は、どちらかというと田圃や畑をしているときの方が大きい。無心になれる時が多いからかもしれない。何も考えずに、ただ土と対している時なんだと思う。それにしても、著者の大山さんが会長をされている日本理化学工業は素晴らしい会社だ。作っているものも、チョークとかパスとか、お馴染みのものばかり。しかも、優れものであるから、これ以上の言葉もない。作っているものも凄いし、従業員の方たちも凄い。俗に知的障害者といわれるかたたちが、半数以上であるということだけでなく、そんな方たちのエネルギーを感じる。だからこそ、すばらしい製品になるのではないか。最近の派遣切りではないが、モノにヒトを合わせるのではなく、ヒトにモノの作り方をあわせるために工夫する。これこそ、経営者の鑑だと思う。あらためて、純粋に汗すること、働くことを考え直した。
2010.01.27
コメント(10)
-

【人生夢物語】嶋崎研一著
夢。『こんな夢がある』という言い方。『まるで夢のようだった』という言い方。時間軸で考えると、ちょうど反対の言い方なのかなと思う。著者の嶋崎さんの本を読んだことがきっかけで、この本をいただくことになった。人のつながり・善意というものを、基本的には信じている自分にとって、「そういう方々もいらっしゃるんだ」という思いと、いろんなことにはタイミングというものもあるんだなと再認識することになった。昨年、息子の通う中学校で開催した「草刈り十字軍の映画鑑賞と講演」でも、そういうったことがあった。縁(えん)。そんな字も思い浮かぶ。しかも、名字という点でも何かあるかもしれない。-----------------------------------アイヌ語の地名には、当時の暮らしが反映されています。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2010.01.27
コメント(2)
-
修業は一生、終わらない
毎度、楽しみにしているプロフェッショナル。そのアンコール放送。小野二郎さん、鮨職人。ミシュラン云々ということがあったが、そんなことは関係ない前回の放送も観たが、今回も見入ってしまった。不器用だからこそ・・・・というのが、一番印象に残っている。不器用だからこそ、他人の何倍も考える。そして努力。将棋の羽生さんのことを思い出した。「努力し続けることが一番の能力」だと。小野さんもまさにそうだと思う。そして、一流は一流を知る。ロブションさんのコメントが良かった「二郎さんの鮨の清らかさが好きだ」。あと、道具は自分で作っていることも。----------------------------------冬のキュウリ、なんかヘンだと感じませんか。(エコプラットフォーム東海)
2010.01.26
コメント(2)
-
願書
今日から国公立大学の入学願書の受付が始まったとニュースで流れていた。夜、おねえが願書を持ってきた。前期志望と後期志望の2組。先生との相談も終り、前期・後期とも志望する大学・学部も決まった。前期は、本来の第一志望校となった。必要事項を記載し、明日、入学試験の受験料を払い込み、そのうえで先生にチェックをしていただいてから、郵送する。いよいよだ。前期も後期も、そんなに甘くない大学。後期は、まあまあセンター試験の結果からみると、幾分合格しやすい。もちろん、それでも油断はできない。おねえ自身も、第一志望に合格することだけを目指して頑張ってきたし、あと1ケ月頑張るだろう。少しずつだが、そんな空気になってきた。が、できるだけ、コレまでどおりの感じでいるようにしたいものだ。
2010.01.25
コメント(4)
-
お年玉
すっかり忘れていたが、お年玉年賀はがきの当選番号が発表された。結果・・・4等の切手シートが6枚当たり4等は50枚に1枚当選の確率。6枚の内訳は、5枚が私宛、1枚がママ宛。確率は、私が15枚に1枚、ママが50枚に1枚くらいの確率になる。そう、何故だというくらいに、末尾が「00」のはがきが多かった。切手シートとはいえ、これだけの確率で当たると、素直に嬉しい数年前は、切手シート1組すら当選しない年もあったくらい。う~ん、これは、今年は何かいいことがある予兆なのかなあ~-------------------------------お寺に続く道の地雷を、まず最初に取り除いてください。(地雷廃絶日本キャンペーン)
2010.01.25
コメント(4)
-

【ギヴァー】ロイス・ローリー著
遂に、新訳で読んだ。ある程度は、旧訳で読んだことも覚えてはいたが、かなり受ける印象が違った。やはり、今に近い分だけ、文章もスッと響いてくる。これだけ、翻訳のしかたで味わいが違うものかと驚いた。苦痛も何もないと思われる理想郷が舞台となる近未来。果たして、そうなんだろうか。すべてが筋書きのとおりに、時間が過ぎていく。まるで、モノトーンの世界。そんな象徴の一つとして、色がでてきているのかもしれない。色が無い世界。想像するだけでも哀しい。人として存在する意義はどこにあるのか。そんなことも考えた。私もメンバーの『ギヴァー』を全国の読者に届ける会はコチラから
2010.01.24
コメント(0)
-
○(丸)付け
中学生になっても、なかなか勉強する癖がつかない息子。宿題もやっとこさ。試験の前も、ちょっとだけ・・・・・で、昨日、おねえが大学受験のための問題集が欲しいということもあったので、親子4人で本屋へ女チームと男チームにわかれ、問題集をあれこれと。「厚いのはやる気にならん」と、以前から言っていた息子だったので、薄いのでいいから毎日やる習慣をと思い、薄いのでいいよと。結局、息子が選んだのは数学と英語の10分間ドリル。1ページ10分のもの。毎日、両方を1ページ以上するということで、夕べからスタート。○つけは、やっていないということなので、私がやることにした。で、今日の分と合わせて、2日分(計12ページ)を○つけ。1年生の最初なので簡単でもあり、この2日間は英語と数学を3ページすつやった息子。○つけをして、息子に返した。やはり、いつもの癖がでていた。これを、これからずっと続けることとした。私の思いは、国語と数学をキッチリとやることが大切だということと、その次に英語かなということ。国語がキッチリできないと、文章自体の理解もできないと思う。そして、数学。やはり、基本的な計算間違いは、いろんなところに影響する。さてさて、息子との根競べだな
2010.01.24
コメント(6)
-

【若き友人たちへ】筑紫哲也著
筑紫さんが亡くなられて1年半近くになってしまった。そんな筑紫さんが、早稲田・立命館の大学院での講義録が中心となっている。口語調なので、とても読みやすいし、筑紫さんの声が聞こえてきそうでもある。柔らかい口調で、厳しいことを話される筑紫さんを思い出す。スタッフをやっている森のゆめ市民大学も、筑紫さんがいたからこそできたものでもある。この本を読んで、改めて筑紫さんのそのカバーする範囲の広さと、その陰での努力を知ってさらに驚いたことがたくさんあった。ごく身近なところで、何度か、その薫陶を受けたことを思い出し、まだまだこれからだと思ったし、この国を考え続けることが自分たちの役目であると思う。---------------------------------絵が好きな人は、絵を描きましょう。書が好きな人は、書を書きましょう。(財団法人 たんぽぽの家)
2010.01.24
コメント(0)
-

【「教える技術」養成講座】遠山法子著
サラサラっと読んでしまった。ファシリテーションのスキルと同じことも多い。基本は、自分の立ち位置をどこにおくか。多少は、人前で話したり、講師をしたりするので、ここに書いてあることは理解できえうし、多少はこころがけている。ただ、自分の周囲を見回すと、その反対の人が多いような・・・
2010.01.23
コメント(0)
-

【すき・やき】楊逸著
一つの青春ストーリーなのかなと思った。読んでいるうちに、なんとなく、主人公をほのぼのと応援したくもなってくる。主人公と韓国人同級生との会話もなんとなく微笑ましい感じもする。ちょっと不思議な日本語の会話が、かえって、その登場人物像をくっきりと浮かび上がらせてくれる。その日本での生活の象徴として『すきやき』があるのかなと思ったのだが、タイトルが『すき・やき』と点が入っているのは何故だろう。もしかして、『すき』&『やき』と『すきやき』をかけているのかも。
2010.01.23
コメント(2)
-

野菜の掘り出し
雪もだいぶんとけたので・・・長靴を履いて畑へ。予想以上にとけてた。2010/01/23 01 畑 posted by (C)けんとまんで、大根を・・・60センチは軽くあって、巨大に。2010/01/23 02 大根 posted by (C)けんとまんついでに、大蕪と赤大根とミズナも掘り出した。2010/01/23 03 大蕪、赤大根、ミズナ posted by (C)けんとまんそして、ホウレンソウにもトライ。2010/01/23 04 ホウレンソウ posted by (C)けんとまんやっぱり、自家製の野菜が食卓に並ぶとホッとするなあ~----------------------------------6700万人の先住民族が、森林で暮らしています。(特定非営利活動法人 ソムニード)
2010.01.23
コメント(4)
-
森のゆめ市民大学 運営委員会
夜7時から、新川学びの森天神山交流館で、森のゆめ市民大学のスタッフミーテイング。最終講座と、次期講師についてがテーマ。最終講座は、いかにして受講生を参加型にもっていくか。ある程度の結論がでたので、次期講師について。現在、決まっている方。5月に菅原文太さん。昨年、農業法人を設立し、農業に取り組んでいらっしゃるとのこと。ただ、これはかなり前からの様だ。7月に木村秋則さん。かなりメジャーになってしまったリンゴですね。11月に古謝美佐子さんと大工哲弘さんのコンサート。故筑紫哲也学長の3回忌にあわせて。時期未定で佐藤初女さん。おにぎり、イスキアで有名な、初女さん。他は、現在交渉中。さてさて、市民大学も9期目を迎える。次期にむけて、ちょっとがんばらねばいかんなあ~------------------------------------アイヌ民族が育んできた文化の一つに、口頭文芸があります。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2010.01.22
コメント(4)
-
”助けてと言えない” ~共鳴する30代~
悲鳴に似たタイトルだと思った。NHKのクローズアップ現代を見た。一向に改善されない、今のこの国(だけではない)の雇用状況。そんな中での30代。番組の中に登場された方の言い分もわかるような気がする。『助けて』といわずに、自分でなんとかしようとしてしまう年代でもあると思う。自分は幸いなことに、定職にもついているし、生活もできている。自分自身はとても弱い人間だと思っている。一人でできることは高が知れている。家族が、知人がいるからこそ、いろんなこともできるし、させてもらっている。いわゆる『おたがいさま』の気持ち。そんな中で、中継出演されていた奥田知志さんの言葉が、一番印象に残っている。『自己責任論は、その人への援助・関わりを切り捨てるための言葉だ』納得した。
2010.01.21
コメント(0)
-
5時間
午後は、経営者研修フォローアップ研修会の講師を担当した。正味4時間。前後もいれて5時間、立ったままで、やはり、いつもと違う疲れはある。田圃や畑で5時間立っているのと違い、何となく疲れが残る。もちろん、研修の合間には適宜休憩は取るのだが、その間もなんのかんのと椅子に座ることは少ない(今回はゼロ)。参加者数や、参加された方の受講状況とかもあり、当初の予定の3分の2くらいで内容をおさえた。振り返りのやり方を演習で体感してもらうことが主眼で、あとは以前にたてた計画などを見返していただければ、当初の狙いとしてはクリアできる。今回も、これまで自分で持っていたネタをベースにしてもやはり3日間くらいの準備時間はかかった。とにかく、これで一段落。精神的にも、ちょっとだけ、ほっとできる。研修講師は、精神的なエネルギーがかなり必要だ。しかし、そのための準備が自分の勉強にもなるので、前向きにチャレンジしていきたいなあ~と思う----------------------------------サンスクリット語で平和と静寂を意味します。(社団法人 シャンティ国際ボランティア会)
2010.01.21
コメント(0)
-
わたしをよんでください (NHK福祉ネットワーク)
「わたしをよんでください」人が本となって読まれる。読まれるというよりは、語りかけてくれることを聴くということ。リビング・ライブラリー。そんな取組があるのかと驚いた。ただ、まだ始まってそんなに間が無いとのことだが、貴重な取組だと思う。本にとっても、読者にとっても。取り上げられていた例を見ていても、そこには「血が通っている」という思いがした。語ることで、自分を整理し表現することができる。それを聴くこと、対話することで、自分の誤解を解き新しいものが発見できる。もちろん、読み手のスタンスも重要だろう。ただ、そこには、お互い素直な気持ちだけは必要だろうと思う。それによって、少しずつだが、社会にうちとけていくのではないだろうか。紹介されていたサイトはコチラから--------------------------------いい土は軽くてフカフカ、いい匂いがします。(財団法人 オイスカ)
2010.01.20
コメント(0)
-

【ファシリテーター養成講座】森時彦著
今、ファシリテーターの勉強を少しずつやっているし、このテーマで研修講師もやらないといけない。知人から借りている本の1冊なのだが、養成講座と銘打っているだけあって、わかりやすい。しかし、実践する、実践し続けるとなると難しいものはあるだろう。ただ、やらないことには始まらないし、それがファシリテーションの一環でもある。基本的に、会議を念頭においてみると、会議のデザインをし、進行のプロセスに注力して実りのあるものにする。基本は、合意形成を目標とする。もちろん、会議だえではなく、いろんな場面で活かせるんだろうなあ。もちろん、メンバーの参加度合いの均一化とか、モレを防ぐ観点とか、いろんな手法を駆使しながらになるが、基本にあるのは人を思いやることかなと思っている。研修用のテキストを作りながら、これも参考になると思っている。
2010.01.19
コメント(2)
-
「ジャズシンガー・綾戸智恵 母との歩み」(福祉ネットワーク)
NHK教育テレビの福祉ネットワーク。時々見ることがある。今回は偶然チャンネルを回したら、綾戸智恵さんがでていたので、見た。綾戸さんが、お母さんの介護をやっていらっしゃるのは、知っていた。途中のギリギリの精神・肉体状況のことは、なかなか想像がつかないのだが、周囲の人たちのサポートもあったのだろう。音楽事務所の方や、リハビリの先生とか・・・・そして、一番感激したのは、綾戸さんの息子さんの言葉だった。息子さんがそんなふうに育ったのは、綾戸さんの影響が大きいと思う。人は一人では生きていけない。あらためて、そう思った。-----------------------------------空腹のまま、1分間に17人が亡くなっています。12人は子どもです。(日本国際飢餓対策機構)
2010.01.19
コメント(2)
-
センター試験
土曜、日曜とあった大学入試センター試験。今日は、おねえはで自己採点。いろんな悲喜こもごもがあったようだ。職場の知人に聞いても、そのようで、これは致し方ないところ。おねえは、自分の目標点には残念ながらとどかなかった。ただ、昨年より若干、平均点が下がるのではないかという感じもあるようだ。さてさて、あとは、きっちりとセンターの結果がでて、先生方との相談だ。--------------------------------火ぶり漁では、かご1杯以上の魚は獲らないことがルールでした。(特定非営利活動法人 ECOPLUS)
2010.01.18
コメント(2)
-
なまえを書いた ~吉田一子84歳~ (ETV特集)
字を自分の手で書く。自分の名前を書く。それが、どんなに尊いことか、あらためて考えることができた。吉田一子さん 84歳。そして、識字教室という存在と、その意義、そして背景。吉田さんをテーマにした絵本「ひらがなにっき」のことはママが知っていた。子ども達の前で話をされ、字をホワイトボードに書かれた。その字を「とても綺麗」と子ども達が感じていたことが、素晴らしいと思う。実際、その時に書かれた「母」という字は、ほんとうに綺麗な字だと思ったし、その後、また一所懸命に練習されているのも凄いと思った。今、こうやってキーボードを叩いているが、やはり、自分の手で書くことの意味を考えずにはいられない。
2010.01.17
コメント(0)
-
野口健さん講演会
午後、登山家の野口健さんの講演会にママと行った。今回は、コスモ・アース・コンシャス・アクトとしての講演で、環境を大きなテーマとしての講演だった。数年前、運営スタッフをしている森のゆめ市民大学でも講演をお願いしたので、どんなお話をされるかは有る程度予想もできた。今回は、その時よりも環境というテーマに重きを置いたものだったが、やはり、面白かった。8000メートルの世界。最近は、栗城さんにスポットがあたっているが、凄い世界だ。(と、想像するしかない)死と隣り合わせ。何とも、表現のしようがない。それはそれとして、やはり、生還して初めて成功と言えるということだけは、そのとおりだと思った。まだまだ、沢山の遺体もそのままになっているという。さて、ゴミ。悪意のこもったゴミの撤去は、精神的にもとてもキツイと話されていた。いわゆる不法投棄というやつだ。ほかにも沢山、これからのヒントになる言葉があった。また、いろいろできることが沢山あるなあ~と考えるきっかけになる。
2010.01.17
コメント(2)
-
NHK メガクエイク(第2回)
先週に続いて2回目をみた。丁度、阪神・淡路大震災から15年。その仕組も少しずつではあるが、わかってきているようだ。それにしても、そのメカニズムは何とも微妙で、ある意味繊細で、ある意味驚愕の一言。地球を科学する。そんな感じがしたとともに、人々の暮らしも科学していると。あまりにも、大きなテーマだが、こんなところにこそしろんな資源(ヒト・モノ・カネ)が使われるべきだ。
2010.01.17
コメント(0)
-

【すてきなひとりぼっち】谷川俊太郎著
すてきなひとりぼっち・・・・そう、1人ぼっちは孤独だけということでもない。人は1人で生まれてくるわけでもない。いろんな面もあるし、1人だからこそ気付くこともある。この本は、谷川さんの既存の詩集からあつめられたもの。いろんな味があって、凄いなあと改めて思う。ことばあそびうたの流れが、とてもよい。
2010.01.17
コメント(2)
-

【刻まれない明日】三崎亜記著
亡き人への思い出、記憶。そんな記憶も段々と薄れていくのも事実。しかし、その記憶がある間は、いや、無くなってもつながりは消えない。そんな思い出とも、どこかで区切りをつけることも必要なときもある。それは、明日への希望でもあるのかもしれない。忘れ、昇華することで、新しい一歩を歩みだせるのかも。そんな、ある意味寂しいが、ある意味明日への希望に満ちた一冊。
2010.01.17
コメント(2)
-

成長した氷柱(つらら)
昨日、結構大きかったつらら。朝、見てみると、成長していた。2010/01/17 01 つらら posted by (C)けんとまん一番、長いのは1メートル30~50センチくらいある。太さも結構あって、本当に、こんなになるのは何年ぶりだろうか2010/01/17 02 つらら posted by (C)けんとまんここは家の西側になって、ちょうど杉の木や、蔵の陰になって日当たりが悪いこともあって、長く伸びるのだろうと思う。小さい頃は、こんなのごく普通だったように思う。そうそう、カキ氷にしたような記憶が・・・・最近は、つらら自体が珍しい。これも温暖化の影響なのかな・・・と思った。-----------------------------------アイヌ語は、特別な文字で表記するルールが定まっていません。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2010.01.17
コメント(0)
-

【幸いなるかな本を読む人】長田弘著
そうであてほしい、そうだよなあ~、きっとそうだ。そんな思いを持たせてくれる長田さんの詩集。ここにでてくる本を読んでみるのもまた一興かな。本を読む。ということは、今の自分の中では、ごくごく普通のことになっている。おかげで、テレビを見る時間は極端に少なくなったと思う。媒体が違うものではあるが、受け取るものがかなり違うだろうなとは思う。PULL と PUSH の違いのようなもの。
2010.01.16
コメント(0)
-

【神去なあなあ日常】三浦しをん著
神去村。いいですね、ネーミング。神様が去る・・・ではなく、神様とともにある村。そんな感じがした。ちょうど、森林整備ボランテイアをやり始めて2年経ち、ここで書かれていることも、実作業としていくらかやっているので、とても身近に感じることができた。しかし、それはそれとしていいですね~キャラが。こうやって、1人の人間が、周囲の人とのかかわりのなかで成長していく。まあ、設定がいきなりそんなのありという部分もあるが、それもまた微笑ましい。続きが読みたいと思う。そして、「なあなあ」でやっていこうとも。
2010.01.16
コメント(0)
-

立山国際ホテル
夕べの中、何とか立山国際ホテルに辿り着いた。森林サポーター三期会の役員の新年会。職場が、立山国際ホテルさんと保養所契約を結んでいるので、利用することにしたのだが、こんな天候になるとは、思っても見なかった。まあまあ、それなりに飲んで食べて、いろいろ話もして楽しい時間だった。で、帰ろうとして車を見ると 埋もれていた・・・・何とか掘り出して、周囲の写真をパチパチと。2010/01/16 01 立山国際ホテル posted by (C)けんとまんホテルの玄関が全く見えない。2010/01/16 02 立山国際ホテル posted by (C)けんとまん車を掘り出した。2010/01/16 03 立山国際ホテル posted by (C)けんとまん大型の重機が走り回っている。自宅に着くと、一面真新しい雪の世界。2010/01/16 01 我が家からの風景 posted by (C)けんとまんお向かいとの間は・・・2010/01/16 02 我が家からの風景 posted by (C)けんとまん久しぶりのツララが軒下に下がっていた。1メートルくらいはありそうだ。2010/01/16 03 我が家からの風景 posted by (C)けんとまん---------------------------------オホーツク海では過去17年で、流氷が40パーセント減少しました。(特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会)
2010.01.16
コメント(0)
-

【ロジカル・ディスカッション】堀公俊・加藤彰著
ファシリテーション、ロジカル・シンキング・・・・・今、勉強している。来月、これにについての社内研修の講師もしないといけなくなった。以前から、少しずつ勉強したり実践したりはしていたのだが、ついに社内講師もとなると、やはりキッチリと準備も必要になる。ロジカル・シンキングについては2時間ほどのミニ研修を実施した経験はある。まあ、その他研修講師やイベントでの喋りも少しはやっているので、準備をして人前で喋ること自体には、あまり抵抗感はなくなってきた。自分の周囲を見回すと、会議とかミーテイングの内容・質がとても気になるのが多い。殆どは、一方通行のコミュニケーションに終始している。会議。会して議する。ところが、そうではない。声の大きなものが勝つ、役職の上の者が勝つ・・・・みたいなのが圧倒的だし、合意形成なんというのは、はるか先のまま。それを少しでも良くするためには、絶対必要だと思う。----------------------------------ただ見に行くというのではなく、会いに行く。会うまでを楽しみ、会った後も思い出す。(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)
2010.01.15
コメント(0)
-
生き方を学ぶ講演会
の中、PTAの常任委員会のためへ。何とかギリギリ間に合った。さすがに、ほとんどの事業が終り、あとは広報ぐらいのもの・・・そんな中、先生のほうから「生き方を学ぶ講演会」についての依頼があった。これまでは、校区外の方にお願いしていたのが、昨年は校区内の方にお願いをしたということ。1年生を10~20人ぐらいのグループにわけ、関心のあるテーマにわかれて、そのテーマに関連する人から、いろんな話を聞いたりするという、一種の授業のようなもの。で、今年は、その講師を保護者でお願いしたいということ。まあ、正式には学校から依頼文がでたりするのだと思うが、その前にということ。一番身近な保護者が、どんな仕事をしてどんな苦労をしているか、どんな時に喜びを感じるかなど、ありのままを話したり実演したりする。実施は3月中旬の平日の5・6限。ちょっと迷ったが、手を上げた。子ども達に直接、話しかけることができるし、何より、仕事ということに関して自分自身の整理にもなる。仕事柄、コンピュータ室を使用することをお願いした。2時間をどう使うかこれから2ケ月間あるので、じっくりと組み立てて行こうと思う。------------------------------------先生のいない学校があります。(特定非営利活動法人 ホールアース研究所)
2010.01.14
コメント(2)
-
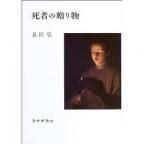
【死者の贈り物】長田弘著
人間だけでなく、命あるものにとっての「死」。そのイメージはいろいろ、人それぞれ。しかし、ここで長田さんが書かれている世界は、とても横溢で読んでいてこころの曇りがとれていくようだ。長田さんの詩は、とても好きだ。長田さんならではの世界。唯一無二。何度も手にとってみたくなる。
2010.01.13
コメント(0)
-

【宮大工の人育て】菊池恭二著
宮大工。独特の響きを感じる言葉であり、職人。従兄弟に大工もいるが、やはり職人だと思う。しかし、宮大工と大工では、かなり違うのだろうと漠然と思っていたが、ほんの少しだけだが予想以上に違うのだと思った。副題がまたいい。木も人も癖があり、それを理解したうえでそれを活かすこと。なるほどと思った。それが棟梁なのだと書いてあるし、納得した。文章自体は淡々としたもので、とても読みやすい。受け取る人がどう受け取るかで、随分評価も違う本だとも思う。菊池さんのサイトはこちら-------------------------------京都、奈良、岡崎。寺社の多さで知られるまちです。(おかざき匠の会)
2010.01.13
コメント(0)
-
夜間補導巡視
午後9時、地域の交番に集合。3つの校下で合同の夜間補導パトロール。とにかく、寒くなってきた。それに、いよいよ受験シーズンにも突入。外に人影自体少ない。補導とは直接関係ないが、除雪の爪あとがあちらこちらに。雪だけではない。雪をブルドーザーなどでよかす時に、看板などが倒れ掛かっていたり、一部破損したりして、結構危ないものも。それが、通学路だったりすると、よけいにそう感じる。このあたりは、難しいところだと思うが、人手をかけるしかないのだろうと思う。-------------------------------レジ袋1枚は、原油にすると20ミニリットルです。(国際環境NGO FoE JAPAN)
2010.01.12
コメント(2)
-

【世界はうつくしいと】長田弘著
詩人の中で、谷川俊太郎さんと並んで大好きな詩人。『深呼吸の必要』で、完全に長田さんの詩の世界に惹き込まれてしまった。今回、久しぶりに読んだのだが、ますますその穏やかながらも深い世界が凄くなっていると思う。さっと読めてしまう。が、時々、ふっと目がとまってしまう。そして、う~んと唸って納得してしまう。世界はうつくしい。基本的にそのとおりだと思う。そうではない世界もある。そうでない世界がますます拡がっているような時代のような気がする今だからこそ、長田さんのこの言葉がこころに響く。小さな、さりげない、日常のなかにこそ、うつくしいといえるものが沢山ある。
2010.01.11
コメント(3)
-

鳥たちの食堂
ふと柿木を見たら、鳥たちが飛び立っていったところで、柿の実も急激に少なくなってきた。1本だけある富有柿。今年は、ほとんど食べなかった結果として・・・鳥たちの食べ物になったわけだ。2010/01/11 01 柿の木 posted by (C)けんとまん目を転じると。2010/01/11 02 立山 posted by (C)けんとまん久しぶりに比較的穏やかな天気。明後日からはまたのようだが。
2010.01.11
コメント(2)
-

【またあした】安藤勇寿絵/森詠文
そうそう、小さい頃こんな感じで遊びまわってたよなあ~夜の小学校での映写会。真っ暗な教室や廊下を、結構ワクワク・ドキドキ・ハラハラしながら歩いていたこともあった。どれもこれも、今の子ども達にはどれだけ経験できるのかな。まあ、自分の周りだと、まだまだたくさん経験できるとは思うが、やっぱりゲームなのなかな。藁の中のあったかさも、懐かしい。
2010.01.11
コメント(0)
-

【にっぽん町工場遺産】小林泰彦著
日本のものづくりを支えるのは、こういった町工場だと思う。(ここでは農林水産があまりないのが、ちょっと残念ではあるが)何よりも、熱い思いと、人間の暮らし=使う人のための目線が基本にあるからだと思う。ここで取り上げられているのは、ほんの一握りだと思うが、ここから感じ取るものはあまりにもたくさんある。フィギア、リヤカー、紙製のペーパーナイフ、磨きのプロ、沖縄のハンドメイド・ソープ、竹製車椅子、お香、プラネタリウム万華鏡、ハンドメイド自転車、ラジコン模型、生湯葉、痛くない注射針、福祉食器スプーン、山の深層水、一休さんの納豆、沖縄きっぱん、三線の音色、切り出し七輪、伝統の醤油、日本聴導犬協会、椿油、ダレスバッグ、八丁味噌、天然塩、カヤット----------------------------------ツキノワグマに、九州ではもう会えません。(特定非営利活動法人 生態教育センター)
2010.01.11
コメント(0)
-
よみがえれ里山 ~小さな米屋と農家の大きな挑戦~
ETV特集は、たまにしか見ないのだが、見るといつも感動する。何も言う言葉を持たない。頭が下がる。古川勝幸さんの言葉は、とても奥行きのある言葉だと思う。凄い苦労をされているにも関わらず、「いらいらしないこと」だと言い切っていた。いらいらしたから、米の味が落ちたんだと。自分も3、4年前からようやく畑を本気で(いちおう)やるようになって、「いらいらしないこと」だというのは、少しではあるが納得できる。騒いでも何をしても、目の前に結果がある。しかも、基本的には、年単位でものごとを考えるしかない。放棄田が増える一方で、このような取り組みがあることは、励みになる。手をかける。手をかけただけ、キチンと恵はあると思う。もちろん、意味のない手をかけるのは、逆効果だろう。あくまで、主役は、その土地・米・野菜が持っている力であって、我々はその背中を押すくらいだろう。
2010.01.10
コメント(0)
-
巨大地震(NHKスペシャル)
凄いと思った。今、地震に関してここまできているのだと思って、凄いと。巨大地震に限らず、日本は地震の巣の近くにある。一番印象に残った言葉。「我々は、どうやって地震が起きるのかわかっていない。」阪神淡路大震災に伴い、世界の地震学者の動きと思考が変ったのだと思った。プレートのこととか、大まかなことは何となく知ってはいたが、ここまで細かく解るようになっているのだとは。地震は防ぐことはできないと思うが、余地し備えることはできると思う。その差は大きい。こんなところにこそ、資源(税金、人)をかけるべきだ。
2010.01.10
コメント(0)
-
18歳
今日は、おねえの誕生日。そうかあ~、早いもので18歳になってしまったのか。週末に迫ったセンター試験があるし、3日にお寿司を食べたばかりということもあるので、さいげなくお祝い。ママ特製のちらし寿しと、ショートケーキ。気がつくと、親父とお袋がサンダース叔父さんのチキンを買ってきていた。やはり、孫に食べてもらおうということだろう。遅くなってから、ママから聞いたのだが、おねえが今後のことで決意をしたとか。今までは結構いい加減にやってきたのだが、こうしようと決めたらしい。どうも、数日前からいろいろ考えていたのだとか。ただ、それを披露するのは、センター試験が終わってから・・・ということ。一人で、そんなことも考えるようになったんだと・・・・
2010.01.10
コメント(0)
-

【俺のロック・ステディ】花村萬月著
懐かしくて涙がでそうになった。ただ、100%懐かしいとも言い切れないのは、自分が音楽を聴き始めた前の部分もそれなりにあるからだが。それでも、懐かしい。ロックの定義。もちろん、それは聴く人間が決めればいいのだと思う。グラムロック/アメリカンロック/ジャズロック/ブリティッシュロック/ハードロック/プログレッシブロック・・・沢山のバンドやロッカーが目に浮かぶし、曲やアルバム・ジャケットも浮かぶ。そう、いいものはいいのだ---------------------------------韓国の学校は、中国から吹く黄砂のために休校になることがあります。(東アジア環境情報発伝所)
2010.01.10
コメント(0)
-

【かけがえのないもの】養老孟司著
養老先生のおっしゃっている「脳化社会」の意味が、ようやく少しわかったように思う。いつも思う。養老先生の本は、比較的平易な言葉で書かれているのだが、実は難しいと。何となくは解るのだが、もう少しのところで納得とはいかないままできていた。が、少しスッキリした。それにしても、目からウロコの視点がたくさんあるなあ~といつも思う。そんな中で特に2つ。「現在」の意味と「未来」の意味。今の時代は子どもたちの未来をつぶしている時代だ。この2つ。そこから「かけがえのない」という意味、「自然」という意味がわかってきた。さすが養老先生、奥が深いや
2010.01.09
コメント(2)
-

【ひなた弁当】山本甲士著
前半はちょっとこの先はと思ったが、中盤から一気に最後まで読んでしまった。「ひなた弁当」というタイトルと装丁の絵から、何となく自分には合う本だとは思っていたが、それ以上だった。主人公を取り巻くキャラクターも、なかなかいい。もし、今、自分がこの主人公のような状況に置かれたらどうなるだろうある程度は生きていけるとは思うが、果たしてどこまでかなあ~。こんな弁当なら、食べてみたいそして、作ってみたい違う意味で、春から少しやってみようかなと思った。ほんわかとした勇気が沸いてくる。---------------------------------自分の暮らしは、自分が担う。自分のまちも、自分が担う。(特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会)
2010.01.09
コメント(0)
全70件 (70件中 1-50件目)
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-
-
-
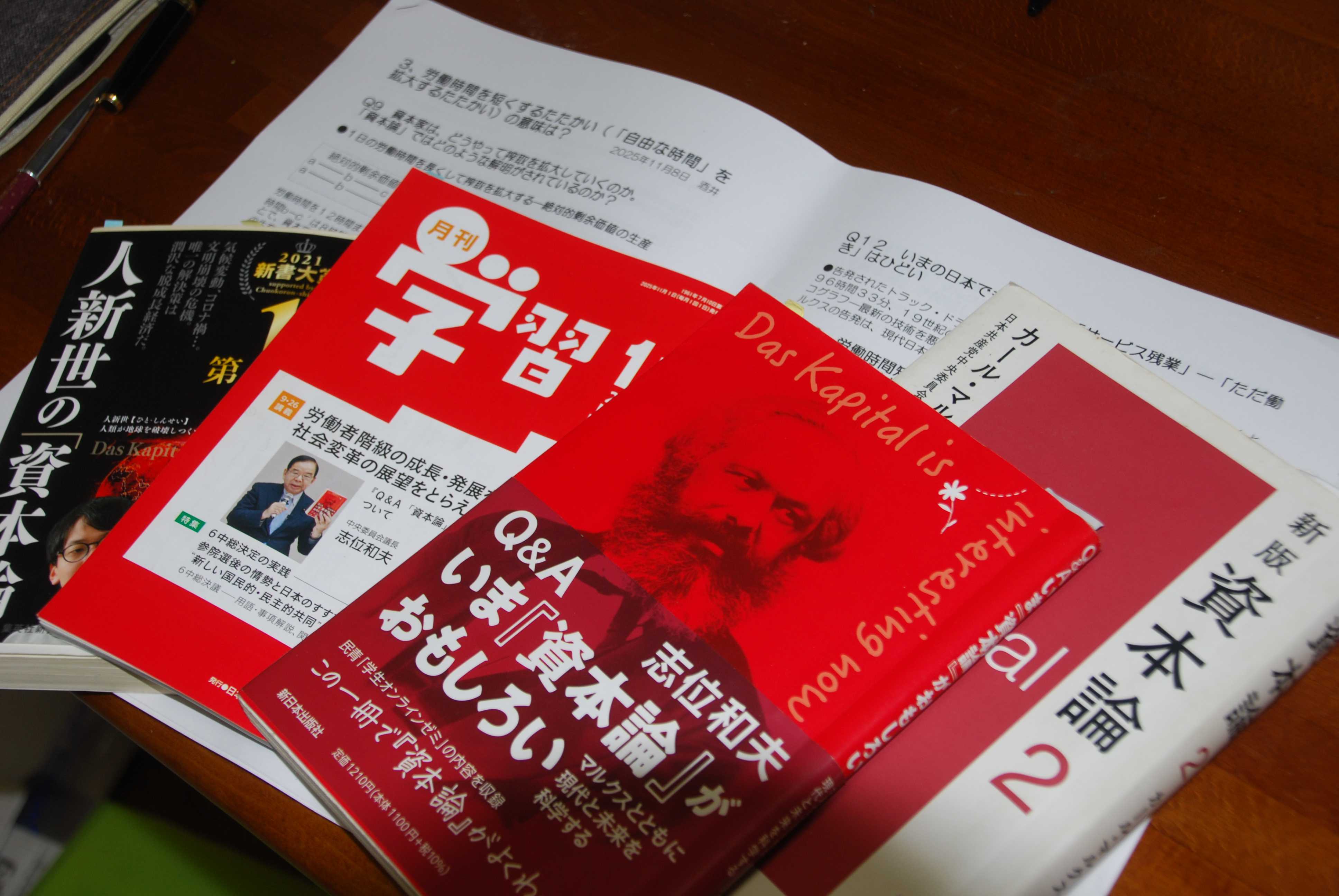
- 今日どんな本をよみましたか?
- 志位『Q&A資本論』の第四回学習会が…
- (2025-11-14 17:13:18)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(10月31日分)
- (2025-11-14 01:01:44)
-








