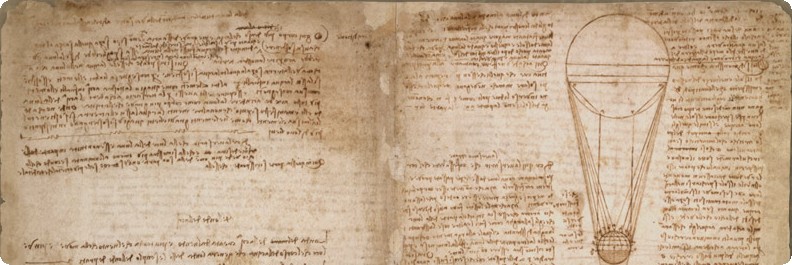◆きくスキル研究会の視点
「顧客満足」は「顧客を満足させる」ことではなく、「顧客が満足する」こと。
そのためには顧客の中にしかない状況や要望を引き出し、正確に把握することが重要である。顧客の情報を引き出すときに、最も必要となるのが「きくスキル」である。
<2>「聞く」「聴く」「訊く」の違い
電話対応のコミュニケーションで使う「きく」は、「聞く」「聴く」「訊く」の3種類。とこの研究会では下記のように定義している。
*前提として「きく」は「意味」のやり取りと「感情」のやり取りから
り立つものと定義する
a「聞く」=「意味」のやり取りを行い、「聞いている姿勢」や「正確に意味を理解した」事を伝える
b「聴く」=「感情」のやり取りを行い、「相手の立場に立って注意深く聴いている姿勢」や「相手への共感・同意」「炊いての気持ちや状況の受け止め」を伝える
c「訊く」=「意味」や「感情」のやり取りを確認したり、会話を広げたり、深めたりする
<3>「スイッチング」というスキル
a 3種類の「聞く」「聴く」「訊く」の相関関係
・「聞く(意味)」のやり取りの先に、漠然と「聴く(感情)」のやり取りがあるのではなく、話し手(顧客)の言葉や状況から聞き手(応対者)が判断し、どちらの「きくスキル」で会話を進めるのかを選択する必要がある。
b「スイッチング」というスキル
どのような「きき方」をすべきかを判断し、顧客との会話に適切なモードに切り替えることを「スイッチング」と研究会では定義している。
「スイッチング」には2種類ある。
・第1のスイッチング=「聞く(意味のやり取り)」の中でその意味に相応しいモードに変化させる
例えば、「商品を購入したい」という顧客に「ありがとうございます」とお礼の言葉を言うなど。
・第2のスイッチング=「聞く(意味のやり取り)」から「聴く(感情のやりとり)」に変化させる、逆に「聴く」から「聞く」に変化させる。
例えば、問い合わせの電話がクレームに変わった場合や、 逆にクレーム対応で顧客が納得して商品の受注ができた場合などがある。
c「スイッチング」の瞬間
1)顧客との会話の中に「キーワード」がある場合
・顧客が自分の感情を表現する
・会話の中で同じ言葉を繰り返す
・言葉や表現を変えて同じことを訊く
・具体的な要望として伝えずに、質問な形で問いかける
2)キーワードはないが「キーシチュエーション」がある場合
・「要望」「着地点」がともに見えていない
・「要望」は明確だが「着地点」が見えていない
・「要望」「着地点」ともに明確だが、同意を求めていたり背中を押して欲しいという潜在意識が存在している
<4>「訊くスキル」こそ「アクティブリスニング」
1)「きくスキル」は能動的なスキル!
「きくスキル」は受動的なスキルではなく、むしろ能動的なスキルといえる。
商品や提案を選ぶのは顧客だが、顧客の中にある情報を引き出し、その状況や要望に添って会話を誘導するのが応対者の仕事。
2)「ビジネス・コミュニケーションン」には明確なゴールがある!
ビジネスとカウンセリングでは「きき方」に違いがある。それは「目的=ゴール」の違いといえる。話し手の「気づき」を重要視するのは同じでも、ビジネスでは企業の目的やミッションに添っていなければ意味はない。最終的に相手(顧客)が決めることに変わりはないが、ビジネスでは顧客の選択肢はその企業の商品やサービス、センターの役割など範囲が限られる。そこの「きき方」の違いがある。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天写真館
- 年間60万円歳費を増やそうとする屑…
- (2025-11-20 17:30:12)
-
-
-
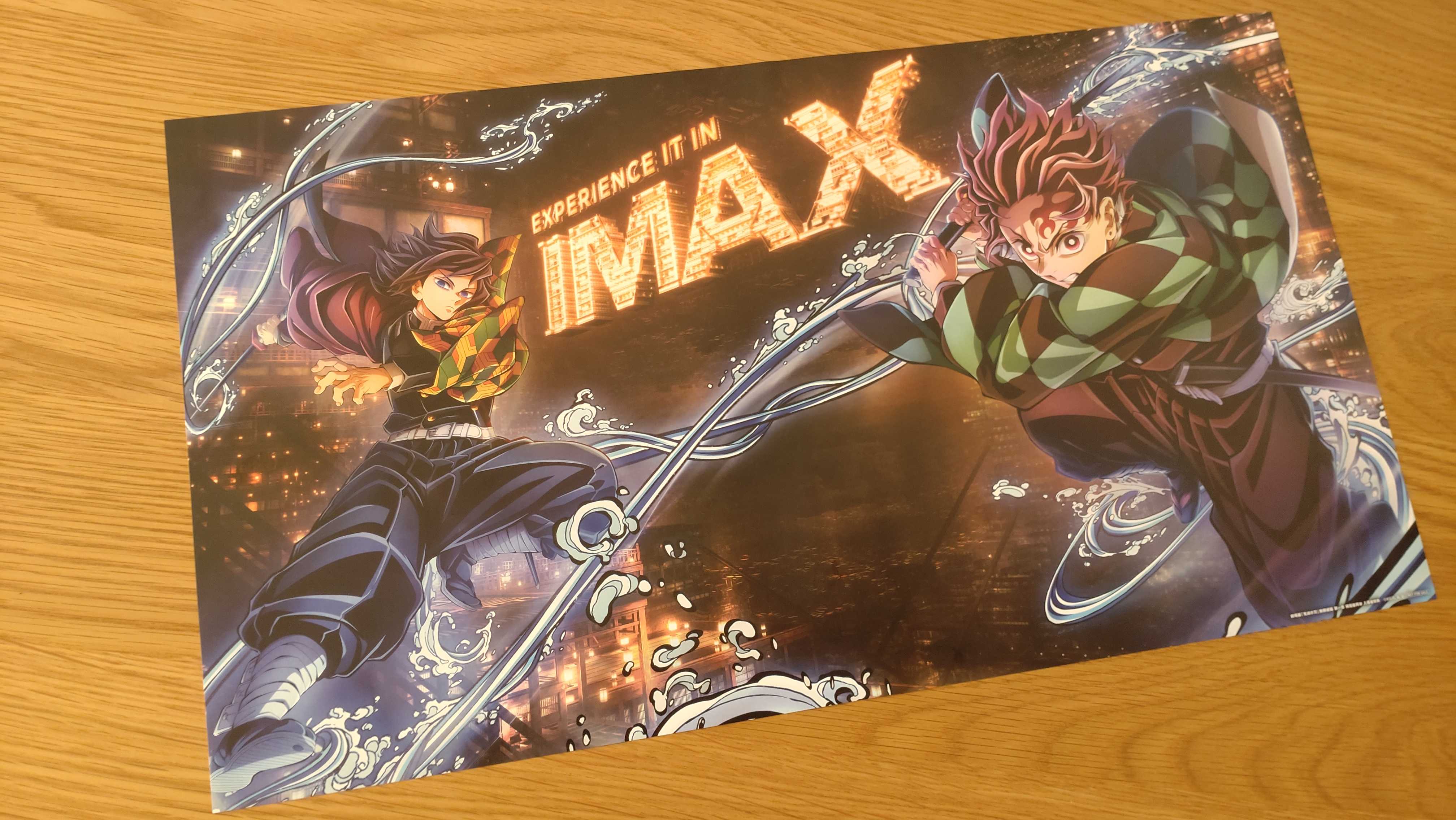
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- どうしても欲しかった映画の特典と楽…
- (2025-11-20 18:11:33)
-
-
-

- 楽天市場
- よなよなエール「マジ福袋2026」:限…
- (2025-11-20 19:00:14)
-
© Rakuten Group, Inc.