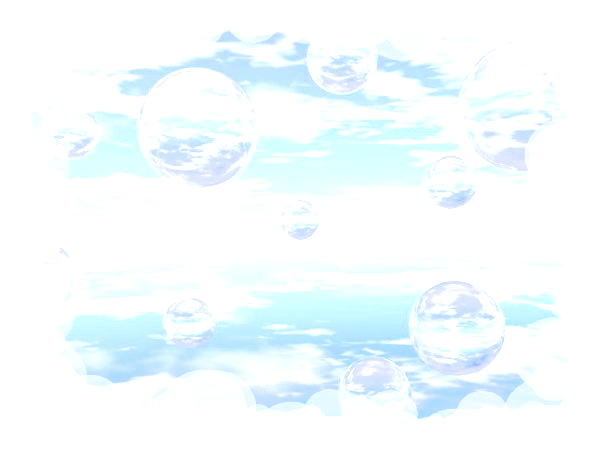ということでまとめ 5
頼り切った東証の危機管理体制の弱さが露呈した。11月のシステム障害による
全銘柄の売買停止に続く今回のシステム欠陥で、東京市場の信頼を落とし
かねない深刻な事態を招いた。「市場の番人」の存在意義が大きく揺らいでいる。
東証は8日夕方、富士通からの連絡で売買システムの欠陥を初めて知った。
システムは2000年から稼働し、11月のシステム障害の後から見直し作業を
行っているにもかかわらず、全く問題に気付かなかったってここが大きな問題。
ミスを繰り返すメーカーを信頼しきっている、それしか対応ができない人材しかいない
東証側の責任を問われても無理はない。日本のマーケット全体の中枢となるシステム
なのだから、このくらい強く言ってもいいだろう。メーカー任せのシステム管理の
問題点がこうしてまた浮き彫りになってしまった。コンピューターシステムの欠陥を
人間が防ぐ機会は何度もあった。東証の担当者はみずほの異常な注文に気づき、
電話で連絡を取っている。その時点で東証は誤発注と把握したが、その後の対応を
みずほに任せきりにした。この時、みずほは注文取り消しに失敗し続けており、
東証が事情を詳しく問いただすなどしていれば、すぐに売買停止措置をとり、
事態の悪化を防げた可能性が高いのだから。全てを相手に任せておいて、その
システムが訂正を不可能にするものであったのならば、みずほさんに非があるとは
到底言い切れないレベルのものだ。
しかし、注文取り消しを断念したみずほが買い戻しに踏み切ったことで、東証は
売買停止を見送った。東証の規定では、売買状況に異常を認めれば強制的に
停止しなければならない。しかし、東証の担当者が「マニュアル通り」(天野富夫
常務)の対応に終始した結果、みずほとの意思疎通を欠き、最後の安全装置が
外れた。会見で天野常務は「売買停止などの対応をもう少し早くやれば」と悔いて
みせ、「みずほが1回目の取り消し作業をした後の責任は東証にある」と認めた。
ここが新しい展開となる。今までのコメントでは、責任は一切東証にはなく、
全ては適切に指示されたかのようなコメントを東証は繰り返していたのだから。
東証は前回のトラブルを受け、社長直属の「システム諮問委員会」の設置など
対策を決めたばかり。市場が納得する対策を早期に打ち出せなければ、活況を
続ける日本市場への国際的な信頼にも疑問符が付きかねないことを考えると
また、個人投資家がこれだけ多く参加し、日々のデイトレードを行っている今、
もっと強固な信頼を投資家から勝ち得るだけの行動と戦略を見せてほしいところ。
© Rakuten Group, Inc.