2010年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

ダヴィンチ・コードを読む
今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見て、午後は、家内の実家に関連する雑事をしに行った。空いた時間は、図書館で借りた「ダヴィンチ・コード」を読んだ。「ダヴィンチ・コード」は、半月前にビデオで映画版を見たのだが、もっと詳しく知りたいと思って、本を借りて来たもの。上・中・下の3巻で総ページ900ページ弱。原作が映画化されるとき、「読んでから見るか、見てから読むか」が議論されるが、私の場合は「見てから読む」。しかし、読んでいるうちに、もう一度映画を見たくなった。原作では、いろいろな事象が詳しく書かれてあるが、映画ではほとんと触れられていなかったように思う。どの程度映画にとりいれられていたのかを知りたい。画像は、文庫本の「ダヴィンチ・コード」の表紙と図版より。
2010.01.31
コメント(0)
-

大阪俳句史研究会の講話を聴く
今日は、午前中は、読書をしたり、俳句王国を見たりして過し、午後は、伊丹市の柿衛文庫で開催された大阪俳句史研究会主催の例会に参加した。この会の講話を聴くのはこれで2回目。今日は「白燕60年」と題して和田悟朗氏が話をされた。白燕は「びゃくえん」と読む。橋間石氏(1903-1992)によって昭和24年に創刊された俳句誌であり、結社の名前でもある。講師の和田氏は間石の一番弟子。(間石の間は正式には門構えに月と書くが、ネットではその字は使えないので、間と記す)間石は金沢生れ、中学生の頃から俳句を詠む。四高、京大へと進むが生来の交際嫌いで京大俳句会にも入っていない。卒業後、英語教師をする傍ら俳句を続け、戦前「俳句史講話」を著す。間石46歳のとき白燕を創刊。句集も次々と著す。1967年64歳で退職、俳句に専念。1992年死去。この間、1974年蛇笏賞、1988年詩歌文学館賞等受賞。現代俳句協会副会長を務める。間石没後は、和田氏が主宰として白燕を継続、間石の遺稿を整理し「間石全句集」(2003)「俳諧余談」(2009)などの出版化を実現。一段落したとして「白燕」も2009年6月、第425号を以て終刊とした。創刊後、ちょうど60年であった。上述の経緯を、俳人との交友関係やときどきの代表句を示しながらの講話であった。間石の句は写生句というよりむしろ抽象、人生句というものが多い。 階段がなくて海鼠の日暮かな 時間からこぼれていたり葱坊主 枕から外れて秋の頭あり画像は、サイトの記事、講話する和田氏、下は付近みやのまえ文化の里で催されていた盆梅展の梅。
2010.01.30
コメント(0)
-

壬生寺展、チベット展、楳茂都陸平展を見る
今日は、午前中は、英クロを解いたり、雑事をしたあと家を出て、美術展3つを見た。大阪高島屋で開催されている「京都・壬生寺展」、大阪市歴史博物館で開催されている「聖地・チベット展」と「楳茂都陸平展」の3つだ。家を10時半に出て、高島屋には、11時10分に着いた。壬生寺は、新選組の本部があったことで有名で、京都での勤務地の近くにあり、何度か行ったことがあったが、余り詳しくは知らなかった。今回の展示は、寺の縁起をはじめ全般的な説明とともの、特に壬生狂言と紹介と、一昨年に描かれた障壁画の展示が目玉である。展示は次のように分類されていた。1.壬生寺の歴史 壬生寺縁起絵巻、円覚上人彫像、伽藍図、勧進帳、金鼓、舎利塔、鬼神面など2.壬生狂言 嵯峨釈迦堂狂言、千本閻魔堂狂言とともに京の3狂言の一つ。 壬生三面、狂言面30面、番号札、衣裳、大幕(1.3M×5.9M 今年新調、お披露目前のもの)、小道具(楽器、棒、杯、槌、桶、被り物、札、弓矢、)、壬生狂言の映像(19分)3.壬生寺本堂障壁画 あだち幸氏の作品(平成19年に奉納)、地獄変(襖4面)、宙みつ誓願、宙みつ祈り、明珠不滅、明珠不生、銀河の使者、永遠の今(以上6点いずれも3M×3M)、浄土幻想(襖4面)4.壬生寺の文化財 地蔵菩薩立蔵、薬師如来座像、十一面観音座像、菩薩像、羅漢像、曼荼羅図など。壬生狂言は一度見たことがあるが、沢山ある演目のうち3つか4つしか見たことがない。映像でいくつかの演目のさわり部分を見せていたので、全部見た。あたち幸氏は、友禅下絵画家で、仏像を優しい色合いで描いている。この作品はいつまでも見ていたいと思った。画像は、パンフレットより。宙みつ祈り(部分)、本堂内の様子、永遠の今(部分)、壬生寺縁起「元禄本」、壬生三面(狛蔵主、姥、猿)、地蔵菩薩立像、地蔵菩薩半迦像、狂言衣裳壬生展を見終わったら、12時10分だった。難波で昼食を取り、地下鉄で谷町4丁目まで行き、歴史博物館に着いたのは、13時10分だった。ここでは、2つの展覧会を見るのだが、先ずは、「楳茂都陸平展」から見た。楳茂都陸平(1987-1985)のことは今まで知らなかったが、楳茂都家は歌舞伎、能楽、舞踊の家元で、陸平はその三代目、宝塚音楽学校の教師兼振付師として多くの作品を作り出した人だそうだ。展示は次のように分類されていた。1.初代楳茂都扇性 風流舞鷲谷正蔵の子。天満の地に楳茂都流を開く。2.二代目楳茂都扇性 扇性の三男。浪速おどりの振付、楳茂都流舞踊の基礎を築く。俳人でもあった。3.三代目家元陸平の活動4.楳茂都流の事始5.楳茂都流の舞踊衣裳 3点を展示6.楳茂都流の道具 鈴、笛、小鼓、扇子など7.戦後の陸平8.四代目家元へ 俳人の長女鷲谷七菜子が暫定的に継いでいたが、片岡愛之助が正式に四代目を襲名。画像は、パンフレットより。宮比大神像、陸平の写真、楳茂都陸平舞踊イラストノート、初代楳茂都扇性像、鶯集庵での句会の図、モーツアルト像(陸平筆)、雑誌「舞踊」第3号、楳茂都流舞踊譜、宝塚少女歌劇「パンフレット」、同、新舞踊劇「和歌の浦」パンフレット。楳茂都展を見終わったら、13時45分であった。6階に降り、「聖地ーチベット展」を見た。チベットは仏教がインドから中国に伝わるより前に伝来していた。一旦は滅びたが、7世紀初めにソンチェンガンポ王のとき、ネパールと中国から娶った王妃により仏教が復興する。その後独自の発展をとげるが、その特色は仏像や仏画がカラフルなことだ。今回は、チベットのポタラ宮を初めチベットの寺院から国宝級の品36点を含む123点の仏教美術が展示されている。展示は次のように分類されていた。序章 吐蕃王国のチベット統一 ソンチェンガンポ王坐像、魔女仰臥図など3点第1章 仏教文化の受容と発展 弥勒菩薩立像、ダマルバ坐像など29点第2章 チベット仏教の精華 十一面千手千眼観音菩薩立像、カーラチャクラ父母仏立像など62点第3章 元・明・清との往来 大元帝師統領諸国僧尼中興釈教之印、青花高足碗など13点第4章 チベットの暮し 民族衣装(チティパティ)、たて琴、ホルン、胸飾りなど16点色彩が鮮やかなので、仏像が厳かで陰気な感じがせず、明るく陽気な感じがする。仏像は日本のような木造は一つもなく殆どが金属製。絵は日本の掛軸のようなものに描かれていてタンカというそうだ。これも色がきれい。ゆっくりと一通り見て回るとちょうど15時になっていた。 画像は、パンフレットより。十一面千手千眼観音菩薩立像、カーラチャクラマンダラ・タンカ(部分)、カーラチャクラ父母仏立像、カーラチャクラマンダラ・タンカ、ダーキニー立像、グヒヤサマージャ坐像・タンカ、白傘蓋仏母立像、十一面千手千眼観音菩薩立像、大元帝師統領諸国僧尼中興釈教之印、青花高足碗、ダマルバ坐像、弥勒菩薩立像
2010.01.29
コメント(0)
-

家出用バッグ
今日は、午前中は、年賀状の当りを調べたり、2222の日の記念押印の郵頼を申し込んだりしながら過し、昼ごろ、俳句仲間の2人と落ち合い、一緒に昼食をとりながら雑談をした。年賀状は、例年は期待値より少ない枚数しか当らないが、今年は250枚来て7枚当ったので、ラッキーだった。それも、最初見たときは、4枚しか見つからなかったのに、念のためもう一度見てみると、3枚が新たに見つかったのである。いつも、一回だけしか調べないが、こんなこともあるものだ。俳句仲間とは、俳句、音楽、落語、旅行、緑懇会、知人、詰め碁、パズル、写真など、いろいろなことを話しあい、気がつけば4時近くになっていた。今日の写真はあるかばん屋で見つけた面白いフレーズ。家出用バッグ わずらわしい日常から逃れ、おしゃれなバッグを手に、短期の家出はいかがでしょう・・・ 決意! お父さん、お母さん、お世話になりました。東京で頑張って働きます。出世をします。そして、このバッグに万札を一杯にして送ります。送料は悪いですが、着払いということで・・ (二度と帰りませんバージョン) お母さん、ごめんなさい。お父さんとは、うまくいきません! 子供が出来ればメールします。などと書かれてある。
2010.01.28
コメント(0)
-

大阪城早朝探鳥会
今日は、大阪城早朝探鳥会の日。朝6時半に家を出て、大阪城の噴水前に7時に集まった。今日は元山先生が休みだったので、鳥の名が分からず、珍しい鳥を見つけることもできず、つまらなかった。探鳥会のあと、梅林を見ながら帰宅した。午後から、ヨドバシカメラへ行ってデジカメを買い、図書館へ行って、「白鳥の湖」のオペラ、「ダヴィンチ・コード」の本などを借りて来た。帰宅後、2月2日の2並び数日のための郵頼の準備をした。集まったのはいつものメンバーで9人。森の中にはツグミだけしか見つからなかった。また、堀の中にも、キンクロハジロとホシハジロしか見られなかった。しかし、帰り道で、ユリカモメ、カワウを見ることができた。今日見た鳥は、前出のほか、シロハラ(声のみ)、シジュウカラ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス。写真は、探鳥する参加者、ツグミ、ツグミ、キンクロハジロ、ホシハジロ、ホシハジロ、ユリカモメ、カワウ、ハクセキレイ大阪城の梅林はまだ1分咲き以下。それでも見頃に木が10数本くらいはある。カメラはキャノンのパワーショットSX120。光学10倍ズームが付いている。
2010.01.27
コメント(0)
-

大阪天満宮星合池まわりの梅
今日は朝から昨日の句会のまとめを行った。昼過ぎに一段落したので、K病院に血液検査に行きがてら、ヨドバシカメラへデジカメを見に行った。最近のデジカメは液晶画面が大きく、手振れ防止がついたり、望遠ができたり、連写ができたり、状況によって最適の撮影方法をカメラが選ぶようになっている。現在のカメラは2年間使ったので、そろそろ換え買え時だろう。今日は、写真を撮らなかったので、一昨日撮った大阪天満宮の星合池まわりの梅。満開の梅から咲き始めの梅までいろいろあり、蝋梅は終りに近い。梅のほか、白椿、紅椿もある。
2010.01.26
コメント(0)
-

今日は句会そして新年会
今日は句会、してその新年会の日。今日の句会は大阪天満宮の初天神、鷽替神事を見てのいわば吟行句会であった。早い人は11時くらいから、天満宮境内で行われる初天神の催しを見たり境内を回ったりして過し、多くの人は13時からの鷽替神事に参加した。鷽替のあと、いつもの会場に戻り、句会を催した。下記は、鷽替神事の様子。句会の成績は上々であった。5句のうち、先生から3句選ばれ、あと1句が仲間から選ばれ、1句は誰からの選ばれなかった。先生に選ばれたのは、次の句。 鷽札の向きを正して替へにけり (先生ほか9票) 初天神繁昌亭の繁昌す (先生ほか1票) 初天神南から入り北へ抜く (先生)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎鷽替の数だけ笑顔貰ひけり (先生特選ほか6票) ◎腰かがめ幼子と替ふ鷽の札 (先生特選ほか2票) ◎何の木か僧は知らぬと大枯木 (先生特選)今日、一番票を集めたのは、上記私の句。先生の句で今日一番人気だったのは、次の句。 鷽替のまことしやかに替へゐたり 塩川雄三先生 (6票)新年会は、このところ常席となった都島区の「S中」で開催、カラオケも歌い楽しいときを過した。写真は句会の模様(左上)と新年会の様子。
2010.01.25
コメント(0)
-

関西ぱずる会例会
今日は、昨日から引き続いて、関西ぱずる会の宿泊例会。いわば昨日は前夜祭で今日が本番の例会である。宿泊した17名は8時から朝食、当日参加の1名を待って、9時から例会が始まった。1月の例会は、恒例により、届いた年賀状をすべて解き、資料にまとめられているY氏の発表から始まり、参加者が自作の年賀パズルについて説明を加える。それにしても、50人ほどからの年賀パズルを全部解くY氏の頭脳と根気には驚かされる。だが、私が解けなかったM氏の問題は、Y氏も解けなかったそうだ。K氏のしり取り遊びについては、187ステップの私の解が最大だったとのこと。M氏の間違い探しは22個見つけた積もりだが、あと2か所が洩れていた。年賀パズル関連の発表のあと、通常の発表に移ったが今回は各自多くの発表があり、書きとめるのも忙しいほどであった。パズル、パズル関係の本など、100を超える回覧物があった。下記写真は、例会風景とパズル類、本などのごく一部。例会は、12時15分に終了。その後、これも恒例の回転寿司屋に行き、昼食後解散となった。私は、途中南森町でで降りて、大阪天満宮の初天神の模様を見に行った。鷽替え神事は終っていて、合格祈願の学生らが登龍門を渡り「本殿の通り抜け」を行っているところであった。
2010.01.24
コメント(0)
-

関西ぱずる会宿泊例会
今日は、夕方から関西ぱずる会の宿泊例会に行くので、午前中は、その準備や、句会資料の仕上げなどを行った。宿泊例会に行く前に、くらしの今昔観のに寄り、今昔亭で落語2題を聞いた。今昔亭でも落語会は毎月1~2回行われていて、今日は、桂出丸の「ふぐ鍋」と桂米輔の「初天神」が演じられた。「ふぐ鍋」を作ったが、なんとなく食べるのが怖い。運よく乞食が来たので、ふぐの一切れを与えた。しばらくして乞食の様子を見に行くと元気そうなので、安心して食べてしまった。また、乞食がやって来て「先ほどのふぐはお宅ではもう食べましたか。それでは私も食べしょう」というのがオチ。「初天神」は、子供を連れて来たところ、飴やみかんやりんごやみたらしなどそれぞれの屋台の前で物を買わされるはめになる親を描く。オチまで行かず、「大騒ぎをしております。お馴染の初天神でございます」で切り上げた。写真は、パンフレットと落語会の様子。パズル会の宿泊例会の会場には、4時ごろに着いた。早速、各自持参のパズルを机の上に並べ、思い思いに触ったり、解いたり、眺めたり、年賀状パズルの解を持ち寄ったり、パズルコンテストをしたり、夕食の1時間を除いて、就寝までの時間をパズル三昧で過した。早い者は12時ごろ就寝したが、遅いものは5時ごろまで起きていた。写真は、パズル会の前夜の様子。
2010.01.23
コメント(0)
-

「世界のチェス・将棋展II」を見る
今日は、午前は、英クロを解いたあと、東大阪市の大阪商業大学で開催されている「世界のチェス・将棋展II」を見に行った。午後は大阪に帰り、大阪中央会館での「関西郵趣サロン」に出席した。大商大アミューズメント研究所主催の当展示会は9年前から毎年この時期にテーマを変えて開催されていて、今年は9回目になる。これまで、いろいろなアミューズメントのテーマが取り上げられて来たが、今年のテーマ「チェス・将棋」は第1回のテーマと同じで、今回は2度目である。前回も世界各国の珍しいチェス・将棋が展示されていたが、今回はその後の収集品を含めてより歴史的、系統的に分類して展示したもの。展示は次のように分類されていた。 1.アジアの将棋 中国、タイ、モンゴル、インドほか 2.アラブのトランジ(昔のチェス) 3.ヨーロッパのチェス 4.アメリカ大陸のチェス・将棋 北アメリカ、南アメリカ 5.アフリカのチェス・将棋アジアの将棋 6.アジアのチェス 7.ルイスの駒 世界最古の駒、イギリスルイス島で1831年に発見。12世紀のもの。 8.軍人将棋 海外、日本 9.いろいろな将棋 三人将棋、四人将棋10.将棋の駒の名品チェス・将棋の類は、百数十種類もあるそうで、それぞれ、磐の形、駒の形・数が異なり、駒の役目も違う。大まかには国によって違うことが多い。その中で、よく遊ばれているベスト5は、チェス、中国将棋、日本将棋、朝鮮将棋、タイ将棋だそうだ。競技人口は、上位二つが5億人と断トツで、日本将棋は1500万人、朝鮮が700万人、タイが500万人だそうだ。チェス・将棋というのは、戦争をゲーム化したもので、当初は駒も実際の兵士や大将、馬、武器などの形を象っていたが、次第に簡略化され、チェスでは抽象立体形に、将棋では文字だけになった。駒を見ているとお国がらが見えるものもあり、本当にバラエティが多い。色・形がさまざまである。これは見なければわからない。文字では説明できない。画像は、バンフレット、カタログの表紙、展示会場の概観、日本の将棋の駒の名品、インド将棋の駒、?のチェス、イギリスのチェス展示を40分ほどかけて見たあと、カタログを買って、会場をあとにした。大阪に戻り、昼食を済ませ、午後の会場=大阪市中央会館へ行き、関西郵趣サロンの例会に参加した。今日は、N氏のコレクション拝見があり、氏の膨大なコレクションの中から、スイスの通常切手を披露された。裏に番号を印刷したもの、独・仏・伊の3カ国で書かれたものなどが珍しく、その他、同じように見えるが細部が異なっている切手も面白かった。コレクション拝見のあとは、盆まわしとなった。今日も夥しい数の切手が回覧されたが、私は、数の切手、美術切手などで気に入った10数枚を購入した。画像は、例会風景。
2010.01.22
コメント(0)
-

ハプスブルグ展
今日は、一日中在宅で、家内の実家に関する雑事をしながら過した。今日は、写真を撮らなかったので、昨日見た「ハプスブルグ展」のことを書く。「ハプスブルグ展」は日本とオーストリア、ハンガリーが国交を樹立してから140年経つことを記念して、京都国立博物館で1月6日から3月14日まで開催されているもの。ハプスブルグ家は、日本が国交を持った1869年当時、オーストリア・ハンガリー帝国の王家であった。600年の間、勢力の拡大・縮小を繰り返しながらヨーロッパ全域に君臨したが、1918年の第一次世界大戦で崩壊した。王家の美術品は、現在、オーストリアのウィーン美術史美術館、ハンガリーのブタペスト国立西洋美術館に継承されている。本美術展では、両美術館の所蔵品の中から、デューラー、ベラスケス、ルーベンス、ラファエロ、ティッツァーノ、ゴヤなどの名画75点と工芸品などが計120点が展示されている。展示品は次のように分類されていた。1.特別出品:明治天皇から皇帝ヨーゼフ1世に贈られた画帳と蒔絵箱 狩野永応、住友広賢、服部雪斎、松本楓湖、歌川広重、豊原国周らの絵画。2.イタリア絵画 フォロフェルネすの首を持つユディット(ヴェロネーゼ)など26点3.スペイン絵画 受胎告知(グレコ)など8点4.ハプスブルグ家の肖像画と武具コレクション 白衣の王女マルガリータ・テレサ(ベラスケス)など20点5.ドイツ絵画 洗礼者ヨハネの首を持つサロメ(クラナッハ)など9点6.フランドル・オランダ絵画 懺悔のマグダラのマリアと姉マルタ(ルーベンス)など21点7.美術工芸品 多面体形赤道式日時計など28点 王家の肖像画は子供であっても気品にあふれていて迫力がある。これまで、写真などで見たことはあったが、本物はやはり素晴らしいと思った。敵の生首を持つ女や、首を切られた男の首の断面など生々しい絵もあったが、それが残酷性を感じさせないのは、ドレスや人物の美しさのためであろう。天然石をふんだんに使った時計など工芸品も見応えがあった。画像は、パンフレットより。11歳の女帝マリア・テレジア(メラー)、オーストリア王妃エリザベート(ヴィンターハルター)、白衣の王女マルガリータ・テレサ(ベラスケス)、皇太子プロスペロ(ベラスケス)、聖母子と聖パウロ(ティツアーノ)、若いベネツィア女性の肖像(デューラー)、洗礼者ヨハネの首を持つサロメ(クラナッハ)、懺悔のマグダラのマリアと姉マルタ(ルーベンス)、駕篭かきと美人(豊原国周)
2010.01.21
コメント(0)
-

契月展、夢二展、ハプスブルグ展を見る
今日は、朝のうちは、俳句誌へ例月の句を郵送投句したり、美術館情報を下調べしたあと、美術展3つを見るため、昼前に家を出た。3つの美術展とは、伊勢丹デパートの菊地契月展、京都高島屋の竹久夢二展、それに、京都国立博物館のハプスブルグ展である。いずれも、いい美術展で、混雑もなくゆっくり鑑賞でき、気温も暖かく移動も楽だった。大阪を11時の新快速に乗り、京都には11時半に着いた。先ず、伊勢丹7階の駅ミュージアムの契月展に入った。菊地契月(1879-1955)は京都で活躍した日本画家。菊地契月展は、生誕130年を記念した展覧会で、初期の作品から円熟期の作品まで約100点が展示されていた。これまで契月といえば美人画だけしか印象になかったが、初期は歴史画を多く画いていたことを知った。展示は次のように分類されていた。第1章 画家をめざして-南画から四条派へ 悪者の童など中国や日本の歴史画 9点第2章 模索の時ー至高の画風を求めて 少女、鶴など美人画 10点第3章 欧州視察から得たものー苦境へのまなざし 立女など16点第4章 完成と成熟の時代 光明皇后、聖徳太子御影など30点第5章 契月の画蹟に触れる 西洋絵画の模写、写生帖、参考資料など10余点作品は、どの作品も味わいがあり、見応えがあったが、上記例示の作品が特に印象的だった。清楚、清純などの言葉がぴったりの絵であった。画像は、パンフレットより。友禅の少女(1933)、少女(1932)、深窓(19??)、石榴(1933)、福原故事(1899)、光明皇后(1944)、朱唇(1931)契月展を見終わり、地下鉄で四条まで行き、四条高倉の「井川丸」という店に着いたのは12時半、そこの大盛天丼で昼食とした。13時15分に高島屋に着き、7階グランドホールの夢二展に入った。竹久夢二(1884-1934)の展覧会はこれまでにも何度か見たことがあり、その作品も目に触れることは多い。大正ロマンの美人画として有名な画家だ。今回の美術展は、夢二生誕125年を記念して開催されたもので、展示品は、色紙、屏風などの肉筆画、雑誌・本などの表紙絵、絵本、ポスター、デザイン画、手拭絵など多岐にわたりその数も約400点。じっくり見ると何時間もかかるほど。夢二は、完成画だけでも約1000点、挿絵やデザイン画を入れると10000もの絵を残しているそうだ。展示は次のように分類されていた。1.メディアへの登場2.新しい試み3.展覧会とギャラリー4.京都へ5.夢二のスケッチブック6.秋のいこいー絵画表現の深まりとデザインの展開7.榛名山美術研究所の夢8.二つのふるさとと二つのコレクション 岡山の松田基コレクションと榛名(伊香保)の長田幹雄コレクション美人画ばかり画いた夢二も、若いときは、普通の画題の絵も画きたかったようで、美校に入学しようとして画いた「BROKEN MILL AND BROKEN HEART」という絵が展示されていた。しかし美校はあきらめ美人画専門に独学の画風を築き上げることになる。美人画の影には、たまき、彦乃、お葉など、きれいなモデルがいたことも紹介されていた。(それぞれ夢ニの妻となっている)画像は、パンフレットより。立田姫(1931)、邪宗渡来(1918)、旅の唄(1918)、スケッチブック、こたつ(1915)、とんぼ(1914-16)、茸の図鑑(1914)、半襟図案(1914-16)、同(1914-16)、いちご(1914-15)夢二展を見終わり、京阪電車で四条から七条まで行き、京都国立博物館には、14時40分に着いた。ハプスプルグ展を約1時間かけて鑑賞し、喫茶店で休憩したのち、16時46分の快速急行に乗り17時40分大阪の自宅に帰った。ハプスブルグ展のことについては、明日のブログに掲載の予定。
2010.01.20
コメント(0)
-

ハバタン
今日は、一日中在宅で、昨日の句会のまとめを作成した。それが一段落した午後3時から、先日借りた映画「ダヴィンチ・コード」のビデオを返却前にもう一度見た。今日は、写真を撮らなかったので、先日、西宮で見かけた兵庫県のゆるキャラ、ハバタンの着ぐるみの写真を載せる。
2010.01.19
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会、午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。今回は前回の句会から日が空いたので、すっかり句作りから疎遠になり、カンが戻らなかった。成績の方はまずまずでの出来。先生から2句選ばれ、仲間から2句が選ばれ、1句は誰からも選ばれなかった。先生に選ばれたのは次の句。 福笹の福の重さを持ち帰る (先生ほか6票) 松過ぎて粗食の暮し戻りけり (先生)仲間から選ばれたのは次の句。 すべもなくく押さるるままの初詣 (2票) 琴人の右手左手淑気満つ (1票)誰からも選ばれなかったのは、次の句。 雪の舞ふ土佐堀通急ぐ人 今日、先生の特選に選ばれたのは、次の句。 ◎会ひたしと二重丸せし賀状来る 愛子(先生特選ほか1票) ◎仕来りの薺打ちをり粥ぎらひ 豊子 (先生特選ほか1票) ◎大絵馬の虎に睨まれ初詣 洋子 (先生特選)今日、最高得点を得たのは、上記の私の句。先生の句で、今日一番人気だったのは、次の句。 別人の顔にて暮らす三ケ日 塩川雄三先生 (4票)句会のあとは、いつものようにジョッキを傾けながらの反省会となった。今日は、カメラの調子が悪く句会の様子は撮れなかったので、句会前に訪れた大阪天満宮の星合池の梅を載せる。左下は蝋梅、右下は白椿。
2010.01.18
コメント(0)
-

新春・歌の調べを聴きに行く
今日は、夕方までは在宅で、テレビでNHK俳句や日曜美術館などを見ながら、年賀パズルの問題を解いて過し、夕方から、南港ATCサンセットホールへ「新春・歌の調べ」というコンサートを聴きに行った。今日の出演は、ソプラノ勝桂子、テノール細見大輔、バリトン松沢政也の3人とピアノ2名の計5人で、約2時間にわたって、オペラからの歌曲を11曲とアンコール3曲をすべてソロで聴いた。私が聴いたことのある歌は、カルメンより「闘牛士の歌」(バリトン)とリゴレットより「慕わしい人の名は」(ソプラノ)の2曲だけであとは初めて聴く曲だった。モーツアルトの魔笛やヴェルディの椿姫などは聴いたことはあると思うのだが、覚えていなかった。声楽の生の声を3~4メートルの至近距離で聴くのは初めてで、その声量の大きさに驚いた。1000人規模の大ホールでも響きわたることだろうと思った。また、ソプラノ歌手の高音も物凄く高い声を出していて、しかもきれいで声量もあり、ほれぼれして聴いたが、さずがに歌い終わった後は、苦しそうな様子だった。画像は、パンフレット、プログラムと会場の様子。下は、左から、テノールの細見氏、ソプラノの勝さん、バリトンの松沢氏。
2010.01.17
コメント(0)
-

大脇芳夫のピアノコンサート
今日は、午前中は、年賀パズルの一つをほぼ仕上げ出題者に送ったあと、昼前から、西宮で開催された震災復興祈念コンサートに参加した。このコンサートは、阪神大震災の犠牲者を弔い、被災者を励ますために続けられている。今日のピアノコンサートの出演者は、大脇芳夫氏とリム・ユヒャンさん。共に被災者であり、特に大脇氏はオーストリアからわざわざ帰国しての演奏である。会の冒頭、参加者全員起立して犠牲者に黙祷を捧げた。今日の曲目は、水本誠の「神々への誓い」、ベートーベンの「テンペスト」、ショパンの「雨だれ」、「ノクターン」、「ポロネーズ」、「バラード」、「ピアノソナター葬送行進曲付き」、リストの「コンソレーション」、「ハンガリー狂詩曲」で、アンコール曲は「ハンガリアダンス」、「ラデツキー行進曲」だった。大脇のピアノは流れるような演奏の中に力強さが感じられた。リム・ユヒャンのピアノもうっとりと聴きほれるほどだった。特に「ハンガリー狂詩曲」に感動した。演奏中、チマ・チョゴリを3回も着替え、目でも楽しませてくれた。また、今日は、偶然に一番前の真ん中の座席が得られ、演奏者の表情が手に取るようにわかり、マイクを通さない生のピアノの音も聴け、ラッキーであった。演奏後は、出口で見送ってくれ、2人と握手もすることができた。画像は、プログラムと当日の写真。帰りに、会場近くにある海清寺の大クスを見に行った。樹齢600年で、高さ30メートルだそうだ。そばの山門の写真とともに、下記に示す。
2010.01.16
コメント(0)
-

映画「ダビンチ・コード」ほか
今日は、寒い日だったので、一日中在宅で、ビデオで映画を3本見た。うち2本は昨日見たものを見直したもの、他の1本は「類人猿ターザン」「ハリーポッターと不死鳥の騎士団」は2回見て理解が深まったが、やはり余り面白くない。過去の4作は、ストーリに引き込まれるようにわくわくしながら見ることはできたが、この第5作はだらだらと続いていて、早く終ればよいと思うくらい退屈に思う。それに比べ「ダビンチ・コード」は、殺人事件の謎解きなのだが、何度見ても面白い。この映画は2006年のアメリカ映画で、キリスト教の歴史がテーマとなっている。今ではキリストは神だと崇められているが、人間キリストがどのようにして神にされたのか、そして、キリストに子供がいてその子孫の家系がずっと続いていると信ずる教団が存在することなど、日本人には新鮮なことであった。殺人事件の発生から映画は始まるが、犯人探しが中心というわけではない不思議なストーリーだ。映画の中にいろいろなパズルや謎が出てくるが短いので分かり難い。映画でキリスト教史の概要はわかったので、本の方でも読んでみたくなった。画像は、関連サイトなどより。「類人猿ターザン」は、1932年のアメリカ映画。原題は、”Tarzan, the Ape Man”つまり、猿のような人間。類人猿というより、猿人訳した方がいいと思った。ターザンを主人公とした映画はこれ以前にもあったそうだが、ワイズ・ミュラー主演のこの映画がトーキーとしては初めてだそうだ。ライオン、トラ、カバ、ワニ、ゴリラなどの動物や、いくつかの種族の原住民が出演しており、78年も前の映画とは思えないほどいい出来である。子供の頃聞いて真似た「あああ~~~~~あ~~~あ」という叫び声を久しぶりに聞いて懐かしく思った。画像は、ビデオカバーより。
2010.01.15
コメント(0)
-

ハリーポッターと不死鳥の騎士団
今日は、午前中はビデオで「ハリーポッターと不死鳥の騎士団」を見て、午後は、俳句仲間と会合、その後その仲間と堀川戎へ行った。帰宅後は、ビデオで「ダビンチ・コード」を見た。ハリーポッターと不死鳥の騎士団は、2007年のイギリス映画で、シリーズ第5作目。第4作目の「炎のゴブレット」は先日見たばかりだが、第5作目は、これまでの作品とはちょっと違った感じがした。登場人物がハイティーンになったこともあろうが、これまでのような特撮を駆使したびっくりするようなすごい場面というものが少ないように思った。物語がどんどん複雑になって、夢と現実が一緒になったり、過去の人間と現在の人間が交錯したりして分かりにくい。監督がこれまでのアルフォンソ・キュアロンからデビッド・イェーツに変わったことも関係あるのだろう。画像は、関連サイトなどより。堀川戎は3日前とは様変わりして、参拝する人はまばら。それよりも境内に高々と積み上げられたごみの山。よく見ると、古い笹飾りや熊手や破魔矢など。むき出しのものから、段ボールの箱に入ったもの、ビニール袋に入ったものなど、夥しい量だ。今までどこに置いてあったのだろうか。そして、このごみはここで焼かれるわけではないと思われるので、一体どこへ持っていかれるのだろうか?
2010.01.14
コメント(0)
-

大阪城の鴨など
今日は、今年一番の寒い日となった。午前中は昨日習ったムービーメーカーの復習などをし、昼前から大阪城へ鴨を見に行った。帰りに天満橋付近で雪が降り始めた。帰宅後は、レンタルビデオ店で借りたビデオ2本を返しに行く前にもう一度見た。鳥は、北外堀、内堀などで、ユリカモメ、キンクロハジロ、ホシハジロ、ヒドリガモ、オナガガモなどが見られた。梅林の梅は10日ぶりに覗いてみたが、まだ殆ど咲いていなかった。今日は風も強く寒いとは思っていたが、天満橋付近に来たとき、雪が降りだした、積もるところまでは降らなかったが、やはり雪が降るのを見るのはいいものだ。年末にも降ったようだがこの時は家の中にいて見逃した。写真は、ユリカモメの飛翔と堀に浮く鴨たち、大阪城の石垣の木々の上を舞うユリカモメ、梅林の紅梅、ちらつく雪。ビデオは返却日を忘れていて、今日返すと延滞料を取られる。ついでだからと返す前にもう一度見てから返すことに決め、「ボニョ」と「ハリーポッター」の2本を夕方までかかって見直した。何回見ても新しい発見がある。2本を返しに行き、また、2本「ハリーポッター:不死鳥の騎士団」と「ダビンチ・コード」を借りて来た。
2010.01.13
コメント(0)
-

わいわいパソコン例会
今日は、午前中は雑用で過し、午後はわいわいパソコンの例会に参加した。例会のあとは新年会となった。わいわいパソコンの今日のテーマは、ムービーメーカーによる写真のスライドショーの作成。講師はSさん。WindowsXPの中の、Windowsムービーメーカーというソフトを使うのだ。こんなソフトが入っていることを私は知らなかったが、これを使うと、写真を順々に一枚ずつ映してくれる。写真と写真の間はいろいろな効果を使って切り替えることが出来る。また、写真に説明の文字を入れることも出来、タイトルやエンディングの文字も入れられるし、音楽も入れられる。各自あらかじめ準備して来た写真を使って、スライドショウを作ったあと、出来上がった作品を、順次見せ合った。自分の描いた絵を集めた人、イギリス旅行の写真を並べた人、ハイキングの写真、嵐山の写真、比叡山延暦寺の写真など、夫々立派なスライドショウに仕上げていた。写真は、実習中の参加者。教えているSさん、記念撮影、ムービーメーカーでのスライドショー作成画面。新年会は、近くの居酒屋で開催。3時間飲み、食べ、しゃべり、今年も楽しく仲良くやろうと誓いあった。写真はオフレコ。
2010.01.12
コメント(0)
-

「レオナール・フジタ展」を見る。
今日は、午前中は、年賀状パズルを解いたり、俳句を考えたりしながら過し、午後は、神戸大丸で開催されている「レオナール・フジタ展」を見に行った。展覧会をあと、南京町を散策し、大阪に帰ってから、堀川戎の残り福に行った。レオナール・フジタ(1886-1968)は、日本名藤田嗣治で、17歳のときフランスに渡りフランス画壇で活躍する。1940年に帰国するが、1949年再び渡仏、1955年には日本国籍を捨てフランス国籍を取得。1959年にカトリックの洗礼を受けレオナール・フジタとなる。1960年アトリエをランスに移し、1966年ランスに「平和の聖母礼拝堂」を建てる。今回の展覧会は、生誕140年を記念して一昨年から日本各地で開催されているもので、日本での初出展の作品が多い。特に、1928年に描かれ長い間行方不明になっていた壁画(4メートル4方の大キャンバスに描かれたもの)が1992年に見つかり修復の上来日した作品は見応えがある。平和の聖母礼拝堂内の絵やステンドグラスも全部、フジタが描いていて、その原画やステンドグラスの写真が部屋一杯に展示されていたのにも圧倒された。画像は、パンフレット、絵はがき、関連サイトなどより。花の洗礼(1959)、裸婦と猫(1923)、自画像(1922)、壁画:ライオンのいる構図(1928)、犬のいる構図部分(1928)、争闘2(1928)、フランスの冨部分(1960-61)、アトリエの実物大再現模型、平和の聖母礼拝堂外観の写真。南京町は、祭日の午後とあって、大勢の人出で賑わっていた。ちょっと面白い看板や置物などを写真に撮ったので紹介する。往復の阪神電車では、西宮戎の福笹を持った人をたくさん見かけたが、今日は、残り福の日。私は、自宅近所の堀川戎にお参りしてきた。画像は、堀川戎の様子。
2010.01.11
コメント(0)
-

「第三の男」を見る
今日は、午前中はテレビで、NHK俳句、日曜美術館などを見たり、昨日の鴨観察の写真の整理などをして過し、午後は一時外出し、帰宅後ビデオで映画「第三の男」を見た。その他、年賀状のしりとりパズルに挑戦した。「第三の男」は1949年のイギリス映画。先日ある会合で、この映画の話が出て、ラストシーンがよかったと言っていたが、私にはそのシーンが思い出せず、一度は見たはずの映画のなのに、思い出せないのを情けなく思っていた。先日、図書館で見かけて借りて来て今日見たのである。舞台は第2次大戦後4カ国に占領にされているオーストリアのウィーン。いきなり、一昨日、鶴見緑地公園で見たヨハンシュトラウス像が現われたのにはびっくりした。それほど、ウィーンを代表する景観の一つになっているのだろう。ストーリーは殆ど忘れていたが、なんとなく見たような気もするという程度。私は映画を見てもあまり感動しないからであろうか?親友だと思っていた男ハリーが実はペニシリンの闇ブローカーで大悪党であることを知った主人公のホリーが、正義のために友を裏切るというもの。そのラストシーンで、ハリーの愛人だったアンナは、ホリーの愛を受け入れることはなかった。画像は、関連サイトなどより。もう一つの発見は音楽。テーマ曲はアントン・カラスのチターでいい曲であるが、終盤近く、モンティのチャルダッシュが演奏されているのだ。この曲は聴いたことはあったが、その曲名と作曲者名を知ったのは、つい最近のことなのだ。(12月26日の谷本華子のバイオリン演奏会)そして、昨日、津軽三味線とピアノの競演でも、この曲を聴いたばかりなのだ。一昨日見たヨハンシュトラウス像をまた見て、昨日聴いたチャルダッシュをまた聴くとは、なんという偶然のいたずらであろうか!
2010.01.10
コメント(0)
-

鴨観察会とコンサート2つ
今日は、午前中は、淀川の鴨観察会に参加し、午後は、西宮のコンサート、夕方からは、大阪南港のコンサートを聴きに行った。淀川の鴨観察会は、大阪環境保護協会の主催で毎年1月初旬に開催されていて、私は5年ほど前から参加している。毎年寒い日になるが、今日は珍しく暖かい日になり、鴨の数は例年よりは少なかったものの、いろいろな種類を見ることができた。10時に阪神淀川駅前に集合し、数名のインストラクターの指導で、海老江干潟の鴨を中心に観察した。私の今日の収穫は、スズガモを見分けられるようになったこと。キンクロハジロに似ているが、背の色がうすく、頭から首の黒に緑色が混じっていること、風切り羽根がないことなどが違う。ハマシギ、シロチドリも沢山見ることができた。今日見た鳥は、下記35種。カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、オオバン、ユリカモメ、カモメ、セグロカモメ、イソシギ、シロチドリ、ハマシギ、トビ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、ウグイス、スズメ、セッカ、アオジ、オオジュリン、ハシブトガラス、クイナ。写真は、開会の挨拶とインストラクターの紹介、阪神淀川鉄橋、鴨の群、同、スズガモ、カンムリカイツブリ、ダイサギ、ハマシギ、シロチドリ。観察会は、12時15分に終わり、阪神淀川駅から西宮に着いたのは、12時50分だった。市民ホールの食堂で大急ぎで昼食を済ませ、13時15分の開演にぎりぎり間に合った。西宮の震災復興祈念コンサートを聴くのはこれで5度目。今日のプログラムは、弥月大次の津軽三味線、尾崎江利子のピアノの競演という珍しいものだった。前半はオリジナル曲が披露されたが、私は後半のポピュラー曲の方が心地よく聴けた。後半の曲は、ガーシュインメドレー、シングシングシング、ジュピター、情熱大陸など、アンコール曲は、こきりこ節、剣の舞、チャルダッシュなど。演奏は、二人のほか、パーカッションの池田安友子、津軽三味線・ベースギターの西村孝樹、ドラムの井刈温子などが共演、津軽三味線だけの演奏や、パーカッションだけの演奏もあり、パラエティに富んだ内容で、十分に楽しむことができた。一番盛り上がったのは、アンコールの3曲。画像は、プログラムと演奏風景。津軽三味線とピアノのコンサートを終え、梅田に戻ったのは、16時少し前。地下鉄で南港のATCビルの会場に着いたのは、開演の15分前の4時45分だった。ここのサンセットホールでコンサートを聴くのはこれで5回目。今日の出演は、琴の片岡リサと尺八の星田一山。題名は「春の海~新春に聴く和の心~」。「春の海」をはじめアンコール曲を含めて5曲が演奏された。その内、「汽車ごっこ」は琴の独奏、「手鞠」は琴の弾き語り、「本曲木枯」は尺八の独奏、アンコール曲の「千の風になって」は尺八との合奏で琴の弾き語りだった。演奏の間にトークが入り、琴の構造、琴の弾き方、右手・左手の使い方、歌も歌うことがあること、尺八の音(息が漏れたような)の特徴、譜面は流儀によって違うことなど、興味深い話しを聴くことができた。画像は、ポスター、プログラムなどより。コンサートのあとは、ATC3階の和風健康食レストラン「ETSU」でビールを飲みながら夕食を摂った。夕食後、酔いを醒ますため海岸に出て、海と船と星空を眺めていると、ロマンティックな気分になった。今日は、鴨観察会とコンサート2つのはしご。今年初めての長時間の外出となり、充実した一日となった。心地よい疲れを感じ、いつもより早目に床に就いた。
2010.01.09
コメント(0)
-

鶴見緑地公園大池の鴨
今日は、午前中は、英クロを解いたり、年賀状パズルを考えたりして過し、午後からは、暖かでいいお天気に誘われ、鶴見緑地へ鴨を見に行った。鴨を見たあと、池を一周し、国際庭園でヨハンシュトラウスの銅像を見て来た。大池には鴨とユリカモメが沢山来ていた。どちらも数百羽、ほぼ同数くらいいたであろう。鴨は90%以上がヒドリガモ、10%くらいがオナガガモ、あとは、ホシハジロが少しと名前のはっきりしない鴨がいた。人が餌をやるたびに、その人の方に集まって来ていた。写真は、大池全景、近景、鴨とユリカモメの群れ、オナガガモ、ホシハジロ、ヒドリガモの雌雄、ユリカモメの着水、ハクセキレイ、雀の群れヨハンシュトラウスの銅像は、1990年の花博のとき、国際庭園のオーストリア館に設置された。博覧会終了後も据置かれ、当初は黒色だった塗り色は1998年金色に塗替えられたそうだが*(コメント参照)、その後年代とともに色は褪せ緑青が出ているが、その姿は変わらない。下の写真は今日撮ったもの。実は私はこの銅像の存在を知らなかったのだが、会社OBのK氏がその写真と音楽をYou-tubeに載せていることを知り、それを思い出して今日見に行ったものである。K氏のYou-Tubeのサイトはこちら。「美しく碧きドナウ」が聴ける。
2010.01.08
コメント(2)
-

ユリカモメ
今日は、午前中は、昨日見た「ハリーポッター4」のビデオを英語字幕で見たり、字幕なしで見たりしながら過し、午後は、俳句仲間2人と昼食、喫茶をともにしながら話し込んだ。夕方からは、俳句仲間から貸してもらった健康雑誌で、高血圧、狭心症などの記事を読んだり、年賀状パズルの未解決問題の続きを考えたりした。俳句仲間とは、俳句雑誌「築港」のこと、休会中の俳句仲間のこと、新聞俳句のこと、摩耶山の新しい誓子句碑のこと、音楽のこと、豆腐ようのこと、写真のこと、旅行計画のこと、スキー板のことなどを話し、帰路、藍・柿渋染めの店に寄ってきれいな作品を見た。今日は写真を撮らなかったので、先日(3日に)撮ったユリカモメの写真を載せる。
2010.01.07
コメント(0)
-

ハリーポッター:炎のゴブレット
今日は、一日中在宅で、You-Tubeで、主として古今亭志ん朝の落語を聴きながら過した。夜は、ビデオで映画「ハリーポッター:炎のゴブレット」を見た。聴いた落語は、大工調べ、風呂敷、愛宕山、元犬、狸賽、たがや、文七元結、冨久、二番煎じ、首提灯、干物箱。志ん朝の落語は聴きやすく、江戸っ子口調がスピード感があって心地よい。内容的にも人情味のある話が多く、一日退屈せずに聴くことがでした。大工調べ 46分 家賃のカタに大工道具を家主に取られた件で、人情味のある裁き。風呂敷 16分 間男を隠した女房を助けるため風呂敷で旦那の顔を覆う。「その男の顔が見たい」愛宕山 30分 愛宕山のかわらけ投げで投げた小判を取りに行き「小判は忘れて来ました」元犬 14分 犬が信心を末、人間になり「もとは居ぬか」「はい今朝人間になりました」狸賽 15分 狸が恩返しにさいころに化けばくちに使われる。梅で5の目が出るはずが…たがや 27分 たがやが橋の上で侍たちと鉢合わせ。侍たちをやっつけて、たが~や~」文七元結 75分 貧乏だがお人好しの左官が、番頭文七を身投げから助けた話し。冨久 22分 久蔵が富札を当て、「これで方々におハラいが出来ます」二番煎じ 60分 煎じ薬と言って飲んでいた酒がなくなり「次までに二番を煎じてをけ」首提灯 25分 首を切られたことに気付かず、首を持ち上げて「八五郎でござんす」干物箱 30分 丁稚の善に自分の身代りを頼み、「善公は器用だ、親父そっくり」ハリーポッターはシリーズの4作目。どんどん魔法の世界が広がって行く感じ。今回は川の中にもカメラが入っている。2時間40分の大作。今回DVDを借りて、面白いことを発見した。普通、外国映画を映画館で見る場合、字幕(1)が付いている。テレビで放映される場合や市販ビデオでは、日本語の吹き替え(2)になることもある。DVDでは、1、2のどちらでも選べるようになっているほか、次のようなこともできるのだ。3.英語だけで見る。4.英語の音声に英語の字幕を付けて見る。5.日本語の音声に英語の字幕を付けて見る。今回は、先ず1で見て、次に4で見てみた。そのあと3で見ようとしたが、殆ど聞き取れない。画像は、関連サイトより。
2010.01.06
コメント(0)
-

崖の上のポニョ
今日は、午前中は写真の整理をして過し、午後は図書館とビデオレンタルショップへ行き、帰宅後はビデオを見たり、You-Tubeで落語を聴いたりして過した。図書館で借りたのは、「類人猿ターザン」と「第三の男」のビデオ、「コジファンテュッテ」と「志ん生 火焔太鼓、唐茄子屋政談」のCD、「俳句の作り方」金子兜太と「知っておきたいこの一句」黛まどかと「句会の楽しみ」俳句別冊の本3冊。ビデオショップで借りたのは、「崖の上のポニョ」と「ハリーポッターと炎のゴブレット」のDVD。帰宅後は、まず、「崖の上のポニョ」を見、次いで、志ん生の落語を聴き、その後は、You-Tubeで、志ん生の黄金餅、志ん朝の井戸の茶碗、幾代餅、大山詣りなどを聴いた。落語の中では、井戸の茶碗が一番いい話だと思った。画像は、崖の上のポニョより。
2010.01.05
コメント(0)
-

映画「キングコング」(1933)を見る
今日は、一日中在宅で、2222の数楽の問題を考えたり、年賀パズルを解いたりしながら過した。午後は、ビデオで映画「キングコング」の1933年版を見た。2222、22222の数楽は、来月やって来る平成22年2月2日と同22日の並び数日に備えて準備しているもので、昨年の11月初めから始めてやっと今日完成した。まだよりよい解もあるかも知れないが、一応これを第一案とする。映画「キングコング」は1933年のアメリカ映画。子供のときに見たかも知れないが忘れてしまった。キングコングシリーズはその後も5~6本作られていて、「キングコング対ゴジラ」は見た覚えがある。第1作のこの映画は72年経った2005年に再制作されたが、今回見たのはオリジナルのモノクロ版。特撮が駆使されていて今見ても、十分に迫力がある。1時間40分のうち、キングコングが登場するまでの40分は退屈な映画だと思ったが、後半の1時間は手に汗を握るアクションシーンの連続だった。画像は、ビデオカバーなどより。
2010.01.04
コメント(0)
-

OAPのイルミネーション
今日は、午前中は、テレビで美術番組「韓国と日本の国宝」を見たり音楽番組「ウィーンフィル」を聴いたりしながら過ごし、午後からは介護施設に義母を訪ねた。義母は、訪れるたびに認知症がひどくなっている気がする。でも、風邪も引かず食欲も旺盛で歩行器で歩くこともでき、身体は元気である。今日の写真は、帰りの撮ったOAPの夜のイルミネーション。クリスマスが終っても4月の花見シーズンまで点灯が続けられるようだ。
2010.01.03
コメント(0)
-

大阪城梅園の梅
今日は午前中は、年賀状パズルを解いたり、2222の数楽を考えたりしながら過し、午後はいい天気に誘われて、一時、大阪城梅園の梅の開き具合を見に行った。帰宅後もパズル解きで過した。大阪城梅林にはいろいろな種類の梅があり、早いものは一月初めから開き始める。しかし今年は遅いようで、白梅が2~3本、紅梅が1本だけ、開花している木を見つけた。蝋梅は咲き始めていて見頃も近そうだ。写真は、蝋梅、蝋梅と大阪城、白梅、同、紅梅、同、内堀のユリカモメ(極楽橋)、梅園からの大阪城、水仙と大阪城
2010.01.02
コメント(0)
-

謹賀新年
今日から2010年、平成22年が始まった。皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。下記は、私の年賀状。左:パズル家向け、右:郵趣家向け。今日は、雑煮とお節とお屠蘇で新年を祝ったあと、新聞に目を通し、年賀状に目を通し、未差出の数人に返事を書いたあと、大阪天満宮に初詣に行った。寒い元日となったが人出はいつもの年と同じくらい込んでいて、本殿の前にはいけなかった。横の方からお賽銭を投げてお参りをし、破魔矢を買って帰った。帰りにOAPの喫茶店で寛いだ。写真は、大阪天満宮の模様、絵馬は殆ど100%合格祈願のもの、繁昌亭も繁盛している帰宅後は、ホームページの更新をし、毎年の年中行事である仲間からのパズル年賀状の問題を解きにかかった。いろいろなジャンルの問題があり、それぞれに難しくいつも3日間はパズル漬けになってしまう。
2010.01.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…
- (2025-11-14 14:35:53)
-
-
-
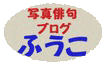
- 写真俳句ブログ
- 夕焼けチャイム fu
- (2025-11-14 14:28:22)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ☆そんなつながりも
- (2025-11-14 10:50:04)
-







