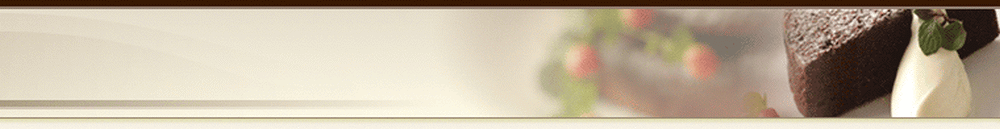異性化糖とは?
日本スターチ・糖化工業会
異性化糖の自己紹介
「異性化糖」と聞いて、食品関係以外の人々にはあまり馴染みがありませんが、砂糖と同じ天然甘味料で、主な原料はとうもろこしから作ったでん粉(コーンスターチ)です。
まず、でん粉を加水分解してぶどう糖を作り、その一部を酵素で果糖に「異性化(変換)」したものがその中身で、砂糖のように粉の形ではなく、液糖として使用します。「異性化」とは、化学的には「分子の原子数を変えないで、分子内の結合状態を変える」ことをいいますが、専門家以外に分かるはずもなく、異性化糖の理解が一般化しない大きな理由となっています。
果糖やぶどう糖等の構造式をご覧いただきますが、念のために申し添えますと、果糖とぶどう糖が異性化糖の主な「成分」であって、両者が化学的に繋がっているのではありません。ちなみに、ショ糖(砂糖)を分解すると果糖とぶどう糖になります。
また、「異性化」には各種の「酵素」が重要な働きをしますので、ご参考までに酵素名とその働きをお示しいたします。(表1参照)
異性化糖は天然甘味料として多くの食品に利用され、ジュース缶や清涼飲料缶の原料欄に「異性化糖」と表示されることもありますが、多くは「ぶどう糖果糖液糖」または「果糖ぶどう糖液糖」と表示されていますので、機会がありましたら確かめて下さい。
表示の「ぶどう糖」と「果糖」の並び順のちがいは、1980年(昭和55年)に日本農林規格(JAS規格)で果糖が50%未満を「ぶどう糖果糖液糖」に、50%以上を「果糖ぶどう糖液糖」と決定したためです。
異性化糖の成分は、ぶどう糖と果糖とごく少量のオリゴ糖ですので、その表記は成分の多い方からするという、ごく当たり前の命名法でしょう。
また、後年、90%以上を「高果糖液糖」として新たにJAS規格に追加され、その他にも異性化糖を上回らない量の砂糖との混合液糖(「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」と「砂糖混合果糖ぶどう糖液糖」)も多く製造されています。(表2参照)
「ぶどう糖を果糖に異性化」して名付けられた「異性化糖」ですが、その歴史が浅いことと、使用先のほとんどが食品メーカー向け原料であり、消費者が直接に使うことがないため馴染みが薄く、そのためか何か変な物質のように思われ、ときたまですが「心配だから、どんなものか教えろ」とのご質問の電話があります。あくまでも一般的なことですが、原料欄に各種用途用として表記されている物質名はときに長ったらしくて難しくて、代替できる適訳の日本名もないこともあって、何か体に良くないもののように誤解されがちですが、製造者側としては、できるだけ正確に表記して正しく理解していただきたい結果なのです。
ちなみに、アメリカでは異性化糖の原料は全部コーンスターチですから、HFCS(High-fractose corn syrap)と称しています。 異性化液糖の良さは「キレのよい味質」で、温度が低くなるほど甘みが強くなる性質から、冷菓・乳飲料・清涼飲料等に幅広く使われています。(表3参照)
その他の長所としては、高濃度でも結晶性が少なくて安定であり、さらに浸透圧が高くて防黴効果が大きく、また、吸湿性が高いので保水性や保湿性が求められる製品向きであります。
それに、粘性が少なくサラッとしているために取り扱いが容易で、タンクローリーで大量に運送したり、タンクに保存できることも大きな長所です。
異性化糖は低温での利用に向いていますが、反対に成分の果糖が熱に弱く、加熱調理すると着色するのが欠点です。(勿論、この着色性を利用することもあります)
そのほかに果糖には果物、特に柑橘系の香りを引き立てる効果もあり、このため果物の缶詰やジュース等に多く利用されています。 高果糖液糖は、アスパルテーム(現在、テレビCMで有名なアミノ酸から作られた合成甘味料)やステビア(ステビアの葉から抽出した甘味料)などの甘味料と併用して低カロリー飲料に利用され、やはり味質の良いのが好まれています。
α-アミラーゼ α-1、4結合を任意の位置で切断する。でん粉の液化、すなわち、でん粉糊液の粘度低下のための部分的加水分解に用いられる。液化酵素と称する。
β-アミラーゼ α-1、4結合をでん粉分子の末端から麦芽糖単位で切断する。麦芽糖あるいはハイマルと称している高マルトース水あめの製造に用いられる。糖化酵素と称する。
グルコアミラーゼ ぶどう糖への完全加水分解に用いられる。糖化酵素と称する。
グルコースイソメラーゼ(イソアミラーゼ) グルコース(ぶどう糖)のフルクトース(果糖)への転化、すなわち異性化糖の製造に用いられる。異性化酵素を称する。
プルラナーゼ アミロペクチンのα-1、6結合の加水分解に用いられる。枝切り酵素と称する。
第1条 この規格は、異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖に適用する。
(定義)
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
異性化液糖 でん粉をアミラーゼ等の酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を、グルコースイソメラーゼ又はアルカリにより異性化したぶどう糖又は果糖を主成分とする液状の糖であって、果糖含有率(糖のうちの果糖の割合をいう。以下同じ。)が50%未満のもの(以下「ぶどう糖果糖液糖」という。)、50%以上90%未満のもの(以下「果糖ぶどう糖液糖」という。)及び90%以上のもの(以下「高果糖液糖」という。)をいう。
砂糖混合異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖に当該ぶどう糖果糖液糖の糖の量を超えない量の砂糖を加えたもの(以下「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」という。)、果糖ぶどう糖液糖に当該果糖ぶどう糖液糖の糖の量を超えない量の砂糖を加えたもの(以下「砂糖混合果糖ぶどう糖液糖」という。)及び高果糖液糖に当該高果糖液糖の糖の量を超えない量の砂糖を加えたもの(以下「砂糖混合高果糖液糖」という。)をいう。
(異性化液糖の規格)
第3条 異性化液糖の規格は、次のとおりとする。
区分 基準
品質 水分 30%以下であること。
糖分 70%以上であること。
灰分 0.1%以下であること。
果糖含有率 35%以上であり、かつ、表示含有率に適合していること。
糖のうちのぶどう糖及び果糖以外の還元糖の割合 果糖含有率が40%未満のものにあっては15%以下、40%以上50%未満のものにあっては8%以下、50%以上のものにあっては6%以下であること。
水素イオン濃度 ph3.5以上5.5以下であること。
着色度 第5条に規定する着色度の測定において0.20以下であること。
濁度 第5条に規定する濁度の測定において0.15以下であること。
原材料 でん粉以外のものを使用していないこと。
異物 混入していないこと。
内容量 表示重量に適合していること。
表3 異性化糖の用途別販売量の推移
(日本スターチ・糖化工業会調べ)
異性化糖について (2)
日本スターチ・糖化工業会
~ 異性化糖の原料と製造工程 ~
異性化糖の原料
技術の進歩により、異性化糖・ぶどう糖・水あめの原料はでん粉であれば何でもよく、昔からの国内産の甘藷でん粉や馬鈴薯でん粉も多く利用されていて、現在、それらの振興のために、当工業会が一定量の引き取り義務がある制度下にあります。
具体的には、国内産でん粉を1トン購入することにより、12トンのコーンスターチを製造する原料とうもろこし18トンを関税無税で輸入できます。(原料とうもろこしの「でん粉歩留り」は一般的に66%ですので、12÷0.66=約18トン)
トウモロコシの構成など
原料としては他にタイのタピオカでん粉等もありますが、コーンスターチは「価格が安い、年間を通じて入手できる、貯蔵安定性が高い、コーン油やコーングルテンミール等の副産物の用途がある」等の理由で現在、主流はコーンスターチとなっています。原料とうもろこしは主にアメリカや南アフリカ及び中国から輸入していますが、最近はブラジルやアルゼンチンからも輸入しています。
とうもろこしは、日本では家畜の飼料用やコーンスターチ用等として、世界で最も生産量の多い種類のデント種(馬歯種)が年間一千六百万トン程度輸入されています。
ただし、(馬歯種)と表記されるものの、正しくは「とうもろこしが乾燥すると軟質澱粉部と呼ばれる部分が収縮して陥没して、凹みDentを生じる」ためであって、「馬の歯(Dent)のようだから」というのは、単なる連想(または誤訳)からきているようです。よく、神社のお祭などで丸かじりしたり、缶詰に入っているのはスイートコーン種で、デント種に比べるとでん粉が少なく、糖分が多くなっています。とうもろこしの色は黄色だけと思われがちですが、白色種もあり、主に南アフリカで栽培され、一般的にでん粉価が黄色種より高いためコーンスターチにも使用しています。しかし、南アフリカでの生産量が気候条件により豊凶が激しくて、安定輸入が困難です。白色種でん粉の使用先は、コーンスターチ用の他にクリーニングで使用する糊、食品の取り粉、穀粉用、医薬向けが少量あります。
ホワイトコーン(左) イエローコーン(右)
異性化糖の工場と製造工程
とうもろこしの輸入風景 異性化糖の工場
原料の大半が外国産とうもろこしですので、現在では輸入に便利なように多くの製造企業が臨海部、特に古くから甘藷でん粉の生産地でもあった東海地方に立地しています。
ここで、コーンスターチと異性化糖の簡単な製造工程をご覧いただきますが、実際の作業はほとんど自動化されており、工場内は多くのタンクとその間をパイプが繋がっているだけのきわめて殺風景で、そのためか地元の小学生の社会見学ではあまり人気がありません。
異性化糖やぶどう糖は砂糖と異なり歴史も浅く、また工場で生産されますから、砂糖のように沖縄の「さとうきび畑」の映像から原料に遡っての具体的なイメージもありません。ましてや、その原料がでん粉であるとはほとんど知られていなくて、さらに果糖となると、ぶどう糖を原料にしているということはもっと知られていません。何しろ「果糖」ですから、一目見ればその意味がすぐに分かり、その原料は当然何かの「果物だろう」と思われるのが普通です。
果糖は天然にある糖の中では最も甘くて、条件の違いにより比較が非常に難しいのですが、甘味度はショ糖(砂糖)の1.2~1.8倍(『でん粉科学の事典』朝倉書房 2003年)といわれ、果物や蜂蜜の中に多く存在して、別名フルーツシュガーと呼ばれています。
そして、人の体内で吸収されエネルギーになる過程でインシュリンを必要としないために、糖尿病に対してリスクが少ないといわれています。
また、果糖はぶどう糖よりも速くエネルギーとして利用されますから、脂肪として組織に貯蔵される機会が少なく、肥満に対してもリスクが少ないともいわれています。
ただし、最近は各種甘味料の過剰摂取を心配する声もありますので、何事もほどほどが良いようです。
異性化糖について (3)
日本スターチ・糖化工業会
異性化糖の工業生産の歴史
異性化糖の誕生史を探りますと、日本での工業生産は1965年(昭和40年)で参松工業が世界に先駆けて生産しました。それまで通産省工業技術院発酵研究所(当時)と農林水産省食糧研究所(当時)が、でん粉を原料にしたぶどう糖を、さらに砂糖のように甘い果糖に転換することを競って研究していました。
当時の歴史を回顧しますと、太平洋戦争後の食糧難を緩和するために甘藷や馬鈴薯の生産が奨励され、その後事情が緩和されると余ったイモからでん粉を造りました。さらにでん粉も政府倉庫に山積みになって保管料に耐えきれなくなると、ぶどう糖の製造を奨励しました。当時砂糖が高価で輸入のための外貨も不足していたために、代替品として果糖の開発が期待されたのです。より効率的な酵素の発見競争があり、結果的に通産省工業技術院発酵研究所と参松工業との協力が実を結んで、異性化糖の工業生産技術が開発され、以後さまざまな改良を加えて広く普及しています。ちなみに、開発期前後の両研究所の競争は有名で、その回顧記事が読売新聞2003年9月21日付「編集委員が読む」欄に記載されています。
異性化糖は、発明からしばらくは評価が高くなかったのですが、コカ・コーラ社がまずアメリカで、次いで日本で甘味料として採用してから広く普及しました。
余談ですが、ヨーロッパ諸国では異性化糖はアメリカで発明されたと強固に誤解しているようで、2002年に当工業会から3名の技術者を、CODEX第24回分析・サンプリング部会に日本政府代表団の技術アドバイザーとして派遣しましたが、その後でヨーロッパの澱粉工業会(aAc)で意見交換した際にも、専門家であるはずの出席者もアメリカ発明説を信じていて、日本側が懸命に説明しても容易には信じてもらえなかったそうです。
異性化糖の前史というか、なぜ液糖が必要とされたかについては『砂糖類情報』2000年9月号59頁に、1920年代のアメリカの禁酒法時代にまでさかのぼって「液糖(異性化糖)はどうして生まれたのか?」(当工業会作成)と題して掲載されていますので、ご興味がありましたらご覧下さい。
異性化糖は、日本での数少ない大きな発明の一つ(先述の読売新聞の記事もそのことを強調しています)ですが、当業界が望むほどには消費者の認知度は高くなく、一層の広報に努めるつもりです。
(この文の多くの資料は、『糖の散歩道』糖質事業開発協議会編 三水社1993年から引用させていただきました。)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- 美容院に歯医者さんに忙しいぞ。
- (2025-11-20 06:54:24)
-
-
-

- 入浴後の体重
- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…
- (2025-06-30 17:00:00)
-
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
© Rakuten Group, Inc.