第2章-1(完成!)
第二章 デビューへの道のり
■合言葉は「わたしの歌を聞け」
とうとう初日を迎えた。6月11日。私はこの日のことを生涯わすれないだろう。夜7時半。教室に、初めにやってきたのは、朝倉緑さん。初めての場所へ来る不安と笑顔を絶やさないサービス精神が一度に彼女を襲ったかのように交互に表情が変化する。にこやかに「こんばんわあ」不安げに「ここはどこ?」にこやかに「歌を歌うの?」不安げに「誰が?」にこやかに「あっそう」不安げに「純子ちゃんも来る?」にこやかに「あっそう」。「どこで?」「何をするの?」「誰が?」「ここはどこ?」…これらの質問とその回答が延々と続いた。誰でも同じことだが、今日何があるのかは、やってみないとわからないのだ。早く安心してもらわなければならない。
何分か後に遅れて登場した家入純子さんを見て、緑さんはやっと落ち着く。純子さんは緑さんより学年でいうと一つ上で、養護学校を卒業したばかり。久し振りの再会に緑さんと抱き合って喜んでいる。ジェスチャーが大きく、何か伝えたい気持ちに溢れている大きな目。私も引き寄せられるようにして近づいていった。だが純子さん、身体を触られるのが嫌いらしい。激しく抵抗して逃げていく。私は受け入れられるだろうか?
7時半を開始時刻と決めたのに、8時を回ってもこの二人しか来ない。男性はどうした?
玄関が開く。男性二人の登場だ。岡田拓也君と村内貞雄君。拓也君は自分が行きたいといって申し出た、と聞いている。遅くなったのは、一緒に行くはずの貞雄君が「行かない」と言い張ったから。貞雄君は母親が「行かせたい」といって申し込んだらしい。今日は半ば強引に連れて来られた。貞雄君、最初から「いや」を連発している。これを聞いたからには、今日はピシっと決めなくてはならない。
まず自己紹介。私は舌を噛みそうな「クスハラカズヨ」という自分の名前を省略して、ペンネームの「くすか」を名乗ることにした。
「くすかといいます。これからみなさんと一緒に歌を楽しく歌っていきたいと思います。イエーイ!」
みんなが拍手した。すると、
「私もする」
と、緑さんが一番に自己紹介をしたがった。彼らはこんなことは馴れているらしい。全員が、それぞれ自分をアピール。言うだけでなく、人の発表もとてもよく聞く。学校で一緒だったこともあるからか、それぞれに非常に仲が良い。特に貞雄君は、拓也君のことを「先輩」と呼んで敬意を表している。同じ作業所の先輩なのだ。拓也君が21歳。貞雄君も21歳。純子さん、19歳。緑さんが17歳。四人とも、三股町内に住んでいる。
さあ、この四人と私とでこれから歌を歌っていくことになる。合言葉を私は用意していた。「わたしの歌を聞け!」だ。初めての場所で、初対面の人からいきなり「歌え」「声を出せ」と言われても出ないのが普通だ。練習ではなく、大勢の前で歌う場面では、余計に強い心が必要になってくる。その時「聞いてください」ではなく、「わたしの歌を聞け!」くらいの強い気持ちを持っておくことを、これから何度も何度も話していこうと考えていた。だから、この合言葉なのだ。貞雄君にも、それはすんなりと受け入れられた。そんなこと当たり前だ、という顔で。みんなでジェスチャーを交えて、何度も大きな声で言ってみた。
「わたしの歌を聞け!わたしの歌を聞け!わたしの歌を聞けー!」
みんなで声を合わせると、心が強くなった気がする。これから毎回言うことにしよう。
「マイ・セレナーデ」のCDをかけた。垢抜けたオープニングにみんなが顔を合わせてにっこりする。ウキウキする曲だと直感した目の輝きだ。これに合わせて、身体を動かすエクササイズ。まず私が踊る、手を叩く、走り回る。これには、みんなとても嬉しそうに乗ってきた。特に、緑さんと貞雄君。私と同じように好き勝手に身体を動かしている。そして、それを見て笑う純子さん。音楽が好きだからと言って、リズムに合わせて動くのが好きかどうかは人によって違う。でも、彼らはみな、好きそうだ。嫌だったら動かないだろう。貞雄君なんかは、アドリブでカッコイイ振りをつけている。お母さんたちも参加してくれて、みんな息切れしながら曲が終わった。
呼吸を整えるために、座って一休み。事前に選んでおいた歌4曲を聴く。その中で「風になりたい」に一番反応があった。「カッコイイ~!」と。でも、難しそうだ。声が出ない。4人で歌って楽しいだろうか。
「みんなは何の歌が歌いたいですか」
と質問してみた。すぐに純子さんが何か言った。
「えっ?」
ごめんなさい。私にはわからない。純子さんのお母さんがすかさず
「スマップの『世界に一つだけの花』と言っています」
と教えてくれた。うわっ!感動だ。すぐに言えるほど歌いたい歌があるって。みんなも賛成してくれた。よし!とりあえず練習する曲が決まった。そうか、スマップだったのか。ここ何週間もの呪縛から解き放たれたような気持ちだった。次からはこの曲を練習するので、家で毎日聞いて練習してくるようにという宿題を出した。みんな大喜びで手を叩いた。宿題を出してこんなに大喜びされたのは初めての経験だった。
おしまいに『くもんの童謡カード』30枚を床に広げて、童謡のCDをランダムにかける。歌に合う絵カードを拾う「かるた取り」だ。知っている歌がかかるとついつい大きな声で歌う純子さん。たくさんのカードをとる拓也君。悔しがる緑さん。腕組みをして構える貞雄君。みんな真剣だ。これは楽しい。みんな童謡がとても好きらしい。
あんなに心配顔をしていた緑さんも
「明日も来たい」
と言ってくれた。とても満足した顔の4人、そしてキャアキャア喜ぶお母さん達を見て、私が一番ほっとしたことは言うまでもない。興奮しすぎて眠れなかったほどだ。
そうそう、会の名前。4人で始まったその夜。この4人を見て、一人一人が違いすぎること。お祭りみたいに賑やかだったこと。このイメージから「カーニバル」と付けることにした。4人でカーニバルとは、よく付けたものだと思う。
■初のオリジナル曲「SMILE」誕生
初日の練習が終わると、すぐ私は電話を入れた。相手は、後にカーニバルの強力なサポートメンバーとなる小山貴也さん。音楽を通じた数年来の友人である。この歌の会が始まることを話してあった。
「この間話した歌の会ね、今日だったの。オリジナル曲を作りたいの。詞はだれかに頼んでください。リズムはレゲエで。とにかく2週間後にはみんなに手渡したいから、すぐ作って」
練習が終わり、みんな今帰ったばかり。興奮しきっている私のこの言い方では、彼が理解するどころではなかった。電話の向こうでは私の勢いに只々驚いている様子。
「落ち着いてください。そんなぽんぽん言わないでください」
私は今度は同じ内容をゆっくり話した。それでも何かいつもと違う私の勢い。有無を言わせない何か。小山さんもそれを感じていた。
「はい、わかりました。2週間後にデモテープが出来ていればいいんですね」
彼は私を静めるかのように言った。だが、私の勢いは止まらなかった。彼に追い討ちをかける一言を言ってしまったのだ。
「そう。引き受けた以上は、絶対に約束は守ってください」
と。しかし、彼は途方もないのんびり屋。すぐ作る筈がない。今までがそうだったから。ところが、3日後に彼の方から連絡があった。
「大体できたんだけど、これでいいかどうか聞きに来て欲しい」
「えっ、本当にできたの?」
「がんばりましたよ。だって作らなきゃ大変なことになるって思いましたから」
これには驚いた。こんなことは初めてだ。
彼のようにポップス音楽やフォークに通じている人に、私はこれまでお目にかかったことがない。私の数倍も音楽好きで、並はずれた歌唱力と声量を持つ。自力で音楽を勉強し、作曲も編曲もできる。ギターも一人でマスターした。私はこれまでに数曲、作ってもらったことがある。彼が作るメロディーは、どこか懐かしく美しい。「こういう歌を」と注文すれば、かなりいい確率でドンピシャリのものを作ってくる。カーニバルのみんなと是が非でも引き合わせたい人物だ。
三股町の隣町、山之口町にある小山家を訪問すると、小山さんは庭仕事の最中だった。部屋には小山さんの友人の中井功さんがいた。彼もまた、大の音楽好きで自分の曲を作詞・作曲して歌ってCDにするという活動をしている人だ。今回の作詞はこの中井さんがしてくれた。
「会ったこともないんで、イメージがわかんなくて」
と言いながらも、パソコンできれいに印字された歌詞を見せてくれた。
「気に入らないところがあったら、直しますよ。喜んでもらえた方がいいから」
なんとも有難い言葉だ。
新曲のタイトルは「SMILE」。
人生なんか 何でもいい
好きなことして暮らせばいい
仕事なんか 何でもいい
一生懸命 働けばいい
くよくよすんなよ 人生は 何度だってやり直し利くんだよ
悩んでたって しょうがない 落ち込んだって仕方ないだろう
涙なんか流さないで 笑いながら過ごそうよ
僕たち 未来があるんだ 明日に向かって走ろうよ
この一番の歌詞を読んで驚いた。「好きなことして暮らせばいい」「一生懸命働けばいい」 この2行は、カーニバルのメッセージに十分なりうる。これはスゴイ!だらけたようなレゲエのリズムとも合うかもしれない。中井さんは2番の歌詞が1行空白だったので、まだ産みの苦しみの中にいた。しかし、1番の歌詞だけで私はもう合格!と思った。
さて、曲はどうなのだろう?作業を終えて部屋に戻ってきた小山さんに、ギターで演奏してもらう。彼の作る曲はポップス。なのに、詞を見てから曲をつけていく。
「まるで演歌みたい」
と笑われても、ハハハと笑い飛ばしながらメロディーを入れていく。ほとんど即興である。私にとっては貴重な人だ。先に曲ができてしまうと、詞に制約ができてしまうから。今回彼はこの詞の字数をどう処理していくのだろう?興味津々で耳を傾けた。ギターでのストロークでは、レゲエという感じが今ひとつしなかったが、覚えやすいメロディーのいい曲だ。「涙なんか」以降のサビで盛り上がって、全体的に明るいイメージが強調された仕上がりだ。編曲がまた楽しみになってきた。この日、2番の歌詞もできあがり、カーニバル初のオリジナル曲は異例の速さで完成した。
■ステージを目指しませんか?
第2回の練習日。楽しい歌の会を確保することが私の役目。初日から、あの楽しさだ。私はずいぶん気が楽になっていた。具体的に彼らのイメージがつかめると、やることは一気に増える。今日は字が苦手な人のために絵カードでメニューを説明しよう。発声練習を今日から始めるぞ。そうそう、「世界に一つだけの花」の歌詞カード。拡大印刷してみんなで1枚を見ることにすれば、気持ちを合わせやすいかもしれない。
自宅で楽しく準備をしている私に、朝倉さんから少々興奮気味の連絡が入る。
「今日、女性のメンバーが二人増えますよ」
「うん、うん、OK,OK」
「三股町役場の広報の取材がこれから毎回入るんですよ」
「ん?まあ、いいでしょう」
「もう一つあるんですよ。役場の福祉保健課から『10月の社会福祉大会で、アトラクションとして発表しませんか?』と言われて、私は『はい。出ます』と言ったのよ。いいでしょ、やりましょう」
私の目の前に薄暗く、ただっ広いステージが広がった。そこに声もまだよく出ない4人がマイクの前に。音楽が始まる。400席の会場は満席のお客様。聞き取れない歌詞もところどころある。歌が終わる。拍手が沸き起こる。それはおそらく同情の拍手かもしれない。よくがんばってるねえ~みたいな。
いやだ、いやだ。いくら私がプロでないからといって、そんなステージ……いやだ。でも、もう受けてしまったのだ。親はわが子がステージで歌う姿を見たいのだ。はあ?あと4ヶ月?今日の練習を入れて、あと8回の練習でそのステージまで持って行かなくてはならないのか!
このカーニバルは三股町社会福祉協議会のボランティア団体として始まった。そして、今回の話は役場から。そういう場を作ってあげれば、練習にも励みになるにちがいない。そう考えるのはもっともだ。たくさんの拍手。これもあたりまえだ。用意された場所は社会福祉大会。きっと惨憺たるものであっても彼らには「よかったねえ」と賞賛の拍手が来る。しかし、それでいいのか?私が考えている成功のイメージはそんなあたりまえのことではない。障害にもめげず……という涙の物語もいやだ。だからといって、今の私には彼らの何に自信を持ち、それをステージに乗せられるのだろうか。私のこのモヤモヤとした思いは、形になり、果たして彼らと一体になるのだろうか。保護者とはどうだろうか。日程も決まっている。いやとはいえない。では、どんなステージを考えたらいいのか。二日目の練習を目の前にして、また長いトンネルに入ってしまった。
だが、練習だけは私の不安など微塵も感じさせてはならない。二日目に初登場の女性二人は、42歳の康子さん(三股町)と19歳の恵さん(都城市)。恥ずかしそうにしているが、よく笑う。やはり笑顔がいい。なぜ彼らはこんなにいい顔なんだろう。これで6人となった。ステージを考えれば、人数は多い方がいい。この日から三股町の広報の取材も入って、うれしいにぎやかな始まりだ。
発声のレクチャーを初めてやってみる。
「いい?見てて。息を吸います。お腹の前も横も後ろもふくらませまーす」
私は自分の左右の横腹に手を当てる。息を吸ったときに手が動くから、変化がわかりやすいのだ。
「ここに横隔膜があります。この横隔膜を広げたり、ゆるめたりしながら声を出します。やってみますから見ていてください」
私がハッハッハッハッハッハッハッハッと声を出す。すると、私の両手はその度に横に広がったり、もとに戻ったりする。
「では、みんなでやってみましょう。手を当ててください」
緑さんがすぐ真似をする。それを見て他の人も次々と真似をする。
「声を出してみましょう。ハッハッハッハッ」
みんなも互いに顔を見合わせ、笑いながら声を出す。一人ずつの声を聞くために、一人一人に近づいてみる。ん?声があまり聞こえてこない。横腹に当てた手は何も動かない。おなかを膨らませるということがわからないようだ。
「じゃ、寝てやってみましょう」
私は床に寝て仰向けになり、自分のお腹にティッシュの箱を乗せた。息を吸うと、箱が上に上がり、吐くと下がる。純子さんがそれを見て大笑いする。
「さあ、寝てください」
全員その場に寝っころがる。キャアキャア笑い声を上げながら。でも本物志向を追求。私が学生時代に合唱団で先輩から習って身につけた呼吸法と発声の仕方をそのまま伝える。
「懐かしいなあ。でもあの時、やってなかったら今のこの楽しさはなかっただろうなあ」とちらっとそんなことが頭をよぎる。
寝ている間は腹式呼吸になるのが普通。だから、仰向けに寝るとお腹が膨らむ。みんなが自分のお腹でそれを理解する。
「え~。そうなんだあ」
と朝倉さんが驚く。
「ほら。お腹は絶対に膨らみますね。今度は立ってやってみましょう」
拓也君のお腹が大きく膨らんだ。
「すごい。すごい」
みんなで拍手。拓也君は照れながらとても得意そう。
「わたしもやる!」
緑さんがやって見せる。あっ、お腹が少し動く。もうすぐ出来そうな気配。それを見て、恵さんも目を輝かせている。
康子さんが笑う。笑うとお腹が動く。
「ほら、動いた」
恥ずかしいやら可笑しいやら、康子さんはもう笑いすぎ。貞雄君は手を小さく振り、「もう結構です」という仕草をしながらも、みんなの様子をうかがっている。純子さんは遠くへ逃げたまま。でもこちらをちらりちらりと見ている。
「声を出してみましょう。ハッハッハッハッ」
「ハッハッハッハッハッハッハッハッ」
あっ、今度は違う。真似して声が出る。最初よりずっといい。だが、まだみんなへなへなした声だ。それは当然だ。だって、お腹から声を出すのは、1年以上かかることなのだ。合唱団の頃、後輩にしつこく指導して泣かれてしまったことを思い出す。目の前のみんなは初めての内容なのによくついて来てくれる。
さて、純子さんが歌いたいと言った、スマップの『世界に一つだけの花』。驚いた。みんなが歌っている。家で練習してきているのだ。好きだから苦もなくできるのだ。ただこの歌は、歌詞にちりばめられた言葉が多く、発音するのに現段階では少々無理がある。発表できるだろうか。聞いていてサビのところしかよくわからない。かなり不安だ。
次に、オリジナル曲「SMILE」をみんなに聞いてもらう。初めて聞く歌だ。私はドキドキしながらみんなの顔を見ている。全員が不思議そうな面持ちで聞く。曲が終わると「うわあ、すごい」と朝倉さんの声。お母さんたちから大きな拍手が起こり、みんなも拍手。受け入れられたことを感じた。一安心。ダビングをしてテープを配ることにする。これで次回からオリジナル曲の練習に入ることができる。ステージで歌うのは、この2曲ということになるのだろうか。伴奏は?楽器は?誰が?
■サポートメンバーを募る。
二回目が終わってから数日後、社会福祉協議会から連絡が入る。
「ピアノの伴奏の人が見つかりました。音楽療法士を目指して短大で勉強している女性です。あとは本人と相談して決めてください」
そうだった。伴奏の人を探してくださいって頼んであったのだ。でも本当にすぐ見つかるなんて。失礼だけど、そんなに当てにしていなかったのだ。
「ありがたいなあ。どんな人なのだろう」
すぐ彼女に連絡をとり、面接。二川めぐみさんという19歳の学生さん。私と同じ時期にボランティア登録をしていて、すぐ声がかかったのだ。
話し方もおっとりとして、少しも自分を自慢げに語ることがない。
「すごいですねえ。オリジナル曲ができたんですかあ」
やさしい雰囲気でカーニバルとの相性もよさそう。家もすぐ近くだ。即決。キーボードの予算が下りたら購入して、キーボードを担当してもらうことにする。
「これがオリジナル曲なの。伴奏を考えてください」
私はそう言って「SMILE」のテープと歌詞カードを手渡す。
「えっ、楽譜ないんですか?」
「そう。歌詞にコードが書いてあるから、これでお願いします」
「…………」
コードというのは、和音のこと。これがCとかGとかAmとかの記号で表される。フォークギターやジャズピアノを演奏する人は、このコード進行さえあれば即興で演奏できることが多い。だがクラシック音楽だけしか習わなかった人は、楽譜がないと演奏できないことが多い。二川さんはとまどっている。クラシックピアノをずっとやってきた彼女にとって、「コード譜を付けた歌詞カードだけで、伴奏を作り上げる」なんて、初めてのこと。「がんばって!」と言うほかはない。私も小山さんも、ピアノ伴奏の楽譜を書くなんて出来ないのだから。
二川さんが手伝ってくれると決まったことで、私の心に弾みがついた。ステージは、とうてい私一人で出来ることではない。今のうちに、サポート体制をしっかり作っておこう。そうだ。「ボランティア」という言葉でなく、「サポートメンバー」。いい響きだ。役割まで決まっているイメージさえする。カーニバルのサポートメンバーを集めよう。さっそく電話を開始した。
気負いとは裏腹に、それはあっけなく終了した。たった一日でサポートメンバーが集まってしまったのだ。それもそのはず。これまでもカーニバルのことで相談していた人たちに電話したのだから。SMILEを作ってくれた小山さんは作曲や編曲担当。中井さんも快諾してくれた。彼は作詞担当だ。練習が進んで形になってきたら、小山さんや中井さんを練習に誘い、ステージに一緒に立ってもらおう。友人の小村淳子さん、八木裕子さんは私の相談役だ。企画から練習方法まで、シロウトで経験の無い私は、確実に相談する人を求めている。そして、堂領さん。心強いお抱えのボランティアコーディネーター。私と二川さんを含め、カーニバルのサポートメンバーは7人でスタートすることになった。
あとは、どんなステージにするかで、音や服装や照明などのバランスを考えよう。文化会館のスタッフと相談しながら練り上げる。プロの技術が入れば、格段と見栄えがよくなる。しかし、肝心なのは彼らが楽しくできるということだ。表情に一生懸命さや明るさがなければ、どんな技術を駆使しても感動は伝わらない。
ひとつひとつの考え方が行動に出て、それがステージに集約される。小手先の技術ではどうにもならないものが出てしまう。だったら本物にする。私が胸張って、これです!と言える本物を持つこと。その本物が練習の楽しさを呼び、彼らがステージで輝くのだ。
しかし、どうやったら本物は見つかるのだろうか。それはまだ遠い道のりのように思えた。
■コーラスからバンドに
7月9日。3回目の練習日。二川さんも練習に加わった。キーボードの音色やリズム選びを模索する段階だ。この日、また一人メンバーが増えた。知毅(ともき)君、17歳(高城町)。緑さんと同じ養護学校3年生。玄関でお母さんに隠れるようにして立っている。おとなしそうだ。気の毒なほど緊張でこわばっている。
「歌を歌うということはないんですが」
とお母さん。
「音楽が大好きなので、居させてもらうだけでいいです」
歌うことがないのに歌の会に入るって…。え~?いるだけでいいの?音楽が好きだからといって、歌う仲間の中に、彼はいることだけで満足するのだろうか。私が親だったら、練習はともかくとして、ステージはどうだろう。ステージに立っているだけのわが子を見たいと思うだろうか。他の人たちはみんな歌っているのだ。彼をただ立たせておくだけのステージを私が作ってしまうなんて。その姿を想像しただけでも、こちらがキツイ。え~どうしよう。メンバーは是非とも欲しい。人数が増えればステージは華やかになる。でも彼はそれでいいのだろうか。
「まあ、どうぞお入りください」
練習場には、小山さんから借りてきたキーボードや私のギターが準備してあった。どうしようかと戸惑う私の目の前。知毅君は母親から離れ、一人でスタスタと教室に入っていった。そして慈しむようにギターを…キーボードを眺め、ゆっくりギターへと手を伸ばした。弦が揺れてポロロローンと音が響くと、彼にいきなり笑顔が。しかめ面をしていた数秒前とは全く別人のようだ。目を細めて微笑み、音に納得したのか何度も小さく頷いている。楽器が大好きらしい。母親が「居させてもらうだけでいい」と連れてきた理由がわかる気がした。この笑顔。何とか守れないだろうか。
そうだ、いっそのことみんなに楽器を持ってもらってバンドにしたらどうだろう。知毅君だけでなく、歌声があまり出ない人はまだいる。それに、バンドにすれば音楽の幅も広がる。
また、ここで問題がでてきた。バンドの経験も無く、これまでバンドに関心すらなかった私に、今からそんなことができるのだろうか。彼らもまた、バンドなんておそらく初めてだろう。歌よりもずっとシロウトのバンドになることは間違いない。
では、こう考えたらどうだろう。歩みは遅くてもいい。私の成長に合わせて伸びていってくれたら。いや、逆に私が知らないからこそ、余計に助けてくれる人も出てくるのではないだろうか。そうなれば、私の成長以上に彼らが伸びることにもなる。ここは考え方ひとつなのだ。
知毅君が入ってくれたことで、カーニバルは新たな一歩を踏み出すことになった。県の社会福祉協議会では、ボランティア立ち上げの年度に大きな助成をしてくれる。今年だけの優遇措置を楽器購入に大きく充てることにした。楽器店に行き、打楽器のカタログをもらってくる。打楽器といってもアフリカ音楽・アラブ系の音楽・ブラジル系・キューバ系そのほかキッズ用のカラフルなもの、セラピー用のものいろいろあることを知った。カーニバルはどんな音色をまず作っていけばいいのだろう。楽器の力は大きい。全部買うわけにはいかないから店員さんにひとつひとつしつこく質問をして帰る。
彼らは一人一人違っている。けれども、その場の空気をやわらげてしまう不思議な雰囲気がある。それを表現するには、金属系の音よりも自然素材の民族楽器が似合う。
キューバ・ブラジルあたりでそろえていこうか…と考えがまとまった時、初日にみんながカッコイイ、やりたいと言ってくれた「風になりたい」を思い出した。もうこれはやるしかない。やっぱりやる運命だったのだ。ここまでたどり着かせてくれた知毅君に感謝した。
■目指せ!「サルサ・ガムテープ」
バンド「サルサ・ガムテープ」。知っている人は知っている。ミュージシャンの「かしわ哲」さんが、1994年、神奈川県の知的障害者が利用している福祉施設を訪問してバンドを立ち上げた。初めはポリバケツにガムテープを貼っただけの手作り太鼓で演奏。それがこのユニークな名前の由来だ。数年前にオリジナル曲「まひるのほし」がNHKの「みんなのうた」で知的障害者の描いた絵とともに紹介されて、大ブレイク。その後、忌野清志郎さんと競演するなど、現在はプロのミュージシャンも参加して、ライブ活動を精力的に行っている。もちろんCDも出している。最近では「どっちの料理ショー」のエンディングテーマで彼らの音楽が使われた。
このサルサがNHKのスタジオパークに忌野清志郎さんと生出演したときのビデオを、以前小山さんに見せてもらったことを思い出した。もう一度このビデオを見せてもらうことにする。化粧をした清志郎さんが
「うん、リズムがいいねえ。ばりばりのロックっすよ」
かしわ哲さんが
「ぼくらはねえ、がんばんない。がんばんないのが特徴だね」
この素敵な会話から始まって、演奏へ。サルサのみんなも化粧をほどこし、服装も清志郎さんに負けず劣らずファッショナブルだ。イントロで二人のプロが彼らのばらばらのリズム打ちをうまくリードしていく。そして彼らなりの味のある演奏が始まった。それは何も無理をさせない。かといって、だらけているのではない。一生懸命なリズム打ちと歌だ。決してきれいではない。ズレたようなぼこぼこした太鼓のリズムだ。女性ボーカルがまたすっとんきょうないい声をしている。何か心地よい。どこにもない個性がそこにほとばしり出ていた。
このビデオを再び見ていて、私はモヤモヤしていたものが、晴れていくのを感じた。キレイにまとめるだけが音楽ではない。むしろ、まとまっていない方が温かみや息づかいさえ感じるではないか。
そうだ、彼ら独特の、そのままのパワーを出せばいいのだ。カーニバル独特の。これは、作らなくてもいい。私が感じたものをそのままステージに乗っけるだけなのだ。かしわ哲さんや清志郎さんがサポートすることによってうまくそれを引き出し、ちゃんとコラボレーションが成立している!私たちにもできる!
ビデオを借りて帰る。これをみんなに、みんなに見せるんだ!
「わかりました。すぐ保護者を集めます」
朝倉さんは、二日後には保護者会を開いた。急な呼びかけだったが、社会福祉協議会の堂領さんと大高さんも駆けつけてくれた。「皆さんが集合するのなら」と、ボランティア保険のことや補助金申請の仕方などを説明してくれた。私はこんなことが苦手で何度説明を受けてもすぐに忘れてしまう。でも、これからは苦手ではすまなくなってくる。ステージの話が先行して私の頭の中は、もう10月25日のことでいっぱいなのに、まだ組織作りとか器作りとかができていない。あとからついてきている感じだ。保護者も全員揃うまではいかない。この時点での温度差はいたしかたないこと。焦っても仕方がない。
これがどうなっていくのかも楽しみだ。私はホットな割には、かなりクールだと自己分析している。そう、慌てない慌てない。だって他人を変えることは至難の業なのだ。自分ができることを一生懸命やれば、そのうちに周りが変わってくる。その時は、きっと期待してたことなんか、とっくに忘れた頃にやってくる。
「発表なんてできるのかな?」ついこの間までの私と同じように、きっと保護者も思っているはずだ。ステージ?ん?何?…と。情報としてわかっているのは、10月25日。土曜日。社会福祉大会のアトラクションで障害者のグループの発表がある。宮崎市のエデンの園という視覚障害者の施設。そこで長く活動している「グレープフルーツ」というバンド。その発表がメインである。
グレープフルーツさんは、歌のうまさはプロ級だということ。会場を魅了する歌声だという評判だ。私たちカーニバルは、その前座を務めるのだ。果たしてそんな大役ができるのだろうかと誰もが思っている。
「ではこれを観てください」
あのサルサ・ガムテープのビデオを観てもらう。同じ知的障害者のステージだ。保護者は食い入るように画面を見つめる。「カーニバルより年齢が少し上みたいね」自分の子の成長した姿と重ね合わせて観ている。楽器もたくさんだ。
「あっいい!お化粧して楽しそう」「うわあ!すごい」何年かするとこんなふうになるんだ、きっと。テレビにも出られて、しかもプロとの競演。どんなにか嬉しいことだろう。
演奏が終わる。保護者から歓声と共に大きな拍手がおこった。こんなに華やかなステージをやってのけるサルサに対する賞賛の拍手だ。よくぞやってくれた。私たちにこんなことを教えてくれてありがとう、という意味もある。
「ね、できると思いませんか。大事なのは、元気いっぱい、一生懸命やること。そうすれば、きっと感動が伝わると思う」
「できる、できると思う。これならできるよねえ」
ここまでは予想したリアクション。しかし、朝倉さんは
「私たちの方がきっとすごいと思う」
出た!さすが、4人でもステージの話を受けてきた人の言葉だ。映像は視覚で多くのことを教えてくれる。
こちらが言わなくても、保護者の間では、ステージ衣装の話になる。
「お化粧もいいよねえ」
ステージが保護者にもぐんと近づいてきた。
「これを次回練習日に子どもたちにも見せましょう」
ステージのイメージを保護者と共有できた夜だった。
■11人になった
4回目の練習日。エクササイズや発声練習など、メニューの内容も順番も絵カードとともにすっかり定着し、次は何?次は?と聞かれなくなった。慣れと共にひとつひとつのことがスムースに運ぶようになってきた。イヤ!と冗談を連発していた貞雄君も、私が近づくと抵抗をする純子さんも、好きなところで好きなやり方で参加している。無理に揃えてはいけない、むしろ揃っていない方がいいくらいだ。このように考えると実に楽だ。
SMILEの練習をしている時、部屋のドアが開いて、新メンバーがぞろぞろと入ってきた。安持ゆかりさん20歳(都城市)と西広大君20歳(高城町)と南崎弘樹君17歳(山田町)だ。ゆかりさんと広大君はまるで初めからのメンバーのように歌の輪の中に入って歌う。知らないはずの歌なのに、なぜ彼らは歌えるのか。弘樹君は珍しいところへ来た喜びを体中で表現して大きな声で笑い続けている。何なんだ、これは?と思い切り戸惑っている私だが、やめるわけにはいかず、そのまま歌い続ける。歌いながら思った。このまたしても強烈な個性の三人は、私を助けに来てくれたのだろうか。
私は障害のある子どもの教育を学ぼうとして大学に行った。しかし、いざ就職試験というときに私は教育現場に行くことに希望が持てなかった。教育実習もあと1週間で終わりというところで実習学校に行くことすらできず、部屋にこもってしまった。今考えると、この私が、と思うようなデリケートぶりだ。その後、保育士の資格(当時は保母資格)を取り、保育園で仕事をしながら障害児がいるクラスの担任に。しかし、もち上がりではないから、1年でお別れだ。その後、公文式の学習塾を開設する。公文式は幼児や障害児の指導事例を出し合うことにより、多くの教育成果を出している。いつしか、障害児を担当して役に立ちたいと思った。しかし、そういう機会になかなか恵まれなかった。
福祉の仕事や学校の管理職についている私の同級生たちと比べて、今の自分をどうだこうだと考えたことはない。しかし、障害児教育を諦めたうしろめたさは残っていた。私は彼らについて学びながら、使命感を感じながら、彼らのために何もしていないことがずっと気がかりだった。今の仕事をしながら彼らと向き合うこともなく、一日一日が過ぎていき、もうこんなに年月を重ねてしまった。出会う努力さえもしなかったのだ。
しかし今、目の前に起こっていることは夢にも思わなかったような光景だ。私があんなに待ち続けていた人たちが、こうして束になってやってきてくれている。しかも、自分と同じ音楽を好きな人たちばかり。一緒に歌っている。こんなことってあるだろうか?
次の回にも新たにメンバーが一人増えた。久寿米木寿美子さん、38歳(三股町)。すっごく明るい元気な声の人。この明るさは貴重だ。ますます楽しみになってきた。こうして、今日でメンバーは11人となった。これに楽器が加わればステージはずいぶんにぎやかになる。もうはしゃぎ出したいほど、うれしい。カーニバルの名前にふさわしい人数と個性の集まりだ。本当にカーニバルだ。
■カーニバルの音作りが始まる
ステージでの2曲。「SMILE」はレゲエで、「風になりたい」はサンバ。楽器も共通して使える。それなのに、感じが異なる2曲。だからおいしい選曲。
小山さんからボンゴを借りてきた。それを見つけた貞雄君がとても気に入って離さない。手のひらとのなじみがよく、初めてなのに器用に音を鳴らしている。私なんかよりずっとうまいことがうれしい。貞雄君以外にも、こんなふうに気に入った楽器にめぐり合わせてあげられたらいい。
さて、歌ったことのないという知毅君のための楽器を何にするか?知毅君はほっそりしているが、お母さんの話では、力持ちだし体力もあるとのこと。サルサ・ガムテープも使っていたスルドという大太鼓を注文した。低音部を彼にしっかり支えてもらおう。
後は誰に何の楽器がいいか考えていく。拓也君にはバンドリーダーとしての風格と資質が感じられる。彼は初めから自分のはっきりとした意志で参加してきたのだから、その気持ちにふさわしい楽器を選びたい。そうだ。ハーモニカに挑戦してもらおう。「SMILE」のイントロはキーボードに合わせて拓也君のハーモニカから始める。そしてエンディングも彼の演奏でしめくくったら感動的だ。きっと仲間の信頼を集める。彼ならきっとやってくれるだろう。そして、「風になりたい」ではホイッスルがいいかもしれない。
申請した助成金が下りたとの連絡が入る。すぐに二川さんとキーボードを買いに行った。そして、サポートメンバーの小村さんからも、小物楽器を貸してくれるという申し出があった。小村さんは、ピアノ教室をしていた経験があり、発表会で使用していた楽器が倉庫に眠っているのだという。ありがたい、ありがたい。数日後、小村さんは教室にたくさんの楽器を運んできてくれた。ボンゴ・ギロ・ウッドブロック……名前のわからないものもあった。温もりを感じさせる自然素材の手作り楽器が並ぶと急にワクワクしてきた。
これらを誰が手にすることになるのだろう。ひとりひとりの才能がまだ隠れている状態なので、少しの変化を見落とさないこと、才能を信じることが私の一番の仕事だ。押し付けにならないように、それだけは戒めたい。メンバーが集まり、曲が決まり、楽器が手に入った。さあいよいよステージに向けて、カーニバルの音作りが始まる。
「SMILE」はカーニバルらしいメッセージを織り込んだ曲。歌うほどに馴染んできている。男女パートに分けてめりはりをつけ、楽しさを倍増させたい。人生の応援歌ともなるので、チアガールのようなかけ声を女性が入れる。イントロの拓也君のハーモニカも練習に入った。個人練習となるので拓也君には少し早めに来てもらう。男女にわけたことで、歌詞の覚えが急速に速まる効果も出てきた。カスタネット・ボンゴ・キーボード・ハーモニカだけを使用してシンプルに。これは何とかなりそうだ。
逆に「風になりたい」では、たくさんの楽器を使用して思い切り派手さを演出していけたらいい。問題はこの難しい楽曲をオリジナルカラオケで歌えるか?ということ。CDに合わせて歌うのはできそうなのだが。そしてもう一つ。それぞれの楽器をどこでどうやって使うかという問題だ。私はこの2週間ずっとこの曲を聞いているが、音を拾えない。あまり複雑にしてしまうと私自身が覚えられない。これは困った。
カーニバルのメンバーは皆、楽譜を使わない。耳で身体で音楽を受け止める。私もそれを見習って今回は楽譜を探さなかった。CDをとにかく聞きまくり、次回の練習日に臨む。
■練習場に集まるサポート
5回目の練習日。初めての楽器練習で楽器数も多いので、サポートしてくれる人を4人お願いした。サポートメンバーの八木さん。堂領さんと、お嬢さんの堂領ちとせさん。都城市民吹奏楽の団員の塘尚美さん。
一つの楽器に一人ずつサポートがついた。もちろんお母さんたちの手も借りた。初めはスルドから練習し、一つずつ楽器を増やしていくやり方。スルドの知毅君はお母さんが付き、全部の楽器が入るまで、計8回くらい練習したかもしれない。長時間だったが、彼はとてもうれしそうだった。反対に最後の楽器のマラカス隊は、ずっとスタンバイ状態で待ちくたびれていた。楽器はみんなからすんなりと受け入れられた。「どれでもいいですよ」という感じで。う~ん、ガチャガチャで騒音を撒き散らしていた。気づくと、歌を練習する時間がなかった。
6回目の練習日。月日の経つのは残酷なほど早い。もう、8月も終わり。本番まで、あと2ヶ月。本当に月2回しか練習日がないのだ。そのうち5回は、曲決めとメンバーを固めるのに費やしてしまった。「SMILE」だって、まだまだ元気いっぱいの歌声とは言えない。毎回「私の歌を聞け~!」と叫んではいるが。それに前回の「風になりたい」は、楽器の導入だけで歌う時間すらなかった。
私は、今日の練習で秘策を出すことにした。「SMILE」を作ってくれた中井さんと小山さんを練習に呼んである。今日は一緒に歌ってくれる。相性がよければ、そのままステージへと連れ出したいと私は密かに思っている。
いつものように発声練習をしている時、二人は登場した。「SMILEを作ってくれた人が来る」ということを連絡しておいたので、お母さんたちやメンバーから大歓迎を受けた。そして「SMILE」の練習へ。二人が大きな声でリードしてくれたので歌いやすく、「SMILE」がグレードアップして聞こえた。小山さんは声も身体も大きいだけではなく、とにかく音楽を楽しんでいる。のりのりで歌ってみせてくれる。いいお手本となるはずだ。中井さんもまた、感受性豊かな人。お互いにいい刺激を与え合うことになるだろう。
今までは借り物のキーボードを使っていた二川さん。買いたてのキーボードを家に持ち帰り、きちんとマスターしてきてくれた。やわらかい音がいい。彼女の責任感に感謝。また、前回サポートに来てくれた塘さんが、今日は息子さんの又輔さんを派遣してくれた。打楽器でドイツ留学した人。「自分の代わりに、息子に何でも聞いて!」ということだ。私は楽器の持ち方から演奏の仕方、どのようにステージに配置したらいいのかもわからないのだ。又輔さんを遅くまで引き止めて、聞きまくった。やさしくアドバイスしてくれた。わが町にもいろんな人材がいる。活動と共にだんだん発掘されていきそうな、そんな予感がした。
メンバーと保護者、そしてサポートする人で練習場はいっぱいだ。初めての人を見ても全く萎縮することなく、却って張り切るメンバー。こんなにたくさんの人たちが関わることに、お母さんたちはびっくりしている。「それは大変!」と駆けつけてくれる音楽好きな人たちばかり。楽しい2時間があっという間に過ぎていく。小山さんと中井さんに私はおそるおそる聞いてみる。
「どう、これからもずっと練習に来て手伝ってくれる?」
「いいですよ」
彼らの返事にどんなに私が喜んだことか。
こうした人と人とのつながりは、偶然に見えて必然である。そこにタイミングが絡む。だから神秘的でもある。そう、恋愛のように。
■わたしは「つんく」
メンバーが11人に固まった時、私の中に、ある一つのイメージがこびり付いた。「サルサ・ガムテープ」ではなく、「モーニング娘。」である。笑われても、浮かんでしまったのだから仕方がない。「私はモー娘。をプロデュースするつんくだ。つんくだ」と独り言を言う日が続いた。しかし一人一人のキャラ作りをしなくてもいいほど、彼ら一人一人は違っている。「モー娘。」に負けないほど。
♪バンドマスターのような風格の拓也君
♪ひょうきんな貞雄君
♪自分だけの世界と協調の世界を行ったり来たりする弘樹君
♪やさしさが全身にあふれる広大君
♪職人のような知毅君
♪努力家でアイドルの緑さん
♪雲をつかむような感覚派の純子さん
♪かわいい癒し系の恵さん
♪歌姫のゆかりさん
♪元気な仕切り屋の寿美子さん
♪思慮深い康子さん
こんなにも素晴らしい人材が揃っているなんて、プロデュースするのには恵まれすぎる条件だ。そう、私が彼らひとりひとりに惚れこむこと。決して同じように揃えないこと。むしろ、ひとりひとり違うことをアピールできないものだろうか。そう、私は「つんく」なんだから。
障害者というと一括りにされがち。そして知的障害者というと、あるイメージを浮かべてしまいがちだ。誰かと付き合った人ならわかるだろう。彼らもまた、私たちと同じように一人一人違っているのだ。そのことを多くの人は知らない。
知的障害者のバンド演奏が始まる。今までの経験で知的障害者の何かをイメージして、観客は席に着く。そこへいろんなタイプの人たちが今までの自分の常識を壊すかのように、いきいきと演奏する。「えっ、何これ。知的障害者?どの人が?めちゃくちゃ楽しそう。超うらやましい。一緒に歌いたいなあ。入れて欲しい」こう思われるほどみんなが楽しく演奏できること。これが私の成功のイメージとして浮かんできた。初めに抱いていた、モヤモヤとした思いは、霧が晴れてゆく時の景色のように、だんだん形が見え始めた。「つんく」なら彼らのプロデュースなんて軽く出来るだろう。
9月に入り、7回目の練習。盛り上がる妄想とは裏腹に、現実の2曲はまだまだ仕上がりどころではない。
「SMILE」のイントロ。拓也君のハーモニカもまだ自信のない小さな音だ。スースースーという息の中に少しだけハーモニカの音が入る状態。繰り返し吹いたり吸ったりして、音が出るコツを彼はこれから自分で掴まなくてはならない。どうしたら音を出すことができるのだろう。さて、歌の部分。男性は小山さんと中井さんの声が突出して聞こえる。メンバーの大きな声がほしい。女性はかなり元気。だが、好き勝手な音程で歌う人がいる。私もつられそうになる。歌いにくいこと、はなはだしい。
「風になりたい」の楽器。はじめに楽器別にどこで鳴らすか確認する。それからみんなで合わせる。でも、歌が始まると、さっきの決め事は無かったかのようになる。好きなところで、好きなようにガチャガチャと鳴らしてしまう。だからめりはりをつけることなど夢の夢。合わせて流しているCDも音量を最大にしているのに聞こえてこない。マラカスを見ているとタンバリンが。タンバリンを見ていると、ボンゴが。ボンゴを見ているとマラカスが……。私は歌いながらメンバーの間をミツバチのように飛んでは止まり、また飛び回る。1回練習するだけで喉がからからになる。誰がどのように鳴らしていて、どんな表情をしているのか、11人もいると把握できない。とても彼ら一人一人の個性をアピールするなんて無理だ。
「どうですか」
毎回、練習に取材に来ている役場の広報担当の岩元さんが聞く。
「だめです。誰がどんな音を出しているのか、歌っているのか歌ってないのかもわからない。誰かビデオに撮ってくれたらいいのだけれど」
と愚痴をこぼした。
「役場の福祉の山田に頼みましょう。彼がステージの話を持ってきたんですから、協力しますよ」
とその場で連絡をとってくれた。やっぱり助けてくれる人はいるんだ。具体的に言うことだ、なるべく具体的に。私は確実に助けを求めている。ちょっと気弱な「つんく」。
-
-
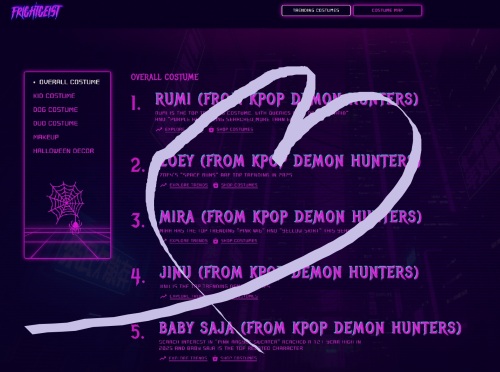
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- 吹奏楽
- 演奏会に行ってきた。
- (2025-11-19 16:33:12)
-
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- The Beatles(ビートルズ) 『アン…
- (2025-11-20 11:02:10)
-



