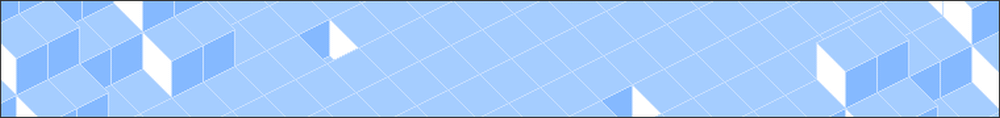化学療法
化学療法とは言っても、幾つかの治療手順(プロトコール)が存在するので、どれで行くかを決定しなければなりません。
僕の場合、治療開始前に、家族と主治医を交えた話し合いの結果、JALSG-ALL202という最新のプロトコールにのっとって進めて行くことにして貰いました。
ちなみに「202」の前は、日本成人白血病研究グループ(JALSG)-ALL97というのが存在しました。僕に行って貰った「202」は、「97」プロトにのっとって治療を進めた患者さん方の治療状況や治療成績を元に、血液内科の専門医方が意見を出し合って改良された治療手順です。つまり「202」プロトは、「97」プロトのマイナーチェンジ版、と言うことになります。だいたい5年ごとに治療手順の見直しが行われているようです。各プロトコールの違いは、投与する抗がん剤の種類、投与期間、投与のタイミングです。
どのプロトコールを選んでも、化学療法は、これを行う時期により、寛解導入療法、地固め療法、維持(強化)療法の、3つに分けられます。
最初に行われる治療は「寛解導入療法」です。
僕の場合、2005年5月30日開始でした。
白血病が発症すると、骨髄内はほぼ白血病細胞で占められ、多くは末梢血管内にも白血病細胞がこぼれ出てその存在が認められるようになります。このうじゃうじゃいる白血病細胞の大半をたたき(死滅させ)、顕微鏡下で、白血病細胞を確認できなくなる状態とし、正常な細胞が増えてくる状態(完全寛解(CR))を目指して行う治療が寛解導入療法なのです。CRになると白血病による症状は完全になくなります。
寛解導入療法では、通常1~2週間前後の連日、抗がん剤を投与します。この治療の結果は、予後を決定する可能性が高いため、最も強力な治療と考えられており、その結果、副作用もかなりの頻度で認められます。早ければ、治療を始めて約3週間~1ヶ月後にはCRに導入されます。1回の治療でCRへ導入する確率は70~90%とかなり高いです。1回の治療でCRに入らない場合には、2回以上繰り返されます。
僕の場合、治療開始後29日目に行った骨髄穿刺(マルク)でCR導入が確認されました(*^_^*)。
急性白血病において、CR後にどのような治療を行うのが一番良いかは、現時点でははっきりしていないようですが、その多くは投与する抗がん剤の種類、投与期間、投与タイミングを変えた化学療法が繰り返されます(寛解後療法)。寛解後療法は、地固め療法、維持(強化)療法に分けられます。
ここでは「地固め療法」を説明します。
CRに導入されると、骨髄や末梢血液中に白血病細胞は殆ど認められなくなります。しかし、目には見えなくても、身体の中には1億個以上の白血病細胞が残存しているとされ、ここで治療をやめると確実に再発するようです。このように、目には見えない残存した白血病細胞の根絶を目的とした、抗がん剤による治療が地固め療法なのです。
地固め療法では、投与する抗がん剤の種類、投与期間、投与タイミングを変えた数クールで構成されることが多いようです。各クールでは、数日から1、2週間前後、抗がん剤を投与します。
僕の場合、全部で、5クールが行われました。
以上の寛解導入療法と地固め療法は、入院治療でみっちりと行われます。どうしても通常、半年前後はかかります。
僕の場合、2005年5月30日開始、2006年2月7日退院の、8ヶ月強がかかりました。
その後は、一時退院し、外来にて、「維持(強化)療法」が行われます。維持療法は寛解導入療法を開始してから2年が経過するまで継続して続けられます。サイクルは、概ね1ヶ月(正確には28日)です。
僕の場合、全部で、9回の維持療法を行った後、移植に臨みました。
© Rakuten Group, Inc.