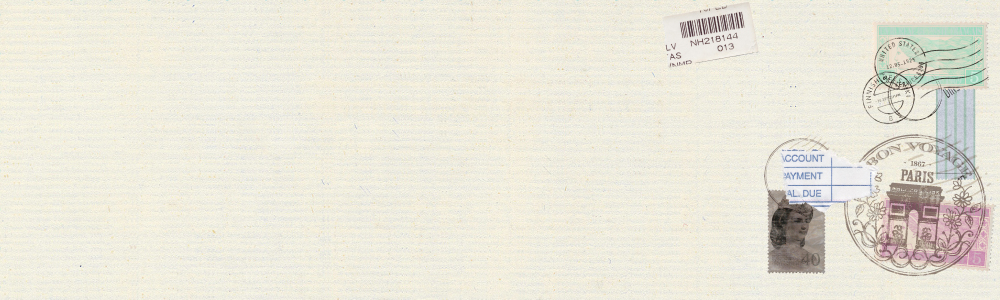2005年
講師 脇 明子氏 ノートルダム清心女子大学教授「岡山子どもの本の会」代表
著書に『読む力は生きる力』(岩波書店)
訳書にマクドナルド『お姫さまとゴブリンの物語』
キャロル『不思議な国のアリス』など
「ファンタジーの魅力を探る」レポート
1)絵本から物語への橋渡しの問題
・現在、ファンタジーブームである。
・現代の子は絵本にはたっぷり親しんでいる文学には馴染みが薄い
・<幼児期>ファンタジーを受け入れやすい
子どもはファンタジーを求めている
昔は学校から帰れば満たしてくれる楽しみがたくさんあった。ファンタジーの世界がすぐ側にあった。現在はその状況が失われつつある。あっても入ってこない。
・<児童期>
自分の常識が絶対である。頑固←ファンタジーを受け入れられない理由のひとつ
合理的に物事を受け入れる
論理的、保守的傾向がある
2)児童期にファンタジーを読むことのむずかしさ
・ファンタジーもどきに親しみ、古典ファンタジーに触れる機会があるのか?
・ファンタジーの世界には幾つかのルールがある。物語を読み進めるうちに
「ルール」を読み取ることができるとおもしろい
それはごっこ遊びと同じこと。見立て遊びの応用でファンタジーを読めれば
スーッと世界に入っていける。
3)児童期にファンタジーを読むことはなぜ必要か
・「非現実の仮定」のトレーニング ←あらゆることに必要なこと
もし…○○だったら。
・現代の子どもたちはビジュアルなファンタジーに馴染んでいる(優れた作品には馴染みがない)
理解できないことがあると想像力がストップして、先へ進めない。想像力がいらなければファンタジーは受け入れ易いともいえる。
・「ものを見る目を磨く」
小動物の目線で物を見る世界が大切(「たのしい川べ」など)
普段では見えないものが見えてくる力
4)ヴィジュアルなファンタジーの問題点
・「なぜヴィジュアルなファンタジーなら受け入れられるのか」
想像力や思考力は映像を見ている限り働かない。映像の切り換えによっておかしいことがあっても気にならない。←このままでは判断力が育っていかない。
・ヴィジュアルなファンタジーの根本的な欠点」
現代の物語は粗悪である。
世界観・人間観が薄れている。
グロテスク
映像の刺激が強いものが多い。
・読書の利点・・・・読むことだけで想像力・判断力が育つ
見極める力も育つ
読む力・選ぶ力も育つ
7)子どもたちに本物のファンタジーを手渡すには
<入口のしっかりした長編を>
物語にはまるためには… 短編では登場人物に感情移入できない。だからこそ長編の方がはまりやすい
↓
入口のしっかりした長編を
入口がしっかりした長編は読んでいて長さを気にしなくなる。
だから長さで選ばないで欲しい!
また、読み慣れないときは、現実的な部分があった方が読みやすい。
※入口がしっかりした長編
『とぶ船』(H.ルイス) 『ドリトル先生航海記』(ロフティング)
『ライオンと魔女』(C.Sルイス)『はてしない物語』(エンデ)
・現在、マンガを読み物(作品)にすることが増えている。
これは想像力の働かせ方が頭の中にアニメやホラー映画をみているような働かせ方をしているため、読みやすい。読めない子どもでも、読んでしまう。
[映像を文章化していく]
<昔話から昔話的なファンタジーへ>
昔話やストーリーテリングをよくい聞いた子どもだが、昔話の本を読むようにならないのははぜか? ⇒[昔話はそのようにつくられたものではないから]
語り継がれたものである
昔話はコンパクトにできていて、後をひかない。
リアルな描写がない。
主人公に感情移入するほど長くはない。
子どもたちは、自分の体験のようにリアル感があると自分から読むようになる。
↓
アンデルセンの仕事の意味
昔話の骨組みにリアル感がある『野の白鳥』『白鳥』
※今の子どもたちはつまずきやすい。つまずいても行き着くところがある(ヴィジュアルへ)私たち大人が、そこをうまくサポートしてあげなければいけない。
© Rakuten Group, Inc.