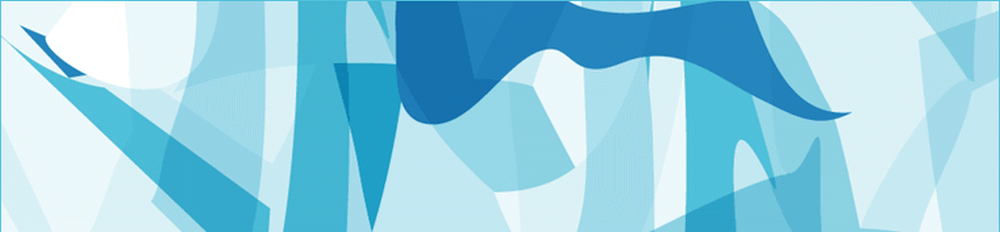カズキ
カズキサラリーマンが接待で使う高級クラブの雑居ビルが
立ち並ぶこのあたりは、
行き交う若い女と中年のカップルが多い。
同伴か・・・
ホステスと思わしき彼女らの手には
お決まりのようにセリーヌやグッチやシャネルが
上品にぶらさがっている。
こんな時
自分の肩に引っかかっているルイヴィトンが
全然お洒落に見えなくなるのは気分が悪い。
お気に入りのダミエのチェルシーなのだが
やはり、仕事用バッグに過ぎない。
1ヶ月ぶりにカズキと待ち合わせをした。
この繁華街の真ん中に
カズキの行き着けがあるのだ。
細い路地を入った奥に「山路」はある。
カウンター席しかない、
しかも10席だけの居酒屋である。
常連客だけの店。しかも予約制。
暖簾をくぐってガラガラと戸を引いて中に入ると
カズキは一番奥の席ですでに出来上がっていた。
他に客はまだ2人だった。
「いつから来てたの?」
わたしはカズキの隣に腰掛けながら尋ねる。
「5時半ごろかな。」
カズキはにっこりした。
待ち合わせの時間はとくに決めていなかった。
仕事が終わったら行くというのが
わたしとカズキの待ち合わせだ。
予約はカズキが入れるので
どっちが早く着いても席は2人分確保されている。
「カズキは早かったね。今日は。」
大将のカズさんがカウンター越しにおしぼりをくれた。
「珍しいよね。いつもわたしが待つのに。」
「待ってる方がいい?」
カズキがセブンスターに火をつけながら首をかしげて
私を見た。
「待った?」わたしはわざとカズキに聞き返した。
「待ちました。」
「待ってる気分はどうだった?」
「ゆっくり飲んでたよ。ねえ。」
カズキはカズさんを見上げた。
カズさんは黙って笑った。
相変わらずビートルズが流れている。
店がこんなに狭いのに
カウンターの向こう側の壁一面にビートルズ
コレクションがギッシリ並んでいる。
カズさんの趣味なのだ。
カズさんは板前なのに昔バンドをやっていたらしい。
ビートルズナンバー専門のバンドで
担当はポールマッカートニーだったそうだ。
カズキはビートルズ好きというわけではないのに
なんでこの店にこんなに愛着を持っているのか
未だに分からない。
「とりあえず、生?」
カズキが聞いてきた。
「ウン。」
「お嬢さん、とりえず生だそうです。」
カズキの声優のような声が響いた。
今時カズキはセブンスターなんか吸っている。
自動販売機にも売っていないぞ。
「吸う?」
セブンスターの箱に目をやるわたしに
カズキが尋ねた。
「いらない。」
カズキはじっとわたしを見た。
「なに?」
「久しぶりだね。レミ。元気だった?」
「おかげさまでね。」
カズキの優しい空気に包まれる安堵。
でも、なんか納得できない気持ちになってくる。
こんな狭い店でカズキと体を寄せ合って
飲んでる。
イエローサブマリン・・・
あぁ潜水艦の歌か。
ビートルズとセブンスターとカマ焼き。
料理はそこそこオイシイ。
お酒もそこそこ揃ってる。
カズキさあ、
恋人連れてくる場所じゃないっしょ。
どう考えても、納得できない。
いつからこうなったんだろう?
カズキは心からくつろいでいるようだった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 運気をアップするには?
- オーラのパワーアップでタクシー運転…
- (2024-11-30 22:58:04)
-
-
-

- DIY
- カギの修理〈増森神社(埼玉県越谷市…
- (2024-12-01 19:24:40)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- ★。娘の事&UNIQLO×MARIMEKKOコラボ…
- (2024-11-30 11:18:36)
-
© Rakuten Group, Inc.