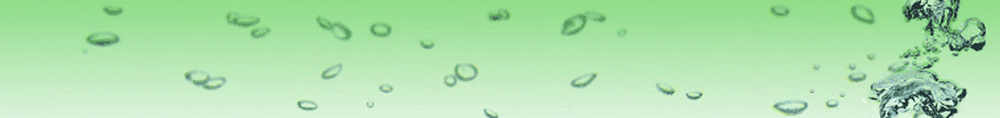2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年05月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
Inside A Dream
という訳でいろいろありましたけど、ついにメルマガ最大の危機を迎えました。一応現在の所隔週ないしは月刊の可能性が高いのですけど場合によっては3ヶ月程度休む可能性もあります。その場合は楽天のここのブログも休止したいと思っています。まあ少し精神的に疲れたというのがありますけどしょうがない。いつもうまくいくとは限らないし仕方ない。さてメルマガについてですけど、今回取り上げたジェーンウィーンドリンという人。勿論ゴーゴーズのメンバーでした。その絡みでゴーゴーズの事も少し調べましたけど、本当に米では人気のある人達だったというのがよくわかりました。しかし一番面白かったのは、米のケーブルTV局のVH-1が製作した「Behind The Music」というドキュメント映像でした。この「Behind The Music」。アーティストやバンドの裏話や当時の逸話をうまくまとめたシリーズで、すでにかなりの数の人達が取り上げられています。ゴーゴーズは’00年に登場したようです。VH-1のサイトで約5分程度の映像が見れますけど、例えばメンバーの何人かがドラッグに溺れていたとか、ベリンダカーライルばかりスポットが当たって他のメンバーとの仲が悪くなったとかいうエピソードが実際の当事者の口から語られます。(しかし動いているマイケル・コープランド初めて見たよ。)ジェーンもインタビューに登場しますけど、これが本当に変な話声なので深刻な事語っているのにあまりそう見えなかったりします。(何故声優の仕事もしているのがよくわかった。)そういえば再結成ゴーゴーズのCD出したレコード会社はビヨンドという会社ですけど、この会社のカタログは本当に懐かしめの人ばかりだったりします。例えば再結成ブロンディとか、フィックスとか、モトリークルーとかイエスとか何故か’80年代の香り漂うラインナップなのが面白い。なお以前にジル・ソビュールという歌手の事を書きましたけど、この人もこのレコード会社からCD出しているんですけど、契約のきっかけになったのはジェーンが関係しているらしいです。いい人だ。成る程少しジル・ソビュールとジェーンの曲は少し似た面あるかもしれません。どちらも現実感覚ゼロみたいな曲よく作っています。特に今回取り上げた「Fur」というアルバム、基本的なコンセプトが「’80年代のガールポップス」という感じの音造りだったためか、そういう雰囲気が一番あるアルバムです。この文のタイトルの「Inside A Dream」というのは「Rush Hour」の次のシングルだった曲ですけどこれがアレンジは’80年代の音なのに、曲は完全に’60年代ガールポップスなんだから不思議な曲です。実は某所で聴けますけど、興味ある人は検索してください。(教えないよ)しかしせめてベスト盤だけでも再発してくれないかな?今のところの最新作は自身のレコード会社から出しているらしいから、もしかしてソロのカタログ全て自分で所有しようとしているとかそういう話だったらいいのにな。(そんな事はないだろうけど)しかしゴーゴーズのメンバーは思ったよりいい感じに年取っているきているなあ。昔日本の女性バンドの殆どがレベッカのカバーバンドだったという時期があったけど、そんなバンドしていた人達も元気かね?最後にメルマガとは関係ないですけど、現在VH-1ではこんな企画をしているらしい。(やはりバニラ・アイスがいる。期待を裏切らない)こういう多少悪趣味な企画が出来るVH-1って健全な会社だ。私も投票したけどやはり’80年代洋楽がいくつかエントリーしているのは仕方ないか。
2004年05月31日
コメント(0)
-
へろへろ君
今ふとNHKで以前放送されていたアニメ「へろへろ君」の事を思い出したのであった。多分「おじゃる丸」がそこそこカルトな人気になったので「柳の下のドジョウ」狙いで作ったキャラだったと思うけど、さすがに当たんないわな。あんな変なキャラじゃ。しかし私は結構好きなアニメだった。見れる時は大体欠かさず見ていた記憶がある。でもどんな話だったか全部忘れたけど。「へろへろ」で思い出すアーティストといえばジェリーガルシア。グレイトフル・デッドのリーダーだったあの人だ。とにかく一本筋が通っていないなんとも不思議なギターの弾き手でも有名だったけど、そんな根無し草的な面はフランク・ザッパあたりにはとにかく嫌われてよくネタにされていた。でも不思議とこの両者には似通った面(ファンが熱狂的。ライブ盤が以上に多い様々なジャンルでの活動とか)があるから不思議だ。私デッドもそれなりに好きだけど、それよりもジェリー・ガルシアのソロ作の方が好きという変わった奴で、デッドのCDは全く持っていない(その代わりテープはかなり持っている)けどジェリー・ガルシアのソロ作はデビッド・グリスマンと一緒に演った作品を含めて結構持っている。そんな私には朗報なニュースだけど、ジェリー・ガルシアのソロ作を全て収めたボックスがついこの間6枚組で発売された。http://www.jerrygarcia.com/allgoodthings.htmlこれと同時にジェリー・ガルシア・バンドの’77年のライブも同時発売された。http://www.jerrygarcia.com/purejerry.html私は’80年代後半に出たジェリー・ガルシア・バンドのCD(日本では未発売だった)を聴いてからこの人のファンになったけど、亡くなって早9年。やっとソロ活動の方も脚光が浴びるようになったという事かな?しかしこんなにいろいろ出されてもなかなか財布の方が厳しいので買うのはもう少し先になりそうだ。
2004年05月30日
コメント(0)
-
衆院審議始まる
まずはこの前書いた文章の訂正。タワーは法案賛成だと書いたわけですが、どうやら「アジア盤CDの還流規制には賛成だけど、輸入盤の規制につながる動きには反対」という立場らしいです。(音楽評論家藤川毅氏のブログより)一応訂正という事です。そりゃそうだ。「輸入盤規制賛成」なんて小売が堂々と言ったら客は離れるわな。しかしあの声明文だと誤解する人は多そうだ。ちゃんと書き換えた方がいいと思うぞ。HMVも反対を表明しましたけど、この件に関して高橋健太郎氏が自身のブログでHMVのこの法案に対しての独自の取り組みについて触れています。そんな中でついに衆院の審議が始まりまして、これがいきなり5時間もあるのでまだ私は視聴していませんけど審議の模様の要約記事がここにあります。どうやら改正につながるデーターの信憑性について突く質問が多かったようです。なお民主党はこの法案については修正で対応することを決定しています。なお来週の火曜日には参考人質疑が行われ、参院の参考人質疑にも出席した日本レコード協会会長、弘兼氏の他高橋健太郎氏やHMVジャパンの会長も出席予定だそうです。なおこんな話もあるらしくこの場合なら今国会での成立が微妙になる可能性が高くなると思います。しかし少し相手が悪いねえ。親分の野中氏とかにメール送った方が効き目があると思うけどどうかな?なお今回の改正案を作成する以前に文化庁がパブリックコメントを募集していたのですが、これが何故か今頃前出の藤川毅氏が入手に成功しまして、藤川氏のブログからダウンロード出来るみたいです。ただファイルサイズが大きいので一応ダウンロードの際にはご注意下さい。しかし予想以上にこの問題に関しては動きが急展開という感じになってきました。来週あたりもいろいろあると思いますけど、どうなるかな?
2004年05月29日
コメント(0)
-
答弁書とかいろいろ
本当は昨日の続きで、答弁書3と4を翻訳しようかと思ったけど、あまり意味のない答弁書なので止めた。いちおう説明すれば、3については知的財産戦略本部構成員と内閣官房知的財産戦略推進事務局員の人事と構成に関する質問なんですけど、本質的には今回の著作権法改正とは関係ありません。ただ今後の知的財産の権利に対する法的整備が図られる過程で、今回のようなユーザーの権利をないがしろにするような法的整備が図られる事もあると思います。その意味で、この審議会は結構重要なので、委員の選定基準などを吟味するという事は大事な事だと思います。4は今回の改正案に関係があるのですが、単純に法案の文面の解釈の話で、参議院の審議の際にも出てきた議論ですので新鮮味はありません。この質問書はあまり意味がないような気がしないでもないです。総論としてはこの答弁書を見る限り、今後の衆院審議は参院審議の焼き直し的なものに終わる懸念が私には感じられます。とはいってもあくまで法案の審議なので今回のような仮定の質問をしても、答弁書のように逃げられるという事になるでしょう。しかし具体的運用に関わると何故かやたら抽象的な説明に終始するのは何故なのだろう?とにかく法律の文面が漠然としているのが一番の理由なんでしょうけど最終的にはやはり輸入盤の輸入をストップさせる力を持った法案であることは間違いない事に変わりありません。まあ今回は答弁書なので、国会審議用に隠し球があると思いますので、それに期待したいと思います。あと知っている人は多いとは思いますけど、ネット通販の大手アマゾン・ジャパン(旧CD NOW)はこの法案に反対を表明しました。ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/1162670/ref=amb_right-1_92626_1/250-0240315-9049062輸入音楽CDに関するAmazon.co.jpからの重要なお知らせ しかし、私も思い出深い輸入盤屋のタワー・レコードは法案賛成の立場を表明しました。輸入CD問題についてのお知らせ現在のタワーの品揃えからいって、予想してはいましたけど少し個人的にショックです。これとは関係ないですけど、著作権や商標権に関しての面白い記事がここにあります。前に私「アーニー・ローリー」という曲に関して調べた事あって、楽曲はともかくまだ訳詩に著作権が残っている事に驚いた記憶がありますけど、ほんとに世紀末的な文化状況になってきているなあ。という感じです。しかしこれでは例えば映画のワンシーンで「ハッピーバースデー」を歌うシーンが作れないではないか。映画の世界ではよく有名曲を承諾なくて使用してしまい権利関係がクリアできずにお蔵入りするという話は聞いたことあったけどここまでいろいろあると迂闊な映像撮れないね。
2004年05月26日
コメント(0)
-
答弁書について
まだ今回の著作権法改正案は衆院では審議されていない状態ですけど、国会議員でこの法案に反対している人達が質問主意書を提出していました。そのうち4つが今日の日付で閣議で了承され、答弁書として提出されました。ちなみに質問主意書というのは、一応国会の答弁と同じ効力を持つものです。今後の衆院の審議の動向を見るうえではかなり重要な文書だと思います。しかしこれがとにかく難しい。というのも著作権法というのはとにかく文面がやたら同じ言葉の使いまわしが多く、わかりずらい文面だというのがあって、そのために何書いているのかわからない人も多いと思います。そこで、私が勝手に翻訳してみました。それでも結構難しくて、そのうえ私も初学者だからニュアンスが間違っているかもしれません。その場合はコメントなり掲示板でご指摘して下さい。なおこれの全文が載っている(質問書も)サイトはここです。また括弧つきの文章は私が勝手に挿入した文章です。長いので今日は答弁書1と2だけにします。まず答弁書1は、今回の法案改正が最初に検討された文化審議会著作権文化審議会についての質問です。文化審議会著作権文化審議会についての質問。1、法制問題小委員会の委員の人選偏りについて。(消費者サイドに立つ委員が不在)2、消費者団体の審議委員が法制問題小委員会の人選偏りを指摘するも参加を拒絶する理由は何か?3、分科会の非公開性(報道機関のみ傍聴可能)と、発言に氏名などの記入がないのは何故か?4、何故「関係者間の協議・合意」の中に消費者団体等が含まれていないのか。(今回の著作権法改正案も、この『関係者間の協議・合意』が必要とされる案件だった。)答え1、専門家じゃないとわかんないから。まあ検討するよ。2、専門的な人が多いし、消費者の事もわかっている人達だから大丈夫だよ。だいたいちゃんと約3回消費者系の人を発言させているよ。3、法律では公開となっているけど、会場が無くてね。名前がないのはみんな名前出ると萎縮しちゃうからだよ。4、関係者というのはだなあ、それを仕事としている奴だとか法律変えて欲しい団体だとか、仕事としていて変えるの反対な人とか団体だよ。でもな、ちゃんと審議の過程で消費者団体も入れて審議してんだよ。これからも入れるつもりだよ。答弁書2は今回の改正案についての質問書です。1、アメリカのレコード会社があるCDに対して輸入権発動した場合。以下の異なる場合の対応はどうなるか?一、音楽CDジャケットに「US Version」と印刷されている二、音楽CDジャケットに「US Only」と印刷されている三、輸入業者に米のレコード会社が内容証明郵便を送って(輸入権の行使を書いた物)その写しが提出された場合。四、三と同一の内容で、「全てのCDを輸入禁止とする」旨書かれている。五、米レコード会社の代表者がインタビューで輸入権行使を口にした新聞の写し。六、米盤と全く価格が異なる日本盤が提出されたとき。(この質問の前提として、2の答えのような証拠品を税関に提出するという場合。以下の物が証拠になりうるかという事を聞いているのがこの質問の内容。なお三と四は入れ替えて下さい。)2、輸入を差し止める場合どのような基準で判断するか?またそのためにどのような資料を提出させるのか?3、輸入権が及ばないCDを売っていた輸入盤屋が、米のレコード会社から「おまえの売っているCDは日本では売れないんだから撤去してくれ」といわれたにもかかわらず売っていて、米レコード会社が著作権法違反でこの輸入盤屋を起訴した。その場合どうなるの?4、今文化庁は洋楽CDには輸入権は及ばないと言っている。だったらもし輸入盤屋が輸入CD沢山仕入れたものの、米のレコード会社から「売るな」というお達しが来て泣く泣く処分した。この場合国家賠償の対象になるんじゃないのかい?5、今回の改正案で、輸入権を行使するのを最初からしないっていう前提の人たちがいるんだけど、こんな事いままであったの?(本来権利が設定されたらそれを行使するのは当然なのが著作権法のような財産権を設定する法律なのでこんな質問が入ったと思われる)6、日米租税条約というものがあって、それは日本の大手レコード会社には殆ど当てはまるんだけど、それは日本の税金が減って、アメリカの税金が増えるという事だと思うけど、文化庁は知っているの?1、一、輸入規制の対象とはなりえないと思われる。二、一の答えと同じ。三、少し長いけど答えは一と同じ。四、一と同じ。五、一と同じ。六、一と同じ。2、この答えは少し重要なのでそのまま答弁書を写します。法案第百十三条五項にいう「当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合」については、権利者に与える法的影響を考慮して判断することとなるが、具体的には、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「頒布目的商業用レコード」という。)が国外で一般販売されることにより得られる利益と国内において頒布することを目的とする商業用レコードが国内において一般販売されることにより得られる利益の差が基本的な判断基準になるものと考えている。このため、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条の二第一項の規定に基づき、当該商業用レコードが輸入禁制品に該当するか否かの認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てる者には、双方の商業用レコードに係る複製及び頒布の許諾に係る対価を算出する条件等が記載された契約書などの提出を求める予定である。(国会答弁と同じだが、明確な基準は明らかにされていない。)3、検察が決める事だから答えられない。4、国会答弁という行為が、ただちに国賠に結びつくという事は多分ない。(これは判例法が根拠と思われる。)5、権利を行使する事を控える事なんか法律作る時考える訳ないよ。6、別に法案通ってもレコード会社が儲けるとは限らないから前提から間違っているよ。だいたい日本レコード協会会長も「輸入盤止めないよ」って言っているからね。日本の税金がかからなくなる事は知っているよ。明日は答弁書3と4について書きたいと思います。
2004年05月25日
コメント(0)
-
市民キーン
しかしこれほどB級的な感じが全編感じられる人も珍しい。グレッグ・キーンという人(というかバンド含めて)は実は音楽的な面の引き出しは深くて、ガレージぽい曲があったり、典型的なルーツ・ロック風の曲があったりトミー・ロウの「シイラ」をカバーしていたり、結構キンクスのファンだったり、ディスコ風のサウンドがあったり、ブルース・スプリングスティーンの曲を歌っていたり、とにかくジャンル分けするのにどうも難しいバンドだ。一応同じレコード会社だったルビナーズなどと同じ「パワー・ポップ」の範疇に入れてもいいと思うけどやはり普通に「ロック・バンド」というのが一番いいかなと思っていたりする。ヒットした「The Brakeup Song」にしても、「Jeopardy」にしてもタイプが違う曲だし、引き出しが多すぎて焦点がぼけてしまう所が感じられる。その後のキーンの活動を考えたらこの人かなりのオタクだったんだろうと思わせるけど、いろんな所に視点がいってしまい本筋がぼやけてしまい結果なんだかよくわかんない物が出来上がる。ファンになったら死ぬまでついていく人もいるけどそれ以外の人にはなんだかよくわかんないのでとりあえず「ジェパーディー」の一発屋という位置付けとなってしまう。まあ仕方ない事だけど。とにかく平気に「Jeopardy」の後に「Reunited」のような冗談としか思えない曲を出す人である。一筋縄ではいかない面白みがある。「Reunited」という曲、一応結構日本でもビデオとかテレビで流れていて、聴いた事ある人も多いと思うけどキーンのボーカルは歪みまくっているし、ドラムはドカドカうるさいし、ギターもガンガン弾いている。「ジェパーディ」でファンになった人には「?」だったと思うけど(私もそう)しかしこれこそロックの醍醐味である。(それに気が付くには時間がかかったけど。)ちなみに私がキーンが作家活動していると気が付いたのは去年だか今年にグレアム・パーカーの公式サイトを閲覧したときに、パーカーの事も書いた本が出版されるというニュースがあって、編集者がグレッグキーンという事を発見してからです。結構面白そうな本なので米アマゾンなら買えるので買ってみようかな?しかしアマゾンの書評でも「ディスクジョッキー」と紹介されていたのには少し複雑な気分。さすがに新作を発表できる環境ではないという事だろうか?アル・ヤンコビックのパロディは、ビデオでは何故かクイズ番組が出てきます。何故そうなのか最初は気が付かなかったけど、米ではかなり有名なクイズ番組のタイトルが「ジェパーディ」だったので、そこからアルが発想をふくらませパロディ化したという事みたいです。その番組のファンサイトはここ。ビデオでは当時の番組の司会者アート・フレミング以下番組スタッフが総出演しています。しかし日本でもあった「パネルクイズ25」みたいな番組に見えるけど実際はどうなのかな?(現在でも同名のクイズ番組がいくつか存在するみたいです。)しかし絶対アメリカ人じゃないと笑えないネタだなあ。でもこの曲日本でも「クイズ・ジェパーディ」のタイトルで日本でもシングル化されていたみたいです。ちなみに米ヤフーのlunchではアル・ヤンコビックのビデオがかなり置いてある。しかし「今夜はイート・イット」のビデオがないのが残念。
2004年05月24日
コメント(1)
-
But It's Alright
前にもここで書いたインターネット・ラジオでよくオンエアされていて、それが元になって気に入った曲について。’80年代洋楽を語る上で外せないバンドの1つであるヒューイ・ルイス&ニュースが’94年に発表した全編カバー曲ばかりのアルバムである「Four Chords & Several Years Ago」にも入っていた曲で、シングルでも発売されてスマッシュ・ヒット(米54位)した曲なんだけど、長い間オリジナル版を聴いた事がなかった。「But It's Alright」 J.J Jackson何と言うか昔SPWFに上がっていた「アクション・ジャクソン」を思い出す名前だが(コアな人しかわからない事書いてすいません)なかなかかっこいい曲だ。なかなか豪快なボーカルで、朗々と歌い上げている。しかしこの人はどとらかといえば裏方だった人で、編曲とかの仕事が中心だったらしい。ヒューイ・ルイスのバージョンは基本的にオリジナルに忠実なんだけど、ボーカルはさすがに負けている。ヒューイは今ではかなりノドが衰えているけど、以前のヒューイならオリジナルに負けない歌声だっただろうから少し残念。でも彼らしいカバーなのでそんなに悪くない。この曲欧米ではかなり有名な曲らしく、コード表を載せているサイトもあったりする。なお英国ではかなりヒットしたらしく、そのためか彼は’70年から英国に移住したらしい。(その後の消息はつかめず。なおAMGの記述には一部間違いあり。多分同名の人と勘違いしている。)ちなみにMTV初期のVJにも同じ名前の人がいたけど全くの別人らしい。そのVJの方は今年亡くなったらしい。http://www.mtv.com/news/articles/1485838/20040318/index.jhtml?headlines=true日本では何故かこの人だけは多分VJとしては出ていなかったけど、当時の日本のMTVは地方ごとに放送内容が別だったので中にはこの人のVJ姿を見たことある人もあるかもしれない。しかしこの時代のMTVといえばブラック系の曲があまりオンエアされないため「人種差別をしている」と糾弾された事があったなあなんて事を思いだしたのだった。
2004年05月23日
コメント(0)
-
了解しました
remi10さん了解しました。削除いたしました。え~と確かに少しわかりずらい機能だと思いますのですごくわかりやすいフラッシュがありますのでこれを是非参考にして下さい。
2004年05月20日
コメント(1)
-
バックトラック
楽天でもトラックバック機能がついたという訳でここも今後はブログ状態が加速するという事かなと思う。「楽天広場」といえば、gooの「Gaiax」と並んで子供が多い事で有名だけど、現在多くのブログにはあまりそういう稚拙な所はないような感じだ。かえってブログが盛況になるにつれレベルの高い書き手を見かけるようになったと思う。つまり、掲示板感覚で書き込みをする人は思ったほど多くない印象がある。まだ始まったばかりなのでわからないけど、そうであるならこのトラックバック機能を歓迎したいとは思うけど。さてどうなるか?一応トラックバック機能は使わない設定にも出来るので、めんどくさい人やなんだかよくわからない人は使わない方が無難だと思う。場合によっては自身の書いた事が思わぬ広がりを見せる可能性があるのだから、注意は必要だ。しかし「トラックバック」で現在グーグル検索で1位になる所は、トラックバックを簡単に説明したフラッシュが閲覧できるブルグなんだけどこれの作者が「輸入盤シンポジウム」で一番わかりやすいまとめのサイトを作っていた人だったのには驚いた。(後楽天広場からの昨日からのトラックバックの多さも驚いた。)しかし楽天は普通に掲示板が常設している所なので少しややこしくなった。大体どこのブログでもコメントは書いた人が一々コメントをつけていないのが現状なので、今後私も「コメント」欄に何か書いても基本的には答えない事にしようと思う。どうしてもレスが欲しいというコメントは直接掲示板に書いて欲しいと思う。とにかく掲示板が今後使用が減るのだろう。でも面白い書き手はブログ界には沢山いるので今後私がトラックバックするという回数は増えるのだけは間違いない。個人的にはそういう面でも歓迎するのだった。
2004年05月19日
コメント(0)
-
クリーデンス・クリアウォーター・リビジテッド
今回のメルマガはリクエストがきっかけだったのですけど前から書いてみたかった事でした。もし洋楽の世界のトラブルをまとめた本を書くとしたら、CCRの訴訟合戦で十分1章書けるぐらい訴訟のニュースが多く、こんなにもめているとはCCR好きの私でも知らなかった。簡単にまとめてみれば。●ジョンがファンタジー・レコードを相手にレコード会社を移籍する訴訟を起こす。('75年頃?)●ソウル・ゼインツがジョンの曲に対して訴訟を起こす。('85年頃、この時CCRの曲が歌えなくなる仮処分が認められジョンはCCRの曲が歌えなくなる。)●ジョンは法廷外でビル・グレアムを頼りにソウル・ゼインツと交渉してCCRの権利が戻るように交渉するも不調に終わる。('86~'90)●トム・フォガティ死去。死因は実はHIVだったらしい。('90年)●「ロックの殿堂」にCCRが選ばれるもののジョンは式典に参加せず、久しぶりのメンバー同士の再会とならなかった。('93年)●残ったメンバーのスチュ・クックとダグ・クリフォードがCCRをナツメロバンドとして復活しようとするが、ジョンが名前の使用を差し止める訴訟('97年)そのためクリーデンス・クリアウォータ・リビジテッドという名前で活動しなければいけなくなる。●何故かスチュ・クックがジョンとダグを相手として訴える。「CCRの価値を不当に貶めている。」というのが訴状だったようだがこれは多分すぐ引っ込めたのだろう。現在でもスチュとダグは同じバンドで活動している。('97年)なんでこんなに仲悪いのかよくわかんないけど、確かラスカルズも同じ時期メンバー間で訴訟して、フェリックス・キャバリエが「ラスカルズの復活は100%ない」という状態まで仲悪くなったという話があったけど、ここまでいろいろあるとCCRの音楽が大好きな私としては悲しくなってしまう。しかし何が根底にあるかと言えば、やはりCCRのいたファンタジーというレコード会社に何かありそうだ。ファンタジーという会社は今でも健在で、主にリイシュー会社として存在している。しかしこの会社のカタログはなかなか通好み。元々メインだったジャズはデイブ・ブルーベックやビル・エヴァンズなどの作品があるし、あのスタックスのカタログも現在はここが所有している。またジョン・フェイヒーの興したタコマなんて完全に通好みのレーベルもこの会社と関係あったらしく、現在でもカタログはここから再発されている。なにせレニー・ブルースのレコードを出していた会社である。ブルースは沢山のレコードのあるコメディアンだけど、他にこの人のレコード出していた会社はスペクターのフィレスやザッパのストレイトなど。とにかく’60年代的な言葉でいえば「ヒップ」な会社だった訳だ。なおこの会社のカタログで「ロック」といえる人達はCCRぐらい。フォガティはインタビューで「とにかく小さな会社だった。」と言っていたけど、実際米ではよくある一介のインディ・レーベルだったのだろう。そこで登場するのがソウル・ゼインツというファンタジーの経営者になった人物。ゼインツは’55年からこの会社でセールス担当者だったらしいけど、このCCRと契約したのも彼らしい。それが大当たりしたため最初は彼の会社じゃなかったんだけど、’67年から経営権を持つにいたったらしい。CCRのおかげで結果ファンタジーは独立系では現在でもかなり大きな規模の会社になったんだけど、それではあきたらなくなり映画への投資を始める。'75年に公開された「カッコーの巣の下に」をプロデュース。チェコ移民だったミロス・フォアマンに投資したのは彼もロシア&ポーランド移民の子供というのも関係あるかもしれないけどこれが大当たり。アカデミー賞受賞作品にまでなる。ここからは本当に素晴らしい嗅覚を感じさせるプロデュース業が中心となる。この人は「最後の独立系プロデューサー」と呼ばれているらしいけど、とにかく作品のチョイスは神業的。いままで3度のアカデミー賞受賞作品('84年アマデウスと'98年イングリッシュペイシェンス)がある。その割にはプロデュースした作品は多くなかったりする。(アマデウスのサウンドトラックはファンタジーから出ているんだけど、まさかCCRと同じ会社とは発売当時は思っていなかった。)これ以外にも「存在の耐えられない軽さ」(’87)「モスキートコースト」(’86)「指輪物語」(’84)などの作品があるけど公開時にコケたラルフ・バクシのアニメ版「指輪物語」が、ピータージャクソンにより映画化されることにより、版権を持っていたゼインツにかなりの版権料が舞い込んだろうと想像される。現在はプロデューサー業より、ソール・ゼインツフィルムセンターという映画の版権や音楽などの権利の管理をする会社のトップとして君臨している。個人的にはフォガティとゼインツの対立は、少しフォガティが大人げない態度だったとはいえるけど、昔書いた曲が自分のコントロール出来ない状態にあるというのは確かに可哀想ではある。なかなか複雑な気分だ。でもゼインツはCCRの利益のおかげで今の地位があると考えたらもう少し譲歩してもよかったような気もしないでもない。そしたらCCRのメンバー同士の対立ももう少し解消されたかもしれない。しかし「Zanz Kant Danz」のビデオは粘土の豚が踊ったりしてなかなかかわいいビデオだけどこんな騒動起こしていてビデオまで作ったのだからフォガティも人が悪い。ちなみにCCR残党’は96年には来日していたらしいけど、今でも頑張っているみたいだ。エリオット・イーストン(元カーズ)の勇姿が見れるのは嬉しい。
2004年05月18日
コメント(2)
-
さようなら鈴木貴
本来ならメルマガについて書かなければいけないんだけど、さすがに今日はその気になれない。とにかくメルマガについては明日書きます。大阪近鉄バファローズの現2軍打撃コーチの鈴木貴久氏が、まだ40歳の若さで亡くなってしまったからだ。http://sports.yahoo.co.jp/hl?c=sports&d=20040517&a=20040517-00020635-jij-spoしかしとにかく突然なので少し驚いているけど、風邪をこじらせたという報道がされているらしい。鈴木貴といえば私はいつも思い出すのは、日本シリーズに出た時、彼の打席で解説の江川卓が「この選手ストライクだと何でも振ってきますね」と驚いていた事だ。今でも「いてまえ打線」と近鉄の打線は呼ばれるけど特に鈴木貴は思い切りのいいスイングをしていた。生涯成績を見ると思ったよりホームランは少ないんだけど、4年連続20本を打った時期にはかなり期待したのだった。(5番か6番をよく打っていた)でもケガと選手層の入れ替わりで不振に陥り、その後またレギュラーの座を手に入れたけどどうしても30本の大台には届かなかった。でもこの選手が打席に立つと私はいつでもホームランを期待していた。’84年にドラフト5位で入団。この年のドラフトは当たり年で、6位の選手以外は全て一時期レギュラーか主戦投手だった。今一軍コーチの山下和彦も同期だ。しかし今日の近鉄はよく勝ったなあ。タイムリー打った水口のコメントで少しホロッときてしまった。今年近鉄の2軍が高知でキャンプしていて、地元の新聞に載っていた記事には「近鉄は細かい守備練習は少なく、とにかく思いっきり振りぬくという事を主題にした打撃練習が多い」という記事だった。ああ鈴木コーチ頑張っているなあと思ったものだがまさか…お前の怪力で スタンドぶちこめ豪快に今日もまた 行け貴久とにかくご冥福をお祈りします。
2004年05月17日
コメント(0)
-
ソニー&シェールと著作権
今回はもしかしてあまり関係ないかもしれないけど実は関係ある事について。今回の著作権法改正案の問題が出てからよく行くライターの津田大介氏のブログで紹介されていたものなんだけどスタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授の講演をフラッシュで日本語の字幕を付けたものを視聴してみた。このレッシグ教授という人はここに簡単な紹介文があるけど要するに「サイバー法の大家」らしい。そんな人の講演なんだけど、多少難しい所はあるものの、私には面白いものだった。彼にとって最新作になる著作「free culture」の内容を簡潔にまとめているものなんだけど、完全なアジテーション演説でもあるので一応注意は必要だ。(でも私はこの人の思想は共鳴する。これまで出ている著作買わないといけないな。)この講演で気になったのは、やたら「Sonny Bono」って固有名詞が登場するんだけど、最初は別人かと思っていたけど、調べてみたらあの「ソニー&シェール」のソニー・ボノだった。ソニー・ボノについては私も「ヘアスプレー」の時取り上げているんだけど、’90年代から政界に進出して、最終的には下院議員まで勤めた事は知っていた。でも米の著作権界ではこの人は「ミッキーマウス法」と言われた著作権の延長を求めた法案の象徴的な人物として死後も有名な人物だった。(法案の名称は『The Sonny Bono Copyright Term Extension Act』)レッシグ教授はこの著作権の拡大法案に反対していてこの法案の裁判にも関わったらしいけど負けてしまった。つまりレッシグ教授にとっては、ソニー・ボノは不倶戴天の敵という事なんだろうと思う。(レッシグ教授の日本語で読めるブログにはこんな事書いている。)ソニー・ボノは’98年に事故で亡くなるけど、同じ選挙区から現在でも妻のメリー・ボノが下院議員として活動していて、彼女も著作権保護の立場から活動しているらしい。また一時期はあの今回の騒動ですっかり悪名高くなったRIAAの次期会長になるという噂もあったらしい。(しかしこの記事翻訳間違っているな。)しかしあのソニー・ボノがねえ。とんでもない物残してくれたものだなあ。「ヘアスプレー」でもイヤミな役だったけど、リアルでイヤミな人物だとは知らなかった。米ではこの法案に反対する動きがかなりあったみたいだけど、その現状についてはレッシグ教授のこのインタビューが参考になる。今回の日本での問題に本質的には関係ないけど、今回の改正法が米の著作権に対する保護の思想が日本にもやって来たと考えてみれば、海の向こうの話だと暢気に構える事も出来なくなるかもねえ。
2004年05月16日
コメント(0)
-
夢へのレクイエム
昨日からメルマガを書いていたけど、今回は丁度タイミング良いというかあまりミュージシャンにとっては良い話ではない事を調べていてなかなか面白かった。(当人にしてみれば、キャリア潰されたのだから面白いなんてものじゃないけど。)しかしこれが立場変われば業界にとっては「功労者」になるのだから不思議な話だね。(詳しくは月曜に)少し古いニュースだけどこんなニュースがあった。http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jinji/fu/news/20040428dde041060033000c.htmlヒューバート・セルビーJRを知ったのは何かの本にこの人の最初の作品「ブルックリン最終出口」について書いていたのを読んだのがきっかけだったと思う。とにかく一時結核で死にかけたとか、ホームレスになっていたとかそんな話だったと思う。その後あまり気にはしていなかったけど、たまたま深夜の映画にその「ブルックリン最終出口」が放送されていて、この映画の音楽がマーク・ノップラーだったのを知っていたのでそれが目当てで見たのだった。今となってはこの映画はジェニファー・ジェイソン・リーの出世作という扱いがされる程度だけど、見てみたらとにかく暗い映画だった。この「暗い」というのは映像そのものが夜の風景が多いいうのもあるけど、とにかく狭い社会から抜けられないという閉塞感が話全体にあって、そこから「暗い」と感じたのだろうと思う。しかし深夜映画で何も予備知識無しに見るには最高の映画だと思う。そして「レクイエム・フォー・ドリームス」の映画化である。この作品、監督のDarren Aronofsky がどうしても撮りたい映画だったらしく、当初はその内容ゆえに何処も配給したがらなかった映画らしい。その作品に作者のセルビー自身も参加して、脚本と主演している。話自体はとにかく単純な話なのに、この映画はとにかくリアリズムに徹していてそこが怖い。特に後半は全く救いのない状況が延々続く。ラストですら(ああ、まだ続くんだ)と思わせる所が凄い。この映画かなり世評は良くて、imbdでは現在52位の支持率(約3万票の投票がある。)なんだけど、確実にテレビでは放送できない映画だ。単純なドラマなんだけど私にはホラー映画だった。そういう訳でこの2作がセルビーの代表作という事になるだろうけど、実はもう1作映画の脚本に関わっているらしい。それがこの作品。http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/film/16745.htmlこの映画、英国、デンマーク、カナダの合作という物なので今のところ日本では公開未定みたいだけどジョン・タトゥーロ出ているし、音楽はブライアンイーノだしそのうち日本にも入ってくると信じよう。ちなみにもう一作原作を担当している映画があるらしいけど、フランス映画なのでよくわからなかった。なおセルビーにはちゃんと公式サイトがあるのでそこに行けばもっといろいろこの人についてわかると思う。しかしジェリー・リー・ルイスの伝記書いてデビューしたニック・トシスと親密だったとは知らなかった。とにかく死の淵からここまで長く活動できたのは幸せな一生だっただろうと思う。http://exitwounds.com/Hubert-Selby-Jr-2.htm
2004年05月15日
コメント(4)
-
音楽関係者の記者会見について
すでに一部で報道された通り、今日文部科学省記者クラブ内で、今回の著作権法改正案に反対する音楽関係者の記者会見が行われました。いままで動きが鈍かったマスコミ関係者ですが、今回のこの会見は今のところWeb版の朝日新聞とTBSテレビが報道しています。TBSテレビの報道の模様は動画で見る事が出来ます。(TBSニュースのサイトの「逆輸入CD制限に関係者が反対声明」をクリックしてください。なお明日には消えていると思いますのでお早めに。高橋健太郎氏が喋っています。)web版朝日では、一時期トップ記事にもなっていたみたいです。実はこの記者会見を仕掛けたのはまず間違いなくこの新聞社の力が大きい筈です。シンポジウムも実はそうだったのですが、普段いろいろ言われる所ですけどこの件に関してはこれからも頑張って欲しいです。これ以外にもタワー・レコードのbounce.comが報道しているみたいです。なおこの一連の問題に関連しまして、itmediaが特集を組んでいます。一回目がシンポジウムの模様。2回目が文化庁法規課長のインタビューとなっています。なかなか面白い記事です。是非興味ある人は一読を薦めます。この流れだと3回目は音楽業界の人が登場するかな?なお国会審議の方はもう委員会は開催されていますがこの改正法案の審議はもう少し後になるみたいです。
2004年05月13日
コメント(0)
-
気が付けば
近頃気が付いたけど、千葉ロッテがダントツの最下位になっていた。まあここ最近10試合の成績見たら1勝9敗なんだから仕方ないけどここまで落ち込むとは全くの予想外だった。今日も打たれて最悪の負け方だった。このままでは去年のオリックスみたいに投打共に最悪の状況に陥るかもしれない。パリーグの火を消さないためにも頑張って欲しいものだ。リーグ1の投手陣の奮起がカギだと思うけど、少し配置換えが必要になっているかもしねない。とにかく昨日の続きを少し。あと登場する人はジャッキー・ウィルソン、シャングリラズヤング・ラスカルズ。マーサ・リーヴス(マーサ&ヴァンデラス)そしてジェームス・ブラウンとなるんだけど、さすがに知名度ある人が多いのでまあいいか。ジャッキー・ウィルソンについては以前にも少し書いているし、シャングリラズはマニアの多い女性コーラスグループなので結構いろんなサイトに載っているので面白いよ。というのも書いていて消しちゃったので、またわざわざ書くのが面倒なだけなんだけどね。しかし著作権絡みで、Winnyの作者が逮捕されたり、今後こういう感じに厳格な姿勢を見せていくのかなあという感じですかね。私はセキュリティが甘くなるので使わないけど、確かに便利な物ではある。こういう新しい技術には今までの著作権の概念とは違った形の新しい概念が必要となっているという事なんだろうと思うけど、技術の進歩に従来の制度が追いつかない時代に来ているんだなあという感じです。
2004年05月12日
コメント(0)
-
「R.O.C.K In The U.S.A.」の背景
まずは昨日予告した事を書く前に、先週取り上げた著作権法改正案に反対する動きに関して大きな前進がありました。それについて。シンポジウムに参加していた高橋健太郎氏のブログに「72時間後には大きな動きが」とか書いていたんですけどこれのことだったんですねえ。そのうえちゃんと反対の記者会見まで行うのですからこれは面白くなってきました。(しかしこんなに音楽ライターっているんですね。その数の多さには仕事面でのリスクを考えると少し驚き。ミュージシャン達もかなり数が増えました。)どうやら明日には衆院の委員会審議も行われるみたいです。しかし4月にこの問題知った時点を考えるとかなり広範囲にこの問題が論じられるような機運が広がってきたという感じがしています。参議院の時のような「可決を前提とした」審議状況とは違った議論を期待します。さて「R.O.C.K In The U.S.A.」という曲、歌詞に実際の’60sのミュージシャン達が歌われています。かなりメレンキャンプの趣味が反映されていますけど、メジャーとマイナーの中間みたいな人が多いのでなかなかいい趣味しているなあと思います。まずフランキー・ライモンですけど、ティーンエイジャーズというコーラス・グループを率いて'56年に「Why DoFool Fall In Love」という曲を米でヒットさせています。この当時フランキー・ライモンは14歳。ジャクソン5のような子供がボーカルを取って歌うグループの先駆けのような存在です。この曲は米では完全にスタンダートナンバー化していて、様々なカバー曲があります。しかし大きなヒットはこの曲だけで、その後は人気が落ちてしまい。ライモンはソロ活動もしますが、これもパッとせず、どんどんドラッグに溺れて、’68年にまだ25歳の若さでドラッグの過剰摂取のため亡くなっています。アメリカ版「アイドル残酷物語」として今でも有名な話です。http://www.history-of-rock.com/lymon.htm(バイオや写真を載せている所です。)メレンキャンプの曲では少し「Ain't Even Done With TheNight」('81年 米17位)に影響あるかな?次のボビー・フラーは4人組のボビー・フラー・フォーというグループで、とにかくクラッシュのカバーで有名な「I Fought The Law」をヒットさせた事で有名なグループです。結構下積みの長かった人たちなんですけど、やっと売れ出した途端にリーダーのボビー・フラーが停車中の車の中で亡くなっているという不可思議な事件によっても今でも有名です。(死因は窒息死らしいです。)バディ・ホリーの模倣者としても有名で、この「I Fought The Law」はホリーのバック・バンドのメンバーの曲ですし、(ちなみにフラーは’61年からこの曲を歌っていた。)次のヒット曲はバディ・ホリーの作った曲でした。メレンキャンプの曲では影響を受けたと感じ取れるのは何と言っても昨日も少し取り上げた「Authority Song」がもうそのままスタイルを真似ています。なおメレンキャンプはバディ・ホリーもその後「Rave On」をカバーしています。(『カクテル』のサントラ盤に収録されています。)ミッチ・ライダーはデトロイト・ホイールズを率いて活動した歌手ですけど、そのシャウト型のボーカルとライブ形式の録音スタイル。また過去の曲をメドレー調にしてうまく編曲した曲の数々で全盛期は短かったものの人気の高かった人です。この人は同郷のボブ・シーガーあたりにも影響与えていますけど、今聴いてもこの人のサウンドはカッコイイ。なおこの人の公式サイトは現在でも存在します。しかしこのサイトは「楽天広場」でサイトもっている人見たいな感じだなあ。でも現役にこだわりがあるんだろうと思います。別の公式サイトでは映像や音楽がかなり視聴できます。しかしこの人のソロ活動期の作品は現在殆ど未CD化なので、どこか有志が出してくれないかな。買うよ。ソロ名義で出た「What Now My Love」なんて殆どギャグ寸前の過剰なボーカルで楽しましてくれる。メレンキャンプはこの人のカムバック作となった「Never Kicks A Sleeping Do」をプロデュースしていますけど、プリンスの曲の「When You Were Mine」をロマンティックス風にアレンジしたバージョンをシングルで小ヒットさせています。(’83年 米87位)しかしボーカルの衰えは隠せない。惜しい事だ。あと何組かありますけど、また明日でも書いてみます。
2004年05月11日
コメント(0)
-
Authority always wins
今日はいろいろニュースがあったみたいだけどとりあえずメルマガの事について。まずどうやら来週から週刊維持が難しくなりそうです。場合によれば長期休暇の可能性が出てきました。詳しくは次号のメルマガに書きます。今回取り上げたジョン・メレンキャンプは’80年代を中心にかなりのヒット曲の数がありますけど、実はまだ出していない作品が結構あります。まずは全ての時代を網羅したベスト盤がありません。’80年代の作品集はあるんですけど、’90年代以降の作品を集めた物はありません。あとはライブ盤を未だにだしていません。これは何故なんだろう。プロモではライブ風景を映したビデオがあるんですけどね。あと何気に「未発表曲」や「シングルのB面曲」にレアな物が多い人ですけど、今でもそういった作品を集めたボックス的な作品はありません。しかしこれはそのうち出ると私は思っています。今回調べていて面白かったのは少し古いこのニュース。http://www.tvk42.co.jp/top40/topicks/020131.htmlメレンキャンプって実は家を買う歌を作った事あるんだよねえ。(『Check It Out』の事。’87年にヒットしている。)そんな人に手抜き工事をしてしまったのは失敗だという事だろうけど、いかにもというニュースでした。彼が監督した映画「Falling From Graces」について、私はこの映画見た事ないですけど、CNNの映画紹介のコーナーで少しだけ映像を見た事があります。しかしビデオ発売はされていたとは知らなかった。脚本書いたのはラリーマクマートリーで、「ラスト・ショー」('71年)「愛と追憶の日々」('83年)の原作者ですが、彼の息子のジェームス・マクマートリーは歌手としてデビューした際にメレンキャンプがプロデュースしています。そういったつながりから生まれた映画で、この他にもソングライター・歌手のジョン・プラインが出演しているみたいです。その後もスティーブン・キングと一緒にミュージカル作っているなんてニュースもありましたけど、これはどうなったのかな?そういえばこの「Authority always wins」というタイトルですけど、彼の曲の「Authority Song」から取ったものです。私はこの曲の歌詞今でも好きです。なおメルマガに書いていた登場ミュージシャンについては明日書きたいと思います。
2004年05月10日
コメント(0)
-
シンポジウム動画を視聴
このシンポジウムがそれなりに効果あったのかどうか知らないけど、一部マスコミや雑誌なども特集する動きが出てくるようになってきて、何故かこの時期に日本レコード協会も不思議な声明文を発表したりして問題の沈静化に図ろうとしているけど、そもそもすでにレコード協会は参院審議でこの問題の確認書を提出しており、その内容と同じく殆ど意味のない空文である。こういった文書を出すより、全米レコード協会なり国際レコード産業連盟などの団体からのはっきりとした意思表示の文書がなければ日本のレコード協会がどういう意思をもっていようが輸入規制が海外法人の意思により公然と行われるという事になってしまう。(そんな構成の法律になっているのだ。)という訳でやっとシンポジウムの動画を視聴してみた。(ダウンロードしたい方はここから)私はピーター・バラカン氏のNHKで初めてこの人がDJやりはじめた頃からのファンだけど、(今でも最初の番組のテープ持っている。)私の田舎では「CBSドキュメント」は放送していないので久しぶりに映像で見る事ができた。少し年食ったけど、元々若白髪だった人なのであまり変わっていない。司会役なのに実は結構神発言が多い。さすが一言多いのは全然変わっていない。「プートレグと海賊盤は違う」(これはその通り)「音楽業界は購買者を犯罪者予備軍と扱っている」ちなみに動画版には約3分程度編集した箇所があります。(ほかにも実はありますけど、まだ特定できない)これは「反対しているアーティストはいるのか?」という観客の質問を受けて実際に反対しているアーティストが出てくる場面です。この模様は音声版でないと模様がわかんないですけど、この問題に公然と反対できない立場があるという事だと思います。にもかかわらず出席した約3名のアーティストには敬意を表したいと思っています。しかし高橋氏なんて私が洋楽聴き始めた時期から評論していたけど今でもあまり変わっていないのには少し驚きました。あと佐々木氏は文章と同じく理路整然とした話振りで、レコード会社の価格設定の内幕を暴露してくれます。(なお石川氏、高見氏も同様のなかなか厳しい業界の現状を話していました。)しかし中原氏はまた音楽活動再開したとは知らなかった。それもエイベックス所属とは?エイベックスという会社は不思議と懐広いのが面白い。あと某エンジニア氏の発言は怖い話だ。リージョンコード付きCDとか追跡可能なMP3とかそこまでしなくては確実な利益が出ないという事でしょうけどあと3年もすれば本当にネット上に音楽がない時代が来るかもしれないなどと思ってしまいました。まあ米の産業の底の深さに期待するしかないですけど。約3時間程度あるものですけど、これからの音楽のあり方を知るには面白いものです。是非皆さんダウンロードして視聴なりしていただきたいと思います。
2004年05月08日
コメント(2)
-
消しちゃった
今日書いた事は消してしまった。そのうちまた書いて見よう。昨日書いた件に関連して、すでにシンポジウムの様子は音声、動画、テキスト版がすでに様々な場所でダウンロードできますけど、動画は特にファイル・サイズが大きいのでご注意下さい。しかしこういう風に一部の有志の人が頑張ってこの問題を広めてくれるのはネットの世界も悪い人ばかりでもないなあとかなり見なおしています。皆さんありがとう。私も来週のメルマガにはまたこの件を載せる予定です。ちなみにこの問題に関連しないんですけど、年金法案の修正が自民、民主、公明の3党で合意しましたけどこれ実は結構関連あります。年金法案の審議が長引く事になれば、当然一番早く通したい法案なわけで、他の法案の審議も遅れる事になるんです。しかしこのままでは早期成立が確実となってしまいましたので、大きな問題もなく個々の法案審議も日程通りに進む事になります。という訳で、参院で全会一致の法案なんてあまり審議されず委員会採決なんて可能性もあります。しかしなかなかこの問題を知らせるのは難しいですね。とにかく問題が多岐に渡っており、表向きは権利保護が目的だから公然と反対するのはなにか後ろめたい事でもあるんだろうかと勘ぐる人も多分いるのではないかと思います。個人的にこの問題に何故反対するかといえば、これにより日本の洋楽文化が崩壊するからなのですけど、何故そうなるかを説明するのが2重、3重の話なので難しいです。だからマスコミ的にもあまり問題になっていないんじゃないかと思いますけど、一部では取り上げる動きが出てきたのがうれしいです。とにかく明日もこの件を書きます。
2004年05月07日
コメント(1)
-
5月4日著作権シンポジウムを視聴
以前から気になっていた著作権シンポジウムについてやっと視聴出来たので書きたいと思います。このシンポジウムは5月4日に開催されたものでタイトル「選択肢を保護しよう!! 著作権法改正でCDの輸入が規制される? 実態を知るためのシンポジウム」場所:新宿ロフトプラスワン司会進行:ピーター・バラカンパネラー:民主党 川内博史議員(衆院議員 比例九州)音楽評論家/HEADZ代表 佐々木敦氏輸入盤ディストリビューター、リヴァーブ副社長 石川真一氏イースト・ワークス・エンタテインメント 高見一樹氏音楽家 中原昌也氏(小説家・映画評論家)ビルボード誌日本支局 スティーヴ・マックルーア氏Rimix スーパーヴァイザー 野田努発起人:ピーター・バラカン、高橋健太郎(音楽評論家)協力:藤川毅(音楽評論家)パネラーの多くが業界関係者ですが、これ以外にも大手レコード会社の人やミュージシャンや文化庁の職員にも声をかけたらしいですが参加を断られたそうです。このシンポジウム開催のきっかけはバラカン氏と高橋氏が連載している朝日新聞の担当者からこの問題を聞かされて、そこからシンポジウム開催へと至ったそうです。実際には高橋氏がかなり様々なセッティングを行ったそうです。業界関係者が中心に開催されたため、語られた内容は今回の改正法案にとどまらず、実際の輸入盤取引の内幕や、著作権管理団体についての話、海外レコード会社の思惑や、租税条約との関係。還流CDについての現状。再販制度の問題などかなり様々な内容が討議されました。昨日の時点ではまだこの模様は音声とテキスト形式(一部)でしか視聴できませんでしたが、今日になって動画も配信可能となったようです。そのリンクをまとめた所はここにあります。またこのシンポジウムをまとまたサイトはここです。大まかな議論の流れとしては、前半はパネリストが個々に現状の問題点を指摘し、後半から質疑応答となっています。前半は真面目に討議していますが、後半からなかなかエグイ発言が増えてきます。全編聴いてみて感じた事について書いてみますと、どうやらやはり規制される方向に固まってきているという感じがしました。結局米国の知的財産管理の方向は、今後のグローバリズム時代を迎えていかに多国籍企業の利益を確保するかという問題に関して、本国では出来ない権利行使を行使しやすい日本で行おうとしているという事だと思います。しかしまさか輸入盤が買えない時代がやってくるとは思わなかった。本来グローバリズムというのは自由な商行為が基本になるという事だった筈だけど実は大手多国籍企業にとっての自由だったという話です。そういう世界では段々消費者は不自由な選択が増えるという事になってしまいます。去年あたりから、米盤にもかかわらず日本で購入できないCDがポツポツ出てきているのを知っていましたがやはり以前から規制を考えていたという事だと思います。とはいえ流れにさからうのも厳しい世の中になってきました。とにかく現在の法案の審議状況は5月下旬から委員会審議が始まるみたいです。RIAAのパブリック・コメントを文化庁が隠していた件から何とかまだ数は少ないですが反対派議員達には頑張って廃案なり修正案を勝ち取って欲しいものだと思います。今後もこの問題を追いかけていきたいと思います。
2004年05月06日
コメント(6)
-
You Are My Starship
今日は西武vs近鉄戦を見たけど松坂が未だに1人相撲をする癖が抜けないのを見ることが出来た。しかしあまり近鉄の方も褒められた内容ではなかったけど、赤堀を久しぶりに見れたのでよしとするか。しかしあれだけ故障しても今でもMAX147キロは凄い。まだ細かいコントロールがないので抑えは無理だけどこのまま故障しなければ本当に抑えになるかもしれない。それはともかく、月曜に少し書いたけど、今よく聴いているインターネット・ラジオはここだったりする。http://www.kxgq.com/実はインターネット・ラジオでクラシック・ソウル物を流すラジオ局は思ったより少なく、そのため前からここを良く聴いている。実はここは選曲が大体一週間程度同じ物を流していて’60年代から’80年代のソウル・ミュージックのヒット曲が中心。売りの言葉が「ドウ・アップなしラップなし。」だったりする。しかしここがいいのは、何といっても、「曲目表示が出ない」点に尽きる。本来多くのインターネット・ラジオはプレイヤーやプラウザに現在流れている曲の表示があるのだけど、このラジオにはそれがない。ゆえに何が流れているか自分で調べなくてはいけない。しかし、元々昔から雑音ばかりのFENで曲の歌詞をたよりに曲名調べていたので、それを少し思い出して気になる曲は調べたりして聴いたりしている。今は資料も持っているので大体わかるけど、’80年代のものには結構苦労させられたりする。たとえばこんな感じの選曲だったりする。Sweet Inspirations 「Sweet Inspiration」Brook Benton 「Rainy Night In Georgia」Enchantment 「Gloria」Sister Slage 「He's A Great Dancer」Manhattans 「There's No Me Without You」Lou Rawls 「Love Is The Hurtin' Thing」Tyrone Davis 「Turning Point」Miracles 「More Love」これは一例で、一応有名なヒット曲とか少しだけ白人のヒット曲とかもオンエアされるけど何ともいえないマイナーメジャーな選曲がなかなかよろしい。しかしこのラジオ局オークランドにあるみたいだけどタワー・オブ・パワーがオンエアされないのは何故なんだろう。あと何故か3日前から格段に音が良くなった(回線速度が速くなったため。)のだけど、やたら接続不良が増えた。まだまだこれからのラジオだろうね。ここで以前よくオンエアされていたのがNorman Conners 「You Are My Starship」今では日本でもCDがまだ手に入ると思うけど、いわゆる「クワイエット・ストーム」系の有名な曲なのでラジオで聴いた事ある人もいるかもしれない。ボーカルをマイルス・デイヴィスのバンドのベーシストだったマイケル・ヘンダーソンが担当している。この人はこのヒットですっかり歌手になったけど、今ではまたジャズ系のバンドでベース弾いているみたい。’00年にノーマン・コナーズがアルバム出していてここで久しぶりにこの曲を再演しているけど、この時のボーカルはピーボ・ブライソン。ヘンダーソンとはタイプが違う歌い手だけど、このバージョンもなかなかいい。一度聴いてみるといいと思う。
2004年05月05日
コメント(0)
-
反逆の歴史
このタイトル気に入った。ビリー・アイドルの2枚目のアルバム「Rebel Yell」の邦題が「反逆のアイドル」だった事を知っていればよくわかる邦題だけど個人的にかなりウケました。今回はシンプル・マインズだったわけですけど、どうもこの曲に関してはこのバンドの作品の中でもかなり異質な感じがして改めてこのバンドの曲を取り上げてみたいと思っています。しかし本文にも書きましたけど、「See The Light」という曲。個人的にはこのバンドの曲の中でもベストだと思っています。始め良し、中良し、サビ良し、エンディング良し、歌詞良し、ギター・ソロ良しという曲で、’90年代のヒット曲の中では個人的にベスト5には入る曲です。アルバム「Real Life」か、ベスト盤に収録されていますので聴いていない人は一度お試しあれ。シンプル・マインズがトリを取ったコンサートで印象深いのは、ネルソン・マンデラ解放記念コンサートがあります。この頃は米では人気が落ちたけど、まだ本国英国での人気は絶大なものがありました。私はてっきりピーター・ガブリエルがトリを勤めると思っていたけど、このバンドでも違和感はなかったです。このコンサートにはクリッシー・ハインドも出ていてジム・カーがクリッシー呼ぶシーンがあるんですけどこのコンサートが行われた年にこの2人は離婚していて、そのためかどうもぎこちない感じだったりします。(日本ではNHKで放送されました。)ちなみにマンデラさん関係の大規模コンサートってつい去年にも行われていますね。http://music.yahoo.co.jp/rock/music_news/barks/20031202/lauent009.html映画に関していえば、この映画は私見た事ないのでどうこう言えません。ただ、ジョン・ヒューズ関連作に関してはそのうち別の曲の時にまとめてみたいと思っています。今では米ではかなり再評価されている監督で、この人の青春映画の大ファンという若いクリエイターが少なくないみたいです。なおメルマガに書いたE.G・デイリーとジョイス・ケネディは「一発屋列伝」の「またまた5曲」のページにまとめています。特にE.G・デイリーに関しては驚きの連続でした。最後にメルマガに関連しない話ですけど、近頃よく聴いているインターネット・ラジオが格段に音質が良くなっていました。ここに関しては明日あたり取り上げてみよう。
2004年05月03日
コメント(0)
-
新ストッパー福盛?
しかしなかなか黒木が勝てないのは惜しい事だ。とはいえ千葉ロッテが深刻なのは小林雅で勝てないという事だろうね。先週の日曜の試合が全国放送されていたので対オリックス戦見たけど完全にストレートを中心に狙い打たれていた。小林雅の球が狙い打たれる場面なんて久しく見てなかったけど、そういえばオールスターで思いっきり打たれた時がそんな感じだった。ただシーズン中に変更が利くだろうと思っているのでどこかのチームの抑えだった投手のような事にはならないとは思うけど。その何処かのチームの抑えだったカラスコという人は結局2軍に落ちたけど、どうやら一時的な降格らしい。たしかにあれだけ早い球持っているし、オープン戦なんか殆ど打たれていないから、復活の可能性はあるかもしれない。でも個人的にはあまり待ちたくないねえ。ダイエーの抑えの三瀬も打たれてしまった。しかし個人的には鷹野に打たれたとはいえ1アウトランナーなしなんだから替える必要なかったと思うよ。王監督の悪い癖が出たという感じだ。しかし今後ダイエーは投手陣が去年のような安定感がないままだと結構苦しむかもしれないね。竹岡も打たれたしなかなか新戦力だけで乗り切るのは難しい。しかし、近鉄もついに赤堀が帰ってきた。嬉しいな。とにかく近年は少し投げればケガになるという事で殆ど活躍していないけど、かっての絶対的な抑えである。さすがに抑えは無理だろうけど、中継ぎならまだやれると思うよ。しかし近鉄というチームはこと投手陣に関してはベテランばかり元気がある。吉田豊彦(公式HPの日記は面白い)加藤(34球場制覇おめでとう)小池(命投法)赤堀。ここだけやたら平均年齢が高いけど、みんな味のあるベテランなので見ていて面白い。しかし本当に福盛抑えなのか。この投手はデビューした時から殆ど投球スタイルが変わっていないけどかっては「ナチュラルに落ちる球」の持ち主だった。この不思議な球種の持ち主として一番有名なのがあの王監督に756号を打たれた鈴木康二郎だった。しかし鈴木康も後に近鉄にトレードされて抑えで活躍したので、福盛でもやれる筈だ。なにせ権藤監督から抑え指名された事もあるんだよ。(でもシーズンもたなかったけど)という訳でまだまだ長いシーズンは続くのだった。
2004年05月01日
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-
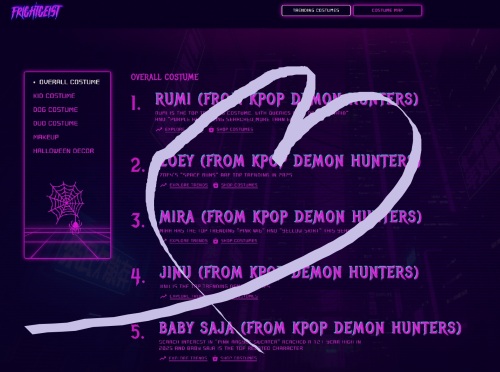
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-
-
-
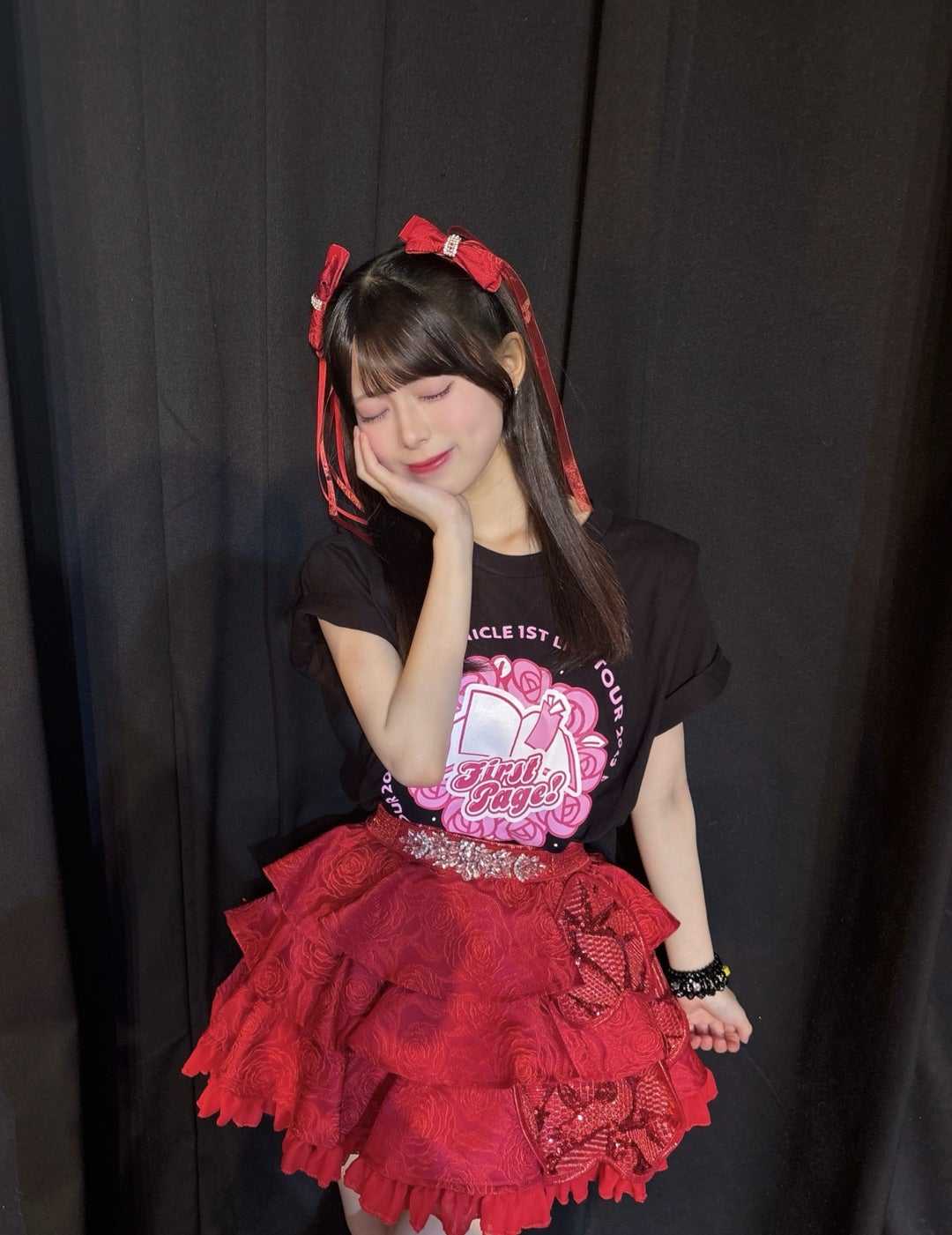
- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【上村麗奈(ロージークロニクル)】ツ…
- (2025-11-14 14:16:33)
-