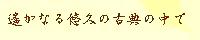おちくぼのあかね姫 4
早速、友雅に知らせた。
二人で、あかねを守りに行くことにした。
屋敷中が大騒ぎで出かけた後、あかねと藤姫は二人、おちくぼの部屋で過ごしていた。
「縫い物もなくて、なんて気楽。ようやくお休みがもらえた気分だわ。詩紋くんがいっちゃったのは、ちょっと困ったわねえ。」
「大丈夫です。代わって守っていただく八葉をお呼びしてありますから。」
「……友雅さんではない?」
「大丈夫です。頼久です。私の部屋に居ていただくようにしますから。神子様のこのようなお姿は、決してお見せしません! ほんとうに、北の方も、もう少しまともな物をくださればいいのに……。母君様からいただかれたことになっている調度の品も、何だかずいぶん、北の方や姫君方の部屋にあるようですよ。あの鏡の箱とお揃いの調度がけっこうありますもの。」
「そうねえ。継母って、そういうものなのかしら。シンデレラのお話でも、シンデレラは継母に財産を全部取られてしまうのよ。」
露が部屋の外で藤姫を呼んだ。
「頼久が来たようです。ちょっと失礼いたしますね。」
藤姫は部屋に戻った。
「本当に人が少ないのですね。神子殿は?」
「お部屋でくつろいでいらっしゃいます。今日は、北の方が持ってくる縫い物もなくて、のんびりしておいでですわ。」
「あの、取り次いでくれた露という少女は? おそばにおいて大丈夫なのですか?」
「あれは、泰明殿が送ってくれた式神です。私が直接召し使う者がなければ不自由だろうと。」
「それはよろしゅうございました。」
あかねの部屋の方で、ことん、と音がした。
「何かしら、御格子を動かす音に似ているけれど……。神子様が御格子を?」
「気楽にしておいでなら、外の月でもご覧になるのでしょう。今日は美しい月夜です。」
「ならよいのですけれど……。頼久、見てきてください。」
「承知しました。」
頼久があかねの部屋に向かうと、そこには友雅がいた。
「少将様……」
「神子姫は私が守る。頼久は、藤姫を見てやってはくれまいか。」
「はあ……」
「大丈夫、無体なまねはしないから。藤姫にもそう伝えておくれ。」
頼久は、返す言葉もなく、藤姫の部屋に戻った。
「何もございませんでした。神子殿は、月に見とれておいででした。」
藤姫は安心して、頼久に続けて警護を頼むと、自分もゆっくりと休むことにした。
友雅は、あかねの部屋にすべりこんだ。
いつも見慣れた姫君方の部屋と違い、身を隠す几帳も屏風もないのが、友雅をとまどわせた。
あかねは、日頃の疲れからか、ぼろぼろの綿入れにすっぽりとくるまって、静かに寝息を立てていた。
友雅は、そんなあかねが愛しくてたまらず、思わずそばへ寄って抱きしめた。
「……!」
あかねはびっくりして目をあけた。
「……友雅さん!」
あかねはうれしかった。でも、同時に、ひどく恥ずかしかった。穴があいて素肌が透けそうな着物、はげちょろけの袴、ぼろぼろの綿入れ……おしゃれで美しいものが好きな友雅の目に、自分はどのように写っているのだろう……。
「神子姫……! 無事でよかった……。心配したのですよ。」
あかねは返事もせず、友雅の腕から逃れようとした。
「何故お逃げになる、かわいい人。私が来たのがご不満ですか? 文もたくさん差し上げたが、返事がないので、もしや鬼に命を取られたのではと気が気でなかったのに……。」
「許してください。お返事は書けなかったんです。」
「では、今宵こうしてお訪ねしたことをお許しくださるか?」
「それは……。」
あかねは必死で逃げようとした。友雅の腕の中で、あかねの体が小刻みにふるえる。友雅は、あかねを抱く腕にいっそう力を込めた。
「私があなたを守る、私の姫君。今まで、こんなに本気になれたことはない。逢うが限りの逢瀬と……でも、あなたのことは心からほしいと思う。あなたを守れるなら、命を懸けてもいいと思える、不思議だねえ、私がこんな気持ちになれるなんて……」
「友雅さん……」
「さあ、こちらを向いておくれ、いとしい人。かわいい顔を見せて、私を安心させてはくれまいか。」
あかねは、友雅の腕の中で、堅くなってふるえるばかりだった。
「神子様が泣いていらっしゃるわ!」
藤姫の耳に、進退窮まってすすり泣くあかねの声が聞こえた。
「何が起こったのかしら、頼久、神子様は?」
「大丈夫でございます。」
「大丈夫なはずがありません、泣いておいでではありませんか。もしや、頼久、友雅殿がおいでなのではないでしょうね。」
頼久は返事ができなかった。
「おいでなのですね! なんということでしょう。今まで神子様がお返事をなさらなかったのは、特別な事情がおありのことでしたのに! きっと、とても困っておいでなのだわ、なぜ、教えてくれなかったのです?」
「それは……。少将様も、『無体なまねはしないから』と、私も神子殿をお守りしたかったのですが……」
「これでは、神子様にお知らせせずに、友雅殿をお守りにお呼びしたように思われてしまいます。ああ、私、神子様にきらわれてしまいそう! この状況で、友雅殿が何もなさらないはずがないではありませんか!」
頼久も、だんだん不安になってきた。
友雅は、言葉通り、あかねにそれ以上の要求はしなかった。
あかねのいやがる理由が、自分に対する感情でないことに気づいたのだ。
(おや……凄いものを着せられている……これでは、恋は語れないね。)
友雅は、黙って、自分の単衣を脱いだ。あたたかそうな梔色の絹の単衣だった。
「はじめて情を交わした男女は、その後朝に、互いの衣を取り替えるのだよ。互いが互いの側にずっと居るようにと。私と神子姫にはまだ何もないけれど、私はなんだか、姫と心がつながった気持ちがするのでね。姫は本当は私のことをどう思っているのだろう。少しでもいとしく思ってくれるならうれしいのだが。」
「好きです……でも、ごめんなさい。」
友雅はふっと微笑むと、衣であかねをそっと包んで、部屋を出た。外では、藤姫と頼久が待っていた。
「友雅殿、黙っておいでになるのは……」
藤姫が不満げに口を開いた。
「頼久に文を何度も届けさせましたから、おわかりだと思っていましたが?」
「急においでになってはいけません。神子様がお困りです。」
「そうだろうねえ、こちらの北の方の仕打ちは実にひどいね。一刻も早く、姫をここから救い出すことにしよう。藤姫様、手伝っていただけますか?」
「もちろんです!」
「では今宵また。神子姫のおそばに。」
夜の明ける前に、友雅と頼久は中納言殿を後にした。
「神子様、ご気分は……」
藤姫は、おそるおそるあかねに声をかけた。友雅の衣の中から、顔を真っ赤に腫らしたあかねが現れた。
「……衣をおいて行かれたわ。」
「では、神子様と友雅殿は!」
「何もないわ。いつものようにされただけよ。でも、なんだか、私と心がつながった気がすると言って、この衣をおいていかれたの。きっと違うわ。私があんまりひどいものを着せられているから、かわいそうに思われたんだわ。ああ、恥ずかしい……。もう、逢えないわ。」
露が文を持ってきた。
「友雅の少将様からです。」
後朝の文だった。帰り道に移動しながら書いたとしか思えない素早さだった。
「こんなに早く届けておいでなんて……きっと、友雅殿は、神子様を本気でお好きになられたのですわ。」
「……そんなようなことも言っていらしたわ。」
藤姫は、友雅を本当にあきらめなければならない日が近いのを感じた。あかねが友雅を最も気にしているのはすでに感じていたし、友雅まであかねに特別な気持ちを抱いているなら、もう、藤姫の入る隙間はないのだろう。
こうなったら、二人には必ず幸せになってもらわなければ。かなわなかった初恋のためにも、藤姫は心に決めた。
次へ
© Rakuten Group, Inc.