身近なくらしの衛生シリーズ-カビ
身近なくらしの衛生シリーズ-カビ



期間限定シリーズ、今回は身近なくらしの衛生についてページを作ってみました。テーマはすばり、「カビ」。沖縄はいよいよ「梅雨入り」。やっかいな「カビ」との格闘が始まります。僕も元・環境衛生監視員の端くれ、この時期の共通の悩みを解決できる手助けができたら…と思い、「カビ」についてのうんちくをたれてみました。これが、家庭でのカビ対策の手助けになれば、嬉しいですねぇ。
(1)まず、結露対策!
1.家庭でのカビ対策、特効薬はあるのかな?
ずばり結露対策!これに尽きます。だけど、これだけでは味気ないですね。ですから、結露対策をまずお話しさせてもらって、それを踏まえてカビ対策をお話ししましょう!
2.では、結露について教えて!
結露とは、ある温度において、ある一定の体積に含まれる水蒸気が、温度が下がることによって、支えきれなくなった余分な水蒸気が水滴になって起こる現象です。例えば、25℃の空気1立方メートルが含むことのできる水蒸気の量は24.1gですが、この空気が温度だけ15℃に下がると、13gしか水蒸気を含むことができず、残りの水蒸気は水滴になります。これが「結露」です。
3.では、どうして結露防止が必要なの?
ある程度の湿気は、鼻や喉の粘膜を保護するためにも必要ですが、過剰な湿気は結露を生じさせ、ダニやカビの成育に好条件となってしまうので、居住環境の悪化にもつながってしまうからです。
4.季節によって、結露の発生パターンは違うのかな?
冬型結露の場合は、室内の高温多湿の空気が、冷たい窓ガラスや壁に触れて温度が下がり、水滴となります。夏型結露は、梅雨から夏期に、高温多湿の外気が冷房で冷やされた室内に入って壁などに触れ、水滴ができます。特に、地下室のように外気との温度差が大きい場所で生じやすくなります。
5.具体的な結露防止の方法を教えて!
さて、家庭内でいちばん湿気の出るところはどこでしょう?それは「お風呂場」です。ですから、家庭における結露対策は、ここの換気を如何に上手に行うかがポイントになります。
(1)具体的には、空気の流れを常に一方通行にすることをまず考えましょう。空気の流れとしては、《廊下》⇒《脱衣室》⇒《浴室(換気扇)》⇒《外》という流れを作ってあげることです。
(2)入浴後も浴室のドアーを閉めて、1時間程度は換気扇を回しましょう。また、浴室に換気扇がない場合は、入浴後2~3時間は浴室のドアーを閉めて、窓を大きく開けて乾かしてください。
(3)沖縄ではあまりないですが、入浴後、浴槽はできるだけ空にしてください。残り湯を翌日の洗濯に使用する場合は、フタを忘れずに。
(4)タイルなどについた石鹸や垢などの汚れは、カビの栄養源になります。入浴後にシャワーで洗い流すようにしましょう。しばらく置いてから、乾いた布で拭くとより効果的です。
(5)脱衣室には換気扇を設置するのは避けましょう。浴室側から高温多湿の空気が脱衣室に流れ込むことがあり、結露の原因になります。
6.他の対策は、どうとればいいのかな?
この時期は、どうしても洗濯物を屋内に干したり、乾燥機の利用が欠かせなくなります。ところが、このことが結露の原因になっています。では、どのような対策をとればよいでしょうか?
(1)除湿器の使用は効果てきめんです。最近では、空気清浄機能を備えた機種も販売されています。使用時には、干している洗濯物の下に除湿器を置くようにしてください。この場合注意するのは、部屋を閉め切ることが絶対条件です。
(2)最近では、ユニット型浴室がそのまま洗濯物の乾燥室になっているものがあります。排気は、ファンで直接外に出すこともできるので、除湿及びカビ対策には最適です。また、現在備えつけている換気扇や換気口を浴室用換気乾燥機に改善することもできます。
(3)乾燥機を使用する場合、注意することは、乾燥機を使用することによって、水分をたっぷり含んだ空気が放出されることです。屋内に乾燥機が設置されている場合、この排気を直接外に出せるようなダクトや換気扇も必要になりますが、その時は洗濯機・乾燥機と換気口の位置をしっかり頭に入れてから、設置するようにしましょう。
(2)いよいよ本題、カビ対策!
1.教えて!カビの基礎知識
カビは微生物の一種で、正式には「真菌」と呼ばれています。この時期嫌な「水虫」の原因菌も、この真菌類に含まれます。カビ共通の生育条件は、温度が20~35℃、湿度が60%以上です。栄養源として、手垢などの汚れ、壁の汚れや壁紙の糊、結露水。加湿器の水などがあげられます。
2.屋内に発生する主なカビの種類は?
住宅内で見かける黒色のカビで、最もよく見られるものはクラドスポリウム属のカビ(クロカビ)です。乾燥や低音に強く、壁や柱、革製品、ビニールクロスやタイル目地、サッシなどのパッキンにも発生します。また、アルタナリア属(ススカビ)もよく見られます。壁などにスス状に生えています。この属は、防カビ剤に対する抵抗性が極めて強く、防カビ処理を施した場所にもしばしば生えることがあるという厄介な代物です。
3.見た目の嫌さ以上に、カビの厄介な点ってあるのかな?
これらのカビの胞子や菌糸の断片を吸い込むと、喘息などの発作を引き起こすことがよくあります。また、ダニ類はカビを好んで食べるので、「カビが生えること」=「ダニを増やすこと」になります。
4.実際にカビを退治するにはどうすればいいの?
カビは条件によって繁殖が早く、また胞子が飛散して他の場所で繁殖しますので、まずは発生させないこと、不幸にも発生したら直ちに退治(処理)することがポイントです。
(1)使用する薬剤は、消毒用アルコール(市販のものを原液で使用)・漂白剤(有効塩素量0.5%に調製する、家庭用のもので十分)・またはこれらを成分とした市販のカビ取り剤・防カビ塗料です。ここで注意したいのは、市販のカビ取り剤を使用する際の時、酸性タイプの洗浄剤との併用は避けてください。というのは、これらを混ぜると有毒な塩素ガスが発生し、大変危険だからです。使用説明書をよく読んで、作業中は換気に十分注意してください。また、作業中にはゴム手袋やマスクも忘れずに。
余談ですが、最近”乳酸”を主成分とした洗浄剤も出ています。人体に対する刺激は少なくなるといえるでしょう。
5.部位別の処理方法を教えて!
(1)浴室の壁
まず、カビの生えているところに消毒用アルコールを噴霧するか、ローラーや布にしみこませて拭き、カビを殺したのち、10分間放置し、乾燥させ、防カビ塗料を塗ります。ここで注意したいのは、いきなり塗料を塗らないこと!それは、塗料分もカビの栄養源になるからです。
(2)タイル目地、シール剤のカビ
カビ取り剤またはスポンジに漂白剤を染み込ませて目地にそって塗り、約10分間放置します。そのあと水で洗い落として乾燥させたのち、必要に応じて防カビ塗料または防カビシールを塗ります。
(3)畳のカビ
これは新築の住宅でよくやられます。まず、漂白剤をポリ容器に入れ、雑巾に染み込ませて畳のカビをふき取ります。そのあと、消毒用アルコールを噴霧するか、または布に染み込ませて、こまめに拭いて殺菌します。
(4)ビニールクロスに発生したカビ
これは、クロス表面だけの場合と、クロスの下地から生えている場合とで処理方法が異なります。表面だけの場合には、漂白剤を布かスポンジに染み込ませ、カビをこすり落としたあと、約10分間放置したのち、きれいな水で漂白剤を拭き取り、乾かします。最後にアルコールで殺菌して、処理終了です。下地からカビが生えている場合は、クロスごと張り替えが必要です。
(5)エアコン
これは結構見落とされがちです。フィルターは自分でも清掃できますが、大掛かりな清掃は専門業者に頼みましょう。ただ、最近市販の洗浄剤が出ていたりで、家庭でもお掃除しやすくなっていますよ。
以上、駆け足でまとめてみましたが、参考になるかなぁ。意見や質問がありましたら、掲示板やメールに送ってくださいねぇ!(^O^)/
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- みんなのレビュー
- 【レポ】便乗した、訳ありお得なザク…
- (2025-11-30 10:39:50)
-
-
-
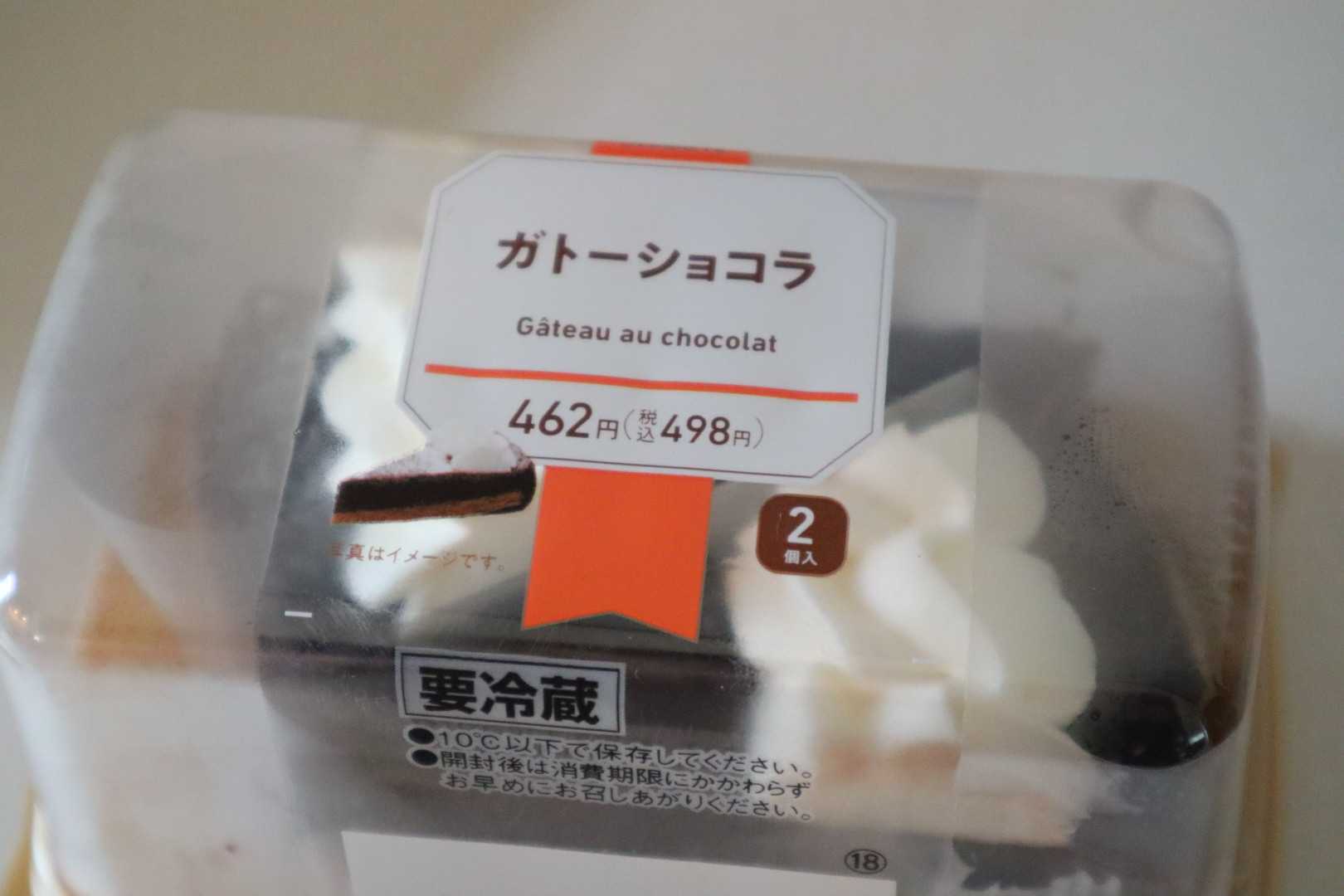
- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- おやつは、やめられない。笑 & 楽天S…
- (2025-11-30 11:09:15)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 今月のNISA利用(2025.11月)
- (2025-11-30 09:50:04)
-
© Rakuten Group, Inc.


