2021年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

かぎろひ(近鉄スナックカー)
Twitterにも投稿をしましたが、近鉄のスナックカー12200系ががいよいよ3月のダイヤ変更に伴って定期運転から引退します。同時に60年にわたって親しまれた濃紺とオレンジの近鉄特急色も終了することに。3月以降も団体列車として運転は予定されていますが、今のしまかぜやひのとりに繋がる豪華特急のはしりとなった車両だけに歴史的意義の高い車両でありました。1975年にはエリザベス女王も乗られるなど、皇族を含めたVIP輸送にも活躍をしました。スナックカーは定期運用からは退きますが、乗りものニュースや新聞報道によれば、団体専用列車としては存続をする見込みです。今日取り上げる「かぎろひ」はスナックカーを改造したジョイフルトレインで、近鉄の子会社のクラブツーリズムが保有をしている珍しいタイプの車両です。管理人はこの車両に実は乗ったことがあり、少しではありますが紹介をしていきたいと思います。外装は濃いグリーンと金帯の装いにリニューアルされていますが、スナックカーの面影がくっきりと残る出で立ちです。写真は高安の車庫を入れ替えている途中の様子です。望遠レンズで撮影をした遠景です。かぎろひは運行時は2両が基本ですが、ツアーの内容によっては4両運行も可能になっています。車内です。イベントスペースの部分は立ち飲みも出来るようになっています。荷物置き場に活用されることも。妻面は後期に改造されたスナックカーの意匠を引き継いだデザインです。シートはフリーストップ型のリクライニングシートで、これも後期にリニューアルされた車両のアコモデーションと同じです。シートの表地は特急用のものとは異なります。かぎろひはサービスカウンターにビールサーバーが設けられていて、ツアーによっては有料ですが生ビールが楽しめるサービスがあります。スナックカーは登場当初、車内で供食サービスが行われていて、アルコールだけでなく、カレーやサンドイッチなども食べることが出来たそうです。当時、提供されていたメニューが以下のブログで掲載されています。「豆たぬきのつれづれ日記」https://ameblo.jp/tanutch2002/entry-12236964480.html供食サービスは、新幹線やブルートレインの食堂車と比べて品数が少なく、昭和40年代の乗車率が芳しくなかった時代の名阪特急のテコ入れ策とはならなかったようで、数年で打ち切りとなってしまいましたが、国鉄やJRの一歩先をゆく車内設備やサービスに関する発想はアーバンライナーや伊勢志摩ライナー、しまかぜ、青の交響曲、ひのとりなどに受け継がれています。確かに、登場当初のスナックカーは普通車ながら国鉄車よりも広いピッチのリクライニングシート(新幹線は940mm、国鉄の特急が910mmに対し980mm)を装備し、食事も出来る車両であったことから、在来線の特急よりもグレードの高い車両でありました。こういったコンセプトは、近鉄の魅力の一つでもあるので是非受け継いで沿線の活性化に寄与してもらいたいですね。かぎろひは通常はクラブツーリズムのツアーの一環で利用するケースが多いので、お目当てのツアーが見つかったら是非、使ってみて下さい。クラブツーリズムHPhttps://www.club-t.com/sp/special/japan/kagirohi/これ以外での利用方法では、10月に行われる近鉄鉄道まつりの五位堂~高安間のお試し乗車で乗るチャンスがあります(ただし、運用される車両は毎年変わるので概ね3年おきのインターバルでの運行みたいです)。普段乗れない列車に乗ることも、乗り鉄の醍醐味であると改めて感じました。もう一つ、近鉄の豪華特急は伊勢神宮の式年遷宮に合わせて登場する傾向があります。と、なると次の式年遷宮は2033年になるので、このときにしまかぜを上回る豪華特急が登場する可能性は高そうですね。その前に、4年後の万博で夢洲~奈良などを結ぶ「あやかぜ」(仮称)がどんな車両(日本初のパンタグラフと第三軌条による異なる集電方式の複電圧車)になるか、こちらも気になるところです。
2021.01.17
コメント(0)
-
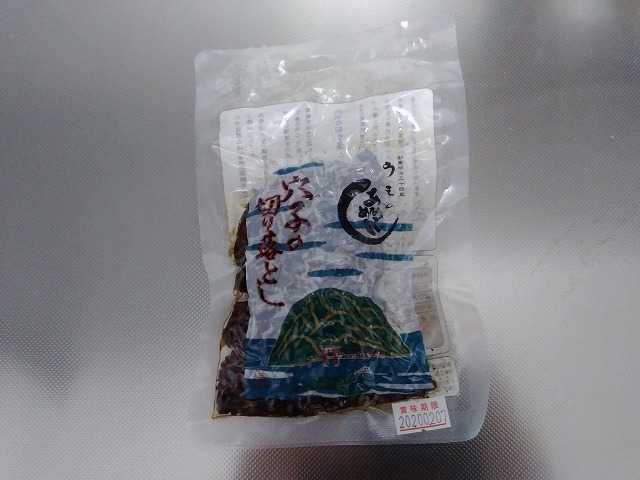
日本三大駅弁大会(京王、阪神、鶴屋)の楽しみ方
新年始まって最大の鉄道イベントの一つといえば、京王、阪神、鶴屋での三大駅弁大会を挙げる人も多いかと思います。昨年は軒並み大掛かりな鉄道イベントや団体列車、臨時列車などが中止になるなど、楽しみが私も少なかったのですが、そんな中でも駅弁大会は今年も開催されます。駅弁は自宅に持ち帰って楽しめるものであるので、改めて基本的な駅弁大会の楽しみ方を記していきます。開催時期ですが、京王(新宿)は1月第2週から概ね2週間、阪神(梅田)は京王の駅弁大会終了後から約1週間、鶴屋(熊本)は2月の初めから約2週間が目安です。特に阪神は1週間と短いので、行く日時が決まったら買う内容を特に絞っておいた方が無難です。【tips 1:お目当てのものを前もって決めましょう】京王と阪神の駅弁大会では約300種類前後、鶴屋は概ね100~120種類ほどの駅弁が並びます。駅弁は百貨店内で実演でアツアツのものを楽しめるものもありますが、多くは輸送駅弁です。先ずはホームページやチラシを見て、買いたい駅弁や土産品を予め決めておきましょう。駅弁のリストは開催の約1~2週間前くらいからアップされますので、これを見て狙いを定めておくことが賢明です。京王百貨店:https://www.keionet.com/info/shinjuku/阪神百貨店:https://www.hanshin-dept.jp/鶴屋百貨店:https://www.tsuruya-dept.co.jp/index.html【tips 2:会場を把握しましょう】実演駅弁や輸送駅弁の販売場所は、上記のホームページでお知らせがあります。当日、店内で迷わないよう地図を持っていくことをお薦めします。或いは、百貨店に行く機会が多い方であれば、事前に下見をしておくと無難です。【tips 3:早起きは三文の得】人気の駅弁や限定の駅弁では整理券制が取られる場合が多いです。特に、宮島口駅のあなごめしや人吉駅の駅弁は人気が高いため整理券制が取られる傾向にあります。ですので、開店早々に売り切れになる駅弁もありますので百貨店に直接行かれる場合は、朝早めに行動しましょう。また、会場の混雑具合によっては入場制限がかけられる場合もありますので、時間のロスとお目当ての品の売り切れを避けるためにも善は急げです。【tips 4:ネット予約を活用しましょう】確実に手に入れたい駅弁の中には、ネットでの予約を受け付けているものもあります。何が何でもというものがあれば、活用していきましょう。また、今年はネット販売限定の駅弁も数多くあります。受け取り時間や日時も指定出来るので、スケジュールの都合を合わせて確保することが可能です。現地での購入と併せて検討してみて下さい。【tips 5:売り切れた場合は?】お目当ての弁当が売り切れた場合は、代替のものを考えておきましょう。宮島口のあなごめしは早々に整理券が終了して完売になるパターンが多いので、昨年は穴子の切り落としを購入して家でごはんを炊いて楽しみました。代替品に変化球を交えていくことも楽しみの一つになるかと思います。【tips 6:エコバッグは必ず持っていきましょう】環境保護推進のため、昨年からプラスチックバッグがコンビニも含めて有料に続々となってきています。余計な出費を避けるためにも、エコバッグは大きめのものを最低でも1つは持っていきましょう。複数枚持っていくと便利ですね。【tips 7:インフォメーションも活用しましょう】今年は例年にない大雪に見舞われている地域もあることから、輸送状況により当日の販売が中止になる駅弁もあります。そういった場合の情報をインフォメーションで聞くことができます。不測の事態に備えて、tips1と5のパターンを踏まえ、代替の候補は念のために。【tips 8:その土地のうまいものもお忘れなく】いずれの駅弁大会も大規模なイベントになりますので、現地でしか味わえないうまいものも販売されることが多いです。うまいものについても、狙い目を定めて楽しみましょう。それでは Let's enjoy!!
2021.01.10
コメント(0)
-

あかまつ・あおまつ
明けましておめでとうございます。2021年になりました。元旦は昨年のくろまつの乗車記の続編として、また書き忘れていた部分の加筆として丹鉄のカフェ列車、あかまつとあおまつについてまとめていきます。本年も宜しくお願いします。あかまつは5年前の乗車なので写真が少し古いのと、車内を撮っていないことについては本当にすみません(>_<)。乗車当初は指定席制を取っていたのですが、現在は定員制になり、乗車整理券550円を支払ってから乗車するようになっています。あかまつは割と人気の列車で、3連休やGW,夏休み、冬休みなどの長期休暇中のシーズンは満席の列車も出てきますので予約時には注意が必要です。あかまつは運行当初は豊岡まで足を運んでいた時期もあり、管理人が乗車したときは豊岡から西舞鶴までのんびり寛げました。現在の運行区間は天橋立~西舞鶴間がメインです。こちらはあおまつです。あおまつは追加料金がかからないのであかまつよりも気軽に利用できます。初発のみ西舞鶴→福知山間を走行しますが、主に福知山~天橋立間を走ります。唯一の注意点は、福知山発のあおまつは、大阪・京都方面からの特急と接続するので、比較的混雑する確率が高いです。あおまつの車内です。あかまつ・あおまつ共にグループ席やソファー席、カウンター席、販売カウンターを備えているので、短時間の乗車でものんびり過ごせます。車内デザインはくろまつと同様、水戸岡鋭治氏が手掛けています。車内ではコーヒー(勿論、丹鉄珈琲です)やアルコールなどの飲み物やお菓子類、お土産などを買うことが可能です。(※あかまつとあおまつでは販売している品が一部異なります。)西舞鶴~天橋立間では、由良川橋梁で速度を落として運転されるので、晴れの日には澄んだ日本海の絶景を撮ることができます。橋の上からはこんな感じです。夏の青空をバックの撮影は本当に最高です(^-^)。丹後半島を訪れるのは学生時代の宮津での合宿や家の用事、あかまつ・あおまつ乗車、くろまつスイーツコースの旅、そして今回と5回目だったのですが、丹鉄はくろまつや丹後の海以外にも、個性的な観光列車や車内設備のグレードの高い列車が多く走っているので、足を運ぶ価値は大です。海の京都も京都市内に負けないくらいの個性的な場所だったので、また暇を見つけてのんびりしに行きたいと思います。
2021.01.01
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1










