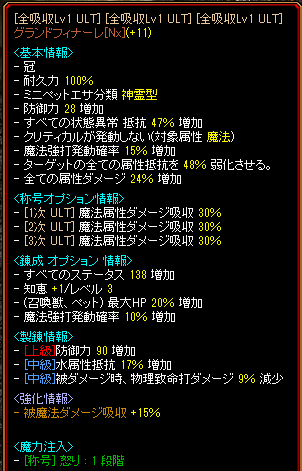第1章③
真っ暗な闇と静寂に包まれた学校の長く続く廊下を拓人は一人歩いていた。
「・・ここは」
周りを見渡してみても、ただ波の音と静寂が広がるばかりで何もない。拓人は特に考えず足が向かうまま、桜が舞い散る廊下の外、裏庭に出ていた。
「ここは一体・・・」
と、そこへ鞠が一定したリズムではねながら、拓人の手に引きつけられるように乗った。
「・・鞠?」
拓人はそれを軽く拾い上げた。
「返して・・お兄ちゃん・・」
珠のように白い肌におかっぱ頭に蝶をなぞった朱色の着物を着た9歳ばかりの少女が覗きこむように拓人を見ながら静かに言った。
「これ?」
「うんっ」
少女が穏やかに笑った瞬間、拓人は自分の身体が煌めやかな光に包まれている事に気付いた。
「!?これは?」
自分の身体がまるでガラスの欠片のようにゆっくりと砕けていった。パラパラと砕けて、花びらとなって消えていく。
「え、な、何だよ、これ・・」
全身に浴びた血を洗い流すように拓人の身体は冷たくクリスタルのようにうっすらとなっていく。
自分が消えるような感覚に拓人は真っ先に襲われた。
「――やめろ!!」
叫んだ声は空しく響いた。
「――お兄ちゃん、また新しく生まれるんだね」
少女はまた拓人に向かってニッコリと微笑んだ。そして、背中を向け拓人の前から去ろうとした。
「!待って、行くなよ!こんな状態でオレを・・・」
そこで、拓人の意識が途絶え、辺り一面何も見えなくなった。
――拓人が目を開けると、荒れた波が打ち寄せる砂浜だった。
「・・・ん」
拓人は飛沫が顔にかかって、それで目を覚ましたのだとわかった。
「・・ここは」
身体を起こし、髪をかきあげて拓人はゆっくりと顔を上げた。
ひときわ大きい波が押し寄せてきて、砂の上を這った水が拓人の爪先をぬらした。
濃く潮のにおいがする。
「オレ、何でここに・・」
―そうだ、ホウテイから落ちそうになって・・。
「う・・、頭がいた・・」
ズキズキする・・。
蒼白い闇の中、拓人の髪が風でふわりと浮かび上がった。
ふと、拓人は姉の姫乃達を思いだし、「近くにいるかもしれない」と立ち上がって、痛む頭を押さえながらふらりとした足つきで倒れていた場所から歩きながら離れていった。
その時、か細い薄紫の光がふわふわと拓人の目の前の松林から現れた。折れた枝の断面が見えたので、拓人はそこに墜落したのだということがわかった。
拓人には、それが消えていく人魂のように感じられた。
「?――何?」
何だろうと思って、その光に触れようとすると羽で弾かれた。
その光の正体は蝶だった。
「蝶が何で、海の近くに?」
ハッ
そうだ、剣は!?
よかった、ある。
拓人は心の中でそっと安堵の息をもらした。
白いもやが薄く流れている。夜明けの空気が漂っていた。波の音が響いている。
拓人は自分の身体がべったりとした血がついている事に気付き、
「・・皆と会う前に身体洗った方がいいかもな」
と独り言のように呟いた。
「でも、代わりの服ここにないんだよな~・・」
拓人はそう言いながら松林へと足を進めた。
ドンッ!
「いたっ」
「きゃ」
拓人が突然後ろから来た少女とぶつかった。
誰だと思って振り向いてみると、拓人の実の姉・神山姫乃が鼻をさすりながらそこに立っていた。
「―姉貴?」
「・・た、拓人?」
拓人と姫乃がお互いの顔を見合わせた。
暗さのせいでお互いの顔は見えなかったが、拓人も姫乃も確かにお互いがよく知っているなじみ深い声だった。
そして――
足元に広がる海の異様さに目を引かれ、しばし呆然となっていた。
海は限りなく黒に近い紺に見えた。水面に下っていく崖の線を見ると、それは恐ろしく澄んでいた。
それは想像を絶するほど深い海の、深海にわだかまる闇が透明な水のせいであらわになったような印象を与えた。光が届かないほど深い底を見下ろしているという感覚。
深い海の、深いところに小さな光が灯っている。
「・・・・すごい」
「!」
姫乃がその時拓人が思ってた事を口に出した。
砂粒ほどに見える光が灯り、あるいは集まって薄い光の集団を作っている。(月の影影の海・小野不由美・p77)
――星のように。
眩暈がして2人同時に崖に座り込んだ。
それはまさしく宇宙の景観だった。写真で見た星や星団や星雲、そういったものが自分の足元に広がっている。
―――ここは知らない場所だ。
突然、拓人の脳裏にわきあがってきた思考。直視するはずがなかった事実が姿を現して現実のものとなって今、自分の目の前にある。
ここは自分達が知っている世界ではない。こんな海を自分は知らない。
漫画やテレビの出来事ではなく、まさしく拓人は別世界に紛れ込んでしまったのだ。
「・・・うそだっ!!」
「いや、こんなのっ!!うそよ!」
ここはどこで、どういうところなのか。危険なのか安全なのか。これから一体どうすればいいのか。
「あいつ・・・彼方を助けにきただけなのに・・」
「・・お母さん、・・お父さん・・」
身を抱えた姫乃の目に涙がこぼれた。
「どうしよう・・拓人・・ッ」と、姫乃が顔を上げて、朝の光に包まれた弟の顔を見た。
「!」
「姉貴?」
姫乃の表情が泣き顔から驚きへと変わった。
「・・・ッ」
驚きのあまり、姫乃が後さずり自分の口に手を添えた。
「どうしたんだよ?」
拓人が急に態度を変えた姫乃の様子を伺えようと、姫乃の肩に触れようとした瞬間、
「・・・あんた、誰よ?」
「・・・・・・え?」
拓人は姉の突然のその一言に違う意味で呆然となった。
その後、しばし沈黙してしまったが何とか気を取りなおして、
「何言ってるんだよ?オレは姉貴・・いや神山姫乃の弟の神山拓人だよ。それ以外に何があるんだよ。・・変な冗談言うなよ」
「・・鏡で自分の顔見てみなさいよ」
姫乃が疑うような目つきのまま、制服のポケットから手鏡を引っ張り出してスッと拓人の顔の前に差し出した
「・・・!」
拓人は息を呑み、鏡に映し出された他人の顔を見た。
手をあげて恐る恐る顔を撫で、その動きにつれて鏡の中の人物の手も動いて、それが自分だとわかると愕然とした。
――これは俺の顔じゃない。
髪の色は夜の闇に近い紫紺、目の色もこげ茶から深い海の底を思わせる冷たい蒼へと変色している。
自分の顔は割とどこにでもいる方で、こんな整った顔立ちをしていない。
「これ、オレじゃない」
狼狽して叫んだ拓人に、姫乃はというと少し怪訝そうな表情を浮かべながら、「・・美少年って感じ・・」と呑気な事をぽつりと言った。
「こんな奴、オレじゃない!」
取り乱した拓人の手から姫乃は手鏡を取り上げた。ごく落ち着いた動作で鏡を覗きこみ、
「――鏡がゆがんでいるわけでもないし・・・」
「こんなの俺の顔じゃないよな・・?姉貴・・・」
と、拓人が弱々しげな声で視線を反らしたまま、静かに言った。
「声は拓人なんだけどね・・・」
「だから、オレが拓人なんだってば・・あね・・・、姉さん」
拓人が姫乃の事を姉さんとかいう時はかなり弱気になっている時だ。だが、それは拓人本人と自分、彼方くらいしか知らない事だ。
「・・・本当に拓人なのね?」
姫乃が確かめるように拓人の頬にそっと触れた。
「うん・・」
2人の間に優しい空気が流れた。
ガサッ
「「!」」
拓人と姫乃が同時に物音がした方に顔を向けた。
人のよさそうな、中年くらいの年頃の日に焼けたキツネ目をした大柄な男だった。背中には、ジャガイモを入れた籠を背負っている。
「―お前さんら、もしや海客か?」
「海客?」
「???」
何、何て言ってるの?
「海から来たんだろ?海から来るのは海客くらいなものだ」
「・・・ま、まあ、そうだけど・・」
「・・・ちょっと、拓人」と、姫乃が拓人の服のすそを引っ張りながら、
「あんた、この人が言ってる事わかるの?」
と聞いてきた。
「わかるのって、めちゃくちゃ日本語だと思うんだけど」
「は?何言ってるのよ?このこ、日本語なんかしゃべってないわよ。だって、言ってる事がわからないし」
「・・姉貴、そうなの?」
「うん」
拓人がいかにも不可不思議な表情を浮かべた。
「―それにしても、お前やけにべったりと血がついているな。獣でも殺してきたのか?」
―獣・・。
その言葉に拓人は心臓をびくつかせた。
「そ、それはその・・・」
「・・・そのままじゃ、外を歩けないな。お前ら、オレの家にこいよ」
「え?」
「まあ、ちょうど暇だったしオレの家に泊めてやろうって言ってるんだよ。どうせ、行く宛なんてないだろうからな。飯はあんまりねえけど、湯船くらいはつかえさせる事が出来るぜ」
拓人は困惑した。
「そんな・・・、いきなり言われても。それに初対面の人にそこまでさせるわけには」
「オレはなあ、根からのお節介でお人好しな性分なもんでね。道で困っている人がいたら放っておけないもんなんだよ」
それを聞いた拓人が何か言おうとした時、隣でぐううう・・、とお腹が鳴く音が聞こえてきた。
「・・・あ」
姫乃が赤面した。
「オレは塵伶って言うんだ。よろしくな」
拓人と姫乃が流れ着いたのは、慶東国。景王・陽子が治め、十二国で東に位置する国である。
拓人達は塵伶の後についていって、農作業を続ける人影のほうへ歩いていった。
近づくにつれ、彼らが日本人ではない事がわかった。
拓人と似たような藍色の髪の女がいて、赤紫の髪の男がいる。何だか、違和感みたいなものを拓人は感じていた。
着ているものは着物に似た少し変わった服で、男の全員が髪を伸ばしてくくっているように見えるが、これといった異常はなかった。
「・・何か、私達異邦人って感じね・・」
「何気に古い言葉知ってるな、姉貴」
「あっ、おっ母」と、塵伶が家の前におかれた椅子に腰をかけた老婆の方に声をかけた。
拓人と姫乃はその老婆の姿を見たときぎょとなった。
なぜなら、その老婆は歴史の教科書戦時中の写真等によく見られる、骨と皮といったとても痛々しい姿だったからだ。
姫乃がその姿に少しだけ恐怖するほどだ。
「おっ母、珍しいお客さんだぜ」
塵伶が籠を下ろしてその老婆に楽しげに言った。
「おお・・塵伶か」
老婆が拓人達の方に視線を向けた。
「・・ほう」
老婆が拓人の顔をじっと見た。
「あ・・、どうも」
拓人が老婆に軽く会釈した。
「坊や、嬢ちゃん、疲れただろう・・私達の家にお泊まり。こんなぼろ家でもいいならね」
心から安心する事の出来る優しい笑顔を老婆は見せた。それを見た拓人と姫乃は安堵した。
「いや、そんな事は・・・」
その光景を傍目から見ている塵伶は拓人達に気付かれない様に微かに意味ありげな笑みを浮かべた。
晴天時に雲海の下の雲が切れ、地上の雪の照り返しによって起きる雲上での現象の事を白陽と言う。
抉り取られたような峠道、騎獣を連れた20代後半の男がこれに気付き、籠に入れた木の実から視線を外して、顔を上げた。白い息がゆっくりと空気の中に流れた。
「さすが、朝の山は寒いな・・。早く、女房の所に戻らないと・・。な、慶鋼」
瞭圃は隣でありをぼーっと眺めている眺めている子供に声をかけた。
「・・・・」
アリに夢中で瞭圃の声が聞こえていないようだ。
「慶鋼」
「あ、お父さん、何?」
もう一度、名を呼ばれてやっと気付いたようだ。
「帰るぞ」
瞭圃は、慶鋼の手を取って、山を降りようと下り坂の方へと足を向けようとした。
「・・お父さん!!あれ見て!」
「ん?慶鋼、どうかしたのか?また、何か珍しいモノでも見つけたのか」
慶鋼が指した方向に変質的に折れた木々が何本もあり、その中には倒れている木の姿もあった。瞭圃が目を取られたのは、そんな木々より倒れている木に寄っかかっている白く細い手首だった。
その手首はあちこちに擦り傷があった。
「・・・・」
瞭圃が恐る恐る近づき、その木に近づいてみると、14歳くらいの奇妙な着物を着た少女が身体のあちこちに傷を負って、気を失って倒れていた。
「!」
―山客か?
でも、山客は金剛山の麓にたどり着くと言うし・・、違うか。
だが、この少女の髪の色は何なんだろう・・・。金に近い茶なんて・・。
はっきり言って、この色は異常だ。
これでは、まるで・・・。
もしかしたら、妖魔が化けているのかも・・。
「お父さん、このお姉ちゃん、身体中にケガしてるね・・。早く村に連れて帰ってお手当てしないと」
「あ、ああ、そうだな」
© Rakuten Group, Inc.