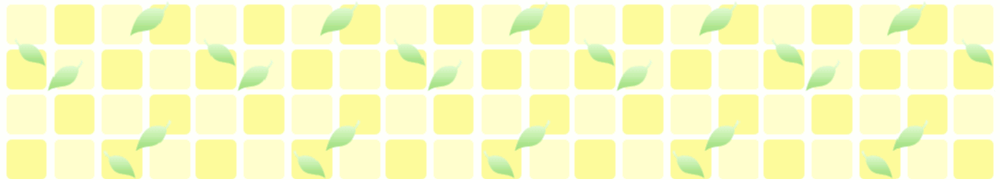II. 顎機能障害(顎関節症)の診療ガイドライン
顎機能障害とは
1) 本ガイドラインの位置づけ
科学的根拠に基づいた医療の重要性が指摘されているが,顎機能障害の診断や治療に関しては補綴を
はじめとする多くの歯科治療や外科系の医科疾患がそうであるように,厳密なRandomized ControlledTrial(RCT)にのっとった科学的研究を行うことが困難であり,したがって,特に治療に関しては信頼できるデータベースがほとんどないのが実状である.また,たとえば心臓外科手術後の生存率が,術式名だけをいえば全く同じ術式を採用していているにもかかわらず,施設によって大きく差があるという現実がある.この差は手術術式の違いではなくて,
執刀医の能力をはじめとする診療体制のレベルの差によると考えられる.
Evidenceを問題にするとき,どの薬をどのように処方するかということが大きなウエイトを占める内科的治療と,
外科治療や歯科治療はおのずと性質が異なることを認識する必要がある.
RCTに基づいた最近の研究で,非復位性の関節円板前方転位症例に対して,治療を行わずに経過観察を行った群と比較して,薬物療法やスプリントがより有効であるという結果が得られなかったという報告 があった.このような研究結果は過剰診療に対する戒めとして真摯に受け止めなければならないが,
その一方でスプリント治療について,もしほかの施設で,あるいはほかの術者が行ったらさらに悪い結果が出ていたかもしれないし,あるいはもっと良い結果が出ていた可能性もあるという懸念がある.治療内容に対するテクノロジーアセスメントが十分でないと,研究結果を左右するようなバイアスがかかることにも配慮が必要であろう.
<テクノロジーアセスメント : 事前の予測評価 >
< バイアス : 偏り>
このようなことをすべて 慮したうえで,顎機能障害の診断や治療の根拠を得るために,RCTだけでなく良質な追跡研究(前向きコホート研究)を積み重ねて,学会をあげてデータベースを構築していかなければならない.しかし,現実には顎機能障害の諸症状を訴えて治療を希望して来院する患者が大勢おり,エビデンスがないといって治療を放棄するわけにはいかない.
このガイドラインは,先人の臨床経験やこれまで行われた臨床の治験あるいは基礎的研究の成果から,
コンセンサスが得られているであろうという内容を整理して本学会員に提供するものであり,将来のより望ましいガイドラインのたたき台として位置づけてもらいたい.
2) 顎機能障害の定義
顎機能障害は顎関節雑音,顎関節や咀嚼筋の疼痛,顎運動障害を主徴とし,顎機能だけではなく,ときには全身的にもさまざまな障害をもたらす症候群で,齲蝕,歯周疾患に次ぐ第三の歯科疾患といわれている.
顎機能障害は国際的に認知されているTemporomandibularDisorders(TMD)に対する日本語疾患名であり,わが国において最も一般的な疾患名であり日本顎関節学会の正式用語である顎関節症と同義である.
日本顎関節学会は顎関節症を以下のように定義している .
顎関節症とは,顎関節や咀嚼筋の疼痛,関節(雑)音,開口障害ないし顎運動異常を主要症候とする慢性疾患群の総括的診断名であり,その病態には咀嚼筋障害,関節包・靱帯障害,関節円板障害,変形性関節症などが含まれる」
アメリカ口腔顔面疼痛学会AmericanAcademyofOrofacialPain(AAOP)はTMDを国際頭痛学会(InternationalHeadacheSociety)による頭痛,頭部神経痛,顔面痛の分類中に位置づけており,顎関節については先天性障害や関節突起の骨折,筋においては新生物の形成などを含み,顎関節学会とは異なった疾患を分類に入れている .
なお,顎機能には,咀嚼,嚥下や発音などの機能があるが,本ガイドラインで扱う顎機能障害はあくまでもTMDに対応する症候群を意味し,ほかの疾患による咀嚼障害,嚥下障害および発音障害などは顎機能障害の範疇には入れない.
3) 顎機能障害の類似用語
顎機能障害の同義語には上述のTMD,顎関節症のほかに顎機能異常 (Temporomandibular Dysfunction)やCraniomandibularDisordersなどがあり,関連用語としてはMPD症候群(MyofascialPainDysfunctionSyndrome)および顎関節内障(InternalDerangementofTMJ)などがある.
顎機能異常はわが国の歯科補綴学領域を中心に,またCraniomandibularDisordersは一時期欧米でよく用いられた用語である.最近欧米では機能障害というよりは痛みを特に重視してOrofacialPainという用語が頻繁に用いられるようになってきた.これは顎顔面を含む頭頸部のあらゆる痛みを対象とするものであり,顎機能障害や顎関節症などのように疾患(症候群)名とは捉え方が違う.わが国では顎関節症が顎関節学会の公式な用語として最も広く用いられているが,相当するTemporomandibular JointArthrosisは顎関節に症状の認められない筋症状主体の症型も含むこの症候群に対応していないことから,用語の再検討が求められている.関連用語のMPD症候群および顎関節内障は本症候群の一部の病態に対応する用語である.
顎機能障害の病態
1) 主要症候
顎機能障害の主要症候としては顎関節雑音,顎関節や咀嚼筋など頭頸部筋の疼痛および下顎運動異常
がある.
・ 関節雑音
顎関節雑音としては,開口などの動作に伴って顎関節部でカクンあるいはコキンという音がするクリッキングClickingとジャリジャリあるいはギジギジという音のクレピテーションCrepitationがある.
・ 疼痛
疼痛は開口や.みしめ動作に伴う運動時痛が最も多く,圧痛がこれに次ぎ,自発痛は比較的少ない.
痛みの程度としては中程度以下の鈍痛であることが多く,強度の鋭痛であることはまれである.また,痛みを訴える部位は顎関節や咬筋,側頭筋および外側翼突筋などの咀嚼筋が多いが,定位は必ずしも良くない.
・ 下顎運動の異常
下顎運動の異常としては開口制限,片側の顆頭運動に制限がある場合にみられる切歯点における開閉口路の偏位などがある.
2) 随伴症状
顎機能障害患者では,頭痛,首や肩の凝り,耳なり,難聴,目眩,舌痛,咬合の不安定感,手足のしびれ,自律神経失調症状など,全身的にあるいは情動的にもさまざまな症状を訴えるものもいる.
これらの主要症候や随伴症状のなかには顎関節雑音や,下顎運動制限などのように客観的に評価できるものもあるが,痛みをはじめとして多くは患者の主観的な症状である.
3) 日本顎関節学会の顎関節症の症型分類
日本顎関節学会では顎関節症を,
・型:咀嚼筋障害,
・型:関節包・靱帯障害,
・型:関節円板障害a:復位を伴うもの,b:復位を伴わないもの,
・型:変形性関節症,
・型:・~・型に該当しないもの,の5つの症型に分類している(2001年改訂) .
顎機能障害患者では複数の病態を持つ場合が多く,単一の症型に明確に分類することは必ずしも容易ではない.また,欧米では上述したように国際頭痛学会の分類に沿った分類が採用されており,わが国の分類との整合は得られていない.
顎機能障害の疫学
1) 患者数
顎機能障害に関する種々の疫学調査があるが,検査基準が同一ではないので比較は困難である.一般の集団において40~75% に他覚的に何らかの異常が認められ,その内治療を必要とする割合は5~7%と推定される .また,病院歯科を訪れる顎機能障害患者の割合は施設によってバラツキがあるが,おおむね初診患者の10% 程度を占めるとみられる.
2) 年齢分布
病院を訪れる顎機能障害患者は10歳代後半から20~30歳代にピークをもち,年齢が高くなるにつれて徐々に減少する一峰性の分布を示すという報告 や,40歳代から50歳前後にもう1つのピークを持つ二峰性の分布を示すという報告 などがある.
3) 性差
非患者群を対象とした疫学的調査では有意な性差が認められなかったとする報告が多いが,治療を求め病院を訪れる患者群においては,女性のほうが男性よりいずれの報告においても多く,その比は1:3~1:9である .
顎機能障害の病因と発症・増悪メカニズム
1) 主な発症・増悪因子
主な発症・増悪因子としては咬合異常,睡眠中のブラキシズム,昼間のクレンチング,舌習癖などの異常習癖,ストレスなどの精神・心理学的因子,急性および陳旧性の外傷,不良姿勢などがあげられている.
咬合異常の関与については近年論争があり,欧米では咬合異常を発症因子として重視しない え方をとるものが多い.しかし,顎関節症状を主徴とする多くの症例では咬合異常が重要な因子の1つであり,これを軽視することはできない.いずれにしても,病因に対する考え方を裏付ける科学的根拠を示す必要がある.
2) 発症・増悪メカニズム
顎機能障害は感染症のように単一の発症因子によるのではなく,上記の発症因子が働き,それらが複合して各個人の生理的な適応範囲を超えたときに発症すると考えられている.患者によって発症メカニズムは異なるが,悪循環となって症状を増悪させたり慢性化させたりすることが多い.また,顎機能障害は自己制限的(SelfLimiting)な疾患であるともいわれており,適応能力の改善などによって時間の経過とともに症状を自覚しなくなることもある.
顎機能障害の検査法と評価
1) 医療面接と診察
・ 医療面接
顎機能障害の病態を把握し,病因をつきとめ,さらに治療方針を立てるうえで医療面接はきわめて重要である.医療面接は患者とのコミュニケーションおよびラポール形成の第一歩であるので,十分に注意して行う必要がある.医療面接は以下の項目について行う.
a. 主訴
先ず,患者の来院理由を具体的に聞き出す.患者自身の言葉を整理して簡明に診療録に記載する.
b. 既往歴
これまで罹患した全身的疾患や外傷などの既往,治療歴,入院歴,手術歴などを聞く.外傷,慢性関節リウマチ,痛風および精神科疾患などが顎機能障害と関連が深く,詳しく問診を行う.局所的な既往歴としては顎関節や顎顔面領域における外傷や炎症および腫瘍などの有無を聞く.矯正治療の既往や顎関節に過剰な負荷を与える可能性のある牽引療法を受けたことがあるか否かも聞き落とさない.
c. 現病歴
現病歴は病因の診断や術後経過を予測するうえで参 となる.現在の症状に対して発症時期,初発症
状,経過,治療の有無などについて詳しく聞く.
d. 家族歴
家族に顎機能障害,慢性関節リウマチ患者などがいないかを聞く.
e. 生活歴
職業,趣味,嗜好,習癖および職場や家庭での人間関係は発症・増悪因子の診断の参 になるので,詳しく聞く.
・ 視診
医療面接と診察時に患者の表情や反応を観察することで,精神的な背景や症状の重篤度がおおよそ判断できる.また,顎顔面・頭部の腫脹,肥大,形態異常,左右対称性を観察して顎関節部の炎症,筋の肥大,顎変形を診断する.
・ 触診
顎顔面・頭頸部の各部を触診することにより症状の存在する部位や程度を判定することができる.なお,圧痛計を使用すると評価の定量性や客観性が増す.
a. 筋の触診
顎顔面・頭頸部の筋を左右同時に手指にて軽く圧して疼痛の有無,程度および硬さを触知する.
b. 顎関節の触診
顎関節の外側ならびに後部を手指にて軽く圧して疼痛の有無および開閉口時の下顎頭の動きやクリッキングなどに伴う振動を触知する.
・ 聴診
顎関節雑音や咬合音を聴診器などを用いて聴診する.
a. 関節雑音
聴診器の集音部を顎関節の前方皮膚上にあて,下顎運動時の関節音を聴診し,雑音の有無と音質を検査する.音質によりクリッキングとクレピテーションが判別できる.
b. 咬合音
聴診器の集音部を頬骨弓の皮膚上にあて,タッピング運動時の咬合音を聴診する.音質により咬頭嵌合位における早期接触が診断できる.早期接触が存在する場合は,連続的で不明瞭な音質(ザック,ザック,など)が聴取される.
・ 疼痛誘発テスト
咬頭干渉部位や歯ぎしりによってできたと思われる咬耗面などで.みしめを行わせ,疼痛誘発の有無を調べる.また,割り箸やロールワッテを片側後方臼歯で.ませ,対側または同側の顎関節に疼痛を誘発するか,あるいは咬頭嵌合位での.かみしめ時に比べて軽減するかなどを調べる..かみしめ側と同側の顎関節に痛みを訴える場合には関節包や靱帯の障害があり,反対側の顎関節部に痛みがあるときは顎関節内に障害があるといわれている .反対側の顎関節部に痛みがある患者では関節空隙が狭くなっていることが多く,.かみしめ部位を支点として顎関節に圧迫負荷がかかることによる痛みである可能性がある.
2) 下顎運動の検査
特別な機器を使用しないで物差しなどを用いて,下顎運動範囲に制限があるか否かなどの検査を行う.
・ 最大開口
最大開口を行わせたときの開口量(域)を測定する.次の3つについて調べる.また,最大開閉口運動における切歯点の左右への偏位も観察する.片側の顆頭運動に制限があると,開口時に下顎は同側に偏位する.
a. 無痛最大開口量
患者が痛みを感ずることなく能動的(自発的)に行える最大開口量のことである.通常は上下顎前歯の切端間距離を測定し,40mm より小さい場合には開口制限ありと判定する.この値は前歯の垂直的被蓋(オーバーバイト)の量や男女差,顔の大きさの差などによっても影響を受けるので普遍的な基準とはいえない.
b. 有痛最大開口量
患者が痛みを我慢して行える最大開口量のことである.
c. 受動的最大開口量
術者の手指による受動的な最大開口量のことである.
受動的最大開口量と有痛最大開口量の差が2mm以上で弾力があるときは筋性の,一方この差がほとんどなく抵抗感が強いときは顎関節性の開口制限を疑うことができる(エンドフィールendfeel).
・ 前方および側方への移動量
最前方咬合位や最側方咬合位までの運動を行わせ,切歯点での運動量を物差しなどで測定する.咬頭嵌合位からいずれの方向へも約10mmの運動量が疼痛なく確保されていることが望ましい.また,前方運動を行ったとき左右のいずれかに偏位するときは,いずれかの顆頭運動に制限があることになる.
・ タッピング運動
アップライトの姿勢で下顎安静位から2~3Hzの周期で開閉口運動(タッピング運動)を行わせ,閉口点(タッピングポイント)が一点に収束するか不安定であるか,あるいはいずれかの歯に接触して,そこから滑走して咬頭嵌合位にいたるような現象が認められるかを判定する
3) 咬合検査
以下のような望ましい咬合の要件に基づいて検査を行うと,系統的な咬合検査が行える .
・ 望ましい咬合の要件
a. 咬頭嵌合位の位置
咬頭嵌合位が本来の望ましい位置にあるか否かということが最も重要な要件である.切歯点の位置関係だけで評価するのではなく,顎関節を含む下顎全体が頭蓋に対してどのような位置関係にあるかによって評価しなければならない.通常は筋肉位や顆頭安定位に対応しており,過去に中心位として定義されていた最後方咬合位(下顎最後退接触位)に一致することは少ない.
b. 咬頭嵌合位における咬合接触の安定性
歯列全体に 均等な咬合接触があることが望ましいが,少なくとも左右側の大,小臼歯部4カ所の咬合支持域に確実な咬合接触がなければならない.安定した咬合接触は.かみしめ時などにおいて顎関節へ過剰な負荷がかかるのを防ぐ.臼歯部においてどの咬合小面で接触しているか,咬合接触点数がどの程度であるかは,咬頭嵌合位の安定性だけでなく,歯の移動や咀嚼機能にも大きく影響する.
c. 滑走運動を誘導する部位
滑走運動がどの歯のどの咬合小面で誘導されるかという要素であり,それぞれの滑走運動について以下の要件を満たすことが望ましい.
a) 前方滑走運動
前方滑走運動は前歯部が誘導し,咬頭嵌合位を離れるとほぼ同時に臼歯部が離開することが望ましく,後方臼歯だけで接触する場合は顎関節への負荷要因となりやすい.
b) 側方滑走運動
側方滑走運動は,作業側の犬歯によって誘導される犬歯誘導か犬歯および小臼歯も誘導に関与するグループファンクションが望ましい.
後方臼歯だけで接触誘導する場合は,それが作業側であっても非作業側であっても,顎関節や歯周組織に対して有害となる.
ただし.みしめ時のみに発現する非作業側大臼歯の咬合接触は,非作業側顎関節を過剰な負荷から保護する作用があるとする報告がある .
側方滑走運動を誘導する咬合小面は,上顎の近心面と下顎の遠心面とが接触して下顎を誘導するM 型のガイドが好ましく,逆のD型は作業側顆頭を後外方に誘導しやすく顆頭運動範囲の拡大につながり好ましくない .
c) 後方滑走運動
咬頭嵌合位と最後方咬合位間の咬合接触および滑走運動は,顎機能障害や歯周病の発症と密接に関連するといわれてきた.後方咬合位では両側の大臼歯部が同時に接触し,後方滑走運動を誘導することが望ましい.睡眠中の仰臥位の姿勢では重力によって下顎が後退するので,後方咬合位での不安定な咬合接触は,ブラキシズム中の咬合性外傷や顎関節への過剰負荷の原因となりうる.
d. 滑走運動を誘導する方向
滑走運動をどの方向に誘導するかという要素であり,歯のガイドの傾斜に代表される.歯のガイドは適度な傾斜が必要であり,歯のガイドと顆路傾斜の関係は,前方滑走運動の場合,矢状顆路傾斜よりガイドの傾斜は等しいかわずかに大きいほうがよく,側方滑走運動においても矢状面投影角で比べた場合,非作業側顆路の傾斜よりガイドの傾斜が大きいほうがよい.顆路傾斜より歯のガイドの傾斜が緩いと,咀嚼ストロークの途中で下顎の回転方向が逆転して,スムーズな咀嚼運動が行いにくくなり機能的に好ましくない .
e. 咬合平面,歯列の位置や滑らかさ
臼歯部の咬頭頂と前歯の切端を結ぶ咬合平面は適度の彎曲をもって滑らかに連続し,舌背の高さとほぼ同じ高さに位置するのがよい.歯列も滑らかで狭窄がなく,適度な広さの舌房を確保し,咀嚼や会話を妨げないことが条件となる.
・ 咬合検査に必要な医療面接
咬合に関連した事項に焦点を絞って医療面接を行う.どこで.んでよいのかわからないというような咬合の不安定感を訴えたり,早期接触や咬頭干渉を患者が自覚していることもある.
・ 咬合検査における視診
安定したタッピング運動の有無,タッピングポイントの収束状態,咬合時の歯の動揺などを観察する.また,各種滑走運動を行ったときにどの部位で接触しているか,どの程度のクリアランスがあるかをある程度は目で確かめることができる
.
・ 咬頭嵌合位―最後方咬合位間距離
咬頭嵌合位と最後方咬合位の間の距離(IP―RCP間距離)をそれぞれのオーバージェットの差として物差しなどで計測する.IP―RCP間距離は通常0.5~1mm程度あり,この距離が全くないか,あるいは2mm を越えるような大きな距離がある場合には咬頭嵌合位の位置に問題がある可能性がある.
・ 咬合検査における触診
歯に手指を軽く触れ,タッピングを行わせたときの手指に伝わる歯の振動によって,早期接触や咬頭干渉があるか否かを判定できる.
・ 各種咬合検査法
咬合紙やシリコーンブラックなどを用いた咬合記録や,薄いプラスチックや金属の箔を用いた引き抜き試験などを行って,咬頭嵌合位や偏心位における咬合接触状態を調べる.
・ X線写真の所見を用いた咬合の補助的検査
顎関節断層X線写真やMRIにおける顆頭位の所見を利用して,咬頭嵌合位の位置の異常に関する診断の補助とする.またデンタルX線写真で歯根膜腔が拡大している場合や歯槽骨の垂直性の吸収がある場合は,外傷性の咬合である可能性が高い.なお,咬合検査の目的だけでX線検査を行うことはまれである.
・ 研究用模型による咬合検査
歯列や咬合平面の異常などマクロな咬合検査が可能である.咬耗の状態を観察してブラキシズム習癖の有無を推定することができる.
咬合器に模型を装着して滑走運動時の咬合接触状態を調べる方法もあるが,咬合器が生体の下顎運動を十分に再現していない場合には,正しい検査は行えない.
・ 疼痛誘発テストを利用した咬合検査
側方ガイドが不良であると思われる症例で,歯ぎしり様の側方グラインディングを行わせると同側の顎関節に痛みを誘発する場合,即時重合レジンでガイドを暫間的に改善し同様に強いグラインディングを行わせ,疼痛が消失すれば,ガイドの異常と顎関節痛の発症との関連が強く疑われる.同じく,咬合高径が低いと思われる症例で咬頭嵌合位における.みしめでは疼痛を訴えるが,ロールワッテや割り箸を.ませると痛みが消失する場合も咬合の低位と症状の関連が疑われる.
4) 画像検査
顎関節部の骨形態の変化,関節窩内における下顎頭の位置などを調べるためにX線撮影を行う.関節円板など軟組織の状態を調べるにはMRIを撮影する.
・ X線画像
主として骨形態や関節窩における下顎頭の位置,関節腔内の石灰化物の検出などに用いられる.骨の形態異常は主に下顎頭に生じ,辺縁性の増生や吸収性骨変化などが認められる場合は変形性顎関節症(・型)と診断される .下顎頭の変位が認められる場合は,臨床症状との組合せで関節円板障害(・型)を疑うことができるが,関節円板の状態を確認できないので確定診断はできない.顎関節に対するX線画像としては次のものが一般的である.
a. 側斜位経頭蓋撮影法(シュラー変法)
骨形態や顆頭位の診断を目的として古くから行われてきたが,本法は顎関節部の外側1/3しか描影できないことや,顆頭位の診断には適切ではないともいわれており ,診断的価値は必ずしも高くない.
b. 顎関節断層撮影法
顎関節の骨構造および関節窩に対する下顎頭の位置などに関する多くの情報を提供し,画像診断法としての価値は大きい.
c. パノラマ顎関節撮影法
パノラマ顎関節分割撮影,四分割撮影と呼ばれるもので,顎関節断層撮影よりは簡便であり顎関節における骨変化などの診断に適している.
・ MR画像
本画像は硬軟両組織をはじめあらゆる物質の描出が可能であるので,各種病態の診断に適している.
顎関節部では,特に関節円板の診断に有効であり顎関節症・型の確定診断には不可欠である.またT2強調画像で関節腔滑液の貯留像であるjointeffusion像が観察される場合,滑膜の滲出性炎が生じているとかんがえられる .
5) 各種の機器を用いた検査
顎機能障害は顎関節や咀嚼筋の異常により生ずる機能障害であるので,前述の検査に加えて下顎運動,筋電図,咬合力などの検査も診断の参 となる.
・ 下顎運動検査
咀嚼をはじめとする顎口腔機能の多くは下顎運動を伴った機能であるため,顆頭運動や切歯点の運動を評価することによって機能状態を評価することができる.下顎運動記録装置で得られた運動路を観察して,おおよその機能状態を評価することが可能であるが,客観的な評価を行うにはデータベースを構築して,種々のパラメータについて診断のための基準値 をつくる必要がある.
a. 切歯点の解析
切歯点の解析に用いられる簡便な運動記録装置にはMKGやシロナソグラフがある.下顎左右中切歯唇側中央部に小型の永久磁石を接着し,顔面・頭部に取り付けた磁気センサによって磁石の三次元的位置を検出する.解析の対象となる下顎運動と解析項目は以下のものがある.
a) 咀嚼運動
咀嚼は代表的な顎機能であるので咀嚼運動は顎口腔系の機能的評価に最も適していると えられている.主に咀嚼運動路の前頭面投影像を用いて,再現性 やパターン分析 が行われている.顎機能障害患者では運動路の再現性が悪く,健常者と異なったパターンを示すことが多いといわれている.
b) 限界運動
限界運動は機能運動ではないので機能評価には適さないが,能力評価が可能である.顎機能障害患者では開口障害や運動障害が多く認められるので障害の程度や部位の診断に適している.特に,側方限界開口運動路の前頭面投影像を用いて,運動域の大きさ,対称性,再現性,滑らかさが分析されている .健常者では,運動域は大きく,左右対称的で,再現性に優れ,滑らかであるが,顎機能障害患者では,障害の程度や部位の違いによって,各項目の数値が劣性を示す.
b. 任意点の解析
MM-JI,トライメット,ナソヘキサグラフなどの6自由度下顎運動記録装置を用いれば,任意点の運動解析が可能である.皮下にあるため観察の難しい下顎頭(顆頭)の運動も計算により求めることができるので,顎機能障害の診断に有効であると思われるが,切歯点に比べて運動が小さいため変化を反映し難いこと,また,作業側顆頭部においては解析点の選択のわずかな違いによって運動方向が大きく変化することなどの特徴があり,解析には注意が必要である.
・ 筋電図検査
咀嚼筋の障害は顎機能障害の重要な病態であり,筋電計を用いて咀嚼筋の活動状態を検査することは,顎機能障害の診断に有効である.臨床検査においては咀嚼筋のなかでも主に咬筋や側頭筋から双極表面導出する方法が一般的である.しかし筋電図のどのパラメータによって機能状態を評価すべきかについては,いまだ統一見解がない.
a. 咀嚼リズムの分析
咀嚼は随意運動であるがなかば反射的な規則正しい下顎運動によって行われる.咀嚼時の咬筋筋電図(EMG)を観察すると,活動期と非活動期が繰り返し記録される.これらを一周期として,連続した複数の周期の規則性(リズム)を変動係数を用いて分析すると,健常者では変動が少なく規則性に優れているが,顎機能障害患者では規則性に劣ることが知られている.
b. サイレントピリオドの分析
タッピング運動における歯の接触直後や,かみしめ時の頤部叩打直後に一過性の閉口筋活動停止期(サイレントピリオド,SP)が出現する .顎機能障害患者ではSPが変化することが報告されているが,診断基準として確立されるまでにはいたっていない.
c. パワースペクトル分析
長時間の.みしめ時に咬筋や側頭筋EMGを記録し,一定の時間帯に分割してEMGの周波数成分の累積度数分布曲線(パワースペクトル)を求めると,時間の経過にともなって低周波数域へと移動する .これは筋の疲労によるものと えられている.
d. 非対称性指数(Asynmetricindex,Ai)
左右の咀嚼筋活動が調和しているか否かを評価する指数で,咬頭嵌合位における.みしめ時に,左右の咬筋や側頭筋EMGを記録して,左右のEMG積分値の差を左右のEMG積分値の和で除し,これに100を掛けた値で表す.左右側が対称的で調和した筋活動を示すときの値は0%,非対称のときは%の値の絶対値が大きくなり,活動の非対称性の程度と符号によって優位側の判定ができる .健常者ではAiは0% に近い値を示す.
----------------------------------------------------------------------・ 咬合力検査
上下歯列間に生ずる力を検査する方法である.顎機能を営むうえでは上下顎の歯列が接触し,かつ一定以上の力が発揮できることが必要である.顎関節や咀嚼筋に疼痛があると,咬合力は充分に発揮できないので,これを検査することで障害の状態がある程度診断できる.
咬合力計(オクルーザルフォースメータ),デンタルプレスケールおよびT-Scanなどが用いられる.デンタルプレスケールは薄いポリシートで加圧により赤く発色し,加圧力の大きさで発色濃度が変化することを利用し,T-Scanは薄い導電シートで加圧力の大きさで抵抗値が変化することを利用している.
© Rakuten Group, Inc.