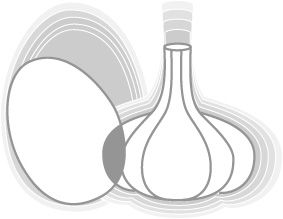PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 世界各国に食めぐり(407)
カテゴリ: 食事
素朴な疑問という感じで、「ウィンナーとソーセージの違いは?」という質問をいただく事があります。簡単に言ってしまえば、ソーセージという肉料理の中の一つ、それがウィンナーです。ウィンナー・ソーセージと言った方が解りやすいでしょうか。豚肉と牛肉を塩漬したものにスパイスを加えて練り合わせ、ケーシングと呼ばれる羊の腸などに充てんした後、燻したり、茹でたりして仕上げるソーセージの事で、オーストリアのウィーンが発祥とされるポピュラーなソーセージの一つです。なぜか本場ウィーンではウィンナーではなく、フランクフルトソーセージと呼ぶそうです。
JAS(日本農林規格)では原料となる肉の種類や燻すかどうかに関わらず、一定の基準で作られたソーセージのうち、羊腸もしくはこれに準じた太さとされる20mm未満のケーシングに詰められたソーセージは、「ウィンナーソーセージ」という名前をつけることができるとされています。この20mm未満という太さは使い勝手が非常に良い事から、一般的に売られている製品に多く採用され、ウィンナー=ソーセージという感じで名称の混同が起こり、判りにくさの元となっています。
世界的に知られたソーセージというとウィンナー、フランクフルト、ボローニャが有名で、それぞれ発祥の地名が付けられていますが、JASの規格上では、フランクフルトは豚の腸をケーシングとして使用して、太さが20mm以上36mm未満。ボローニャは牛の腸を使用して、太さが36mm以上となっています。それ以外にもヨーロッパを中心に地名を冠した物が多く、郷土料理のように各地にたくさんのバリエーションが伝えられています。ソーセージの語源に関しては、Sau(雄豚)とSage(セージ、香辛料)が合さったという説がありますが、ソーセージと思われる料理が記載された最古の文献には、山羊の肉を原料として豚肉の記載がない事から、豚香辛料説は否定的に見られています。
ラテン語で塩で味付けした物をSalsusと言い、それが元になったとする説が今日では有力視されています。Salは塩を意味する言葉で、サラダ、ソース、サラリー(給料)の語源となった言葉でもあります。肉を細かく切った物をSiciumという事から、SalsusはSiciumと合さってSalsicium(塩で味付けした細切れ肉)となります。フランク族の大移動に伴いフランス語圏へと伝わったSalsiciumは、フランス語Saussicheとなった後、ドーバー海峡を越えてイギリスへわたり、英語のSausageとなってソーセージと呼ばれる事となります。似たような塩由来の説では、Sauce(塩水)にAge(寝かせる)が合さったというものもありますが、途中経過となる言葉が各地に残されている事から、ラテン語のSalsicium由来説が有力な事は揺らがないように思えます。最近は荒挽き肉を使った製品が主流なようですが、以前見かけていた「絹挽き」などの製品が懐かしく思えてしまいます。
JAS(日本農林規格)では原料となる肉の種類や燻すかどうかに関わらず、一定の基準で作られたソーセージのうち、羊腸もしくはこれに準じた太さとされる20mm未満のケーシングに詰められたソーセージは、「ウィンナーソーセージ」という名前をつけることができるとされています。この20mm未満という太さは使い勝手が非常に良い事から、一般的に売られている製品に多く採用され、ウィンナー=ソーセージという感じで名称の混同が起こり、判りにくさの元となっています。
世界的に知られたソーセージというとウィンナー、フランクフルト、ボローニャが有名で、それぞれ発祥の地名が付けられていますが、JASの規格上では、フランクフルトは豚の腸をケーシングとして使用して、太さが20mm以上36mm未満。ボローニャは牛の腸を使用して、太さが36mm以上となっています。それ以外にもヨーロッパを中心に地名を冠した物が多く、郷土料理のように各地にたくさんのバリエーションが伝えられています。ソーセージの語源に関しては、Sau(雄豚)とSage(セージ、香辛料)が合さったという説がありますが、ソーセージと思われる料理が記載された最古の文献には、山羊の肉を原料として豚肉の記載がない事から、豚香辛料説は否定的に見られています。
ラテン語で塩で味付けした物をSalsusと言い、それが元になったとする説が今日では有力視されています。Salは塩を意味する言葉で、サラダ、ソース、サラリー(給料)の語源となった言葉でもあります。肉を細かく切った物をSiciumという事から、SalsusはSiciumと合さってSalsicium(塩で味付けした細切れ肉)となります。フランク族の大移動に伴いフランス語圏へと伝わったSalsiciumは、フランス語Saussicheとなった後、ドーバー海峡を越えてイギリスへわたり、英語のSausageとなってソーセージと呼ばれる事となります。似たような塩由来の説では、Sauce(塩水)にAge(寝かせる)が合さったというものもありますが、途中経過となる言葉が各地に残されている事から、ラテン語のSalsicium由来説が有力な事は揺らがないように思えます。最近は荒挽き肉を使った製品が主流なようですが、以前見かけていた「絹挽き」などの製品が懐かしく思えてしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.