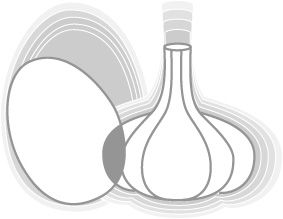PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: ★お菓子★(2932)
カテゴリ: カテゴリ未分類
手に取りやすい大きさの四角い形状で、各面が鉄板や平鍋で一面ずつ程よく焼き上げてあり、引きのある薄い皮の中には粒餡がたっぷり・・・和菓子の「金鍔」は全国的に広く知られた餅菓子の一種ではないでしょうか。金の鍔という名前ですが、確かに小麦粉を緩く溶いた皮は、小麦色に焼き上げると金に例える事はできる感じはしますが、形状としてはあまり刀の鍔には似ていないように思えます。
金鍔は正式には「金鍔焼き」と言い、略して金鍔と呼ばれています。江戸の中期頃から作られるようになったお菓子で、本来は鍔と例えられるに相応しい丸く、薄い形状だったと言います。粒餡を練った物を薄く丸い形に伸ばし小麦粉の生地をかけて、平鍋で焼き上げる、それが元々の金鍔の製法とされ、今日のような角金鍔が登場するのは明治に入ってからの事で、粒餡を寒天で固めて成形するという手法もその頃から行われるようになっています。
原形となったのは、将軍綱吉の頃、京都で流行したお菓子で、小豆餡を上新粉で包み、焼き上げた焼き菓子、「銀鍔」と呼ばれていました。それが江戸の街にもたらされると、「銀より金の方が価値が高く、お目出度い」として「金鍔焼き」と名称が変わり、原料も上新粉から小麦粉へと変更されました。小麦粉の生地を薄く伸ばして焼き上げ、その何倍かの量の粒餡を包むという製法は、初期のどら焼きにも共通したものがあります。
その後、薄く丸いままの状態では食べる際に崩れやすくて食べにくいという事もあり、二つに折り曲げて仕上げられるようになります。二つ折りの段階で「鍔」から離れた形状は、更に角形へと変わり、今日の金鍔のスタイルが確立されます。バリエーションとして粒餡の替わりに芋餡や厚く切った芋羊羹を使った「薩摩金鍔」がありますが、最近、その薩摩金鍔に紫芋を使ったものが評判となり、金鍔としての認知度が上がってきています。お菓子の世界は非常に新陳代謝が激しいものがありますが、伝統的なお菓子はしっかりと後世に伝えられる事を願っています。
金鍔は正式には「金鍔焼き」と言い、略して金鍔と呼ばれています。江戸の中期頃から作られるようになったお菓子で、本来は鍔と例えられるに相応しい丸く、薄い形状だったと言います。粒餡を練った物を薄く丸い形に伸ばし小麦粉の生地をかけて、平鍋で焼き上げる、それが元々の金鍔の製法とされ、今日のような角金鍔が登場するのは明治に入ってからの事で、粒餡を寒天で固めて成形するという手法もその頃から行われるようになっています。
原形となったのは、将軍綱吉の頃、京都で流行したお菓子で、小豆餡を上新粉で包み、焼き上げた焼き菓子、「銀鍔」と呼ばれていました。それが江戸の街にもたらされると、「銀より金の方が価値が高く、お目出度い」として「金鍔焼き」と名称が変わり、原料も上新粉から小麦粉へと変更されました。小麦粉の生地を薄く伸ばして焼き上げ、その何倍かの量の粒餡を包むという製法は、初期のどら焼きにも共通したものがあります。
その後、薄く丸いままの状態では食べる際に崩れやすくて食べにくいという事もあり、二つに折り曲げて仕上げられるようになります。二つ折りの段階で「鍔」から離れた形状は、更に角形へと変わり、今日の金鍔のスタイルが確立されます。バリエーションとして粒餡の替わりに芋餡や厚く切った芋羊羹を使った「薩摩金鍔」がありますが、最近、その薩摩金鍔に紫芋を使ったものが評判となり、金鍔としての認知度が上がってきています。お菓子の世界は非常に新陳代謝が激しいものがありますが、伝統的なお菓子はしっかりと後世に伝えられる事を願っています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.