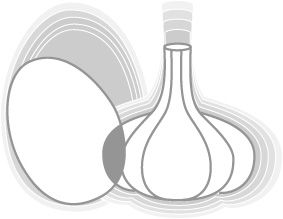PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: カテゴリ未分類
春は気圧の谷の移動に伴い、気候が周期的に変化します。喉かな季節とは対照的に天気が崩れて、激しい雨に突風や雷が鳴り、まさに春の嵐と呼べる天候が見られ、注意深く空を見上げていると、雲を背景に稲光を見る事ができて自然の持つ激しいエネルギーを感じてしまいます。
そんな激しい自然現象である雷を「稲妻」「稲光」などと表記します。この稲妻という言葉は、文字通り稲の「妻」という意味から付けられ、古代信仰によると、稲が結実する時期に雷が多い事から、雷が稲を実らせると考えられた事が元になっています。そのため、稲妻は「稲光」「稲魂」「稲交接」と呼ばれる事もあり、頭に「稲」を付ける事で密接な関係が示されています。
稲妻の「妻(つま)」という言葉は、元々は夫婦や恋人が互いに相手を呼ぶ言葉とされ、男女に関係なく使われていました。「妻」「夫」とも「つま」と言い、夫と書いて「つま」と読んでいます。稲と共に有り、欠かす事のできないものという意味でしょうか。古くは「稲の夫」の意味で稲夫と書かれる事もあったそうですが、現代では「つま」という語に「妻」が用いられているために、「稲妻」になったと考えられています。
実際に稲妻が多い年は稲の生育が良いとされ、古代の信仰が経験に基いたものである事が確認できます。空気中には多くの窒素があり、通常はイオン化した状態で大気中にある窒素が、稲妻が放電する電子を受けてイオンの状態を保てなくなると、大気中から地表に落ちてしまいます。その窒素が植物にとって重要な栄養素となり、植物を育てます。肥料の成分を見ると、窒素が利用されやすくしてある事からも、稲妻は天然の肥料生産機という事が解り、経験に基いた確かな観察に驚かされてしまいます。
そんな激しい自然現象である雷を「稲妻」「稲光」などと表記します。この稲妻という言葉は、文字通り稲の「妻」という意味から付けられ、古代信仰によると、稲が結実する時期に雷が多い事から、雷が稲を実らせると考えられた事が元になっています。そのため、稲妻は「稲光」「稲魂」「稲交接」と呼ばれる事もあり、頭に「稲」を付ける事で密接な関係が示されています。
稲妻の「妻(つま)」という言葉は、元々は夫婦や恋人が互いに相手を呼ぶ言葉とされ、男女に関係なく使われていました。「妻」「夫」とも「つま」と言い、夫と書いて「つま」と読んでいます。稲と共に有り、欠かす事のできないものという意味でしょうか。古くは「稲の夫」の意味で稲夫と書かれる事もあったそうですが、現代では「つま」という語に「妻」が用いられているために、「稲妻」になったと考えられています。
実際に稲妻が多い年は稲の生育が良いとされ、古代の信仰が経験に基いたものである事が確認できます。空気中には多くの窒素があり、通常はイオン化した状態で大気中にある窒素が、稲妻が放電する電子を受けてイオンの状態を保てなくなると、大気中から地表に落ちてしまいます。その窒素が植物にとって重要な栄養素となり、植物を育てます。肥料の成分を見ると、窒素が利用されやすくしてある事からも、稲妻は天然の肥料生産機という事が解り、経験に基いた確かな観察に驚かされてしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.