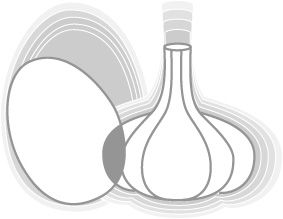PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: スポーツジムに通っている人(2773)
カテゴリ: カテゴリ未分類
プルシナー博士のプリオン説では、コッホの基準を満たせない事を前回書きましたが、その後、長崎大学医学部の片峰博士を中心とした研究グループが興味深い研究結果を発表しています。ヤコブ病に感染した脳をすり潰してマウスに摂取させ、経時変化を見るというものですが、各臓器ごとの感染力とプリオン量の比較が行われています。
最も感染力が高いと思われる脳では、ほぼ感染力とプリオンの量は比例関係にあったのですが、感染力が大きくなる初期の段階ではプリオンが検出されないという結果が出ています。また、他の臓器、唾液腺や脾臓では、感染力の強い時期にはプリオンの蓄積はほとんど検出されず、感染力が弱くなった時期になってプリオンの蓄積が増えるという結果が得られています。
通常ならば、感染力が大きくなる時期には病原体の検出量が多くなり、弱まる頃には一定か減少傾向が見られ、感染力と病原体量は比例関係にあるはずです。風邪の引き始めにはウィルスが検出されず、風邪が治り始めてからウィルスが検出され始める。これではウィルスに感染し、ウィルスの増殖によって症状が発現した。ウィルスが風邪の原因であるとする事はできないが明白です。
そうした結果から、ある一つの仮説が考えられます・・・プリオンは実は病原体ではなく、病原体の足跡ではないのか。変異性CJDの病原体は別に存在し、感染する事によって異常プリオンの蓄積が見られるようになるのではないか・・・実際に異常プリオンが蓄積していないにも関わらず、スポンジ脳症を呈したマウスの例が報告されています。また、感染組織を希釈していくと、やがて病原体の数が薄まりすぎ、感染性のない状態、「限界希釈点」に達します。限界希釈点に達したはずの変異性CJDの感染脳組織から、異常プリオンが大量に見つかったという事例もあります。本当にプリオンは病原体なのでしょうか?
最も感染力が高いと思われる脳では、ほぼ感染力とプリオンの量は比例関係にあったのですが、感染力が大きくなる初期の段階ではプリオンが検出されないという結果が出ています。また、他の臓器、唾液腺や脾臓では、感染力の強い時期にはプリオンの蓄積はほとんど検出されず、感染力が弱くなった時期になってプリオンの蓄積が増えるという結果が得られています。
通常ならば、感染力が大きくなる時期には病原体の検出量が多くなり、弱まる頃には一定か減少傾向が見られ、感染力と病原体量は比例関係にあるはずです。風邪の引き始めにはウィルスが検出されず、風邪が治り始めてからウィルスが検出され始める。これではウィルスに感染し、ウィルスの増殖によって症状が発現した。ウィルスが風邪の原因であるとする事はできないが明白です。
そうした結果から、ある一つの仮説が考えられます・・・プリオンは実は病原体ではなく、病原体の足跡ではないのか。変異性CJDの病原体は別に存在し、感染する事によって異常プリオンの蓄積が見られるようになるのではないか・・・実際に異常プリオンが蓄積していないにも関わらず、スポンジ脳症を呈したマウスの例が報告されています。また、感染組織を希釈していくと、やがて病原体の数が薄まりすぎ、感染性のない状態、「限界希釈点」に達します。限界希釈点に達したはずの変異性CJDの感染脳組織から、異常プリオンが大量に見つかったという事例もあります。本当にプリオンは病原体なのでしょうか?
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.