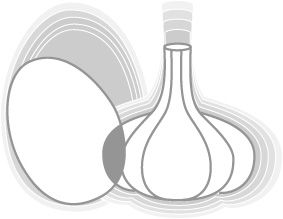PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51663)
カテゴリ: 食事
おせち料理と並んで正月に食される物として「餅」の存在があります。餅は日本に古くから伝えられた食べ物で、もち米を水に漬け、蒸したものを臼で粘り気が出るまで搗いて仕上げます。焼いたり煮たりと加熱する事で食べやすい柔らかさになる事から、直接焼いたり雑煮などの汁物に入れたりして食べられています。
今ではどちらかと言えば冬場を中心に一般的な食材として食べられますが、正月や節句、季節ごとの行事や祝い事などのめでたい日に食べられる食べ物としても伝えられてきています。もともとは正月や祝い事などのための特別な食べ物として扱われてきており、節分や節句、七夕やお盆、お彼岸などの季節の区切りの大切な日の供物とされてきていました。
餅は縄文時代の後期、稲作の伝来と共に東南アジアから伝えられた考えられ、当時の米は赤米で比較的餅に加工しやすかった事が餅の定着に一役買ったと言えます。平安時代には「鏡餅」が誕生し、餅は祭事、仏事などの慶事には欠かせない供物となっています。
室町時代に入ると武家を中心に茶道が急速な発展を遂げ、それに合わせてお茶に添えられる茶道菓子として餅が使われるようになり、お菓子の素材として独自の発達をするという新たな分岐点を迎える事となっています。
武家の年中行事が出入りの商人へ伝わり、商家から農家へと餅を食べる習慣は伝わります。江戸時代には餅を食べる習慣は農家でも一般化し、神仏や農具に餅を供えて豊作と家内安全を祈る事が行われるようになり、餅と農作業が密接な関わりを持つようになってきます。
田植えを終えた後や刈り上げを終えた後の刈上げ餅、秋を迎え収穫を終えた後の庭仕舞などでも餅が振舞われ、餅によって農作業の目途や家族の融和、村の協調などが図られてきたとされています。重要な行事と密接に結び付きながら伝えられてきた餅ですが、今日では普通に食べられる事にちょっと幸せを感じてしまいます。
今ではどちらかと言えば冬場を中心に一般的な食材として食べられますが、正月や節句、季節ごとの行事や祝い事などのめでたい日に食べられる食べ物としても伝えられてきています。もともとは正月や祝い事などのための特別な食べ物として扱われてきており、節分や節句、七夕やお盆、お彼岸などの季節の区切りの大切な日の供物とされてきていました。
餅は縄文時代の後期、稲作の伝来と共に東南アジアから伝えられた考えられ、当時の米は赤米で比較的餅に加工しやすかった事が餅の定着に一役買ったと言えます。平安時代には「鏡餅」が誕生し、餅は祭事、仏事などの慶事には欠かせない供物となっています。
室町時代に入ると武家を中心に茶道が急速な発展を遂げ、それに合わせてお茶に添えられる茶道菓子として餅が使われるようになり、お菓子の素材として独自の発達をするという新たな分岐点を迎える事となっています。
武家の年中行事が出入りの商人へ伝わり、商家から農家へと餅を食べる習慣は伝わります。江戸時代には餅を食べる習慣は農家でも一般化し、神仏や農具に餅を供えて豊作と家内安全を祈る事が行われるようになり、餅と農作業が密接な関わりを持つようになってきます。
田植えを終えた後や刈り上げを終えた後の刈上げ餅、秋を迎え収穫を終えた後の庭仕舞などでも餅が振舞われ、餅によって農作業の目途や家族の融和、村の協調などが図られてきたとされています。重要な行事と密接に結び付きながら伝えられてきた餅ですが、今日では普通に食べられる事にちょっと幸せを感じてしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.