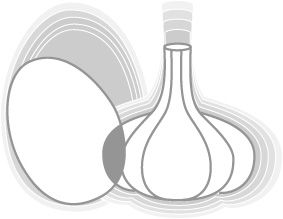PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51662)
カテゴリ: 食事
伯母が元気だった頃は、毎年5月に入ると手作りの粽が送られてきていて、初夏の訪れを感じさせてくれる物となっていました。それも途絶えて久しく、今頃になって素朴な味を懐かしく思い出しています。
送られてきていた粽は、木灰に水を注いで上澄みを取り、それにもち米を漬けて竹の皮に包んで茹でてあるので、正確には「灰汁巻き(あくまき)」であった事や端午の節句に供えるために作られていた事、端午の節句に灰汁巻きを供えるのは鹿児島、宮崎、奄美大島の風習である事などを後になって知りました。
もち米を灰汁に漬ける事で独自の風味が生まれ、保存性が高まる事から、灰汁巻きは保存食としても利用され、秀吉の朝鮮出兵や関が原の戦いなどの際、薩摩藩士が灰汁巻きを兵糧として持ち歩いたとされます。
粽は平安時代に中国から伝えられたとされ、承平年間(931年~938年)に編纂された「倭名類聚抄」に「知萬木」として記され、もち米を植物の葉で包み、これを灰汁で煮込むと製法が記録されています。
日本各地で作られ、さまざまなバリエーションも生まれた事から、江戸時代、元禄10年(1697年)に発行された「本朝食鑑」には、蒸した米を突いて餅にし、マコモの葉で包んでイグサで縛り、お湯で茹でた物や、うるち米の団子を笹の葉で包んだ「御所粽」または「内裏粽」と呼ばれる物、もち米の餅を藁で包んだ「飴粽(あんちまき)」、サザンカの根を焼いて作った灰汁でもち米を湿らせ、餅を作って藁で包んだ「朝比奈粽」の4種類の粽が紹介されています。
4種類の粽の中で朝比奈粽が最も原形に近いといえ、灰汁巻きや長崎の「唐灰汁粽」、新潟の「灰汁笹巻き」や台湾で作られる粽にも似通った製法という事がいえます。
朝比奈粽において灰汁を得るための木がサザンカに限定されている理由は、灰にした際のアルカリ性の度合いにある事が考えられます。
灰汁巻きは灰汁に浸したもち米を竹の皮で包み、お湯で茹でただけなのにまるで餅のようにもち米同士がくっつき合って、べっ甲のような透明感を持った色合いに仕上がります。
そうした灰汁巻きの仕上がりには灰汁のアルカリ度が影響していて、アルカリ性が低いともち米の粒感が残り、薄茶色に仕上がります。灰汁巻きが作られてきた九州南部は照葉樹が多く、照葉樹を燃やして得られる灰からは落葉樹や針葉樹よりも強いアルカリを得る事ができるため、広く九州南部で灰汁巻きが作られ、照葉樹が少ない駿河の朝比奈ではサザンカと木を限定する事で朝比奈粽が作られていたと考えられます。
粽は中国から東南アジアにかけた広い地域で作られてきました。各地に伝わる粽の質感の違いは、具材や作り方に合わせ、素材の一つともいえるアルカリを得るための灰やアルカリ性の強度にもあるのかもしれないと、素朴な美味しさの粽に奥の深いものを感じています。
送られてきていた粽は、木灰に水を注いで上澄みを取り、それにもち米を漬けて竹の皮に包んで茹でてあるので、正確には「灰汁巻き(あくまき)」であった事や端午の節句に供えるために作られていた事、端午の節句に灰汁巻きを供えるのは鹿児島、宮崎、奄美大島の風習である事などを後になって知りました。
もち米を灰汁に漬ける事で独自の風味が生まれ、保存性が高まる事から、灰汁巻きは保存食としても利用され、秀吉の朝鮮出兵や関が原の戦いなどの際、薩摩藩士が灰汁巻きを兵糧として持ち歩いたとされます。
粽は平安時代に中国から伝えられたとされ、承平年間(931年~938年)に編纂された「倭名類聚抄」に「知萬木」として記され、もち米を植物の葉で包み、これを灰汁で煮込むと製法が記録されています。
日本各地で作られ、さまざまなバリエーションも生まれた事から、江戸時代、元禄10年(1697年)に発行された「本朝食鑑」には、蒸した米を突いて餅にし、マコモの葉で包んでイグサで縛り、お湯で茹でた物や、うるち米の団子を笹の葉で包んだ「御所粽」または「内裏粽」と呼ばれる物、もち米の餅を藁で包んだ「飴粽(あんちまき)」、サザンカの根を焼いて作った灰汁でもち米を湿らせ、餅を作って藁で包んだ「朝比奈粽」の4種類の粽が紹介されています。
4種類の粽の中で朝比奈粽が最も原形に近いといえ、灰汁巻きや長崎の「唐灰汁粽」、新潟の「灰汁笹巻き」や台湾で作られる粽にも似通った製法という事がいえます。
朝比奈粽において灰汁を得るための木がサザンカに限定されている理由は、灰にした際のアルカリ性の度合いにある事が考えられます。
灰汁巻きは灰汁に浸したもち米を竹の皮で包み、お湯で茹でただけなのにまるで餅のようにもち米同士がくっつき合って、べっ甲のような透明感を持った色合いに仕上がります。
そうした灰汁巻きの仕上がりには灰汁のアルカリ度が影響していて、アルカリ性が低いともち米の粒感が残り、薄茶色に仕上がります。灰汁巻きが作られてきた九州南部は照葉樹が多く、照葉樹を燃やして得られる灰からは落葉樹や針葉樹よりも強いアルカリを得る事ができるため、広く九州南部で灰汁巻きが作られ、照葉樹が少ない駿河の朝比奈ではサザンカと木を限定する事で朝比奈粽が作られていたと考えられます。
粽は中国から東南アジアにかけた広い地域で作られてきました。各地に伝わる粽の質感の違いは、具材や作り方に合わせ、素材の一つともいえるアルカリを得るための灰やアルカリ性の強度にもあるのかもしれないと、素朴な美味しさの粽に奥の深いものを感じています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.