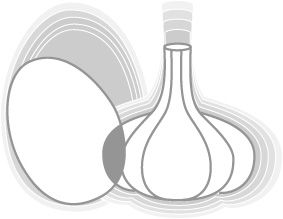PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
苦手な言葉の一つなのですが、羊や山羊を指して「ライブストック」といういい方があります。文字通り「生きた保存食」という事で、家畜として世話をしながら、食糧が不足してくると屠殺して食糧とするという意味で使われます。
同じように家畜として接している牛や馬にはそうしたいい方を使わない事は、牛や馬が労働力として役に立つ事が関わっていると考える事ができます。同じく家畜として飼われている豚に対してもライブストックといういい方はされず、冬が始まると次のシーズンの繁殖に必要な数だけを残して屠殺し、ハムやソーセージなどの「ストック」にされてしまいます。
豚は羊や山羊と同じように労働力としてはあまり期待できない事もあるのですが、冬が始まると一斉に保存食に加工されてしまう事については、羊や山羊が草食動物で人が食べない牧草を食料とする事に対し、豚は雑食性の動物で人と食料が競合する事が深く関係しているという事ができます。
かつて豚は森の中を駆け回り、さまざまな物を食べて生活していました。俊敏で力強く動き、神経質で清潔好きだった彼らは、人が農耕を始めて耕地や家の建材、燃料の確保などの理由で森を切り開くようになると棲みかを奪われ、人に飼われて家畜化していきます。その際、人と食料が競合するために人が食べない食料を飼料とした事が、豚という生物の評価を大きく下げる事に繋がったように思えます。
そのため人用の食料さえも不足しがちな厳しい冬が始まる前に間引きして、保存食に加工してきた事がハムやソーセージといった食文化を育んできたという事ができ、生かして冬を越し、必要に応じて食料とするす羊や山羊、労働力ともなる牛や馬を使ったハムやソーセージといった加工例が極端に少ない理由と考える事ができます。
そんな中、人用の食料が底を尽き、生かして冬を越させる予定だった豚たちに与える飼料がなくなってしまい、止むなく森に放したところ豚たちは野山を駆け巡り、どんぐりなどを食料としながら逞しく、より美味しくなって帰って来た事が一部のブランド豚に見られる放牧の由来ともいわれます。
身近に接する家畜の中で、唯一食料が人と競合するために不当に扱われてきた感がある豚ですが、最近ではペットとして飼われたり、ブランド豚の定着で高値で取引されたりと、少しずつ立場が向上してきたようにも思えます。神経質で清潔好きという認識も広まってきているので、愚鈍で不潔というイメージは早々に無くなってほしいものだと願っています。
同じように家畜として接している牛や馬にはそうしたいい方を使わない事は、牛や馬が労働力として役に立つ事が関わっていると考える事ができます。同じく家畜として飼われている豚に対してもライブストックといういい方はされず、冬が始まると次のシーズンの繁殖に必要な数だけを残して屠殺し、ハムやソーセージなどの「ストック」にされてしまいます。
豚は羊や山羊と同じように労働力としてはあまり期待できない事もあるのですが、冬が始まると一斉に保存食に加工されてしまう事については、羊や山羊が草食動物で人が食べない牧草を食料とする事に対し、豚は雑食性の動物で人と食料が競合する事が深く関係しているという事ができます。
かつて豚は森の中を駆け回り、さまざまな物を食べて生活していました。俊敏で力強く動き、神経質で清潔好きだった彼らは、人が農耕を始めて耕地や家の建材、燃料の確保などの理由で森を切り開くようになると棲みかを奪われ、人に飼われて家畜化していきます。その際、人と食料が競合するために人が食べない食料を飼料とした事が、豚という生物の評価を大きく下げる事に繋がったように思えます。
そのため人用の食料さえも不足しがちな厳しい冬が始まる前に間引きして、保存食に加工してきた事がハムやソーセージといった食文化を育んできたという事ができ、生かして冬を越し、必要に応じて食料とするす羊や山羊、労働力ともなる牛や馬を使ったハムやソーセージといった加工例が極端に少ない理由と考える事ができます。
そんな中、人用の食料が底を尽き、生かして冬を越させる予定だった豚たちに与える飼料がなくなってしまい、止むなく森に放したところ豚たちは野山を駆け巡り、どんぐりなどを食料としながら逞しく、より美味しくなって帰って来た事が一部のブランド豚に見られる放牧の由来ともいわれます。
身近に接する家畜の中で、唯一食料が人と競合するために不当に扱われてきた感がある豚ですが、最近ではペットとして飼われたり、ブランド豚の定着で高値で取引されたりと、少しずつ立場が向上してきたようにも思えます。神経質で清潔好きという認識も広まってきているので、愚鈍で不潔というイメージは早々に無くなってほしいものだと願っています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.