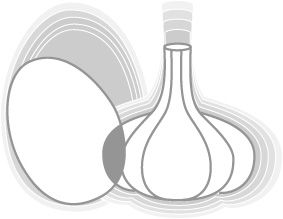PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
先日、パスタについて話をしていて、幾つかの面白い話を聞かせていただく事ができました。最初にうどんやそうめんを茹でるとお湯は白く濁ってしまうのに、パスタを茹でたお湯は何故、あのように濁らないのでしょうという謎かけが行われ、それはデュラム小麦というガラス質と呼ばれる半透明のタンパク質を多く含む胚乳を持つ小麦を粗挽きにし、高い圧力を掛けて生地を結着させているからと判ったのですが、僅かに芯が残された状態、「アルデンテ」に茹でる意味はと聞かれると若干の認識の違いを知る事となりました。
パスタをアルデンテに茹で上げる意味は、パスタに水分を吸収する余地を残しておく事で、ソースの味をより良く吸収させるためと思っていたのですが、それ以外に食べる際に唾液に含まれる消化酵素や胃酸を吸収しやすいようにしておき、よりたくさん食べるための工夫と聞かされると、如何にもイタリア的と思えてきます。
以前から気になっていた乾燥パスタと生パスタの違いについては、かつては南イタリアが乾燥パスタ、北イタリアは生パスタという勢力図になっていたそうで、同じパスタを打ち立てで食べるか、乾燥させた物を食べるかといった違いではなく、双方は別々に発展してきた経緯があるといいます。
乾燥パスタはアラビア人によって伝えられ、乾いた砂漠では小麦などの食料を粉の状態で持ち歩くより、麺などに加工して乾燥させた方が扱いやすく、保存にも適していた物がイタリアに持ち込まれ、南イタリアで栽培されていたデュラム小麦と出会う事で独自の発展を遂げ、生パスタは北からアルプスを越えて持ち込まれた物が定着したとされます。
そのため原材料にも違いがあり、乾燥パスタはデュラム小麦で作られる事に対し、生パスタはフツウコムギが主に使われています。シコシコ感がほしければ乾燥パスタ、モチモチ感なら生パスタといわれますが、そうした食感の違いは乾燥工程の有無ではなく、原料の違いから生じていた事になります。
今では多くのメーカーが生産効率を上げるためにパスタを押し出す金型の内側をフッ素樹脂でコーティングし、乾燥にもタンパク質が線維化しない上限付近の90度程度の高温の温風を使っているといわれます。昔ながらのブロンズの金型を使って高い温度で成型し、自然の風で乾燥させたデュラム小麦本来の風味を感じられるパスタを探してみなければと改めて思ってしまいました。
パスタをアルデンテに茹で上げる意味は、パスタに水分を吸収する余地を残しておく事で、ソースの味をより良く吸収させるためと思っていたのですが、それ以外に食べる際に唾液に含まれる消化酵素や胃酸を吸収しやすいようにしておき、よりたくさん食べるための工夫と聞かされると、如何にもイタリア的と思えてきます。
以前から気になっていた乾燥パスタと生パスタの違いについては、かつては南イタリアが乾燥パスタ、北イタリアは生パスタという勢力図になっていたそうで、同じパスタを打ち立てで食べるか、乾燥させた物を食べるかといった違いではなく、双方は別々に発展してきた経緯があるといいます。
乾燥パスタはアラビア人によって伝えられ、乾いた砂漠では小麦などの食料を粉の状態で持ち歩くより、麺などに加工して乾燥させた方が扱いやすく、保存にも適していた物がイタリアに持ち込まれ、南イタリアで栽培されていたデュラム小麦と出会う事で独自の発展を遂げ、生パスタは北からアルプスを越えて持ち込まれた物が定着したとされます。
そのため原材料にも違いがあり、乾燥パスタはデュラム小麦で作られる事に対し、生パスタはフツウコムギが主に使われています。シコシコ感がほしければ乾燥パスタ、モチモチ感なら生パスタといわれますが、そうした食感の違いは乾燥工程の有無ではなく、原料の違いから生じていた事になります。
今では多くのメーカーが生産効率を上げるためにパスタを押し出す金型の内側をフッ素樹脂でコーティングし、乾燥にもタンパク質が線維化しない上限付近の90度程度の高温の温風を使っているといわれます。昔ながらのブロンズの金型を使って高い温度で成型し、自然の風で乾燥させたデュラム小麦本来の風味を感じられるパスタを探してみなければと改めて思ってしまいました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.