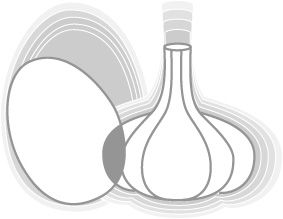PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
鍋物が美味しく感じられる時期、少しお洒落な店では半分に割られた竹の器に盛られ、少量を添えられたスプーンなどで鍋の中に入れる「つみれ」は主役級の存在と思えます。
鍋に入れる際に手を汚さず、スマートに落とし込む事ができる竹の器とスプーンという組み合わせはとても便利で良いものに思えるのですが、つみれの語源から考えるとどこか邪道のようにも思えてきます。
つみれはすり身にした魚肉に片栗粉などのつなぎや調味料を加えて練った物で、食べる際に少量の塊りを手で摘んで入れていく「摘み入れ」が語源となったといわれます。
そのためスプーンを使ってしまうと摘まずにすくってしまう事から、「すくれ」となってしまうように思えてしまうのですが、魚肉のすり身を使った物が「つみれ」で、鶏肉や豚肉などのひき肉を使ったものは「つくね」という分類があるので、スプーンでもつみれなのかもしれません。
魚肉を使ったつみれ、鶏肉や豚肉で作られるつくねと便利な使い分けがあるように思えるのですが、その区別はそれほど厳密ではなく、語源から考えてみても明確に分ける事は難しくなっています。
つみれが「摘み入れ」から来ているように、つくねも「捏ねた(事前に良く練ってきちんと成型した)」が元になっていて、鍋に入れる素材を用意した段階で魚のすり身がきちんと丸めてあった場合、つみれではなくつくねであるという事ができます。
魚肉は鮮度が落ちやすく、特に鍋に使うような大きな切り身が得られない小さな青魚の場合、すり身にすると鮮度が落ちやすくなってしまいます。それに対し鶏肉や豚肉は魚肉ほどには鮮度を気にする必要がない事から、鍋を始める直前にすり身にして鍋に少量ずつ入れていく魚肉と、事前に鍋に入れやすいように小さく丸めておく鶏肉や豚肉。そうした違いが魚肉はつみれ、鶏肉や豚肉はつくねという習慣に繋がり、素材ごとに呼び分ける事になったと思えます。
鶏肉のつくねが何故か得意料理のようにいわれているのですが、いつも鶏団子と呼んでいました。そろそろ調理法によって呼び方を変えても良いのかもしれないと、一人で考えています。
鍋に入れる際に手を汚さず、スマートに落とし込む事ができる竹の器とスプーンという組み合わせはとても便利で良いものに思えるのですが、つみれの語源から考えるとどこか邪道のようにも思えてきます。
つみれはすり身にした魚肉に片栗粉などのつなぎや調味料を加えて練った物で、食べる際に少量の塊りを手で摘んで入れていく「摘み入れ」が語源となったといわれます。
そのためスプーンを使ってしまうと摘まずにすくってしまう事から、「すくれ」となってしまうように思えてしまうのですが、魚肉のすり身を使った物が「つみれ」で、鶏肉や豚肉などのひき肉を使ったものは「つくね」という分類があるので、スプーンでもつみれなのかもしれません。
魚肉を使ったつみれ、鶏肉や豚肉で作られるつくねと便利な使い分けがあるように思えるのですが、その区別はそれほど厳密ではなく、語源から考えてみても明確に分ける事は難しくなっています。
つみれが「摘み入れ」から来ているように、つくねも「捏ねた(事前に良く練ってきちんと成型した)」が元になっていて、鍋に入れる素材を用意した段階で魚のすり身がきちんと丸めてあった場合、つみれではなくつくねであるという事ができます。
魚肉は鮮度が落ちやすく、特に鍋に使うような大きな切り身が得られない小さな青魚の場合、すり身にすると鮮度が落ちやすくなってしまいます。それに対し鶏肉や豚肉は魚肉ほどには鮮度を気にする必要がない事から、鍋を始める直前にすり身にして鍋に少量ずつ入れていく魚肉と、事前に鍋に入れやすいように小さく丸めておく鶏肉や豚肉。そうした違いが魚肉はつみれ、鶏肉や豚肉はつくねという習慣に繋がり、素材ごとに呼び分ける事になったと思えます。
鶏肉のつくねが何故か得意料理のようにいわれているのですが、いつも鶏団子と呼んでいました。そろそろ調理法によって呼び方を変えても良いのかもしれないと、一人で考えています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.