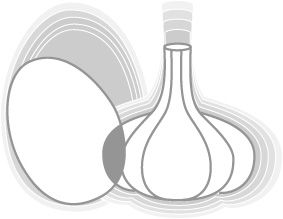PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
明らかに日本の食文化でありながら、和食かといわれると少し抵抗を感じてしまうもの、丼物はそのような微妙な位置付けを持つ食べ物のようにも思えます。
日本の正式な作法では主食であるご飯とおかずは別々に盛り付けられ、それぞれを箸で一口分ずつ口に運ぶ事から、ご飯とおかずが一緒に盛り付けられた丼物は、合理的ではありながら正式ではないように思える所以とも考える事ができます。
丼物の「丼どんぶり)」の語源については諸説があり、江戸時代に安価な食事を提供していた飯屋を「けんどん屋」と称していて、ご飯のおかわりを出さない代わりに最初の一杯を多めに出すために器が大きくなり、それを「けんどん振り鉢」と呼んだものが短縮されて丼鉢となり、丼という名称が生まれたともいわれます。
また、表記された文字が井戸を意味する文字の中に点を持つ事から、井戸の中に何かを投げ入れた際の「どんぶり」という音が語源であり、大きな器で中に何でも投げ入れる事からその名が付いたともいう説も説得力を感じさせてくれます。
しっかりと日本の食文化に根付いている丼物ですが、歴史を見てみると意外と浅く、ルーツと見られている「芳飯」にしても室町時代にならないと登場しません。比較的歴史があるとされる天丼も最初の丼物といわれる事の多い鰻丼も、江戸庶民が愛したとされる深川丼も誕生するのは19世紀に入ってからで、江戸時代末期の事となっています。
そうした歴史の浅さが和食と丼物の微妙な距離感に繋がっているようにも思えます。時代が明治になると今日の牛丼のルーツとなる牛鍋の割り下をご飯に掛けた牛鍋丼や、牛鍋の割り下を卵でとじた開化丼、肉を牛から鶏に変えて卵でとじた親子丼なども登場し、洋食華やかな大正時代にカツ丼が考案されています。
最近では丼物も日本の食文化として海外で紹介され、食べられるようになってきています。現地でその土地の食文化を採り入れて新たな丼物が生まれ、また、日本でも大手のチェーン店を中心にさまざまなバリエーションが考案されています。時と共に変化を続けるという柔軟性も伝統的という観点からは外れてしまうのかとも思えてきて、やはり微妙なものを感じてしまいます。
日本の正式な作法では主食であるご飯とおかずは別々に盛り付けられ、それぞれを箸で一口分ずつ口に運ぶ事から、ご飯とおかずが一緒に盛り付けられた丼物は、合理的ではありながら正式ではないように思える所以とも考える事ができます。
丼物の「丼どんぶり)」の語源については諸説があり、江戸時代に安価な食事を提供していた飯屋を「けんどん屋」と称していて、ご飯のおかわりを出さない代わりに最初の一杯を多めに出すために器が大きくなり、それを「けんどん振り鉢」と呼んだものが短縮されて丼鉢となり、丼という名称が生まれたともいわれます。
また、表記された文字が井戸を意味する文字の中に点を持つ事から、井戸の中に何かを投げ入れた際の「どんぶり」という音が語源であり、大きな器で中に何でも投げ入れる事からその名が付いたともいう説も説得力を感じさせてくれます。
しっかりと日本の食文化に根付いている丼物ですが、歴史を見てみると意外と浅く、ルーツと見られている「芳飯」にしても室町時代にならないと登場しません。比較的歴史があるとされる天丼も最初の丼物といわれる事の多い鰻丼も、江戸庶民が愛したとされる深川丼も誕生するのは19世紀に入ってからで、江戸時代末期の事となっています。
そうした歴史の浅さが和食と丼物の微妙な距離感に繋がっているようにも思えます。時代が明治になると今日の牛丼のルーツとなる牛鍋の割り下をご飯に掛けた牛鍋丼や、牛鍋の割り下を卵でとじた開化丼、肉を牛から鶏に変えて卵でとじた親子丼なども登場し、洋食華やかな大正時代にカツ丼が考案されています。
最近では丼物も日本の食文化として海外で紹介され、食べられるようになってきています。現地でその土地の食文化を採り入れて新たな丼物が生まれ、また、日本でも大手のチェーン店を中心にさまざまなバリエーションが考案されています。時と共に変化を続けるという柔軟性も伝統的という観点からは外れてしまうのかとも思えてきて、やはり微妙なものを感じてしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.