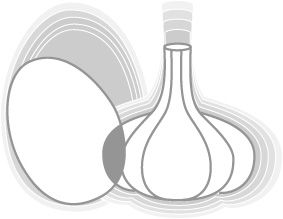PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51663)
カテゴリ: 食事
以前、不思議に思った事なのですが、ヤマメやアユなどの渓流に棲む川魚を名物としている街はあるのですが、塩焼きや甘露煮といった加工品はあっても魚肉練り製品はほとんど見られません。せっかく新鮮な魚があるのにもったいないと思っていると、淡水魚は身が柔らかくて練り物にした際、固まりにくいためという簡単な理由に出会ってしまいました。
魚肉で練り物を作る際、すり身にして練りながら少量の塩を加えるのですが、塩が加わると急にすり身が硬くなったような感じがしてきます。塩が加わった事で魚肉の中の塩溶性タンパク質が溶け出してきてアクトミオシンを形成し、アクトミオシンの網目の構造によって練り製品特有の弾力のある食感が形成されます。この塩溶性タンパク質の少なさが淡水魚が練り製品の素材となりにくい理由となっていると考える事ができます。
多くの場合、練り製品の素材には淡白な白身魚が使われていて、スケトウダラが主要な原料となっています。コスト面からほとんどの練り製品メーカーでは海外で生産される輸入品の冷凍すり身が使用されているのですが、近年、世界的にスケトウダラの需要が高まった事や漁獲制限が設けられた事から、冷凍すり身の値段も高騰してきているといわれます。
そのため、コストを抑えるために工場がある東南アジアの現地産の淡水魚なども使用されるようになり、練り製品の原料は海水魚だけでもなくなってきています。表示の厳格化は進んでいく事と思いますので、いずれ練り製品の原材料欄に聞き慣れない魚の名前が並ぶ日が来るのかもしれません。
魚肉で練り物を作る際、すり身にして練りながら少量の塩を加えるのですが、塩が加わると急にすり身が硬くなったような感じがしてきます。塩が加わった事で魚肉の中の塩溶性タンパク質が溶け出してきてアクトミオシンを形成し、アクトミオシンの網目の構造によって練り製品特有の弾力のある食感が形成されます。この塩溶性タンパク質の少なさが淡水魚が練り製品の素材となりにくい理由となっていると考える事ができます。
多くの場合、練り製品の素材には淡白な白身魚が使われていて、スケトウダラが主要な原料となっています。コスト面からほとんどの練り製品メーカーでは海外で生産される輸入品の冷凍すり身が使用されているのですが、近年、世界的にスケトウダラの需要が高まった事や漁獲制限が設けられた事から、冷凍すり身の値段も高騰してきているといわれます。
そのため、コストを抑えるために工場がある東南アジアの現地産の淡水魚なども使用されるようになり、練り製品の原料は海水魚だけでもなくなってきています。表示の厳格化は進んでいく事と思いますので、いずれ練り製品の原材料欄に聞き慣れない魚の名前が並ぶ日が来るのかもしれません。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.