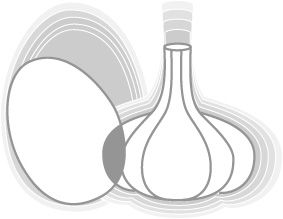PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
カツオのたたきというとカツオの身を節に分け、表面のみに火が通るように焙って適度な厚さに切り分け、薬味とタレを付けていただく刺身の一種が思い浮かんできます。ほとんど同じ言葉ではあるのですが、アジのたたきというとアジをまな板の上で細かく刻んで薬味や調味料を混ぜた物が連想され、アジの表面だけを焙るという発想はありません。
同じ魚のたたきなのにまるで形態が違う事を不思議に思いながら見回してみると、最近は刺身で食べられる事もある牛肉には表面を焙ったたたきが存在し、細かく刻んだタルタルステーキをたたきと呼ぶ事はありません。
野菜類を調理する際は、細かく刻む事に付いてはみじん切りや粗みじんといった表現をしますが、特に粘りを持つ野菜の粘りを引き出すためにはたたくという刻み方の表現が用いられ、粗みじんに近い状態にあるように思えます。
また、野菜に関しては実際に叩く調理法が存在し、たたきを施して組織を破壊し、味が染みやすく、食べやすい状態にした「たたきゴボウ」や「たたきキュウリ」などが調理に用いられ、叩くとは無縁の調理法としては肉や魚などに葛粉をまぶして茹で上げる「葛たたき」といった調理法も存在しています。
カツオのたたきに関しては、表面を焙った後に軽く全体を叩く事で旨味を増したり、薬味やタレをまぶしてから叩く事で味を染ませたりという事が行われるためにたたきと呼ばれるようになったという説もあり、叩く行為と無縁ではなかったようにも思えます。
カツオのたたきの起源については諸説があるのですが、土佐藩の藩主、山内一豊が食中毒防止の観点から名産であったカツオの生食を禁止したため、表面のみを焙る事で焼き魚として食べていたというユニークなものがあり、焙ってみたら旨味が増していて、水分が除かれた事によって味も濃厚になっている事に気付き、後にさらなる工夫として叩きが加わって今日に至っているように思えます。
それにしても和食の中に存在するたたきという調理技法は、日本語や和食の世界観を難しくしてくれ、外国からは理解できないものとなるのではと、どこか心配になってしまいます。
同じ魚のたたきなのにまるで形態が違う事を不思議に思いながら見回してみると、最近は刺身で食べられる事もある牛肉には表面を焙ったたたきが存在し、細かく刻んだタルタルステーキをたたきと呼ぶ事はありません。
野菜類を調理する際は、細かく刻む事に付いてはみじん切りや粗みじんといった表現をしますが、特に粘りを持つ野菜の粘りを引き出すためにはたたくという刻み方の表現が用いられ、粗みじんに近い状態にあるように思えます。
また、野菜に関しては実際に叩く調理法が存在し、たたきを施して組織を破壊し、味が染みやすく、食べやすい状態にした「たたきゴボウ」や「たたきキュウリ」などが調理に用いられ、叩くとは無縁の調理法としては肉や魚などに葛粉をまぶして茹で上げる「葛たたき」といった調理法も存在しています。
カツオのたたきに関しては、表面を焙った後に軽く全体を叩く事で旨味を増したり、薬味やタレをまぶしてから叩く事で味を染ませたりという事が行われるためにたたきと呼ばれるようになったという説もあり、叩く行為と無縁ではなかったようにも思えます。
カツオのたたきの起源については諸説があるのですが、土佐藩の藩主、山内一豊が食中毒防止の観点から名産であったカツオの生食を禁止したため、表面のみを焙る事で焼き魚として食べていたというユニークなものがあり、焙ってみたら旨味が増していて、水分が除かれた事によって味も濃厚になっている事に気付き、後にさらなる工夫として叩きが加わって今日に至っているように思えます。
それにしても和食の中に存在するたたきという調理技法は、日本語や和食の世界観を難しくしてくれ、外国からは理解できないものとなるのではと、どこか心配になってしまいます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.