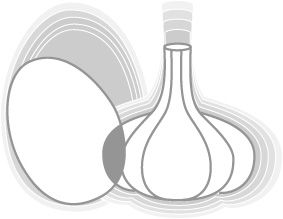PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
風が冷たくなり、肌寒さを感じるようになるとおでんが食べたいと思ってしまいます。いつも自分で作ると根菜類が中心となり、牛スジや練り物が入らない事からできあがりがおでんではなく、根菜類の煮込みとなってしまうため、毎回、これではないと思いながら食べています。
おでんの「お」は丁寧語である事から、「でん」とはと思えてくるのですが、おでんという名前は女房詞であり、宮中の女性たちが「おでんがく」を省略しておでんと呼んだ事が元になっている事から、おでんは田楽から派生したものである事が判ります。
田楽とは本来、豊作を祈願して田の神様を祀るために畦で笛や太鼓を鳴らして舞った「田楽舞」を指すもので、平安時代から伝統的に行われてきた田楽舞では、笛や太鼓、舞いや曲芸を専業に行う田楽法師も見られていました。
田楽法師の舞いの道具の一つに一本の棒に足場を付けた「高足」と呼ばれる一本足の竹馬があり、串にさして焙られる食材の姿がその高足に似ている事から豆腐やこんにゃくを串に刺して焙り、味噌などの調味料を着けた料理を田楽と呼ぶようになっています。
江戸時代に入ると田楽をメニューに加えた飯屋が増えていき、天明の飢饉を境に急速に増えた屋台や辻売りでも田楽を出す店が増えていき、串に刺してある事から手軽に食べられる田楽は庶民の人気の軽食となっていきます。
その後、田楽に使われる食材のバリエーションが増えていき、豆腐やこんにゃくだけでなくナスやサトイモ、魚なども田楽として食べられるようになっていくのですが、本来は串に刺して焙り焼く料理がいつ、どのようにして煮込み料理に変化したのかについては、今日も謎のままとなっています。
田楽が庶民の間に広まり、宮中の女房詞のおでんと呼ばれるようになった事は容易に想像が付くのですが、そこから煮込み田楽が派生して、やがておでんの主役となり、煮込み田楽と焙り田楽を区別するために焙り田楽を本来の名称であった田楽と呼ぶようになったという展開には、いろんな事を考えてしまいます。
あまりにも姿が違う田楽とおでんですが、当初のおでんは今日とは少し違うものであった事が考えられます。今日のおでんの元になったのは明治20年(1887年)に創業した「呑喜」で売り出された「改良おでん」で、鉄鍋を使って汁気を少なくして煮ていたそれまでのおでんを汁気を多くする事で人気となり、特に近くに東京帝国大学があった事から学生たちの間で評判となり、その美味しさを憶えて地元に帰って各地に伝えたという事も考えられます。
串に刺して焼いていたものが鍋で煮る事によって作り置きができるようになり、注文を受けると即座に熱々の状態で出す事ができるため、せっかちな江戸っ子には最適という事ができ、そうしたニーズが煮込み田楽を主流の地位に押し上げ、改良おでんによって完全に田楽とおでんは分かれてしまったと両者の関係について考えています。
おでんの「お」は丁寧語である事から、「でん」とはと思えてくるのですが、おでんという名前は女房詞であり、宮中の女性たちが「おでんがく」を省略しておでんと呼んだ事が元になっている事から、おでんは田楽から派生したものである事が判ります。
田楽とは本来、豊作を祈願して田の神様を祀るために畦で笛や太鼓を鳴らして舞った「田楽舞」を指すもので、平安時代から伝統的に行われてきた田楽舞では、笛や太鼓、舞いや曲芸を専業に行う田楽法師も見られていました。
田楽法師の舞いの道具の一つに一本の棒に足場を付けた「高足」と呼ばれる一本足の竹馬があり、串にさして焙られる食材の姿がその高足に似ている事から豆腐やこんにゃくを串に刺して焙り、味噌などの調味料を着けた料理を田楽と呼ぶようになっています。
江戸時代に入ると田楽をメニューに加えた飯屋が増えていき、天明の飢饉を境に急速に増えた屋台や辻売りでも田楽を出す店が増えていき、串に刺してある事から手軽に食べられる田楽は庶民の人気の軽食となっていきます。
その後、田楽に使われる食材のバリエーションが増えていき、豆腐やこんにゃくだけでなくナスやサトイモ、魚なども田楽として食べられるようになっていくのですが、本来は串に刺して焙り焼く料理がいつ、どのようにして煮込み料理に変化したのかについては、今日も謎のままとなっています。
田楽が庶民の間に広まり、宮中の女房詞のおでんと呼ばれるようになった事は容易に想像が付くのですが、そこから煮込み田楽が派生して、やがておでんの主役となり、煮込み田楽と焙り田楽を区別するために焙り田楽を本来の名称であった田楽と呼ぶようになったという展開には、いろんな事を考えてしまいます。
あまりにも姿が違う田楽とおでんですが、当初のおでんは今日とは少し違うものであった事が考えられます。今日のおでんの元になったのは明治20年(1887年)に創業した「呑喜」で売り出された「改良おでん」で、鉄鍋を使って汁気を少なくして煮ていたそれまでのおでんを汁気を多くする事で人気となり、特に近くに東京帝国大学があった事から学生たちの間で評判となり、その美味しさを憶えて地元に帰って各地に伝えたという事も考えられます。
串に刺して焼いていたものが鍋で煮る事によって作り置きができるようになり、注文を受けると即座に熱々の状態で出す事ができるため、せっかちな江戸っ子には最適という事ができ、そうしたニーズが煮込み田楽を主流の地位に押し上げ、改良おでんによって完全に田楽とおでんは分かれてしまったと両者の関係について考えています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.