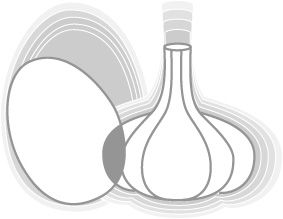PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: カテゴリ未分類
子供の頃、野生動物の様子などを特集した番組があり、とても楽しみに見ていました。未だに世界中の大自然の中を旅して回るという事は現実的にはありえないと思っているので、そうした番組があるとつい見入ってしまいます。
番組の中で野生動物が死に瀕していてもスタッフは決して助けてはいけないというルールが語られていたのですが、大自然に干渉しないという配慮からとは思ってはいても、絶滅の心配がいわれる生物が増えてきている今日では助ける方が正しい事のように思えます。
地球の歴史の中では、さまざまな生物が誕生し、進化を遂げていく中で種として枝分かれしながら絶滅するという事は珍しい事ではないのですが、人の社会が高度に発達して経済活動が盛んになる中、経済活動の結果として特定の種を絶滅させてしまうという事は許されない事といえます。
人によって生物が絶滅させられてしまうパターンは、大きく4つに分ける事ができると思います。一つは人が直接乱獲を行う事によって絶滅させてしまうもので、オーストラリアの飛べない鳥、ドードーが食べ尽くされてしまった事がよく知られています。
先日、絶滅危惧種の第二類に指定されたクロマグロもこのパターンという事ができ、乱獲によって個体数を減らした上、数が減ってしまったために成魚になる前の個体を漁獲する事で数の回復を大きく妨げてしまう事が懸念されていました。
二つ目は環境を汚染したり、環境そのものを人の都合の良い状態に作り変えてしまう事で棲息が困難となり、絶滅してしまうというもので、特定の種の絶滅といわれると真っ先に思い浮かぶ理由となっています。
三つ目はやはり環境に関連した事で、人が特定の種の数を減らしてしまった事でその生物が捕食していたものが異常に繁殖して環境のバランスが崩れたり、捕食者の繁殖に適した環境を作り出してしまったためにエサとなる生物が激減したりといった事があります。
四つ目が最近、最も心配している事で、人の手によってもたらされた外来種との交配によって在来種が本来の種でなくなってしまうという絶滅で、目立たず静かに進行する事から、普段、見掛けていたのに実は絶滅していたという事にもなってしまいます。
先日、雑草のオナモミが絶滅危惧種となっている事を知りました。オナモミはトゲのある実が特徴で、子供の頃、藪の中に入るといつの間にか服にくっついていて、「くっつき虫」とも呼ばれていた馴染み深い雑草です。
絶滅危惧種というと希少な動物にばかり目がいってしまいますが、懐かしいくっつき虫もこれから保護の対象となるのか、とても気になってしまいます。最近目にしていないように思えるので、枯れ始めた草原で探してみようかと思っています。
番組の中で野生動物が死に瀕していてもスタッフは決して助けてはいけないというルールが語られていたのですが、大自然に干渉しないという配慮からとは思ってはいても、絶滅の心配がいわれる生物が増えてきている今日では助ける方が正しい事のように思えます。
地球の歴史の中では、さまざまな生物が誕生し、進化を遂げていく中で種として枝分かれしながら絶滅するという事は珍しい事ではないのですが、人の社会が高度に発達して経済活動が盛んになる中、経済活動の結果として特定の種を絶滅させてしまうという事は許されない事といえます。
人によって生物が絶滅させられてしまうパターンは、大きく4つに分ける事ができると思います。一つは人が直接乱獲を行う事によって絶滅させてしまうもので、オーストラリアの飛べない鳥、ドードーが食べ尽くされてしまった事がよく知られています。
先日、絶滅危惧種の第二類に指定されたクロマグロもこのパターンという事ができ、乱獲によって個体数を減らした上、数が減ってしまったために成魚になる前の個体を漁獲する事で数の回復を大きく妨げてしまう事が懸念されていました。
二つ目は環境を汚染したり、環境そのものを人の都合の良い状態に作り変えてしまう事で棲息が困難となり、絶滅してしまうというもので、特定の種の絶滅といわれると真っ先に思い浮かぶ理由となっています。
三つ目はやはり環境に関連した事で、人が特定の種の数を減らしてしまった事でその生物が捕食していたものが異常に繁殖して環境のバランスが崩れたり、捕食者の繁殖に適した環境を作り出してしまったためにエサとなる生物が激減したりといった事があります。
四つ目が最近、最も心配している事で、人の手によってもたらされた外来種との交配によって在来種が本来の種でなくなってしまうという絶滅で、目立たず静かに進行する事から、普段、見掛けていたのに実は絶滅していたという事にもなってしまいます。
先日、雑草のオナモミが絶滅危惧種となっている事を知りました。オナモミはトゲのある実が特徴で、子供の頃、藪の中に入るといつの間にか服にくっついていて、「くっつき虫」とも呼ばれていた馴染み深い雑草です。
絶滅危惧種というと希少な動物にばかり目がいってしまいますが、懐かしいくっつき虫もこれから保護の対象となるのか、とても気になってしまいます。最近目にしていないように思えるので、枯れ始めた草原で探してみようかと思っています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.