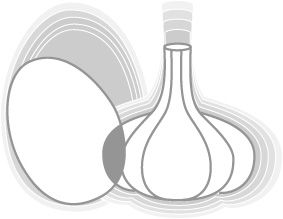PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51663)
カテゴリ: 食事
テクノロジーについていけていない訳ではないのですが、普段からカーナビは使わない人となっています。理由は簡単で、最も知りたいのは目的地の詳細な情報なのに、目的地周辺に到着するとそこで「目的地周辺に着きました」と案内を終了して突き放されてしまう事にあります。
目的地が郊外の大きなショッピングモールなどであれば良いのですが、小規模な事業所や隠れ家的な店舗の場合は、周辺までは一人で行けるので、そこからをしっかりと案内してほしいと思ってしまいます。
そのため初めての場所へ行く際は事前に地図で場所の確認と、ある程度の町並みのイメージをしていくので、迷子になる事もなく目的地に到着できています。また、誰よりも早く匂い気付くことから、一部では「犬の人」とありがたくない呼び名を与えられたりもしています。
一見、関連性がないように思える方向感覚と嗅覚。実は二つの感覚には関連性があり、方向感覚が鋭い人は嗅覚も鋭い傾向にある事が判ってきています。以前からその可能性は示唆されていましたが、最近行われた研究によって裏付けられる事となりました。
カナダ、マギル大学で行われた研究は、参加者57名にVR(バーチャルリアリティ)によって作られた町を散策してもらい、町の様子を憶えてもらった上である場所からある場所へと正確に移動できるかをテストし、さらに40種類の匂い当てテストも行っています。
その結果として匂い当てテストの成績が良いほど散策テストの成績が良い事が判り、方向感覚に優れた人は嗅覚も鋭いという傾向があるという結果が得られています。
両感覚にはあまり関連性がなく、二つのテストは何の関係もないように思えますが、実はどちらも「mOFC(内側眼窩前頭皮質)」と呼ばれる脳の前頭葉の中でも、眼窩の上にある部分を刺激していて、海馬と同じ領域に関わっているとされます。
これまでの研究ではmOFCの左側が厚いほど方向感覚に関わる空間記憶が向上し、右側が厚いほど嗅覚が鋭くなる事が判っていて、両感覚に優れる事が生存に適していた事が進化に影響を与えた事を考える事ができます。
長く狩猟を食糧確保の手段としてきた人類にとって、野生動物や植物の匂いにいち早く気付ける事が食糧確保や危険回避に有効に働く事が考えられ、正確に荒野を移動できる能力と合わせて重要な働きとなっていたと考える事ができます。
mOFCの左側が方向感覚、右側が嗅覚と対応する器官が分かれている事から例外も生じてしまうとは思うのですが、進化の過程を思うと納得できる方向感覚と嗅覚の関係と思えてきます。
目的地が郊外の大きなショッピングモールなどであれば良いのですが、小規模な事業所や隠れ家的な店舗の場合は、周辺までは一人で行けるので、そこからをしっかりと案内してほしいと思ってしまいます。
そのため初めての場所へ行く際は事前に地図で場所の確認と、ある程度の町並みのイメージをしていくので、迷子になる事もなく目的地に到着できています。また、誰よりも早く匂い気付くことから、一部では「犬の人」とありがたくない呼び名を与えられたりもしています。
一見、関連性がないように思える方向感覚と嗅覚。実は二つの感覚には関連性があり、方向感覚が鋭い人は嗅覚も鋭い傾向にある事が判ってきています。以前からその可能性は示唆されていましたが、最近行われた研究によって裏付けられる事となりました。
カナダ、マギル大学で行われた研究は、参加者57名にVR(バーチャルリアリティ)によって作られた町を散策してもらい、町の様子を憶えてもらった上である場所からある場所へと正確に移動できるかをテストし、さらに40種類の匂い当てテストも行っています。
その結果として匂い当てテストの成績が良いほど散策テストの成績が良い事が判り、方向感覚に優れた人は嗅覚も鋭いという傾向があるという結果が得られています。
両感覚にはあまり関連性がなく、二つのテストは何の関係もないように思えますが、実はどちらも「mOFC(内側眼窩前頭皮質)」と呼ばれる脳の前頭葉の中でも、眼窩の上にある部分を刺激していて、海馬と同じ領域に関わっているとされます。
これまでの研究ではmOFCの左側が厚いほど方向感覚に関わる空間記憶が向上し、右側が厚いほど嗅覚が鋭くなる事が判っていて、両感覚に優れる事が生存に適していた事が進化に影響を与えた事を考える事ができます。
長く狩猟を食糧確保の手段としてきた人類にとって、野生動物や植物の匂いにいち早く気付ける事が食糧確保や危険回避に有効に働く事が考えられ、正確に荒野を移動できる能力と合わせて重要な働きとなっていたと考える事ができます。
mOFCの左側が方向感覚、右側が嗅覚と対応する器官が分かれている事から例外も生じてしまうとは思うのですが、進化の過程を思うと納得できる方向感覚と嗅覚の関係と思えてきます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.