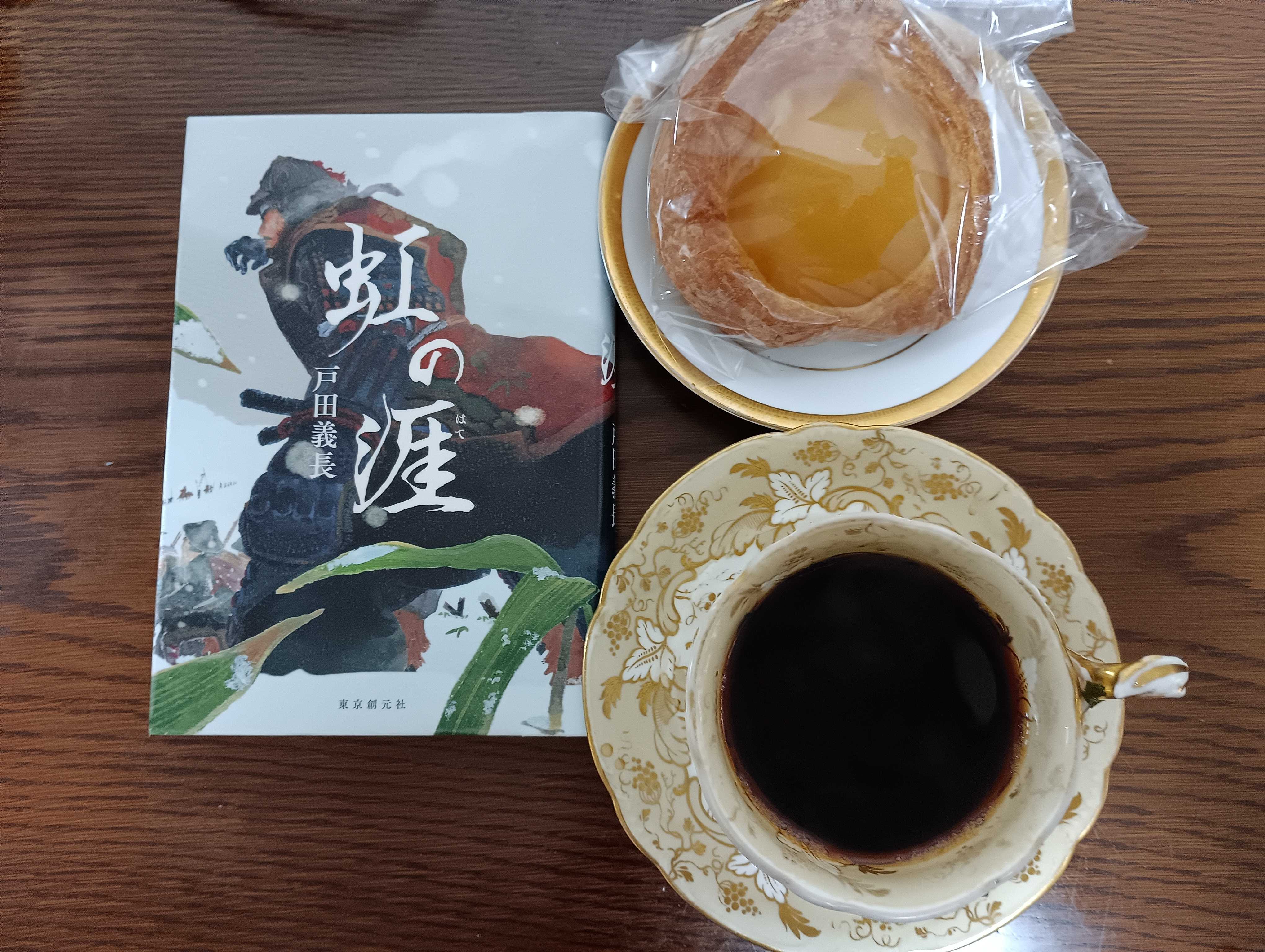2011年12月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
竹下節子『ローマ法王』
竹下節子『ローマ法王』~ちくま新書、1998年~ 西洋史に関する面白そうな著書(『聖母マリア』『「弱い父」ヨセフ』など)を多数執筆されている、竹下節子さんによる『ローマ法王』を紹介します。 本書の構成は次のとおりです。ーーー序章 ローマ法王とはだれか第一章 ローマ法王のホームグラウンド第二章 ローマ法王とヨーロッパの誕生第三章 ローマ法王の盛衰第四章 ヨハネ=パウロ二世と歴史の激動終章 二一世紀のローマ法王あとがき注と参考文献歴代法王表ーーー 本書では、「法王」という呼称で統一されていますが、この記事では、教皇と表記します。 マスコミなどでも「法王」という呼称がしばしば使われているので、日本人にはおそらくなじみがよりなじみのある「法王」で統一されていると思いますが、日本カトリックの正式ホームページでも「教皇」の呼称を使うようにお願いされていること、西洋中世史を勉強するなかでは「教皇」の呼称を用いるのが基本なので、私は教皇と表記していきます。 …さて。 本書は、まず教皇庁の日常を紹介したうえで、通史的に歴代教皇の役割を見た後に、本書執筆当時の教皇だったヨハネ=パウロ二世の意義を詳しく紹介する、という構成になっています。 序章では、教皇庁が、過去のカトリック教会の非を認める「謝罪外交」を展開していること、そしてその背景が指摘されます。 普通の国家なら、ナショナリズムや賠償金の絡みから、謝罪をするにも多くの思惑がつきまといます。 しかし教皇庁には、領土がなく、独身の聖職者から構成されるため腸国家的な性格をもっている(ヴァティカンで生まれて育つ聖職者はいない)、などの特質があり、そして告解・悔い改めがキリスト教のなかで重要な位置を占めているため、謝罪外交がしやすい、というのですね。 ヴァティカン市国は国ではありますが、このように非常に特殊な性質を持っているという面と、キリスト教の教義の面からのこの説明は、とても興味深く、勉強になりました。 第一章では、ヴァティカン市国の構成(軍隊など)、教皇の一日などが紹介されます。なかでも特に、女性職員の境遇について紹介している項が興味深かったです。 第二章・第三章で、通史的に歴代教皇の役割をみていきます。 本当に、いろんな人がいるなぁ、と思います。レオ大教皇やグレゴリウス大教皇など、「大教皇」と呼ばれる教皇や、グレゴリウス七世のように教会改革に尽力した教皇もいれば、「既婚婦人と同衾している時に急死した」ヨハネ12世(私は、この人が、高校生の頃、不倫相手の旦那に殴られて死んだと聞いたように記憶しています)や、教皇になった途端に人がかわり、気に入らない枢機卿を罵倒したウルバヌス6世のような人もいる…。 そして、1978年に教皇に選出されたヨハネ=パウロ二世の意義について、第四章で詳しく論じられます。 彼が、ポーランド出身の教皇だという歴史的意義の大きさが、この章を読んで感じられました。 ロシアの影響が強かったポーランドですが、カトリック教徒が多い国。その自由化のなかで、ヨハネ=パウロ二世も尽力したといいます。 また、ヨハネ=パウロ二世が、とても精力的に諸外国を訪問したということも、勉強になりました。 終章は、感動的な言葉で締めくくられます。 久々の再読。勉強になる一冊でした。※2005年にヨハネ=パウロ二世が亡くなった後、ベネディクト16世が教皇となっています。
2011.12.31
コメント(0)
-
村松剛『教養としてのキリスト教』
村松剛『教養としてのキリスト教』~講談社現代新書、1965年~ フランス文学者、村松剛先生(1929-1994)の『教養としてのキリスト教』を紹介します。 一般的なタイトルですが、「はじめに」でも書かれているように、本書の対象は、時代的には聖書がまとめられた時代に焦点を当てていて、テーマも、イエス・キリストの周辺(背景としてのユダヤ教・旧約聖書、処女懐胎、彼は何を説いたか、弟子たちの活動など…)に限られています。 このように論点がはっきりしているのが良いですね。文体も読みやすかったです。 まずは、本書の構成は次のとおりです。ーーーまえがきはじめに1 イエスは実在したか2 当時の資料はなにを語るか3 『新約聖書』の成り立ち4 『旧約聖書』はどんな意味をもつか5 イエスはだれの子か6 洗礼とは何か7 キリスト教は愛の教えか8 人間キリストの苦悩9 復活の意味するもの10 ローマへの道索引ーーー イエスは実在したのか―。 現代のエルサレムにある聖墳墓教会(イエスの墓の上に建てられた教会)、ゴルゴダの丘(ゴルゴダはアラム語で髑髏を意味するそうです)に触れた後、本書はそう問題提起します。 著者は、この問題に解答するため、同時代の史料を5つ挙げます。それらの史料からは、イエスの実在を語る史料は、(聖書以外には)存在しないといえるそうです。また、イエスがベツヘレムで生まれたということも、否定できる材料があることも指摘され、興味深かったです。 第二章では、特に『死海文書』をめぐる話が面白かったです。話には聞きますが、詳しくは勉強していないので…。イエスが生まれたとされる時代、ユダヤ教の中にもいくつかの宗派がありましたが、『死海文書』を残したグループはクムラン教団といわれるそうです。イエスに洗礼を施した洗礼者ヨハネに関する伝説が死海周辺に残っているそうで、彼とこの教団との間につながりがあったのではないかと指摘されているということも、興味深く読みました。 さて、第三章で『新約聖書』の話をする中で、これが『旧約聖書』と対応するように作られていることが指摘され、第四章では『旧約聖書』の話になります。とても分かりやすいように構成が練られていると感じました。 その後の流れで興味深かった点を挙げると、イエスは「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」と言っている一方で、怒りや呪いの言葉も言っている、ということです。 また、同時代の様々な制約のなかにあってのイエスの苦悩、という話(第8章など)も、面白かったです。 数年ぶりに再読しましたが、上にも書いたようにポイントがしっかりしていて、構成もスムーズで、聖書やイエスに関する概要を理解するには良い1冊だと思います。
2011.12.29
コメント(2)
-
梅田修『世界人名ものがたり』
梅田修『世界人名ものがたり』~講談社現代新書、1999年~ 英語の語源などについて著書を出していらっしゃる、梅田先生の『世界人名ものがたり』を紹介します。 本書の構成は次のとおりです。ーーーはじめに序 名前がもつ豊かな世界 1 名前に込める人々の思い 2 ヨーロッパ人の名前の構成 3 名前のなかのヨーロッパ史1章 救世主が臨在するヨーロッパ人の心 1 男の代名詞ジョン 2 マリアを祝福するヨハネの母エリザベト 3 サタンと戦う大天使ミカエル 4 イスラエル十二支族の祖ヤコブ 5 キリスト受胎の栄光、聖母マリア2章 殉教聖人たちにひそむギリシャ神話の神々や英雄たち 1 運命の美女ヘレネ 2 パリスの添え名アレクサンドロス 3 馬の神ポセイドンにあやかる名前フィリッポス 4 勝利の女神アテナ・ニケと聖ニコラウス 5 豊穣と正義を守る聖ゲオルギオス 6 アフロディテの生まれ変わり、殉教処女マルガリタ3章 東からの光に照らされる覇者ローマ 1 ユピテルの末裔ユリウス・カエサル 2 ロムルスの母アエミュリア 3 ローマの軍神マルス ◆ ユーノーと聖ルチア ◆ 女神ディアナと処女王エリザベス ◆ ありし日のローマの光、ローレンスとローラ4章 キリスト教を受け入れて再生したゲルマン精神 1 ゲルマン人の信仰と名前 2 ゲルマン人の覇者、フランクのクロヴィス 3 誇り高き自由農民の祖カール 4 ザクセンとアングロ・サクソンの聖王たち 5 ノルマンの英雄たち 6 西方十字軍のカトリック王たち5章 現代に生きるケルトのロマン 1 よそ者として奴隷にされたケルト人 2 ドルイド信仰が生んだアイルランドの神々 3 タラの王族とアイルランド・サガの英雄たち 4 ケルト再興の願いアーサー王 5 スコットランド王家の祖たち6章 北欧とビザンティンを繋ぐロシアおわりに主な参考文献ーーー いろんな人名の語源や、人名(や国民)にまつわるエピソードを多数紹介する、というかっこうの本です。 なので、起承転結があるという感じではないため、読み物として読むと、若干きついものがあるかもしれません。 むしろ、新書で読めるちょっとした人名語源事典、くらいの感じで読むと良いかもしれません。 ここでは、興味深かった話題として、大天使聖ミカエルについての節から、いくつかメモしておきます。 大天使のなかでも有名なミカエル、ガブリエル、ウリエル、ラファエルですが、彼らの名前の語源(意味)は次のとおりです(59頁)。 ミカエル…誰が神のごとくあるか ガブリエル…神の力 ウリエル…神の炎 ラファエル…神は癒したまえり 4人の大天使に共通するエル(el)は、神を意味するというのですね(54-55頁) さて、ミカエルは、フランス語読みではミシェル、英語読みではマイケルです。 アイルランドはカトリック教徒が多く、マイケルという名前が、アイルランドを象徴する名前の一つになったとか。 19世紀末頃、アイルランドではじゃがいも飢饉が起こり、アメリカに移民する人も多かったそうですが、その中で、マイケルの愛称であるミッキーという言葉は、蔑称的にアイルランド人を示す言葉だったそうです(20世紀半ばまで)。 アメリカに移民した曾祖父をもつウォルト・ディズニーが作ったキャラクター、ミッキー・マウスのおかげで、ミッキーの名前をアイルランド人の蔑称と考える人は少なくなった、と著者は指摘しています(61-62頁)。 有名な名前にある意外な背景に、考えさせられるものがありました。 中世の人名に関する研究を進めていらっしゃる宮松浩憲先生も、人名の歴史を研究するなかで、差別的表現に直面する点を指摘しています(「セーヌ川を飲み干す」)。 しかし、そこから目をそらしてはいけないわけで、それもまた歴史的にあったことであれば、自らを省みる材料の一つとすべきだと思います。 また、そうしたテーマを抜きにしても、人名という研究テーマはとても興味深いと思います。 たとえば、何度も紹介しているミシェル・パストゥローという歴史家も、アーサー王物語の人名が実際に名付けられた事例の分析を行っているように、ある時代の心性を探る興味深い材料となりえるのですね。(こんにちの日本でも、いろんな名前の流行り廃りがあるように…)。 …と。ちょっと脱線した感はありますが、いろんな人名の語源を知ることのできる、興味深いネタが満載の一冊でした。
2011.12.24
コメント(0)
-
橋爪大三郎『はじめての構造主義』
橋爪大三郎『はじめての構造主義』~講談社現代新書、1988年~ アナール学派に関する著作(たとえば、ピーター・バーク『フランス歴史学革命』)などなど、史学史や歴史学の方法論にふれていると、避けて通れない人物の一人が、レヴィ=ストロースです。そしてその方法論である、「構造主義」。 なんとなく聞きかじってきていますが、あらためてそれがどんな思想(方法論)なのか、といわれると、十分な理解はできていません。 そこで、易しく軽快な語り口でありながら、その本質を分かりやすく解説する本書を読んでみました。 あれこれつめこむのではなく、自分の主張のポイントを絞り、そのポイントについては詳しく記述するという、はっきりした構成が嬉しい一冊です。 本書の構成は次のとおりです。ーーーはしがき第一章 「構造主義」とはなにか第二章 レヴィ=ストロース:構造主義の旗揚げ第三章 構造主義のルーツ第四章 構造主義に関わる人びと:ブックガイド風に第五章 結びーーー※以下の感想は、構造主義とは何か、ということをまとめてはいません。 あくまで、興味深く読んだ点や、感じたことのメモです。 第一章では、構造主義のインパクトと、世間が構造主義に抱くイメージが中心に論じられます。 それまで主流だったマルクス主義的な歴史観(資本主義→共産主義へ)、そしてその歴史に個人が参加できると説いたサルトルに対して、レヴィ=ストロースの考えは、そうした歴史観はヨーロッパ人の錯覚に過ぎない、と主張するものでした。 西欧的な意味での「主体」を否定することにつながる構造主義のインパクトは大きいものでした。同時に、「構造主義は反人間主義だ」というイメージも生まれます。 それでは、構造主義とはどういう考え方なのか? それは、本書の二本柱である第二章と第三章で、特にレヴィ=ストロースの思想について深く論じられることになります。 第二章は、レヴィ=ストロースの経歴を見ながら、その知的背景を探り、また彼の具体的な研究方法を見ていきます。ここでは、ごく簡単に、重点や印象に残った点についてメモをしておきます。 1908年、ベルギーに生まれたクロード・レヴィ=ストロースは、第二次世界大戦のさなか、アメリカに亡命します。亡命先で出会った言語学者、ローマン・ヤーコブソンに出会ったことは、レヴィ=ストロースの研究にとって重要な意義をもちました。というのも、ヤーコブソンから紹介された著名な言語学者ソシュールの研究方法が、後の「構造主義」の方法につながることになるからです。 ここでは、有名ですが実際にはよく知らないソシュールの研究がどういったものなのか、要領よくまとめられていて、勉強になりました。 そして、「贈与論」という論文を発表したモースも、レヴィ=ストロースの研究に大きな影響を与えます。 二人の著名人の研究方法の影響を受けつつ、彼は人類学上の難問のひとつであった、インセスト(近親.相姦)・タブーに関わる問題に、答えを出したのでした。 * 人類学研究にくわえ、レヴィ=ストロースは神話の研究でも新しい方法を生み出します。 それは、物語の筋を追うだけでなく、その中にいくつかのテーマが隠されていて、それらのテーマが少しずつ形を変えて現れているのだ、という分析方法のようです。 著者は、あまり良い例ではないとしながらも、オイディプスの物語についてのレヴィ=ストロースによる分析を挙げています。 人類学の研究については「なるほど!」とよく分かりましたが、こちらはなかなか難しかったです。言わんとすることは分からないでもないのですが、いくらでも恣意的な解釈ができてしまうのでは、と素人ながら考えてしまいました。 第三章は、レヴィ=ストロースの構造主義のルーツとして、数学を見ていきます。 繰り返しになりますが、これが本書の柱の一つであり、またユニークな点でもあるのだろうと思います。構造主義についてほとんど勉強していない私が、本書のみ読んで「ユニーク」というのはおかしいですが、しかし史学史関係の本で何度かレヴィ=ストロースの名は目にしているものの、数学との関連につっこんでいる叙述は読んだことがないような気がします。 この章は、まず、古代ギリシャから現代にいたるまでの、主要な公理・法則について見ていきます。単純に、それだけでも勉強になりました。 レヴィ=ストロースの方法との類似性を論じる部分も、なるほど、と思いつつ、なかなか十分には理解できたとは言い難いです。 第四章は、その標題どおり、構造主義やポスト構造主義と言われる有名な人々の紹介や、有名な著作の紹介となっています。 この中に出てくる人々は、私が何冊か読んでいる史学史関係の本にも登場していて、あらためて勉強になりました。 私が勉強してきている、いわゆるアナール学派の歴史家たちに、レヴィ=ストロースなどの構造主義の人々が影響を与えている、ということはいろいろと読んできました。 今回あらためて、構造主義とはどんな考え方なのか、その背景も含めて勉強できて良かったです。 楽しく、興味深く読めた1冊です。 最後に、印象的で、共感できた部分を引用しておきます。「日本のモダニズム(近代思想)は主として明治期に、政府(国家権力)が外国から導入したものである。モダニズムはもともと、権力から自立をはかるべく、市民階級が自分たちの手でうみだしたもののはずだから、このこと自体、グロテスクなことだ」(226頁)
2011.12.23
コメント(0)
-

横溝正史『青髪鬼』
横溝正史『青髪鬼』~角川文庫、1981年~ 横溝さんのジュヴナイル作品です。表題作の他に、3編の短編が収録された作品集です。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。ーーー「青髪鬼」 三人の死亡広告が新聞に載せられた。しかし名前が載せられた三人は、全員生きていた―。 腕利きの記者・三津木俊助を訪ねてきた客の対応をした、新日報社の探偵小僧こと御子柴進は、三津木に渡してほしいと封筒を置いて、慌てて帰って行ったその客を尾行した。男を追う御子柴は、もう一人の男がその男を尾行していることに気付く。そして男は、公園で殺された。現場にいた男は、恐ろしい形相をして、その髪の色は真っ青だった…。 さらに、事件は謎の怪盗、白蝋仮面も現れる。 はたして青髪鬼の正体は…?「廃屋の少女」 夜中に忍び込んできた泥棒に、千晶は事情を聞き、妹のためと知ると、お金と人形を手渡した。泥棒は感謝して帰って行ったが、その後…。 叔父たちとともに出かけた先で千晶は軽気球に乗るが、その気球の綱が何者かに断ち切られてしまった。そして千晶は、落下した先で悪者たちに捕まり、廃屋に監禁されてしまう。ところが、千晶にある人物が救いの手を差し伸べて…。「バラの呪い」 S学校3年の鏡子は、テニスの名選手である。彼女とダブルスで組んでいた妙子は、この春に亡くなってしまった。鏡子は今年の試合では、シングルで戦わなければならない…。 そんな中、学校の寄宿舎で、幽霊が出るという噂が立ち始める。 そしてある日鏡子に送られた花束の中には、脅迫めいた言葉の書かれたカードが入れられていた。「真夜中の口笛」 病弱な益美は、叔父で昆虫博士の片桐と、温泉旅館に逗留していた。 ある夜、益美は口笛の音を聞く。彼女は、以前に姉を亡くしていたが、姉は死ぬ間際に、口笛の音が聞こえ、悪魔の手が現れたと話していた。そのため益美は、真夜中の口笛を極度に恐れていたのだった。 温泉旅館で知り合った青年の雄策はその話を聞いて、安心するように彼女を諭すが…。ーーー 個人的には表題作よりも、短いながらもきれいにまとまっている短編3作の方を楽しく読みました。特に「バラの呪い」は、幽霊の噂や脅迫状など、スリリングな展開、そして鏡子さんが知っている「秘密」が気になり、楽しく読みました。 表題作も、単なる怪人との戦いには終わっていないのが良いです。 楽しく読める一冊でした。※表紙画像は横溝正史エンサイクロペディア様からいただきました。
2011.12.22
コメント(0)
-
岡田温司『マグダラのマリア―エロスとアガペーの聖女―』
岡田温司『マグダラのマリア―エロスとアガペーの聖女―』~中公新書、2005年~ 今回は、美術史家の岡田温司先生による、『マグダラのマリア』を紹介します。 本書の構成は次のとおりです。ーーーはじめに―両義的なる存在第1章 揺らぐアイデンティティ 1 福音書のなかのマグダラのマリア 2 外典のなかのマグダラのマリア 3 「罪深い女」=マルタの姉妹ベタニアのマリア=マグダラのマリア 4 隠修士としてのマグダラ 5 『黄金伝説』のなかのマグダラ第2章 マグダラに倣って(イミタティオ・マグダレナエ) 1 フランチェスコ修道会 2 ドミニコ修道会 3 信者会(コンフラッテルニタ)とマグダラ 4 聖女たちの模範としてのマグダラ 5 サヴォナローラとマグダラ第3章 娼婦たちのアイドル 1 14世紀のナポリ 2 15世紀のフィレンツェ 3 16世紀のローマ 4 17世紀のローマ第4章 髑髏をまとったヴィーナス 1 「この上なく美しいが、またできるだけ涙にくれている」 2 「何と美しいことか、見なければ良かったほどだ」 3 「たとえ深く傷ついた人でも、なおも美しいということはありうるだろう」 4 エヴァと聖母マリアのあいだ 5 ジョヴァンニ・バッティスタ・マリーノの詩おわりに―生き続けるマグダラ参考文献ーーー 特に興味深く呼んだのは第1章です。新約聖書(福音書)の中に、マグダラのマリアは名指しで何度か登場しますが、こんにちの一般的なイメージである「悔悛した娼婦」という記述は、実は一切ありません。同時に、イエスの足を髪でぬぐうマリアと、いろいろ世話しようとしたマルタの対比で有名なマリア(ベタニアのマリア)がマグダラのマリアと同一人物という記述もまた、ないのです。「罪深い女」(娼婦)とマグダラのマリアの同一視に大きく貢献したのが、6世紀末の、グレゴリウス大教皇という指摘が、とても面白かったです。 また同時に、4つの福音書に現れるマグダラのマリアですが、福音記者によってそのイメージが違っているという指摘も面白かったです。 第2章では、男性の修道士たちがマグダラのマリアを模範と仰いでいる記述が紹介されており、興味深かったです。また、地域の互助会のような役割をもった信者会についても、興味深く読みました。 第3章では、ある意味では娼婦と修道女が同様の社会的境遇にあったことが指摘されます。また、娼婦もいつまでもその職業でいるわけにもいかず、最終的には修道女になる道を選んだ、とも。 娼婦の救済のために尽力した修道女たちにも触れられており、勉強になりました。 第4章は、主にバロック期の絵画にみられるマグダラのマリアの特徴を分析します。 美術史の専門家による著書ですので、図版も多数あって、絵を眺めるだけでも楽しいですが、同時代の文学作品や聖職者・修道士による著作などからの引用・分析によって絵画の歴史的評価や位置づけもなされており、知的好奇心も大いに満たしてくれる一冊です。 中公新書には他にも岡田先生の著作があるので、それらもいずれ読んでみたいと思います。
2011.12.07
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1