2025年11月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

ハリイ・ケメルマン『九マイルは遠すぎる』
ハリイ・ケメルマン(永井敦/深町眞理子訳)『九マイルは遠すぎる』~ハヤカワ文庫、1976年~(Harry Kemelmann, The Nine Mile Walk, 1967) 表題作があまりにも有名な、ハリイ・ケメリマン(1908-1996)による短編集です。 法学部教授をやめて郡検事になる「わたし」の一人称で物語は進みます。 探偵役は、「わたし」の少し年上の、スノードン基金名誉英語・英文学教授のニコラス・ウェルト(愛称はニッキイ)です。 それでは、簡単にそれぞれの内容紹介と感想を。―――「九マイルは遠すぎる」「9マイルもの道を歩くのは容易ではない、ましてや雨の中となるとなおさらだ」わずかな文章から、一連の論理的推論を引き出すと言ったニッキイに、「わたし」が言ったその言葉から、ニッキイが導き出す思いがけない事実とは。「わらの男」雑誌からの切り抜きで作られた脅迫状に、指紋がはっきりと残されていた理由とは。「10時の学者」10時開催の学位論文口頭試験に現れなかった大学院生が、ホテル(下宿)で殺されていた。凶器をめぐる奇妙な謎とは。「エンド・プレイ」チェスの途中、来訪者に殺されたと思われた被害者について、「わたし」と対立する刑事は自殺説を唱えていた。証拠があるという刑事に、ニッキイが示す真相は。「時計を二つ持つ男」常に時間を意識し、時計を二つ持っていた男が、同居するおいが呪いのような言葉を吐いた夜に死亡した。後日、そのおいも死亡。呪いのような事件の真相とは。「おしゃべり湯沸かし」大規模な学会に多くの学者が集まり、ニッキイの住む部屋の向かいにも2人の客が宿泊していた。ある日、その部屋から聞こえた湯沸かしの音から、ニッキイが推理してみせたこととは…。「ありふれた事件」雪が降り続いていた頃、雪の中に死体が埋められていた。被害者を恨む男もはっきりしていたが、その状況から、ニッキイは警察と異なる解釈を提示し…。「梯子の上の男」出版した著書がベストセラーとなった教授が、事故のような状況で死を遂げた。さらに、彼と共同研究していた男と「わたし」たちが一緒にいたとき、彼の知人が作業中に梯子から落下死する。被害者の死の真相とは。――― なにより、ずっと気になっていた「九マイルは遠すぎる」が読めたのが良かったです。あらためて、The Nine Mile Walkを「九マイルは遠すぎる」とした邦題の素敵さを感じました。 表題作以外で印象的だった作品として、「わらの男」は、正体を知られたくないはずの脅迫状作成者がなぜ指紋の残りやすい紙質の雑誌で、指紋だらけの脅迫状を作ったのかという魅力的な謎ですし、「おしゃべり湯沸かし」は、隣室から聞こえる湯沸かしの音を手がかりに裏にある事件を推理するという、こちらも魅力的な展開でした。 冒頭の表題作から好みの方向性で、収録作のどれも楽しく読みました。(2025.08.17読了) ・海外の作家一覧へ
2025.11.03
コメント(0)
-
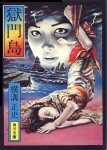
横溝正史『獄門島』
横溝正史『獄門島』~角川文庫、1971年~ 金田一耕助シリーズの長編です。 まずは、簡単に内容紹介を。(内容紹介は2007.07.12の記事から再録)――― 昭和21年(1946年)9月。「俺が死んだら、三人の妹たちが殺される。獄門島へ行ってくれ」―戦友の鬼頭千万太の言葉を受け、彼が託した紹介状を持って、金田一耕助は瀬戸内海に浮かぶ小島、獄門島を訪れた。 漁師の多い島のこと、網元の鬼頭家が大きな力を持っていた。また別格の人々が、千万太が紹介状をあてた和尚、村長、医師の三人。耕助は、和尚のもとにしばらくとどまることになる。 鬼頭家は本鬼頭と分鬼頭に分かれていた。絶大な権力を握っていた本鬼頭の前当主は亡くなり、息子は錯乱して家の座敷牢に入れられていることから、孫の千万太、そのいとこの一に期待がかけられていたのだが、その千万太が死んだ。跡取りをめぐる、血なまぐさい事件―千万太の最後の言葉が実現される嫌な予感を抱く耕助だが、ついに事件が起こる。 鬼頭家の、千万太の三人の妹―花子、雪枝、月代のうち、花子が、千万太の通夜の夜に行方不明になる。彼女の遺体は、寺の木の枝から、逆さに吊されていた。 さらに、事件は続く。花子の次の犠牲者、雪枝の遺体は、釣り鐘の中に閉じこめられていた。恐ろしい事件が続く中、本鬼頭をほとんど一人で支えている早苗も、不審な行動をとりはじめる。――― 何度目かの再読で、もちろんあの言葉の意味も分かった上で読み返しましたが、何度読んでも面白いです。 本題と関係ないところばかりになりますが、たとえば、金田一さんが屏風の俳句を読もうとするシーン。「ぼんやりとしていると、腹の底からいらいらしたものがこみあげてきそうなので、耕助は臍下丹田に力をおさめて、一意専心、これを読むことに努力することにきめる」。俳句を読む覚悟の描写のこの面白さ、抜群です。そして、がんばっているときに駐在所の清水さんに声を掛けられて現実の世界へ呼び戻されると、「其角などくそくらえであった」。大好きです。 床屋の親方と金田一さんの軽妙なトークも面白いです。 そして、物語としては、釣鐘に被害者が押し込められた時間の謎、何かを知っていながら不審な行動をする早苗さんの意図など、魅力的な謎が満載です。 あらためて、金田一耕助シリーズ、そして横溝作品の面白さ、魅力をふんだんに味わえる素敵な読書体験でした。(2025.08.16再読)・や・ら・わ行の作家一覧へ※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディア様からいただきました。
2025.11.02
コメント(0)
-
R・W・サザン『歴史叙述のヨーロッパ的伝統』
R・W・サザン(大江善男・佐藤伊久男・平田隆一・渡部治雄訳)『歴史叙述のヨーロッパ的伝統』~創文社、1977年~(R. W. Southern, “Aspects of the European Tradition of Historical Writing”, Transactions of the Royal Historical Society, 5th Series, vols. 20-23, 1970-1973) リチャード・ウィリアム・サザーン(Richard William Southern, 1912–2001)は、イングランド北部ニューカースル生まれ。『中世の形成』『西欧中世の社会と教会』などの邦訳書があります。 本書は、サザーンが1969年から4年間、王立歴史学会の会長をつとめたとき、各年度に講演した内容をまとめたものです。 本書の構成は次のとおりです。―――凡例第1章 アインハルトからモンマスのジェフリに至る古典古代の伝統第2章 聖ヴィクトルのフーゴーと歴史的発展の理念第3章 預言としての歴史第4章 過去の意味原注訳者あとがき索引――― 第1章で、著者は、「歴史家の第一の任務は芸術作品を作成することだと言明」し、さらに「歴史家は情緒的・知的要求を満足させることを目指さなければならない」(6頁)という自身の立場を表明します。もちろん、「利用しうるデータの制約内」(同)でのことと述べた上で、ではありますが。ここから、先日読んだ兼岩正夫『西洋中世の歴史家』の中で、イギリスの歴史叙述として、「トレヴェリアンによれば歴史は科学であるとともに芸術である」(2頁)と指摘されているのを想起しながら読みました。 なお、同章では、『カール大帝伝』を著したアインハルトについて、彼が材料を改作しているとして近代の学者が非難する中、著者は、「帝国の偉大さのイメージを呼び起こすこと」(23頁)がアインハルトの意図だったとして、その意図の中でその作品を判定することが重要だという立場に立っていることが興味深いです。 第2章は、サン=ヴィクトルのフーゴーの著述に見られる(歴史の)「発展」の理念を丹念に見た後、特にその歴史観を受け継いだ人物としてハーヴェルベルグのアンセルムスとフライジングのオットーに着目し、それぞれの著作の特徴を論じます。 第3章は「預言」というキーワードで歴史叙述を見ていきます。預言の典拠として、大きく(1)聖書、(2)異教的預言(例としてシビュラとマーリン)、(3)キリスト教的預言=幻視、(4)宇宙的預言=占星、の4つを概観した後、これらを預言を研究した人物としてロジャー・ベイコン、フィオーレのヨアキム、そしてニュートンを取り上げます。 第4章はイギリスにおける歴史研究の意味を考えるにあたり、注目すべき時代としてノルマン・コンクェスト後の歴史叙述と、16-17世紀の歴史叙述の2つの時代を取り上げます。前者に関しては、複数の修道院で、「征服」以前から自分たちは偉大であったこと(と征服による不当な侵略)を明らかにするという実際的な動機、後者に関しては、様々な公職を歴任したウィリアム・ラムバードに着目して、彼が自身のついた職に関する歴史を精力的に調査・公刊したことを示した上で、彼らは「自分たちが[過去から]継承したものは一体何であったかを発見するため」に記録文書を探索した、と論じます。 タイトルから想像されるような、ヨーロッパにおける歴史叙述を通史的に論じるというよりは、歴史叙述の様々な側面に着目し、その観点ごとに意味を論じる試みであるように思われます。 解説では、サザーンの略歴と主著、そして本書成立の契機などが紹介されていて、こちらも興味深いです。(2025.08.15読了) ・西洋史関連(邦訳書)一覧へ
2025.11.01
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『無限ガチャ』(17) /最新刊まで
- (2025-11-14 10:30:04)
-







