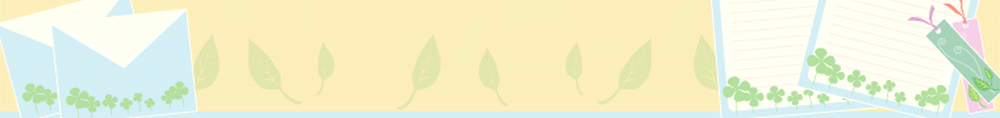カテゴリ: 障がい福祉

[RSL] アルトタスカル 医療ケア 肌着 前開き 全開き プランサー ベビー キッズ 子供服 ベビー服 バリアフリー ロンパース 綿100% 医療用 男の子 女の子 ユニバーサルデザイン 90 100 110 120 130 140 150 160cm

[RSL] アルトタスカル 医療ケア パンツ ズボン 裏シャギー 裏起毛 バリアフリー キッズ 子供服 股上深め 男の子 女の子 医療用 ユニバーサルデザイン あったか 保温 ボトムス 110 120 130 140 150 160cm
 にほんブログ村
にほんブログ村

にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

[RSL] アルトタスカル 医療ケア 肌着 前開き 全開き プランサー ベビー キッズ 子供服 ベビー服 バリアフリー ロンパース 綿100% 医療用 男の子 女の子 ユニバーサルデザイン 90 100 110 120 130 140 150 160cm

[RSL] アルトタスカル 医療ケア パンツ ズボン 裏シャギー 裏起毛 バリアフリー キッズ 子供服 股上深め 男の子 女の子 医療用 ユニバーサルデザイン あったか 保温 ボトムス 110 120 130 140 150 160cm
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いについて丁寧に解説します
「ユニバーサルデザイン」と「バリアフリー」という言葉は、どちらも人にやさしい設計を目指す考え方として広く知られておりますが、その意味や対象とする範囲には明確な違いがございます。特に、ユニバーサルデザインは、誰にとっても使いやすく、わかりやすいことを重視しているのに対し、バリアフリーは障がいのある方や高齢者など、特定の困難を抱えている方々への配慮を中心に据えた考え方でございます。そのため、両者はしばしば混同されがちですが、それぞれの特徴を正しく理解することで、より良い環境づくりに役立てることができます。
ユニバーサルデザインとバリアフリーの基本的な違い
ユニバーサルデザインとは、すべての人が人生のどこかの段階で、何らかの不便さや困難に直面する可能性があるという前提に立ち、誰もが快適に利用できるように設計されたデザインのことを指します。年齢、性別、障がいの有無、人種、文化的背景などに関係なく、あらゆる人が使いやすく、魅力を感じられることを目指している点が特徴です。
一方で、バリアフリーという言葉は、もともと建築分野で使われていた用語であり、段差や障害物など、物理的な「バリア(障壁)」を取り除くことを目的としております。主に、視覚や聴覚、身体的な障がいを持つ方や高齢者など、日常生活において継続的な困難を抱えている方々を対象とし、支障となる要素を排除することで、生活の質を向上させることを目指しています。
対象となる人の違いについて
ユニバーサルデザインでは、特定の人を対象とするのではなく、社会全体のすべての人を対象としております。障がいの有無にかかわらず、年齢や性別、文化的背景などで区別することなく、誰もが平等に使える設計を理想としております。たとえば、子どもから高齢者まで、また一時的にけがをしている方や妊娠中の方など、さまざまな状況にある方々が快適に利用できるように工夫されております。
それに対して、バリアフリーは、障がい者や高齢者など、特定の困難を抱えている方々を主な対象としております。そのため、設計の目的は「不便さの解消」に重点が置かれており、健常者の利便性についてはあまり考慮されない場合もございます。
ユニバーサルデザインでは、障がいを特別なものとして捉えるのではなく、誰もが人生の中で一時的または継続的に不自由さを感じる可能性があるという視点から設計を行っております。たとえば、けがや病気による一時的な不具合、災害や停電などによる環境的な制約、または子ども時代や高齢期における身体的な制限なども「障がい」として捉えることで、より広い視野での配慮が可能になります。
一方で、バリアフリーにおいては、障がいとは「目が見えない」「歩けない」など、日常生活に明確な支障をきたす特定の状態を指しております。そのため、設計の対象はそうした状態にある方々に限定されることが多く、健常者にとっての使いやすさや快適さは、あまり重視されない傾向がございます。
製品の魅力や市場性に対する考え方の違い
ユニバーサルデザインは、製品の魅力や市場性を非常に重視しております。すべての人にとって使いやすく、わかりやすい製品が広く普及するためには、多くの人が「使ってみたい」「持っていたい」と感じる魅力が必要です。また、持続的に製品を提供し続けるためには、経済的なコストや生産効率も重要な要素となります。
それに対して、バリアフリーの設計では、障がいの除去を最優先するため、製品の見た目やデザイン性、市場での競争力などは二の次になることがございます。その結果、ビジュアル面でのバリエーションが少なかったり、製作コストが高くて大量生産が難しいといった課題が生じることもあります。
実際のデザイン例から見る違い
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いを、具体的な設計例から見てまいりましょう。
たとえば、階段に昇降リフトを設置して、車いす利用者が階段を使えるようにするのは、バリアフリーの考え方に基づいた対応です。この方法では、車いす利用者は階段を昇り降りできるようになりますが、他の歩行が困難な方々にとってはあまり利便性がありません。
一方で、ユニバーサルデザインでは、エレベーターの設置を検討いたします。エレベーターであれば、車いす利用者だけでなく、高齢者、妊婦、病気の方、大きな荷物を持っている方など、誰でも快適に利用することができます。
また、車いす専用のスペースを設けたバリアフリートイレに対して、ベビーベッドやオストメイト対応の洗浄機器、子ども用便器などを併設した多目的トイレは、ユニバーサルデザインの一例でございます。誰でも使えるように設計されているため、より多くの方にとって便利な空間となっております。
この続きとして、「共通する目的と精神」以降のセクションも同様に「ですます調」に整えてお届けできます。ご希望でしたら、続きをすぐにご用意いたしますね!
共通する目的と精神
ユニバーサルデザインとバリアフリーには、対象とする人の範囲や障がいの捉え方、市場性などに違いがありますが、どちらも「すべての人が快適に暮らせる社会」を目指しているという点では共通しております。
そのため、環境整備や製品の開発だけでなく、普及教育も非常に重要です。互いを思いやる心、リスペクトの精神、助け合いの気持ちがあってこそ、設計されたものが本当に使いやすく、魅力的なものになります。ハード面の工夫だけでは限界があり、利用する人々の心のやさしさがあって初めて、真の意味でのユニバーサルデザインやバリアフリーが実現されるといえるでしょう。
ユニバーサルデザインはバリアフリーを含む広い概念です
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いを理解することで、誰もが使いやすい環境や製品について、より深く考えることができます。両者は、思いやりや福祉の精神という点では共通しておりますが、バリアフリーが特定の障がいに焦点を当てているのに対し、ユニバーサルデザインは障がいの有無にかかわらず、すべての人を対象としている点が大きな違いです。
ユニバーサルデザインの中には、当然ながらバリアフリーの対象である高齢者や障がい者も含まれております。そのため、ユニバーサルデザインはバリアフリーを内包し、より包括的で発展的な考え方であるといえるでしょう。
教育のユニバーサルデザインとは何でしょうか?
教育のユニバーサルデザインとは、「より多く」の子どもたちにとって、わかりやすく、学びやすく配慮された教育のデザインを指します。
障害者の権利に関する条約第2条では、ユニバーサルデザインを「調整または特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画およびサービスの設計」と定義しております。
このような考え方を教育に反映したものが、教育のユニバーサルデザインです。これを具体化するためには、人的環境、教室環境、授業の3つのユニバーサルデザイン化を柱として、バランスよく取り組むことが効果的です。
小中一貫教育・小中連携教育とは何でしょうか?
小中連携教育とは、情報交換や交流を通じて小学校から中学校への円滑な接続を目指す教育のことです。一方、小中一貫教育は、小・中学校が目指す子ども像を共有し、9年間を通じた系統的な教育課程を編成することを目的としています。
小中連携教育:情報交換や交流を通じて、小学校教育から中学校教育へのスムーズな接続を図る教育です。
小中一貫教育:小・中学校が共通の教育目標を持ち、9年間を通じて系統的な教育を行う取り組みです。
ユニバーサルデザインの視点を取り入れる意義とは?
ユニバーサルデザインの視点を教育に取り入れることで、通常学級の包括性を高め、多様な学びの場を確保することができます。また、9年間の切れ目のない支援を実現することにもつながります。
文部科学省が平成24年に行った調査によると、通常学級において教育的支援を必要とする児童・生徒の割合は6.5%であり、そのうち約4割が何の支援も受けていないことが明らかになりました。発達障がいのある児童・生徒が適切な支援を受けられない場合、理解不足による過度な叱責やいじめなど、否定的な対応を受けることで情緒の不安定や反抗的な行動、深刻な不適応状態を招くことがあります。これを「二次障がい」と呼びます。
ユニバーサルデザインの視点から小中一貫教育(小中連携)の取り組みを見直すことで、こうした問題を緩和し、すべての子どもたちにとって安心して学べる環境を整えることが可能になります。
二次障がいによる悪循環への対応
発達障がいのある児童・生徒が、周囲から否定的な対応を受けると、自己評価が低下し、それによってさらに否定的な対応を受ける機会が増えるという悪循環に陥ることがあります。このような悪循環を断ち切るためには、日頃から児童・生徒の肯定的な面に注目して関わることが大切です。また、状況に応じて、以下のような対応を行うことが効果的です。
方針:問題でない部分に注目する
方法:望ましい行動をしているときに、ほめたり励ましたりします。 「○○しているね」など、言葉にして伝えることが重要です。
支援の担い手:関係者全員が協力して対応します。
方針:情緒の安定を図る
方法:①カウンセリングやプレイセラピーを活用する ②話を丁寧に聴く ③子どもの感情を推測して言葉にして伝える
支援の担い手:①はカウンセラー、②③は教師や保護者が担います。
方針:学級集団全体に配慮する
方法:日常的に、小さな望ましい行動に注目した働きかけを、学級全体に行います。
支援の担い手:主に教師が対応します。
方針:学年や学校全体で取り組む
方法:子どもの状態や対応方針を共有し、役割分担に沿って対応します。
支援の担い手:学校関係者が連携して対応します。
人的環境のユニバーサルデザイン化とは?
人的環境のユニバーサルデザイン化とは、児童・生徒の心に働きかけて、クラスの雰囲気をやわらかくし、児童・生徒が互いに学び合える環境や関係づくりを進めることです。
クラスの雰囲気が穏やかで、児童・生徒同士が支え合える環境は、教育的ニーズを抱える児童・生徒にとって、最大の支援となります。これを実現するためには、日頃の指導に加えて、ソーシャルスキルトレーニングや構成的グループエンカウンター、対人関係ゲームなどを活用した働きかけも有効です。
育成したいソーシャルスキルの例
あいさつに関するスキル
自己認知スキル
相互理解のための言葉・表現スキル
気持ちの認知スキル(相互理解やセルフコントロールのため)
セルフマネジメントスキル
コミュニケーションスキル
小中一貫教育(小中連携)の取組において、人的環境のユニバーサルデザイン化を図るには?
小学生と中学生が一緒に、構成的グループエンカウンターのエクササイズや対人関係ゲームを行うことも有効な方法です。
小中一貫教育(小中連携)では、校種を越えた異学年交流が行われます。これらの交流をより有意義なものにするためには、ソーシャルスキルの育成を意識した活動が効果的です。重要なのは、異学年交流を単なる楽しいイベントで終わらせるのではなく、児童・生徒が互いに学び合える環境や関係づくりのきっかけにすることです。
構成的グループエンカウンターと対人関係ゲームの違いとは?
対人関係ゲームは、ゲームの中でソーシャルスキルトレーニングを行いながら、より良い集団づくりを目指します。一方、構成的グループエンカウンターは、エクササイズの後にその時の気持ちを語り合うことで、親密な人間関係を体験することを目的としています。
対人関係ゲームの例
交流する:「探偵ゲーム」 質問項目のシートを使い、じゃんけんで勝った人から質問をして、答えが「はい」の場合は名前を記入。制限時間内に多くの人の名前を集めます。
心をかよわせる:「背中にメッセージ」 画用紙を背中にかけ、互いの良いところを書き合い、後で読み合います。
協力する:「いろいろビンゴ」 テーマに沿ってグループで項目を出し合い、ビンゴ形式で進めます。
役割分担し連携する:「横つなひき」 綱引きのようにチームで協力しながら、陣地に縄を引き込むゲームです。
折り合う:「新聞紙タワー」 新聞紙を使って高いタワーを作るために、グループで話し合いながら工夫します。
教室環境のユニバーサルデザイン化とは?
教室環境のユニバーサルデザイン化とは、児童・生徒が落ち着いて過ごし、学習活動に集中できる環境を整えることです。
そのためには、不要な掲示物を外すなどして学びを妨げる要因を減らしたり、「暗黙のルール」や見通しを可視化したりすることが大切です。
ポイント例
妨害刺激の撤去:「掲示物を後方に貼る」「無地のカーテンでロッカーを覆う」など
物理的な構造化:「何を入れるか、どう入れるかがわかるようにする」
時間の構造化:「スケジュールを前面に提示」「変更は目立つようにする」
小中一貫教育(小中連携)の取組において、教室環境のユニバーサルデザイン化を図るには?
小・中学校で掲示物の系統性や発展性を確保したり、児童・生徒が協働的に環境整備を進めたりすることが重要です。
掲示物のデータをICT機器で電子化し、共有することで、児童・生徒がどのような環境で学校生活を送ってきたかを把握できます。また、各学年の掲示物を比較して、系統性や発展性を整理することも可能になります。
「暗黙のルール」とは何でしょうか?
「暗黙のルール」とは、整理整頓の仕方や学習活動の進め方など、学校生活をより良く送るための手順や決まりのことです。
教室環境のユニバーサルデザイン化では、児童・生徒の発達段階や動線などを踏まえ、ルールをシンプルにしてわかりやすくするとともに、掲示物などで視覚化して明確にすることが大切です。
授業のユニバーサルデザイン化とは?
授業のユニバーサルデザイン化とは、通常の学級に在籍しているすべての児童・生徒が、楽しく学び合いながら「わかる・できる」ことを目指して授業づくりを進めることです。
この考え方では、学びの階層を「参加」「理解」「習得」「活用」の4段階に分類し、授業でバリアが生じる原因となる発達障がいのある児童・生徒の特徴と、それに対する工夫を整理していきます。
なお、4段階のうち「参加」および「理解」は主に一単位時間の授業に関わる内容であり、「習得」は複数の学年や単元にまたがる学習、「活用」は日常生活や発展的な課題に関する内容となります。
小中一貫教育(小中連携)の取組において、授業のユニバーサルデザイン化を図るには?
各学級担任や教科担任などが創意工夫を共有するとともに、カリキュラム編成や目指す子ども像の設定においてもユニバーサルデザインの視点を意識することが重要です。
「参加」「理解」に関する取り組みについては、各担任が工夫した内容を共有し、「習得」「活用」を目指して9年間を見通したカリキュラム編成を行います。また、「活用」に関しては、小・中学校が目指す子ども像を設定する際にも意識して取り組むことが求められます。
それぞれの創意工夫を、どのようにして共有するのですか?
ネットワーク環境を活用して資料の共有化を進めたり、小・中学校合同で研究授業を行ったりすることが効果的です。
ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりを進める際には、授業づくりの視点をあらかじめリスト化しておくことで、研究授業後の協議が焦点化され、より深い議論が可能になります。その際には、授業の画一化を避けるために、共通して設定する項目と、各授業者が個別に設定する項目を組み合わせることも考えられます。
授業づくりのチェックリスト(校内統一項目)
A:授業の構成に関する項目 ①「導入」「展開」「まとめ」に一貫性があるか ② 学習活動の時間設定が児童・生徒にとって適切か ③ 学習形態(個人・ペア・グループ)が効果的か ④ 課題解決に向けた支援が効果的か ⑤ 課題の難易度が適切か
B:板書や教材・教具に関する項目 ⑥ 板書が授業の流れや内容を捉えやすく構造化されているか ⑦ 字の大きさや行間、色づかいが見やすいか ⑧ ノートやワークシートとの関連が図られているか ⑨ 教材や教具の操作が児童・生徒にとって適切か ⑩ 課題解決の支援として効果的か
C:話し方や説明・指示に関する項目 ⑪ 話し方のスピードや間の取り方が適切か ⑫ 要点が明確な短文を用いているか ⑬ 聴覚情報以外の情報も併用しているか ⑭ 曖昧な表現を避け、具体的な表現を使っているか ⑮ 一指示一活動を心がけているか
D:授業のポイントに関する項目 ⑯ 学習への意欲を高める「ひきつけ」ができているか ⑰ 授業のねらいをしぼって「方向づけ」ができているか ⑱ 思考を「むすびつける」ことができているか ⑲ 理解をこまめに「そろえる」ことができているか ⑳ 最後に「わかった」という実感を持たせることができているか
※評価は「◎とてもそう思う」「○思う」「―評価の対象ではない」で記入します。
取組を始めるにあたり、最初に大切なことは何ですか?
教育のユニバーサルデザインについての正しい認識と必要性を、教職員間で共有することが最も重要です。
教育のユニバーサルデザインは、発達障がいなど教育的ニーズを持つ児童・生徒にとっては「ないと困る支援」であり、その他の児童・生徒にとっては「あると便利で役に立つ支援」です。また、授業においては余計な混乱やつまずきを減らし、学習効果を高めることにもつながります。
取組を始める際には、先進校の情報を収集して参考にしたり、小・中学校合同の研修会に外部講師を招いたりして、教育のユニバーサルデザインに対する理解と必要性を深めることが大切です。
画一的な取組になってしまうのではありませんか?
児童・生徒の実態を尊重しながら、統一性と多様性を両立させる形で取組を進めていくことが重要です。
組織的に取組を進める方法として、指導の在り方や工夫、配慮などをリスト化し、教職員で共有することが考えられます。しかし、教育のユニバーサルデザインを機能させるためには、児童・生徒の実態に応じた柔軟な対応が欠かせません。
そのため、リストはルールとして固定するのではなく、より良い取組のヒントとして活用し、実際の指導の場では児童・生徒の状況に応じて修正を重ねていくことが大切です。
業務の多忙化や教職員の負担感の増大につながるのでは?
教育のユニバーサルデザインの視点は、児童・生徒の困難さの緩和や様々な問題の未然防止につながるため、中長期的には教職員の負担を軽減することが期待されます。
もちろん、取組を始める段階では一定の負担が生じることは避けられません。そのため、教職員の多忙化や負担感を軽減するための工夫も併せて行う必要があります。
たとえば、小中一貫教育(小中連携)の取組と並行して、各学校が独自に校内研究を進めている場合には、取組自体を統一した校内研究のテーマに設定したり、個別の研修と校内研究を組み合わせたりすることで、業務の集約を図ることができます。
取組に対して、適切な評価とその後の改善を行うには?
取組の効果を適切に評価し、その後の改善につなげていくためには、まず根拠となる資料を準備することが大切です。そして、多様な視点から検証を行うことが求められます。また、評価や改善は年度末だけに行うのではなく、定期的に打ち合わせや情報交換を行うことが効果的です。
たとえば、小・中学校の担当者が定期的に集まり、打ち合わせや情報共有の場を設けることで、取組の進捗や課題を共有しやすくなります。そのためには、年間計画の中にこうした打ち合わせの時間を優先的に組み込むことが望ましいです。
さらに、学校評価の項目に小中一貫教育(小中連携)に関する内容を取り入れたり、レディネステストなどを定期的に実施したりすることで、評価のための具体的な資料を得ることができます。これにより、客観的なデータに基づいた振り返りと改善が可能になります。
また、評価の際には、支援教育の専門家を加えることも有効な方法です。専門的な視点からの助言を受けることで、より的確な改善策を導き出すことができます。
#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です
就労・余暇活動の為に障がい者が障がい者の為の出張パソコンインストラクターminute(ミニュート)
就労・余暇活動の為に障がい者が障がい者の為の出張パソコンインストラクターminute(ミニュート)
☆----------------------------------------------------------------☆
minuteがおススメする障がい福祉用品集
悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は
ogayasu☆gaia.eonet.ne.jpへ
※直接入力の際は(☆)は(@)に打ち変えてください
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[障がい福祉] カテゴリの最新記事
-
望まないセルフプラン「ゼロ」、次の障害… 2025年11月15日
-
先天性障害のある記者、義肢装具士めざす… 2025年11月14日
-
QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の意味と… 2025年11月13日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.