2012年06月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

6月のおしゃれ手紙:10年
ブログを始めて6月で10年たった。最近、時々、体調が悪くなったりするが、意地でも、1日おきに書いてしまう。10年を機に、ブログを卒業するか・・・。でも、記録しておかないと忘れるし・・・。で、一日おきから、2~3日おきにしよう。 ■2012年6月の映画■*ジェーン・エア*ミッドナイト・イン・パリ*ミッドナイト・イン・パリ*オレンジと太陽*シャレード*テルマエ・ロマエ*道 白磁の人 ■書き残したネタ■ *もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*「清貧の思想」 *橋元大阪市長 *みどり学*パリネタ。 *ファーストレディ *「小石川の家」*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜 ・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月29日*探偵!ナイトスクープ:にわか/サルビア歳時記:6月の三箇条 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.29
コメント(4)
-

道 白磁の人★木を植える人
■道~白磁の人~■♪音が出ます!明日、世界が滅びるとしても、今日、二人は木を植える。1914年、日本の植民地支配下におかれた朝鮮。山梨県に生まれた浅川巧(吉沢悠)は、朝鮮時代の伝統美術・白磁に民族文化の美を見出していた。日本から朝鮮に渡った彼は、白磁を紹介しながら山々に木を植えて緑を取り戻し、現地の人々に博愛の精神で接していた。その一方、人種差別と戦いながら朝鮮人の李青林(ペ・スビン)と友情を築いていき――。朝鮮で植民地時代の差別と戦った日本人・浅川巧の生誕120周年を記念して製作。浅川の赴任した朝鮮で見た山は、荒れていた。営林署(のような所)で、先輩の日本人の話によると、ロシアや中国が乱伐したという。しかし、もっと乱伐したのは、日本政府だった。それを知った浅川は、朝鮮の人に対して、自然に対して申し訳ないと思う気持ちで、しずんだ表情になる。浅川のよき理解者である朝鮮人の青年は、「私たちも白磁を焼くために、沢山伐ったのですよ」と慰める。私はこれまで、日本が朝鮮の人に対してひどいことをしてきたと聞いている。しかし、木の乱伐までとは知らなかった。木が大好きな浅川巧は、朝鮮の山を緑にしようとする。彼のおもいは、ただそれだけだ。しかし、彼の上役の日本人は、「その木は成長が早い。早く役にたつ」と言う。最初から、「木」は伐って、売るためにあるという考えだ。ただ、生えているだけの木はもったいないと言う考えなのだ。1989年に、■こんな公園あったらいいな■と里山をそのまま公園にしようという市民運動に参加したことがある。私たちの考えは、奇跡的に市街地に残る1万坪の里山を残しすことこそが、いいという意見だったが、市は、空き地には、市民のために建物を建てるという意見だった。木は伐るために植えるという営林署の考えは、私たちが、対市交渉の時にきいた、空き地は、そのままだともったいないという言葉を思い出させた。浅川は、白磁や朝鮮の民具に対しても多くの功績を残した。もし彼が尽力しなければ、もうなくなっていたかもしれない、庶民の暮らしの品々。■李朝の陶磁■は、簡素でおおらかでそれでいてどっしりとした感じは、民芸的でそのごつごつした美しさは、日本の焼きものにはみられません。なかでも白磁には気取らない素朴さと暖かさがあり・・・。浅川の雰囲気が白磁と似てるというのは、きっと誰に対しても気どらない素朴さと暖かさがあったからだろう。浅川は、日本と韓国の教科書に載っているのだそうだ。これも、この映画を見て、ネットで調べるまでは、知らなかった。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月27日*露天風呂の日*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.27
コメント(0)
-

昔語:ウラ(裏庭)のつりしのぶ
私の子どもの時代に住んでいた岡山の家には、前と裏に庭があった。ただし、農家では、ニワというのは土間のことで、一般にいう庭は、カドと呼ばれていた。うちでは、裏庭を単に、ウラと呼んでいた。そのウラには、道に面した東に、スモモの木とナンテンの木。西には、竹林があり、毎年、ハチクを食べたり、竹を切ったりしていた。竹林の傍には、井戸があり、のぞくと石組が見えた。小さなバケツのようなものに、竹にとりつけ、私たちは、それで、飲み水、風呂水など、全ての水汲みをしていた。井戸の近くにイチジクの木があった。その下に、消し炭を入れる壺があった。消し炭とは、燃えている薪をその壺に入れ、蓋をして空気を遮断することによって、消し、炭にするのだ。山から伐ってきた木を無駄に使わないというためのものだ。消し炭の壺の横に、刃物を研ぐ台があった。鎌や包丁などは、ここで丁寧にとがれ、いつでも使えるように待機していた。研ぎ台の隣の小さな入れ物には、灰が少し入っていた。これは、食器を洗うためのものだった。日々の惣菜はほとんど油を使わないで作られたが、たまには使うこともある。その時、食器に灰をつけると油分が落ちるのだった。このように、うちのウラには、必要なものがあるだけで、花などは、植えてなかった。飾りらしいものといえば、たったひとつ、誰にもらったのか、誰が作ったのか、イチジクの枝に、かけられた、「つりしのぶ」。つりしのぶのある、ウラの景色・・・。それは、今も夏が来ると思いだす、懐かしい思い出の夏の景色だ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月26日*父の麦わら帽子:目次*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.26
コメント(0)
-

無買日:足るを知る
どうして次から次へと買ってしまうんだろう?かつて日本には「もったいない」という言葉がありました。 お金を使う ときは本当に必要なモノだけを買っていたのです。 いま、本当に必要なモノは、身の回りにほとんどそろっていますよね?それでもわたしたちは、どうして次から次へと色々なモノを買い込んでしま うのでしょうか? まるで何かに突き動かされるように。 あたかも心の底から欲しいと思っ ていたかのように。 無買日(Buy Nothing Day)は、1年で1日だけ、「余計なモノを買わ ない日」です。 そして「消費」について考えてみる日です。 わたしたちのサイフとココロ、そして地球環境に優しい日です。 ■「無買日」■ 今、私たちの周りには、モノが溢れかえっている。私たちは、モノに振り回されて生活している。先日、NHK教育テレビの「スーパー プレゼンテーション」「モノは少なく 幸せは大きく」 ■を見て、シンプルライフに拍車がかかった。(気持ちだけ)(ノД`)今のあり余る暮らしは、部屋を狭く感じさせる。冷蔵庫の中のものが、ありすぎて、早く食べないとという強迫観念に駆られる。足(た)ることを知らば貧(ひん)といへども冨(ふ)と名づくべし、財ありとも欲多ければこれを貧と名づく。10世紀の源信という僧の著した「往生要集」より。今の世の中、足りないくらいが、ちょうどいい!・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月25日*サルビア歳時記:6月の季語 /昭和恋々:金魚*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.25
コメント(0)
-

鞆の浦架橋中止決定!
広島県■福山市の景勝・鞆の浦の埋め立て・架橋事業■について、県の中止の方針が明らかになった22日、反対の立場の住民は笑顔を見せ、事業推進を望んだ住民らは憤った。住みよいまちを望む思いは一つになるのか。鞆の人たちの声を聞いた。 鞆の浦観光情報センターの片岡明彦事務局長(48)は「世界中の観光客がアニメ映画『崖の上のポニョ』から鞆を知る。ポニョの海が残ることは喜ばしい」と歓迎する。男性住民(65)も「知事の判断は当然だ。橋が架かれば、鞆のシンボルといえる常夜灯を入れた眺望も台無しになる」と話す。 一方、埋め立て・架橋を支持していた住民たちは不満を隠せない。浄泉寺住職の大仲伸隆さん(63)は、狭い県道で自動車とすれ違う際に何度も危険な思いをしていると言い、「町の活性化や安全の確保のために橋は必要。このままでは住民が減り、鞆は限界集落になってしまう」と嘆く。 鞆の浦には、一度行ったことがある。旅行者には、分からない、そこに住む人の言い分があるだろう。しかし浄泉寺住職に言いたい。もし、鞆の浦の景観が壊されると、観光客が来なくなり、今より住民が減るだろうと!・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月23日*キャンドルナイト記念・トリビアの井戸:イッチョウラ /里山の歌・夏はきぬ *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.23
コメント(0)
-

キャンドルナイト2012
■100万人のキャンドルナイト■私たちは100万人のキャンドルナイトを呼びかけます。夏至・冬至、夜8時から10時の2時間、みんなでいっせいにでんきを消しましょう。ロウソクのひかりで子どもに絵本を読んであげるのもいいでしょう。しずかに恋人と食事をするのもいいでしょう。ある人は省エネを、ある人は平和を、ある人は世界のいろいろな場所で生きる人びとのことを思いながら。プラグを抜くことは新たな世界の窓をひらくことです。それは人間の自由と多様性を思いおこすことであり、文明のもっと大きな可能性を発見するプロセスであると私たちは考えます。一人ひとりがそれぞれの考えを胸に、ただ2時間、でんきを消すことで、ゆるやかにつながって「くらやみのウェーブ」を地球上にひろげていきませんか。でんきを消して、スローな夜を。100万人のキャンドルナイト。■最初のキャンドルナイトは2003年6月。■私は、最初から、■参加■しています。ただし、気持ちだけ。2時間のイベントに参加できなくても、こうして、ブログに書いたり、いつもより早く寝るというのもありだと思う。クーラーを扇風機にするのもありだと思う。毎日、環境のことを考えているからといいわけしてるのだ。かつて、アメリカでは、トーマス・エジソンの死に際して、弔意を表すため全米の電灯が1分間消灯された例、グラハム・ベルの死に際して、ベル電話会社の利用者が通話中1分だけ沈黙してその死を悼んだ例があるという。大飯原発は安全だから、再稼働しますという政府。その言葉を丸のみにする福井県知事。去年盛りあがった、脱原発という声がどんどん、小さくなっていってるような気がする。去年の事故の反省のかけらもない!!そんな時だからこそ、キャンドルナイトの意義があると思う。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月21日*100万人のキャンドルナイト:親と月夜はいつもよい/ トリビアの井戸:タソガレの語源 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.21
コメント(2)
-
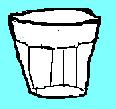
「モノは少なく 幸せは大きく」
月曜日の夜11時からは、NHK教育テレビの■スーパー プレゼンテーション■を見ている。この放送は、■「TEDカンファレンス」■という講演会のテレビ放送。驚きのアイデアや行動、発想などを最高のプレゼンで聞くというものだ。今回のプレゼンターは、グレアム:ヒル。■「モノは少なく 幸せは大きく」■Graham Hill: Less stuff, more happiness大量消費の生活を改め、少しでもお金を節約し、環境に優しく、幸せになる。そのため彼が提案したのは、とにかくモノを減らすこと。具体策は3つ。1.徹底した片付け。2.少ないことはクールだと考えを改めること。3.家具や空間を多機能にすること。不要なモノを捨てて生活を再編すれば、きっと人生はもっと豊かになるはず。 アメリカの家は50年前に比べて3倍の広さになったのだそうだ。それなら、片付きそうだけれど、相変わらず、家の中にはモノが溢れている。家に入りきらないため倉庫産業が伸びているのだそうだ。彼が具体的に言ってたこと。 ◎椅子などは、スタッキング=積み重ねられるもの。日本の座布団なんか、究極のスタッキングだ。 このグラスも、スタッキング出来る。その上、姿がよく、安いし、強い。■たかがグラス、されどグラス■◎できればデジタル化する。私がブログを始めた理由のひとつが、冊子などに書かれている内容を残したいが、モノとして残すのは嫌だと思ったから。■◎地球を救う127の方法◎ ■は、もらったパンフレットをそのまま、うつしたもの。冷蔵庫の中にどんなに食材があろうが、料理上手でないと美味しい料理は出来ない。本棚にどんなに沢山の本があろうと、それが理解できなければ、どんなに高価なバイオリンがあっても、弾くことができなければ無用の長物だ。大切なのは、モノではない。モノを沢山持つことが幸せにはならない。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月19日*大江戸トイレ事情/「佐賀のがばいばあちゃん」★がばい語録 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.19
コメント(0)
-

テルマエ・ロマエ★ヤマザキマリ
■テルマエ・ロマエ:あらすじ■ひとっ風呂、タイムスリップしませんか。舞台はハドリアヌス帝時代、西暦130年代の古代ローマ。浴場を専門とする設計技師ルシウス・モデストゥスは、革新的な建造物が次々に誕生する世相に反した昔ながらの浴場の建設を提案するが採用されず、事務所と喧嘩別れしたことで失業状態に陥ってしまう。 落ち込む彼の気を紛らわせようとする友人マルクスと共に公衆浴場に赴いたものの、周囲の騒々しさに耐えかね雑音を遮るため湯中に身を沈めたルシウスは、壁の一角に奇妙な排水口が開いているのを見つけ、仕組みを調べようと近づいたところ、足を取られて吸い込まれてしまう。不測の事態にもがきながらも水面に顔を出すと、彼はローマ人とは違う「平たい顔」の民族がくつろぐ、見たこともない様式の浴場に移動していた。ルシウスが見た「平たい顔族」と現代日本人であり、ルシウスは浴場を使ったタイムトラベラーとなっていたのだった。 原作が「漫画大賞2010」、「第14回手塚治虫文学賞 短編賞」受賞した気になる映画だったがやっと見に行けた。現代の日本にタイムスリップする古代ローマ人のルシウス(阿部寛)が面白い。*プラスチックの風呂桶(製薬会社のCM入り)*銭湯の壁に描かれた富士山の絵*風呂上がりのフルーツ牛乳*脱いだ服を入れる籠*シャンプーハット*シャワー*暖簾などなどにいちいち、驚いて感心する。その大げさな驚きと感動っぷりが大笑いなのだ。この映画があるまで、「テルマエ・ロマエ」という漫画があることも知らなかったのが残念。早速、図書館で借りよう。作者のヤマザキマリは、1967年4月20日生まれ、東京都出身。17歳で単身イタリアに渡り、フィレンツェの美術学校で絵画の勉強を始める。1996年にイタリアでの暮らしを綴ったエッセイ漫画でデビューする。その後日本、中東、イタリアでの暮らしを経て、2003年にポルトガル・リスボンに移り住む。2008年から『月刊コミックビーム』(エンターブレイン)に『テルマエ・ロマエ』の連載を不定期にスタートさせ、2009年に発売された単行本が大ヒット。 同作は2010年に「マンガ大賞2010」と「第14回手塚治虫文化賞短編賞」を受賞した。 現在はシカゴで、イタリア人の夫と息子と暮らしている。彼女の夫がイタリア人でなければ、古代ローマオタクでなければ、この漫画は生まれなかった。 ■テルマエ■テルマエ (thermae)とは、古代ローマの公衆浴場である。 古代ローマの多くの都市に少なくとも1つの公衆浴場があり、社会生活の中心の1つになっていた。古代ローマ人にとって入浴は非常に重要だった。彼らは1日のうち数時間をそこで過ごし、時には一日中いることもあった。裕福なローマ人が1人か複数人の奴隷を伴ってやってきた。料金を支払った後、裸になり、熱い床から足を守るためにサンダルだけを履いた。奴隷は主人のタオルを運び、飲み物を取ってくるなどした。入浴前には運動をする。例えば、ランニング、軽いウェイトリフティング、レスリング、水泳などである。運動後、奴隷が主人の身体にオイルを塗り、(木製または骨製の)肌かき器で汚れと共にオイルを落とした。テルマエ・ロマエとは、ローマの風呂。韻を踏んでいていいタイトルだ。イタリアでも評判の映画だそうだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月17日*父の麦わら帽子:特別な日/トットが来たら豆を蒔け:時の記念日 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.17
コメント(0)
-

シャレード★二転三転
■シャレード:あらすじ■あなたは敵?見方?フランスの冬の観光地。レジーナ(オードリー・ヘップバーン)はフランスの友達とスキーを楽しんでいた。彼女は夫との離婚を決意している。彼女はそのスキー場で偶然ピーター(ケーリー・グラント)と知り合い、強く心をひかれた。パリのアパートに帰った彼女は夫の殺害を知らされ唖然とした。夫の葬儀のとき、会葬者の中に見知らぬ3人の男ーペンソロー(ジェームズ・コバーン)ギデオン(ネッド・グラス)スコビー(ジョージ・ケネディ)がいた。大使館で彼女は情報部長に、夫は戦時中、会葬に来た男たちと共謀して25万ドルを隠匿、戦後山分けをすることになっていたが、夫はそれを裏切り金を持って逃げるところを殺された、政府のお尋ね者だったと聞かされた。 1963年のアメリカ映画。ヘンリー・マンシーニの音楽が懐かしい。主演のオードリーの着用している服は、ジパンシーの作品。パリに住む、若き富豪の妻という設定なので、何着も素晴らしい服を着る。豹柄の帽子や、シックな帽子、ちょっと襟の立った数着のコート・・・。それをあの、美しい顔とスタイルのオードリーが着るのだから見ているだけで、もうため息が出る。映画の冒頭の列車から、投げ出される死体、スキー場から帰ったレジーナのがらんとした邸宅の不気味さ。スキー場で出会いピーターは、レジーナにとって、敵か味方か?は二転三転する彼に、ドキドキする。緊張感が最後まで途切れることない、洒落た極上のミステリー。 「ローマの休日」が1953年で24歳。1963年の「シャレード」では34歳だ。 「昼下がりの情事」でもそうだったが今回も中年に魅かれる役。若々しいオードリーが、なぜ、おっさんと・・・?納得できない・・・。■シャレード・動画■♪音が出ます!■午前十時の映画祭★青の50本 ■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月15日*雨の名前:空梅雨(からつゆ)/「純情きらり」と「私の昭和」:手ぬぐい *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.15
コメント(0)
-

オレンジと太陽★児童移民
■オレンジと太陽:あらすじ■その手を誰も忘れなかった。英国・ノッティンガム。1986年。でソーシャルワーカーとして働くマーガレットは、ある日、見知らぬ女性、シャーロットに「私は誰なのか調べて欲しい」と訴えられる。幼い頃、ノッティンガムの施設に預けられた彼女は、4歳の時に沢山の子供たちとともに船でオーストラリアに送られ、自分がどこの生まれなのか母親がどこにいるのかも判らないという。最初はその話を信じられなかったマーガレットだが、ある出来ごとを契機に調査を始める。やがて、彼女はシャーロットのような子供たちが数千に上がり、中には母親は死んだという偽りを信じて船に乗った子供たちもいた事を知る。19世紀から1970年代まで、英国は施設などの子供たちを福祉の名のもとに密かに、オーストラリアに送っていたのだ。しかし、オレンジと太陽の国で彼らを待っていたのは…。にわかには信じがたい“児童移民”の真実を明らかにした女性、マーガレット・ハンフリーズを描いた感動の実話。 「私は誰?」「ママはまだ生きているの?」イギリスとオーストラリアが、秘密裏に子供をやりとりしていた、しかも1970年まで!!この事実は、この映画を知るまでまったく知らなかった。この驚きは、北朝鮮に拉致された人たちがいた、しかも何人もという時のショックに似ている。オーストラリアに着くと子供たちは、着ていた服を脱がされ、ぼろぼろの服と靴がそれぞれ1枚与えられる。課せられたのは、重い石を運ぶ重労働。食事も飲み水もろくに与えられず、棒や鞭、その辺のもので殴られる生活。大人になると、子ども時代の食事と衣服代を請求されたという。掃除婦をして働く48歳の女性の女性にマーガレットが「この仕事は長いの?」と聞くと女性は「40年やってます」と答える。連れて来られてた8歳の時からずーとやっているのだ。大人による性的暴力を受けた子供も沢山いる。イギリスなどは、人間を大事にするというイメージだが、孤児院にいるのは人間として認めていなかったのかと怒りがこみ上げる。もうひとつ腹立たしいのは、その事実を認めようとしない、英豪政府やキリスト教会。中には、マーガレットに脅迫電話をかけてきたり、夜中に窓を割って侵入しようとする者もいる。 マーガレットの夫婦のベッドには、キルトのカバーがかけてあった。息子の部屋にも、四角を繋ぎ合せたキルトのベッドカバー。カーテンの模様などもいい感じで、住み心地のよさそうな家だった。その家でマーガレットを助け家事をするのが夫。この夫が素晴らしい。家事はもちろんのこと、「児童移民」を調べるトップになったマーガレットをオーストラリアに単身赴任させ、二人の子どもの世話をする。マーガレットが体調を崩したり、精神的にまいりそうななったら、的確にアドバイスをする。女性が活躍するには、こういう有能で優しい夫が必要なのだ。世の男はみな、マーガレットの夫のような妻と暮らしているのだから、仕事が出来て当たり前なのだ。「オレンジと太陽」の監督は、ジム・ローチ。大好きな映画■「麦の穂を揺らす風」■の監督、ケン・ローチの息子だ。ある日、男の人が来てこう言った。君のママは死んだんだ。だから海の向こうの美しい国へ行くんだよ。そこでは毎日太陽が輝き、そして毎朝、オレンジをもいで食べるんだ。タイトルの「オレンジと太陽」は子供たちを誘う時の大人の言葉。マーガレットと夫は今もこの事実を調べている。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月13日*昔は、どうしていたんだろう。:オトコのファッション*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.13
コメント(2)
-

ミッドナイト・イン・パリ★久世光彦
■ミッドナイト・イン・パリ:あらすじ■♪音が出ます!真夜中のパリに魔法がかかる。 映画脚本家のギルは、婚約者イネズの父親の出張に便乗して憧れのパリにやってきた。脚本家として成功していたギルだが虚しさを感じ、現在は本格的な作家を目指して作品を執筆中だ。そんなギルの前にイネズの男友達ポールが出現。心中穏やかでないギルだが、真夜中のパリの町を歩いているうち、1920年代にタイムトリップしてしまう。そこはヘミングウェイ、ピカソ、ダリなど、ギルの憧れの芸術家たちが活躍する時代だった。 ■またもや■「ミッドナイト・イン・パリ」を見てきた。梅田に用事があって、その時間待ちに一番いい時間に「ミッドナイト・イン・パリ」があったのだ。 前回、映画を見てから、私は、久世光彦のことを考えていた。久世は、「昭和恋々」の中で、第二次世界大戦がはじまるまでの時代、昭和の初期を美しく描いている。私は、彼の小説の中で、 「蕭々館日録(しょうしょうかんにちろく)」というのを読んだことがある。夜ごと「蕭々館」でくりひろげられる、文学談義、名文暗誦合戦、そして嘘か真か判然としない話の数々…。芥川龍之介、菊池寛、小島政二郎。青春をともにした三人の作家を描きながら「大正」という時代への想いを綴る傑作長篇だ。この家の娘は5歳で、麗子という名前。岸田劉生の「麗子像」と同じ名前だということで、同じ格好をしている。芥川龍之介の息子、比呂志も、麗子と言葉を交わす。 向田邦子の描く昭和の初めを久世光彦製作のテレビに映像化していた。私はこのシリーズが大好きでよく見ていたが、久世光彦が2006年に亡くなり、もう見ることができなくなった。久世は、タイムスリップ出来ない代わりに、映像や小説で過去をえがいた。「ミッドナイト・イン・パリ」のギルが1920年代が好きでたまらなかったように、久世さんもまた、昭和の初めという時代が好きでたまらなかったのだ。そして、私もまた、過去をいとしく思うひとりだ。■久世光彦(くぜてるひこ)作品のページ■■昭和恋々■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月12日*時計の無い暮し/はかどるの語源/♪よしわらタケノコ~*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.12
コメント(0)
-

おしゃれ手紙44◆動物実験
■天地 はるな様■ 梅雨がやってきましたねー。 オシャレな長靴と傘が欲しいこの頃。 と言っても「長靴」は野良仕事用で「傘」は日傘なのですが・・・。 まあ、長靴は「スミス&ボーケン社」の長靴を持っているのですから、充分といえばそうなんですけど、物欲いまだ健在なきの私。 履き替え用に、もう一足欲しくて機能的にも、デザイン的にもステキな長靴を探しているのですが、ご存知ないですか? 今持ってる「スミス&ボーゲン」はラッキーなことに知人よりUSEDとして 定価の三分の一で譲ってもらったもので、めちゃお気に入り。 明けても暮れてもそればっかり履いているので、だんだんくたびれてきていてオキノドクな状態。 たまには、お休みをあげないとなー。 そして、日傘。 物心ついた頃から母に 「日焼けは悪」と洗脳され、ソバカスだらけの私の顔は哀れみの対象とされてきました。 そんな経緯があったためか、一度は小麦色に燃えた時期もあったけど 今では紫外線対策にいそしむ日々。 日傘をさすのは、ちょっと面倒だけど、おしゃれも兼ねて夏の外出には欠かせなかったのです。 しかし、しかし、大切にしていた日傘が、なぜか一昨年、行方不明。 以来、日傘を求めてうろつくのですが、 「これ!」という日傘に出会えず、この際、思い切ってオーダーしてみようかと思ったり、 いやいや、もう少しうろついてみようと思ったり・・・。 ステキな傘屋さん、ご存知ないですか? そんな、おり街を歩いていたら 動物実験を反対する反対「AVAーnet」が 街頭で署名運動をしていました。 私は以前からこの問題を重視していたのですで即、署名。 それにしても、回りを見渡せば、多くの人が道を行き交ってるのに署名する人のなんと少ないこと・・・。 皆無に近い・・・。 関心がないのか、目にとまらないのか、面倒くさいのか・・・。 手にしたパンフレットには、目を背けたくなるような写真が載せられていました。 わが家では現在、三匹の犬と二匹の半野良犬の面倒をみています。 動物達は、日頃何気なく使っている「化粧品」だけでなく、 新薬の開発や実験の犠牲になっています。 医療関係に携わっていた私が仕事をやめた理由の一つでもある動物実験。 遺伝子組替えや脳死、移植の問題も併せて「生命」について、みんなでもっと考える必要があると思います。 浜辺 遥 **ザ・ボディショップ化粧品の動物実験反対キャンペーン** 「うさぎたちを救おう!」限定うさぎぬいぐるみ。 化粧品の動物実験は残酷で信頼性に欠けるため、ザ・ボディショップでは、 これに反対しています。 商品の売上の一部はJAVA(動物実験の廃止を求める会)に寄付されます。◆おしゃれ手紙◆・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月9日*■テレビしびれて■関西人気質/ツバメの宿賃 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.09
コメント(0)
-

地名:茶屋町
この町の名の由来は、同町を南北に縦断する池田街道筋に三軒の茶屋があった事に由来する。三軒の茶屋とは「鶴の茶屋」、「萩の茶屋」、「車の茶屋」である。「鶴の茶屋」の由来は鶴野町の段でも述べた通り、豪商であった松並竹塘が二羽の鶴を放し飼いにしたところからきており、その事を記した石碑が現在も茶屋町の一角に残っており、当時を物語っている。今では考えられないが、当時はのどかな田園風景が広がっていたようである。この「鶴の茶屋」について、昔を知る古老の話によれば、鶴の茶屋は黒塀に囲まれた趣のある建物で、二つの大きな門があり、船場の旦那衆が駕籠で乗りつけたそうである。これら茶屋は、いわゆる現在で言うところの風俗店的な茶屋とは違い、当時の大阪の有力者の人々が、与謝蕪村が歌ったように「菜の花や 月は東に 日は西に」と菜の花や萩の花、月の風情を愉しむといった憩いの場として、前記の茶屋などの料亭が客を招いていたところであった。 映画館■テアトル梅田■があるので、茶屋町にはちょいちょい行く。先日は、映画館ではなく、新しく出来た大型書店に行くために、茶屋に行ったら目にとまったのが、上の写真。この写真があった所は■ヌー茶屋町+(ちゃやまちプラス)■の正面。かつて、ここにあった鶴乃茶屋は、大勢の人で賑わっていたらしいが、今は、ファッションビルが建って、若い人で賑わっている。たまに、私のような若くない人もいるが・・・。この時代にタイムスリップしてみたいな・・・。 ■ヌー茶屋町+(ちゃやまちプラス)■碑のある所。大阪市北区茶屋町8番26号・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月7日*昔語り:蛍/雨の名前:茅花流し(つばなながし)*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.07
コメント(0)
-

ミッドナイト・イン・パリ★1920年代
■ミッドナイト・イン・パリ:あらすじ■♪音が出ます!真夜中のパリに魔法がかかる。ハリウッドで売れっ子の脚本家ギル(オーウェン・ウィルソン)は、婚約者イネズ(レイチェル・マクアダムス)とその両親と共に憧れのパリに意気揚々とやって来た。しかし、1920年代、文化・芸術が花咲く時代のパリへ突然タイムスリップしてしまう。真夜中のパリで出会ったのは、ガートルード・スタイン(キャシー・ベイツ)のサロンに集うヘミングウェイやフィッツジェラルド、ピカソたち。ロマンティックでマジカルな夜が始まろうとしていた――。 この映画、3回目である。1回目は、去年のパリ行きのさい飛行機の中で、2回目は、帰りの飛行機の中で・・・。そして今回が3回目。■エッフェル塔■、■凱旋門■、■モンマルトル■、■セーヌ川■、冒頭、パリの名所が次々に出てくる。 「ミッドナイト・イン・パリ」の監督はウッデイ・アレンだが彼の代表作、「マンハッタン」も、NYの名所が次々の出てくるのだそうだ(私はまだ見いない)。脚本家ギルは、1920年代のパリが好きでたまらない。この時代は、■アールデコの時代■。私も大好きだ。 この時代のパリは、有名な芸術家で溢れていた。パーティに誘われて行ってみると、コール・ポーター、F・スコット・フィッツジェラルドと妻ゼルダ。そのパーティはジャン・コクトーのパーティだった。その後、フィッツジェラルド夫妻、ポーター夫妻と行ったクラブでは、ジョセフィン・ベイカーもいた。アーネスト・ヘミングウェイ、ガートルード・スタイン、パブロ・ピカソとその愛人、アドリアナがいた。サルバドール・ダリ、ルイス・ブニュエルとマン・レイ・・・。豪華な、20世紀の有名人が一堂に会している。 ピカソの愛人は、20世紀初めのアール・ヌーボーの時代のパリに行きたいという。そして、思いが叶い、ロートレックに会う。この時代もいい。エッフェル塔が建ち、■ギマール■が地下鉄の入口やランプをデザインした。また、今もパリに残る、■アール・ヌーボー様式の邸宅■もギマールのデザインだ。作家の■コレット■がいた。映画を見た友人は、1140年代のイギリスはウェールズにあるシュルー ズベリ修道院へ行きたいと言う。グーグルでみたら今でも同じ川が流れてる地形の所に遺ってるのだそうだ。そこの薬草園でカドフェル修道士の助手になってシロップの鍋をかき混ぜたり、トローチを干したり。と言う。私は、やっぱり、アール・ヌーボー時代のパリかな・・・。でも、早く現代に帰らないと病弱は私は死んでしまう。この時代は、私が飲んでいる薬や注射がないからだ。夢見るギルは、1920年代に憧れながらも、現代がいいということに気づく。アカデミー賞でオリジナル脚本賞を受賞。他に作品賞、監督賞、美術賞の計4部門にノミネートされた。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月5日*こごめ/大阪しぐれ:マサコさん *・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.05
コメント(5)
-

ジェーン・エア★家庭教師
■ジェーン・エア:あらすじ■♪音が出ます!運命に妬まれた、魂で結ばれた愛。幼くして両親を亡くし、孤児院で酷い扱いを受けながら育ったジェーンは、家庭教師の免許を取り、主不在のソーンフィールドという屋敷で養女の家庭教師として住み込みで働き始める。ある日、ジェーンは暗く冷たい雰囲気を持つロチェスター氏と遭遇する。彼はいないはずのソーンフィールド屋敷の主だった。ジェーンは彼と共に過ごすうちに恋におちていくが、ロチェスター氏には恐ろしい秘密があった…。 私は、若い頃から「ジェーン・エア」を何回も読んでいる。去年の12月にも1944年製作のDVD、■「ジェーン・エア」■を見た。そんな私が今回の映画には、満足した。原作に忠実だったからだ。DVDの方にはなかった、ロチェスター氏の家を出てからが原作に近く描かれていた。まあ、もっとも、細かいところでは不満があるが、それ以上に映像が美しかった。あの頃の女性の服は、こんなになっているのか、掃除はこうやっているのか・・・。なんて、思いながら見ていた。「ジェーン・エア」がなぜ、発表当時に衝撃的で大反響をよんだのか?この当時の女性は、親の財産がたっぷりあって、美しい女性のみが幸せになれた時代だ。■「高慢と偏見」■でも、美しいが財産の少ない娘たちをなんとか結婚させようとする親がコミカルに描かれている。そんな時代にあって、美しくもなく、財産もない孤児のジェーン・エアが自分で幸せな結婚を勝ち取るというのである。しかも、結婚相手は、金持ち。当時、地位のある男性が、家庭教師と結婚するということは、考えられないことだった。家庭教師は、使用人で、貧しい女性がなる仕事だったからだ。この映画の監督は、父親が日本人、母親がアメリカ人のハーフ、キャリー・ジョージ・フクナガ。俳優といっても通じるくらいにイケメンなのだ。ジェーン・エア役は、この役にピッタリで、杏に似ている。■衣装デザイン賞★ノミネート作品■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月3日*子どもの仕事:風呂たき /方言:あほう*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.03
コメント(6)
-

植物切り抜き帳:ドクダミ
日陰にドクダミの花が咲いている。ハートが型の可愛い葉っぱ。白い星のような可憐な花。実はこの白い花のように見えるのは、花ではなく、総苞片(そうほうへん)。しべのように見えるのが花だ。その白い花が日陰のほの暗い場所にあると、はっとするくらい美しい。しかし、ドクダミの本当のいいところは、美しさではない。古くから民間治療薬としてさかんに用いられてきた。しかし、昨今、このことをあまり知らないのか、生えているところがあまりない。だから「雑草」というけれど、私はこれを栽培している。公園などの日陰の部分でも、自生していたら、抜かないで欲しいものだ。◎ドクダミ◎住宅周辺や道ばたなどに自生し、特に半日陰地を好む。全草に悪臭がある。開花期は5~7月頃。茎頂に、4枚の白色の総苞(花弁に見える部分)のある棒状の花序に淡黄色の小花を密生させる。本来の花には花弁も、がくもなく、雌しべと雄しべのみからなる。 加熱することで臭気が和らぐことから、日本では山菜として天ぷらなどにして賞味されることがある。生薬として、開花期の地上部を乾燥させたものは生薬名十薬(じゅうやく、重薬とも書く)とされ、日本薬局方にも収録されている。十薬の煎液には利尿作用、動脈硬化の予防作用などがある。なお臭気はほとんど無い。 また、湿疹、かぶれなどには、生葉をすり潰したものを貼り付けるとよい。 漢方では解毒剤として用いられ、魚腥草桔梗湯(ぎょせいそうききょうとう)、五物解毒散(ごもつげどくさん)などに処方される。しかし、ドクダミ(魚腥草、十薬)は単独で用いることが多く、漢方方剤として他の生薬とともに用いることはあまりない。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年6月1日*命の重み*・・・・・・・・・・・・・・
2012.06.01
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 「届くのが遅すぎて使えない…」楽天…
- (2025-11-14 22:00:05)
-
-
-

- みんなのレビュー
- ☆もりのなす☆Snow Manのコンサートで…
- (2025-11-14 22:23:34)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 【○○蔓延る】こんな日本に戻りたくな…
- (2025-11-15 07:50:14)
-






