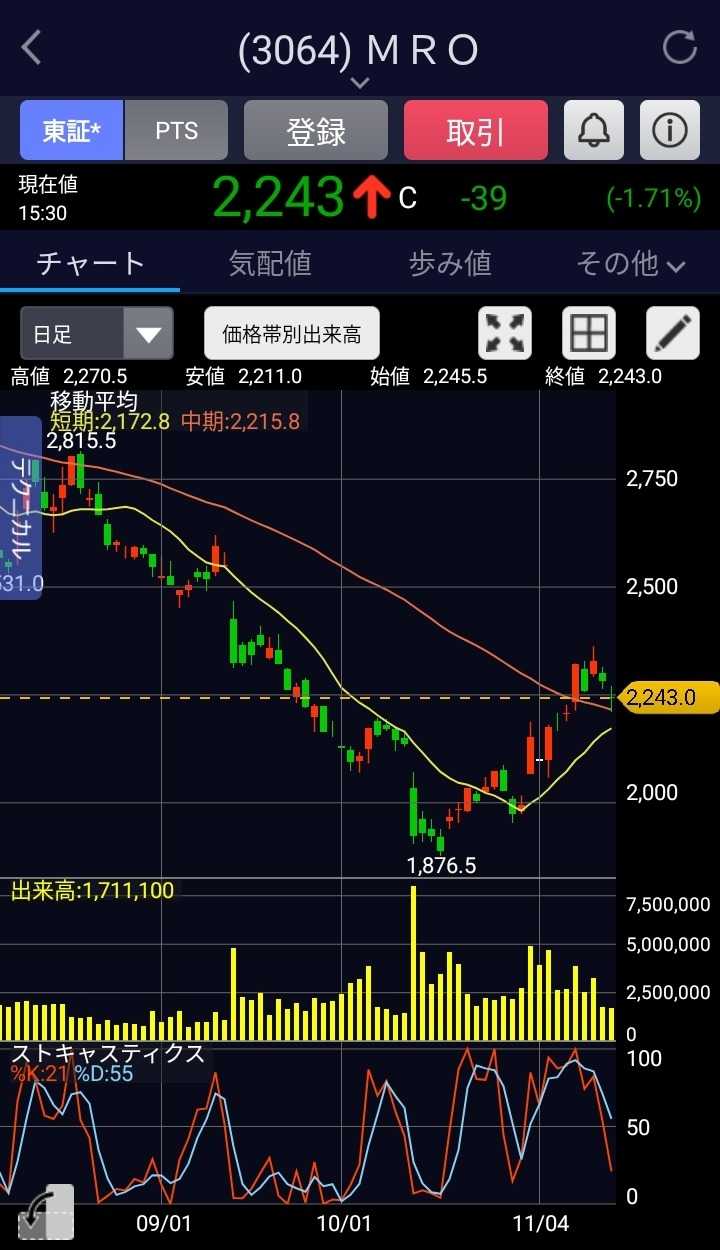2025年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

10/6-1:黄金道路をゆく/ついに襟裳岬に
■2025.10.6(月)-1■黄金道路■国道336号線のえりも町庶野地区から広尾町までを結ぶ約33.5キロメートルは、切り立った岸壁沿いに道路が続きます。このルートの建設が計画されたのは、江戸時代のこと。そり立つ断崖絶壁からは四季を問わず石が崩れ落ち、冬には雪崩が多発していました。しかし調査の結果、海岸・山岳ルートともに建設には困難が予想され、長い間この区間は迂回路に頼ることとなりました。ようやく工事が着工されたのは、それから長い歳月を経た昭和2年(1927年)のこと。トンネルと海岸の埋め立て、崖を削るなどの難工事のため、完成までには7年もかかり、昭和9年(1934年)にようやく日高と十勝を結ぶ海岸ルートが開通しました。竣工当時の名前は日勝海岸道路でしたが、「まるで黄金を敷き詰められるほど、建設に莫大な費用が掛かった道路だ」として黄金道路と呼ばれるようになりました。■フンベの滝■フンベの滝は、国道336号(通称:黄金道路)の広尾橋からえりも方面へ車で5分程走った道路沿いにあります。昔このあたりに鯨が打ちつけられたことからアイヌ語で「鯨の獲れる浜」という意味で「フンベ」と名づけられました。湧き出した地下水が直接道路脇に落下している珍しい滝で、夏は涼を呼び、冬は見事な氷柱となって私たちの目を楽しませてくれます。滝の目の前に駐車帯があるので、ドライブ途中に気軽に立ち寄れますよ。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■百人浜■襟裳岬から十勝方面に約10キロメートル続く砂浜「百人浜」は、その美しさとは逆に悲しい言い伝えが残されています。その昔、海の難所として知られる襟裳岬周辺海域で、南部落の大型船が遭難し多くの水死体がこの浜に打ち上げられ、わずかばかりの生き残った人も、飢えと寒さで亡くなったというもの。その数が100人にもなったため名付けられたといいます。道道34号(襟裳公園線)に駐車場が面していて、海側に百人浜へと続く散策路があります。緑化事業観察塔からは、緑化事業で植栽されたクロマツ林を一望できます。▲道路に群生しているのは、野菊かな。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲宗谷岬(赤〇)から襟裳岬(青〇)ついに襟裳岬に着いた!!アイヌ語で「オンネエンルム(大きな岬)」と呼ばれる襟裳岬。2010(平成22)年には、神威岬や幌尻岳とともに国の名勝ピリカ・ノカ(美しい・形)に指定された、自然豊かな美しいスポットです。ここは、北海道の背骨と呼ばれ全長約150kmにもわたり険しい姿を見せる日高山脈が、徐々に標高を下げて太平洋に沈み込んで行く場所。沖合で暖流の黒潮と寒流の親潮とがぶつかり合うため霧の発生も多く、神秘的な姿を見せてくれます。岬には襟裳岬灯台が立ち、先端から約2km先まで岩礁が続く景観は壮大です。海面下に没してさらに6キロメートルも続くというから驚き。▲襟裳灯台。♪襟裳岬♪ 島倉千代子♪風はひゅるひゅる波はざんぶりこ誰か私を 呼んでるような襟裳岬の 風と波にくいにくいと 怨んだけれどいまじゃ恋しい あの人が♪襟裳岬♪ 森進一♪北の街ではもう 悲しみを暖炉で燃やしはじめてるらしい理由(わけ)のわからないことで 悩んでいるうち老いぼれてしまうから黙りとおした 歳月(としつき)をひろい集めて 暖めあおう襟裳の春は 何もない春です■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-1■然別湖(しかりべつこ)・観光遊覧船/湖底線路■■10月2日(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路■■10月3日(金)-1■ガーデン街道をゆく:帯広市・真鍋庭園/馬の資料館/あるある■■10月3日(金)-2■北海道・宗谷岬から襟裳岬の旅:愛国から幸福へ■■10月4日(土)-1■幕別町・ふるさと館/帯広発祥の地/十勝ヒルズ■■10月4日(土)-2■ばんえい競馬/北海道のターシャが作った紫竹ガーデン/あるある■■10月5日(日)■中札内(なかさつない)美術村/ナウマン象記念館/広尾町海洋博物館&■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.14
コメント(0)
-

モンテ・クリスト伯★復讐
■モンテ・クリスト伯■華麗なる復讐の幕が上がる。将来を約束された航海士ダンテスは、ある策略により無実の罪で投獄されてしまう。次第に生きる気力を失い、絶望のなかにいたダンテスは、ある日脱獄を企てる老司祭と出会い、希望を取り戻していく。司祭から学問と教養を授かり、さらにテンプル騎士団の隠し財宝の存在を打ち明けられたダンテス。投獄から14年後、奇跡的に脱獄を果たした彼は、秘密の財宝を手に入れ、謎に包まれた大富豪として姿を現す。 アレクサンドル・デュマによる小説「巌窟王」を原作に、無実の罪で投獄されてしまった男の復讐を描くヒューマンドラマ。数奇な運命を背負った男、ダンテスを『イヴ・サンローラン』のピエール・ニネが演じるほか、『12日の殺人』のバスティアン・ブイヨン、『アリスと市長』のアナイス・ドゥムースティエらが出演。『お名前はアドルフ?』のアレクサンドル・ド・ラ・パトリエールとマチュー・デラポルトが監督を務める。★子供の頃、「巌窟王」を夢中になって読んだ。筋は分かっていても、映画を見るとドキドキする。映画の中に美しい階段の手すりが出てきて、プチパレ?と思ったけど、プチパレと年代が合わない。どこで撮影したんだろう?★「モンテ・クリスト伯」の作者は、アレクサンドル・デュマという。息子も小説家だった。今回、調べてみたら次のようなことが分かった。父デュマは仏領サン=ドマング(現ハイチ)で、アレクサンドル=アントワーヌ・ダヴィ・ド・ラ・パイユトリー侯爵と黒人奴隷女性であるマリー=セゼットの間に生まれた私生児のムラート(混血)で、トマ=アレクサンドルと名づけられた。デュマは、生前何度も著作権訴訟を起こされている。デュマが混血者であることから、共作者を黒子と称して小説工場と揶揄する向きもあった。とりわけ『三銃士』で協力したオーギュスト・マケとの訴訟合戦はデュマの名誉を汚すことになった。文献研究が進展した現在では、確かに共作者は何人いたが、作品で原作者デュマの存在を否定することができないことが証明されている。 文豪アレクサンドル・デュマが執筆した「巌窟王」の名でもしられる傑作小説が、新たに映画化。“復讐劇の金字塔”とも称されるドラマチックな展開は、ロマンス、サスペンス、アクションの枠を超え、激しい情念が渦巻く“究極の人間ドラマ”として、現代の私たちの心をも揺さぶる。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.13
コメント(0)
-

トリツカレ男★無償の愛
■トリツカレ男■きみの笑顔のためらな、なんだってできる。ジュゼッペはなにかに夢中になると、他のことが目に入らなくなることから、 “トリツカレ男”と呼ばれている。ある日ジュゼッペは、公園で風船売りをしているペチカに一目惚れをする。勇気を出してペチカに話しかけるが、彼女は悲しみを抱えていた。ジュゼッペは、相棒のネズミ、シエロと共にこれまでとりつかれてきた数々の技を使ってペチカの心配事をこっそり解決していく。 いしいしんじの同名小説を原作とするミュージカルアニメーション。なにかに夢中になると他のことが一切見えなくなる男が、大好きな彼女のために、これまでに手に入れた技を使って解決していく姿を描く。監督を『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』の高橋渉が務める。主人公ジュゼッペを『か「」く「」し「」ご「」と「」』の佐野晶哉、ヒロインのペチカを『366日』の上白石萌歌が演じる。★映画メモ★★「トリツカレ男」という本があることは、今回はじめて知った。★舞台がパリっぽくて、出てくる人物も日本人ぽくない。はじめ違和感を感じていたけど、すぐに物語に入っていけた。★トリツカレといえば、去年、映画「ロボットドリームを見たとき、挿入歌を繰り返し繰り返しトリツカレたように聞いてたな・・・。■セプテンバー [日本語字幕付き]■■郡上踊り■もいつも見ている( ´艸`)・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.12
コメント(0)
-

10/5:中札内美術村(六花亭)/ナウマン象記念館/広尾町海洋博物館&郷土文化保存伝習館
■2025.10.5(日)中札内(なかさつない)美術村は、北海道河西郡中札内村にある六花亭による施設に行ってきた。カシワの林に囲まれた敷地内には美術館やレストラン、庭園などが点在している。六花亭、中札内村、大林組は、六花の森とともに地域に根ざした施設づくりが評価され、「日本建築学会賞」学会賞(業績部門)を受賞している。■真野正美作品館■2017年(平成29年)開館。児童詩誌『サイロ』の表紙絵を手掛ける画家・真野正美の作品を展示している。▲昔の農家は美しい▼*************************■相原求一朗美術館■1996年(平成8年)開館。建物は1927年(昭和2年)から1995年(平成7年)まで銭湯として使用していた「帯広湯」を移築復元したものに増築棟を併せて使用している。洋画家・相原求一朗の「北の十名山」など作品、素描(デッサン)を展示している。建物が素晴らしい!!*************************森の中の道もヘリンボーンになっているところもあって美しい!!▲こちらも道の一部で、印象に残っている。■ポロシリ■地元の農産物を使用した家庭料理を提供するレストラン。野菜好きな私たちには、ありがたいレストランだった。*************************建物もいいが道が美しい。これまで見た美術館の中で一番美しい道。■安西水丸美術館■倉庫を移築したという建物は、素晴らしかった。*************************▲廃線になった鉄道の枕木を利用したのかと思うが、歩きやすいし美しいし、エコ。■北の大地美術館■1992年(平成4年)開館。自画像公募展『二十歳の輪郭』『還暦の自画像』応募作品を展示している。▲池の周りはシーーンとして熊がいるかと心配した。▼◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■ナウマン象記念館■忠類でナウマン象の化石が発見されたことを記念して建てられた当館では、その発見から発掘までの感動をパネルや映像、復元模型等を用いて紹介しています。当記念館は、上からみるとナウマン象の姿をイメージしたデザインとなっており、中央の丸いドームの部分が胴体、四隅の展示室などが足、正面入口が頭部、玉石を埋め込んだ外壁は象の肌、『時の道』とよばれる入口までの長い歩道は鼻と牙をイメージしています。(第1回北海道建築賞受賞)『時の道』…駐車場から建物まで続く約100mの歩道の両側の円柱に、古生物の誕生から人類までの進化を記した銅板がついており、現代空間から太古の世界へのタイムトンネルをイメージしています。公園になっていて親子連れがのんびり過ごしていた。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲甘い〇が宗谷岬、青い〇が襟裳岬。広尾町は、襟裳の近くでピンクの〇部分。■広尾町海洋博物館■広尾近海の魚類や漁法を紹介する展示が充実しています。広尾町出身の大相撲第61代横綱北勝海(現八角親方)のコーナーには優勝旗や化粧回しも展示。優勝祝賀会の写真には、私の知っている人の顔が3人いてビックリ。(大阪場所で優勝したのだろう)全国的に有名な「六花亭」の包装紙の絵を描いた坂本直行の展示室もあり、作品のほか、なんと坂本龍馬の末裔であることが記されている書簡も!併設の郷土文化保存伝習館では、広尾町の歴史や開拓時代の生活を再現したコーナー、旧国鉄広尾線の記録展示などがあります。ここへ来れば広尾町の歴史はばっちり!●10129歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.11
コメント(0)
-

10/4-2:ばんえい競馬/北海道のターシャが作った紫竹ガーデン/あるある
■2025.10.4(土)-2ばんえい競馬にやってきた。この日は土曜日で開催日だ。『ばんえい競馬』は、北海道開拓時代を支えた“農耕馬”の文化と深く関係しています。当時、畑を耕したり木材を運んだりする労働力として活躍を見せた“農耕馬”は、ばん馬”という愛称で呼ばれ、北海道の人々と苦労をともにしながら、生活に欠かせない家族のような存在となっていました。全長200m、鉄のソリ、2つの坂。体重1トンの“ばん馬”が挑むのは、世界にひとつだけの力とスピードの勝負。それが「ばんえい競馬」です。▲馬同士の引っ張り合いが原点。そんな中、人々はばん馬を力自慢の“誇り”として農民のお祭りで力比べを行うようになり、次第に荷物を引く競走へと変化する流れに。それこそが現在の『ばんえい競馬』の始まりです。『ばんえい』とは『輓曳(ばんえい)』と書き、“物をひく”という意味が込められています。それにしても、わざわざ、坂を作り、重い荷物を曳かせ、馬に鞭を使う競技、動物愛護協会は、何もいわないのだろうかと思った。何も娯楽がなかった時代、一年に一度のお祭りだったらわかるけど、今は、違う。週3回、それも何レースも・・・。私は辛くて1レース見てすぐに会場を去った。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■紫竹ガーデン■北海道帯広市の郊外にある「紫竹ガーデン」は、お花が大好きな一人の女性が花につつまれ暮らしたいという想いから長い年月をかけて育て上げた北海道を代表するガーデン。18,000坪の中には2,500種の花々やシラカンバ、ホオノキなどの北海道の雑木が植えられ、1992年のオープン以来30年以上もの間、四季折々に様々な植物たちが顔を見せてくれます。2013年に癌で亡くなった私の親友も2011年に、紫竹ガーデンに行ったといって、メールで写真を送ってくれた。2013年3月に亡くなったので、ギリギリ間に合ったと彼女の夫が言っていた。▲数人の女性が植物の世話をしていた。1992年(平成4年)に観光を目的とした庭園「紫竹ガーデン遊華」を、帯広市内に開園した。2021年(令和3年)5月4日、日課の庭の手入れをしている最中、花の種を手にしたまま倒れ、同日に帯広市内の病院で、大動脈瘤破裂のため94歳で死去した。 アメリカの園芸家のターシャ・テューダーに準えて「北海道のターシャ・テューダー」「日本のターシャ・テューダー」とも呼ばれ、「ガーデン街道のグレートマザー」とも呼ばれた。長女によれば、「花畑の中で花に囲まれて死にたい」と言っていたといい、その言葉の通りの最期であった。▲庭は紫色の花が目立ったので「紫竹」という名前と関係は無かった。▼庭の外は、ザ・北海道な風景だった。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♪北海道のあるある言いたい〜、早く言いたい〜北海道の住宅街を歩くと、家の外に何やら長四角い物体を見かける。大きさは120cm×80cm×50cmくらい。長さ80cmほどの足が4本ついていて、これ、実は灯油タンク。タンクの中には灯油が入っていて、ここから出ている細い管が、家の中のストーブやボイラー(給湯器)と直結していて、暖房や給湯に使われている。●11736歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-1■然別湖(しかりべつこ)・観光遊覧船/湖底線路■■10月2日(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路■■10月3日(金)-1■ガーデン街道をゆく:帯広市・真鍋庭園/馬の資料館/あるある■■10月3日(金)-2■北海道・宗谷岬から襟裳岬の旅:愛国から幸福へ■■10月4日(土)-1■幕別町・ふるさと館/帯広発祥の地/十勝ヒルズ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.10
コメント(0)
-

10/4-1:幕別町ふるさと館/帯広発祥の地/十勝ヒルズ
■2025.10.4(土)-1■幕別町ふるさと館■ 幕別町ふるさと館は、昭和54年(1979)に、町の歴史資料を保存・展示する施設としてオープンしました。▲開拓時代に使われた道具の数々が幕別のフロンティア・スピリッツを伝えます。▼これは縄ない機。うちにもあってよく縄をなっていた。ふるさと館には、その当時の小作人が住んでいた「きまり小屋」(実物を館内に移築)が展示されています。この小屋の名前は「6坪の決まりきった大きさの家が十数戸建っていた」ということから、そう呼ばれていたと伝えられています。開拓時代に田畑を掘り起こした鍬や、うっそうと茂る木々を切り倒したのこぎりと斧、バター製造の歴史を刻むバターチャーン(牛乳をかき混ぜる道具)など、ふるさと館に展示されている資料と生活用品はどれも歴史を語る貴重な財産です。 館内に移築・保存している「きまり小屋」は、晩成社途別農場の小作人小屋で、現存する唯一の実物です。「きまり小屋」という名前の由来は、間口3間・奥行き2間の6坪の”決まりきった大きさ”の家が十数戸建っていたことから、と伝えられてます。▲畳などもなく家の中は、板の間と土間▼▲「ふるさと館」の近くには、地元の有志の俳句の碑がずらりとならんでいるところがある。▼◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆帯広駅から北東へ2.5kmほど。帯広国道38号線沿いの東9条南5丁目交差点の三角地帯に「帯広発祥の地」の碑が立つ。北海道開拓を目的とした晩成社を創設した勉三らがこの付近(オベリベリ)に入植したのは明治16年(1883)。13戸27名から、帯広の歴史が始まった。明治政府主導で屯田兵が置かれた北海道の他の都市とは違い、民間の移民で開墾が始まった。▼帯広開拓に尽力した依田勉三の句。「開墾のはじめは豚と一つ鍋」が記されている。「豚と同じものを食べていた」との碑の言葉のとおり開拓は困難を極め離農が相次ぎ、わずか2年で開拓農家は3戸にまで減ってしまった。勉三の開拓は必ずしも成功とは言えなかった面もあるが、農業以外にも畜産や木工など帯広発展の礎を築いた。▲帯広市・中島公園の依田勉三像。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■十勝ヒルズ■花と農と食がコンセプトの十勝ヒルズに行った。名前のとおり、小高い丘の上にある十勝ヒルズ。*スカイミラー*まずは十勝ヒルズを象徴するフォトスポット「スカイミラー」で、ブルーサルビアが彩る美しい庭。深い色合いが印象的なこのガーデンの見ごろは8~10月。*とんぼ池*園内の奥にあるのは、昆虫のパラダイス「とんぼ池」。水面には、西洋シロヤナギやスイレンが張り巡らされ、夏になると多くのとんぼが行き交う様子がみられます。花と農と食がコンセプトの十勝ヒルズというだけあって、トラクターに乗ったカボチャ男( ´艸`)と、たわわに実ったリンゴの木▼▲カボチャの飾りも今の季節にピッタリ。豊作って感じ!▲道が少し盛り上がっている。木の根がはっているいるんだろうな。▲コッツウォルズの塀のような石積み。▲黄色い椅子がアクセントになっている。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-1■然別湖(しかりべつこ)・観光遊覧船/湖底線路■■10月2日(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路■■10月3日(金)-1■ガーデン街道をゆく:帯広市・真鍋庭園/馬の資料館/あるある■■10月3日(金)-2■北海道・宗谷岬から襟裳岬の旅:愛国から幸福へ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.08
コメント(0)
-

10/3-2:北海道・宗谷岬から襟裳岬の旅:愛国から幸福へ
■2025.10.3(金)-2北海道を宗谷岬から襟裳岬までの旅の途中。■愛国駅■愛国の駅名の由来は地名から。当地を開拓した「愛国青年団」の愛国が土地の名前になり駅の名前になった。ホームには「愛国から幸福ゆき」の乗車券をかたどった駅名標が作られていた。1973年(昭和48年)3月、NHKの紀行番組で幸福駅とともに、縁起の良い地名として取り上げられたことで、全国的な人気を博した。駅舎横にある切符型の記念碑。1978年(昭和53年)7月、「愛国→幸福」の乗車券発売枚数が1,000万枚を突破。1981年(昭和56年)末には1,200万枚、売上総額は9億4,000万円に上った。釧路鉄道管理局により駅前に記念碑が設置される。1987年(昭和62年)2月2日 - 広尾線の廃線に伴い廃止となる。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■「幸福駅」■現在の札内川のアイヌ語名「サッナイ(sat-nay)」に「幸震(さつない)」と当て字し、後年音読みの「幸震(こうしん)」を村名としていたが、福井県人の入植が多かった土地であること、また「将来の幸福を願う意味もあって」、「幸福」の地名が生まれたとされている。*福井県の入植者が多いことと幸福という名前のつながりが分からない。現在も、年間20万人以上の観光客が訪れる帯広市を代表する観光スポットです。駅の跡は公園になっていて、オレンジ色の電車がポツンと止まっていた。▲今日見てきた真鍋庭園にあったカボチャと同じ色だった。この日は連泊する。この道は、何回通っただろう・・・。明日の帯広の最高・最低気温予想は、21―12度との事。大阪は、26―21度だという。食事の量を少なくしようと心に誓う。●11199歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路■■10月3日(金)-1■ガーデン街道をゆく:帯広市・真鍋庭園/馬の資料館/あるある■■10月3日(金)-2■北海道・宗谷岬から襟裳岬の旅:愛国から幸福へ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.07
コメント(0)
-

10/3-1:ガーデン街道をゆく:帯広市・真鍋庭園/馬の資料館/あるある
■2025.10.3(金)-1旭川(大雪)〜富良野〜十勝をつなぐ通称「北海道ガーデン街道」を構成する8つの庭園のうち、5つの個性豊かなガーデンを有している北海道・十勝エリア。その中で、帯広市街に位置する「真鍋庭園」は、日本初のコニファーガーデンとして知られています。▲駐車場コニファーとは、ヒノキ科やマツ科など、複数の科をまたいだ針葉樹林の総称です。▲入口の前にも針葉樹。▲入口の建物を彩るツタ。今頃は、真っ赤に色ずいているはず。▲NHK連続テレビ小説「なつぞら」の山田天陽君の家とアトリエのロケセット。▼ ▲ここにも、コニファーが。▲入口近くに、リスの家(* ´艸`)クスクス▼リスの案内で公園を歩く。▲豊かな湧き水。▼この辺りは、水が好きな柳の大木が多かった。▲ヨーロッパ庭園の部分には、赤い屋根のスイス風な家が!!1977年に、3代目の住居として建設された木造2階建ての建物。使用されている木材のほとんどは真鍋家が所有する山林から切り出された。そして、ここにも針葉樹、コニファーが!!▲ヨーロッパ庭園のお約束は、植木鉢が左右対称。▲地下約350mから湧き出る地下水によって、真正閣の手前に鯉の池が作られ、清らかな回遊式庭園が整備されています。▼北海道に日本庭園は珍しい。▲ハート見つけた!!▲背もたれが可愛いベンチ。アマビエのどこかユーモラス(⌒∇⌒)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲『イレネー号』の銅像。ばんえい競馬が開催されている帯広競馬場の敷地内にある『馬の資料館』。『馬の資料館』は、車や機械がなかった時代に活躍した“馬”の歴史が学べる施設。“馬”を通して十勝の歴史に触れてみましょう。便利な車や機械があり、生活することに不便を感じることが少ない現代。しかし、140年ほど前の開拓時代には、便利さとは一切無縁の世界。そんななか、開拓者の荷物を運んだり、畑を耕したりと大活躍したのが“馬”です。1▲ばんえい競馬の元は、こんな形だった。▲馬編の文字▲北海道ならではの農具の展示もあった。これは、肥料をまく農具。▼◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆♪北海道のあるある言いたい〜、早く言いたい〜雪止め金具は、屋根の上に積もった雪が屋根から落下するのを防ぐために取り付けられる金具のことです。降っている雪は、ふわふわしていますが、屋根に積もると凍ってしまい、塊となって屋根から滑り落ち、人や物に当たってしまう危険性があるため。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-1■然別湖(しかりべつこ)・観光遊覧船/湖底線路■■10月2日(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.06
コメント(0)
-

10/2-2:糠平湖(ぬかびらこ):幻の橋/廃線跡を歩く/悲しき線路
■2025.10.2(木)-2■糠平湖(ぬかびらこ)■1955(昭和30)年のダム建設の際に、音更(おとふけ)川をせき止めてできた人工湖が糠平湖(ぬかびらこ)。糠平湖(ぬかびらこ)の湖畔にコンクリート製の大きなメガネ橋があります。このタウシュベツ川橋梁は、帯広から十勝三股間を結んでいた士幌線(しほろせん)の廃線跡(昭和62年に全線廃止)。▲ここが線路になった。昭和34年、北海道総合計画で糠平ダムが建設され、線路が水没するため清水谷~幌加間の路線位置が高台へと変更になりました。▲現在も糠平湖周辺に数多くの橋梁が残っており、「旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群」として北海道遺産に登録されています。▼◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■糠平(ぬかびら)駅跡■北海道河東郡上士幌町にある国鉄士幌線の駅跡が、糠平駅跡。十勝北部の開拓、十勝三股の倒木などの運搬を目的に、士幌線が十勝三股を目指して建設が進み、昭和12年9月26日、清水谷駅~糠平駅の開通で開業した駅で、昭和62年3月23日、士幌線の全線廃止により、廃駅に。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲線路のあったところが歩けるようになっている。▼上士幌町は古くから林業が盛んだった地域で、士幌線は旅客のほか木材の輸送という重要な役割を担っていました。林業従事者の増加に伴って、士幌線沿線に街が形成されていった。また1950年代には糠平ダムの建設が始まり、工事関係者が移り住んだことで街がさらに発展を遂げました。しかしダムが完成したことで工事関係者が去り、さらに木材の輸入自由化によって国内林業が衰退していくと鉄道の需要がなくなり、廃止に至ったのです。上士幌町の歴史は、士幌線の歴史と密接に関わっていることがわかります。北海道の道路や線路は、囚人やタコ労働、朝鮮半島や中国人などの強制労働など辛い歴史で造られている。かつてその森の中で生きていた熊も邪魔者にして作られた鉄道が人間の勝手な理由で造られ、勝手な理由で無くなるって・・・。●12199歩■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■■10月2日(木)-1■然別湖(しかりべつこ)・観光遊覧船/湖底線路■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.04
コメント(0)
-

10/2-1:然別(しかりべつ)湖・観光遊覧船/湖底線路
■2025.10.2(木)-1朝、部屋から湖が見える。穏やかな天気で湖には波もない。然別湖(しかりべつこ)の湖畔の宿に泊まったのだ。然別湖は、大雪山国立公園唯一の自然湖で、標高810mと道内では最も高い場所にあり、最深部は約100メートル。 湖の周囲は原生林(トドマツ、エゾマツ、ダケカンバ)が取り囲み、太古の自然を今に伝えています。昔、道が無かったころは、湖を渡って移動したそうだ。木に吊ってある板を鎚で鳴らすと、近くに住む船頭が出てきて舟を出してくれるという仕組みだった。9時発の然別(しかりべつ)湖観光遊覧船に乗り込んだ。賑やかな団体が乗ってきて、聞いたら大阪からだった。((´∀`*))湖には、「弁天島」と呼ばれる小さな島があり、小さな鳥居が立っている。神秘的な湖には、貴重な魚もいる。船着き場の近くの道もよき!◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆車で少し移動して、然別湖の湖底に線路が見えるところに来た。然別湖の湖底線路は、遊覧船を冬の間に湖から陸揚げするために敷設された引き上げ用のレールです。然別湖は厳冬期になると湖全体が結氷するため、遊覧船を湖から陸に上げる必要があります。その際に使用されていたのがこの線路です。この線路は昭和20年代末にはすでに存在していたことが確認されており、全長は約20メートル。短いながらも、結氷する然別湖の環境に欠かせない重要な役割を果たしていました。当時の人々の知恵が生み出した設備が、現在では観光の目玉として注目されるようになったのです。もともと実用的な目的で作られたこの線路ですが、年月が経つにつれ、湖底にその姿を残すようになり、然別湖を象徴する風景の一つとなりました。冬になると湖が全面結氷し、線路は完全に隠れてしまいます。湖底線路の見えるところから近いところに、門があった。誰が何のために作った建物だろう。近くには、横穴っぽいのがあって、調べてみたが分からなかった。■9月26日(金)■宗谷岬から襟裳岬へ/留萌市(るもいし)/北海道あるある■■9月27日(土)-1■映画「駅 STATION」の舞台:増毛■■9月27日(土)-2■北海道あるある/鰊番屋/風車街道をゆく■■9月28日(日)-1■日本の最北端:ノシャップ岬と宗谷岬■■9月28日(日)-2■稚内:白い道/樺太記念館■■9月29日(月)■最北端の駅・稚内駅/稚内公園/ラッセル車■■9月30日(火)-1■タコ部屋の記憶/塩狩峠記念館(三浦綾子旧宅)■■9月30日(火)-2■珍名・比布(ぴっぷ)/旭川市・旭橋/ふたつの公園■■10月1日(水)■神々の遊ぶ庭・層雲峡/北海道あるある■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.03
コメント(0)
-

へび年ですから:蛇のから何を力に抜け出(い)でし
今年はへび年ですからとヘビにまつわる話を書いている。蛇のから何を力に抜け出(い)でし 正岡子規 1901(明治34)年 子規さんは、「蛇」が嫌いだった。「大阪では鰻の丼を『まむし』という由(よし)。聞くもいやな名なり。「僕が大阪市長になったらまず一番に布令(ふれ)を出して『まむし』という言葉を禁じてしまう」なんて「仰臥漫録(ぎょうがまんろく)」に書いてあるぐらいだから、かなりの弱味噌じゃな。一体、こ奴らは、どういう「力」でもってこの「から」から抜け出るのであろうかと、しげしげと、でも恐る恐る「蛇のから」を眺める子規さんなのだ。「子規365日」夏井いつき1■辰巳は天井■2■杖にからむ蛇■3■蛇篭(じゃかご)■4■干支の名前■5■♪蛇と蛙は仲良くなれぬ・・・■6■蛇の目■7■北条家の家紋「三鱗(みつうろこ)」■8■蛇口■9■巳(みィ)さん信仰:山崎豊子■10■口縄坂■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2025.11.01
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1