2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
番外.登校許可証?なんて聞いてないよ(2004-01-31)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.登校許可証?なんて聞いてないよ《解説》今日は、世間知らずのお恥ずかしい話だ。今週、うちの娘たちは、インフルエンザでバタバタと寝込ん(みんな1日で復活したのだが)だのだが、インフルエンザの場合、医者から「登校許可証」を発行してもらわないと、登校できないらしい。今日、その許可証を発行してもらってくる。たぶん、これが世の中のルールなのだろうがしらなかったのだ。こんな話は、会社の中でもある。昨日は、月末締切日だったのだが、こんなにも多くの部署でと思うほど、手続き漏れが発生していた。社外から物を購入すると、入荷と検収の二つの手続きをして、代金が物を購入した会社に支払われるのだが、最近、システムが変更になったのに伴い、この手続きミス(手続きもれ)が散見された。これらの手続きは、このシステムの画面にある「オンラインマニュアル」を見れば、分かるはずだ。しかし、これは、単に「説明している」だけに過ぎず、「理解させている」とは言えない、という事だと思う。われわれ、事務部門の人間は、「どこそこのページに書いてありますから見てください」と言いやすいが、それは、説明しているだけで「理解してもらう事にはならない」事を十分意識すべきと思った。顧客満足度をあげるためには、自分の意識から変えていかなければならない。
2004.01.31
コメント(0)
-
157.品質のとらえかたを間違っている(2004-01-30)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】157.品質のとらえかたを間違っている《解説》ソフトウェアの品質のとらえかたについて、述べられた言葉だ。ショックだった。入社以来、「ソフトウェアの品質」と言うのは、正しく、間違いなく動く事が、求められたものだ。動かないようなソフトウェアなどは論外で、世の中に出荷してからも、正しく動き続けるソフトウェアが求められてきた、と思っていたのだから当然だ。だが、「アジャイルの父として、新しい開発プロセスの流れを支援している」と紹介される人から、今日の言葉を聞いたのだ。ん~、時代が変わったのか?この人は、人々が欲しがる機能を持ったソフトウェアが、品質が高いソフトウェアと位置づけているようだ。多少、バグ(ソフトウェアが正しく動かない部分)があっても、人々が欲しがる機能を持ったソフトウェアが優れている、と言いたかったのかもしれない。この事は、ソフトウェアに対する新しい価値観かもしれない、みんなが「便利に思う」、「欲しいと思う」そんなソフトウェアが、「品質のいいソフトウェア」と感じる、あるいは思っている人がいる事。この事で、また新たな「契約の方法(考え方)」を見つけなければならない。
2004.01.30
コメント(0)
-
番外.一家団欒の安心感はパワーの源(2004-01-29)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.一家団欒の安心感はパワーの源《解説》今日の昼食は、娘たち3人が、次々にインフルエンザでダウンしたのと、妻のパートが休み、私の仕事が一息つける状況になったのが、いろいろ重なって、通常の木曜日では考えられない「一家団欒の昼食」となった。一家でのいま一番ホットな共通話題、「健康が一番」を肴に(おっとおかずに)昼食をとったのだが、やはり、一家揃って食べる食事は最高だ。午後の仕事にも、パワー全開で取り組めた。家族のパワーに、感謝。
2004.01.29
コメント(0)
-
番外.体調を崩すべからず(2004-01-28)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.体調を崩すべからず《解説》我が家に「インフルエンザ」の波が押し寄せていて、今日3人目の娘が、ダウンした。何をするにも、体が資本だ。万一の事態になっても、会社は何もしてくれない。体が、健康でなければ、夢も実現できない。インフルエンザなんかに負けるか!ちなみに、インフルエンザの波に飲み込まれていないのは、我が家では、私と妻だけだ。丈夫な体に生んでくれた。自分の両親と、妻方の両親に感謝したい。二人が元気なのは、もしかして、「頭悪い」から、だったりして。
2004.01.28
コメント(0)
-
156.大切なのはトラブル・ゼロよりトラブル後(2004-01-27)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】156.大切なのはトラブル・ゼロよりトラブル後《解説》Web新聞で見かけたタイトルだ。今、幸せな気持ちでいっぱいだ。なぜなら、自分は、ずっとこの事を貫いてきたのだから。この記事には「予想できないものは防ぎようがない」とも書いてあった。これも、そのとおりだと思っている。自分が、入社以来取り組んできた姿勢が、まさにこの感覚だ。トラブルを発生させようとして仕事をしていない以上、トラブルが何時発生するのかなど、分かりようが無い。トラブルが発生したら、なぜ発生したのかは、後回しにしても、今どう対処するかに全神経を集中していた。要は、トラブル発生時に、顧客(自分の部署では、社内の設計部門が顧客だ)になるべく迷惑が掛からないように対処することが必要と言うことだと思う。Webでのチケット販売サイト(のサーバ)でのトラブルを例にすると、以下のように記事では書いていた(要約)(1)Web顧客はチケットを予約できればよい(2)Web顧客が求めているのは、システムの安定稼働ではない(3)Web顧客は、ただ、Web上で「チケットが買いたいだけ」だ(4)そのためには、Web顧客が、チケットを購入できる方法を提供すればよく、Web顧客は、サーバの早期復旧を望んでいるのではない。ここで間違いやすいのは、もし、「Web顧客がサーバの早期復旧を望んでいる」とすると、Web顧客が「サーバの早期復旧=チケットの購入可能」と思っているだけだ。そして、その新聞は、以下のように結んでいた。(A)大事なことは、トラブルをゼロにすることではない(B)顧客の信頼を裏切らないことだ顧客のニーズにこたえていくと言うことは、世の中の「変化を許容(変化を抱擁)」しなければならない。この変化を許容(抱擁しようと)すれば、(機能追加、障害修正などで)システムには常に不具合が存在することになる。このことを前提に・トラブル後のフォローを考えて、・トラブルが発生する可能性を少しでも下げる努力をするこの二点が、トラブル対策における重要な視点ではないだろうか。
2004.01.27
コメント(0)
-
155.効率化・自動化の影に潜む自動化のパラドックスに注意せよ(2004-01-26)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】155.効率化・自動化の影に潜む自動化のパラドックスに注意せよ《解説》作業の効率化の名のもとに実施される「自動化」の影には難しい問題が残るので注意が必要、ということだ。作業や、手続きの自動化で、我々の仕事は楽になる、が、同時に自動化されなかった仕事が残るのだ。この残った仕事は、「自動化できなかった仕事」だ。当然、自動化できない複雑な作業や手続きが残ることになる。新たに自動化を進めると、作業量は全体として減るのだが、(自動化できない)残った作業は、さらに難しくなる。この自動化のパラドックスを意識しないと、仕事を楽にするために自動化したはずが、実は残った作業がさらに複雑になってしまう。残る作業も意識した上で、自動化は進めるべきだ。会社でも、システム化が進められているが、このことが意識されていないと、かえって大変な(機械に人が使われる)状態になってしまう。
2004.01.26
コメント(0)
-
番外.働きすぎている管理職は「やるべきでない事」をやっている(2004-01-25)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.働きすぎている管理職は「やるべきでない事」をやっている《解説》申し訳ないが、今日は愚痴だ。管理職が働きすぎている場合、管理職自身を働きすぎの状態に追い込むほど管理以外の事をやっていて、本来の管理の仕事がおろそかになっている、ということだ。これは、会社にとって「損失」であることは言うまでも無いだろう。管理の仕事ができないということは、管理すべき人員を管理できていないことであり、統制の面でも組織はまとめられない。統制されていない組織は、うまく機能しなくなってしまう。効率的に動けない組織は、会社にとって「損失」だ。このような状態は、部下の方からは良く見える。しかし、管理職の方からは見えないのだろうか。その管理職に進言しても、忙しいので、そのような事に陥っていることすら気づいていないようだ。我々はさらに上位の管理職に進言すればいいのか?
2004.01.25
コメント(0)
-
154.的確な情報の持つ威力はすごい(2004-01-24)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】154.的確な情報の持つ威力はすごい《解説》どんな情報でもタイミングがよければ、最高の情報になりうる、という事だ。今日は、やっと「朝の任務1周年記念」夕食会だった。家を出発する前に、「風呂沸かしタイマー」をセットして、帰宅時にすぐ、風呂に入れるようにセッティングして出かけた。食事に満足して、帰り道、じゃんけんで風呂に入る順番を決め、1番に風呂に入れる事に決まった。少し、うれしい気持ちを抑えつつ帰宅。早速、風呂に行ったら、「風呂沸きました」サインは点いているものの、風呂にお湯の気配がない。「風呂桶の栓」をするのを忘れていたのだ、またやってしまった!しかたないので、再度「風呂沸かしスイッチ」を入れた。すると、妻の情報が(ほぼ指令に近い)入ってきた。「風呂沸かしスイッチでは沸くのに時間がかかるので、風呂の設定温度を最高にしたあと、給湯口からお湯を入れよ」そうか、そのような手があったのか、と思いつつ、作戦変更。すぐに風呂を沸かす事ができ、無事一番風呂をゲットできたのだ。普段、あさの任務のおかげで、「掃除機の扱い」は家族で1番うまいと思っているが、他の部分では、まだまだ妻の方が上だ。今回のことで「的確な情報をタイムリーに提供する」ことが、どんな場合にも重要である事が再認識できた。
2004.01.24
コメント(0)
-
番外.とことん突き詰めてみた経験が自分に自信を与える(2004-01-23)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.とことん突き詰めてみた経験が自分に自信を与える《解説》勉強にしても、研究にしても、ひとつのことを突き詰めてみた経験のある人は、他の分野でも、自信を持って物事に挑戦できる、ということだ。「なにくそと頑張れた経験」が、自分を支えてくれる。なにくそとがんばったとは言えないが、1周年を迎えた「朝の任務」は、何かにつけて、自分自身に「自信」というか、「こんな事でへこたれないぞ!」という気持ちを支えていると思う。朝の任務については、今後も続けていくつもりだが、もっと、自分の能力というかポテンシャルというか、「自分を磨いてる」と(ひとにも胸をはって)言えるようなものを継続してゆかねば、と心を引き締める今日この頃だ。
2004.01.23
コメント(0)
-
153.「よく頑張った」で褒める(2004-01-22)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】153.「よく頑張った」で褒める《解説》松下幸之助は、寝る前に「疲れた」ではなく、「よく頑張った」と自分をほめていたそうだ。自分自身を正面から褒める事は、実は、自分自身にパワーを与える事になると思う。「言霊」という言葉を聞いた事があるだろうか。口をついて出る言葉自身に精神と言うか魂が宿るのだ。たとえば、最初はあまりその気が無くても、「ヨーロッパ旅行がしたい」と毎日言い続けることで、本当に「ヨーロッパ旅行に行きたくなる」というもの。自分は、キャリアデザインワークショップに参加してから、自分自身を褒める事が多くなった。自画自賛(self-congratulation)になり過ぎないように注意した方がいいかもしれないが、気持ちをハイにするには、自分自身が気持ちよくなるように褒めるのが一番だ。褒めるネタにしているのが、「$25,000のメモ」だ。ここには、今日やろうとした項目が並んでいて、作業完了したことも分かる。この中でMVPを探して、その項目の作業完了について褒めるのだ。未完了の項目があってもいい、完了した作業に対してMVPを送ろう自分自身に!30000日しかない短い人生、なるべく気分のいい時間を長くしたいものだ。
2004.01.22
コメント(0)
-
番外.恥の上塗りならぬ勘違いの上塗りで失敗(2004-01-21)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.恥の上塗りならぬ勘違いの上塗りで失敗《解説》お恥ずかしい話を披露したい。携帯電話でのメールのやり取りでの失敗談だ。最終的には、解決したのだが、勘違いが勘違いを呼び、とんでもない事になってしまった。自分は、電子メール(パソコンで使用)を使っているのだが、携帯電話でメールをしている娘に携帯メールした(これが事の発端だ)。ここで、ちょっと、解説しておくが、娘が使っているこの携帯メールは、短いメッセージなら無料なのだが、長文メッセージだと1件毎にお金がかかる。このため、なるべく、メッセージは短めにする事を求められていたのだ。(これが混乱の元だったのだが.....)家族で食事に出かけることになっていたのだが、娘の部活の時間が未定だったため、食事をするお店の予約時刻が確定できず、保留になっていた。以下私と娘のメール内容私:部活の予定は決まりましたか?娘:13:00~に決まりました。これだけ見ると何てこと無いが、このメッセージの返信に時間がかかったため、「13:00~に決まりました。」のメッセージを返信した私は、「食事をするお店への予約時刻」と勘違いしてしまったのだ。このあと、家族を巻き込んで、大変なことになったのだが、娘の返信に一言「部活の予定は」13:00~に決まりました。と返信してくれたら誤解せずに済んだのかな、と感じた。そして、今日の気づきだが、(基本的に自分がやっている事であるが)相手のメールに返信する場合は、相手のメッセージも引用しながら、自分の返信メッセージを書く事。これで、誤解をかなり避けられるはずだ。今回の事件のおかげで、普段(何気なく)やっている事が、実はとっても良いやり方である事が分かった。「失敗は気づきの母だった」
2004.01.21
コメント(0)
-
番外.ゆとりは一種の投資である(2004-01-20)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.ゆとりは一種の投資である《解説》プロジェクト管理の権威と言われているアメリカ人の言葉だ。この人の著書では、「ゆとりは一種の投資であると考えられる組織が、ビジネスを理解している」と言える、と言っている。ソフトウェア開発のように「頭で考える作業」をする人々は、仕事と仕事の合間に、息抜きというか、次の仕事に集中するための助走のような時間が必要(私自身もこの経験はある)なのだ。つまり、ゆとりがあるおかげで、集中して次の仕事に取り掛かるための準備ができ、意識を集中させて、効率的な作業ができる、と彼は言っている。まさに、そのとおりだと思う。この「ゆとり」を「何も生み出さない空白の時間」と捉えてしまうマネージャ(管理職)は、ビジネスを理解していない事になる。
2004.01.20
コメント(0)
-
152.よりよいプログラミングが世界中の困難を解決するだろうと信じていました(2004-01-19)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】152.よりよいプログラミングが世界中の困難を解決するだろうと信じていました《解説》人々が求めているソフトウェアを俊敏にそして高品質に開発できる方法を確立した、ケントベックというアメリカ人のインタビューにあった言葉だ。この人には共感できる事が多いと思っていたのだが、その理由がこの言葉を見たときに分かったのだ。どういうことかと言うと「人々が幸せになれますように」と言う気持ちが、この人の考え方の根底にあるので、この人が発する様々な言葉に、それが織り込まれていたのだ。自分の気持ちのベースにあるスタンスという言うものが、口をついて出る言葉に表れてしまうのだろう。自分も気をつけないといけない、表向き、いかに取り繕っても、心の底の気持ちが口をついて出てしまうのだから。
2004.01.19
コメント(0)
-
番外.だらだらとした時間外労働は企業に悪影響を及ぼす(2004-01-18)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.だらだらとした時間外労働は企業に悪影響を及ぼす《解説》このことばも「ゆとりの法則」にあった言葉なのだが、特に、ソフトウェア開発などの「知的労働者」に言えることだ。「知的労働者」と言われる人たちは、年俸制、成果評価などで、給与が決まる事が多く、(時間外労働をしたとしても)「時間外手当」としては支払われない事が多い。プロジェクトのマネージャが、時間外労働(残業時間)を込みでスケジュールを立てた場合、その結果は、企業に悪影響を与える、というのだ。この本では、ソフトウェアの開発を「マラソン」に例えて説明している。マラソンでゴールを目指そうとすれば、ゴールまで(休み無しに走り続けるのを前提に)どのくらいのペースで走ればいいかを考え、自分の体力・経験などから、どのくらいの時間くらいでゴールできるだろう、と予測するはずだ。誰も、「最初から全力疾走して行こう」などと思わないはずだ、途中で力尽きるのは、火を見るより明らかだからだ。それでも、ゴールを目指すには、しばらく休む必要がある。そして、この二つの走り方を比較してみると、全力疾走→休憩、の繰り返しを続けてゴールを目指したのと、ペースを考えてゴールを目指したのでは、ペースを考えてゴールを目指したほうが、早くゴールできるはずだ。さらに、全力疾走では、ゴールまで走る気力がだんだん無くなって来ることにもなるだろう。こうなると、もはや、当初の目的だった「ゴールすること」を忘れ、「走るのをやめたい」と思うようになる。会社で言えば、プロジェクトを完成させようとする前に、会社を辞めたくなる。最後に、長期間の時間外労働は、技術者の作業能率を著しく下げてしまう事も忘れてはならないポイントだ。自分も、会社を辞めたくなるなる前に、長時間残業地獄からの脱出を考えなければならない。
2004.01.18
コメント(0)
-
151.「急げ」は、組織を誤った方向へ導く(2003-01-17)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】151.「急げ」は、組織を誤った方向へ導く《解説》プロジェクト管理の権威といわれるアメリカ人の著書「ゆとりの法則」にあった言葉だ。元の言葉は、「急げ」と言うと遅くなる、なのだが、本当に意味する言葉にした。日本人は勤勉な国民だ、とされている。自分自身もそう思っていたが、この言葉を目にしてとき、気をつけなければいけない、と思った。あまりに、「急いでくれ」を連発する事の危険性を認識させられた。この本で著者が具体的に言っていたのは、あまり「急げ」を繰り返し「忙しくない者は仕事をしていない」という空気を作ってしまうと、「自分は一生懸命仕事をしている」と見せかけるために、「ゆっくり仕事をする」ことがある、というのだ。どういうことかというと、自分がこなすべき仕事がいつも手元にあるように、仕事をする速度をコントロールするのだそうだ。また、別の人は、(やらなくてもいいような)仕事を自分自身で作り出して、いつも忙しそうにして「私にはもう他の仕事を請ける余裕はありません」という行動に出る人も居るだろう。いずれにしても、仕事量の多少に関わらず、いつも忙しそうに仕事をしているが、実はそれは見せかけであり、本来やるべき事をテキパキこなしているとは言えない。これは、明らかに、「急げ」と言う言葉で、「組織を間違った方向に導いている」のだ。このように、誰もが不幸な状況になってしまわないように、人をマネジメントするためには、多少の「ゆとり」が無いとだめだ。このゆとりが無いと、みんなの心がいつも張り詰めていて、いざと言うときにも踏ん張りがきかない組織になってしまうのだ。
2004.01.17
コメント(0)
-
番外.祝!1周年記念。(2004-01-16)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.祝!1周年記念。《解説》いや~、長かったような、短かったような。初めて手に入れた「1年間パーフェクト賞」。この賞は、自分の気持ちの上で、非常に価値あるものとなるはずだ。三日坊主が、大の得意だった自分が手に入れたのだから。当然、この記録を更新知るためにも、明日以降も続けるつもりだ。この賞の受賞で、「自分も変わる事ができる」と思えるようになったのは、何か新しいことを始める際の「ハードル(←これが今までは高かったので三日坊主が得意だった)」を非常に低くする事ができた。次の目標は、TOEICの成績だ。目標目指して「継続して」取り組む事としたい。
2004.01.16
コメント(0)
-
150.ゆとりが無ければ変化ができない(2004-01-15)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】150.ゆとりが無ければ変化ができない《解説》「プロジェクト管理の権威」と言われるアメリカ人が書いた本の中に書かれていた言葉である。作業効率を上げてゆけば、ゆとりが無くなり、最終的に身動きできなくなる、という事だ。このアメリカ人は、パズルゲームを例に出し、こんな表現をしている。たとえば、3×3のタイルのうち、1枚分のタイルが無い(ゆとりがある)状態で、タイルに1~8の番号がついている。最初は、これらのタイルに書かれたこの数字がバラバラに並んでいるが、これを番号順に並び替えるゲームをする時、の事を考える。このとき、1枚のタイルが無い「ゆとり」がある場合には、このゲームが実行できるが、「効率」を追求したがために余裕が無い状態(9の数字が書かれたタイルの出現)になると、もはや、ゲームなどできる余裕が無い状態となる。昨今、世の中では、業務効率/作業効率を向上させる事を追い求めているが、この効率を追い求めすぎると、余裕が無くなり、「変化するための余裕さえなくなってしまう」ので、気を付けよう。
2004.01.15
コメント(0)
-
149.君はどう思う?(2004-01-14)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】149.君はどう思う?《解説》今朝、この大事な言葉を思い出した。栂野先生の講義(キャリアデザインワークショップ)で聞いた言葉だ。自分の意見を他人に伝えるときにこの言葉を使うと、押し付けがましくなくなる、という力を持った言葉だと思っている。栂野先生もこの言葉をGHQにいたアメリカ人から(英語で)聞いたそうだ。実は、今朝、娘の態度に腹を立てて(感情的に怒って)いた。少しクールダウンするために、少し時間をおいて(出社する直前に)、娘の(けしからん)態度について、意見を述べたのだが、最後にこの言葉を言えばよかった、と後悔したのだ。この言葉は、マジックワードだと思う。自分の独りよがり、かも知れない意見も、この言葉を使うことで、相手の意見を聞く機会を持つ事ができる。また、会議などで、意見が途絶えたときにも、使えるだろう。そして、この言葉は、コミニュケーションを広げることができる言葉だと思う。
2004.01.14
コメント(0)
-
148.校長になるにはまだまだ越えなければならない壁がたくさんあります(2004-01-13)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】148.校長になるにはまだまだ越えなければならない壁がたくさんあります《解説》校長を目指している熱血先生(女性)の言葉だ。今日、年賀状の返事が来て、そこに書いてあった近況だ。この人は、15年前、自分自身を見つめ直すセミナに参加した時に知り合った小学校の先生なのだが、現代版熱血先生である。最近は、1年生、5年生、6年生の3学年の担任しか任されないのだそうだが、1年生が一番可愛いらしい。この先生は、驚いたことに15年まえからずっと「校長先生」になるべく、夏休み中に実施される「講義」に参加したり、いろいろなイベント(校長になるために必要な「単位」のようなもの)を受けてきたのだそうだ。自分と比較して、この熱血ぶりには、あたまが下がる。現在は、学年主任を任されているらしく、それほど遠くない将来、彼女は校長先生になっていることだろう。自分はまだ、継続して取り組んでこれた経験が1年足らず。しかも、朝の任務なのだから、比較すらできないほどの差があるが、自分としては、この1年間(正確にはあと3日)継続できたことを足がかりに、もっと大きな目標にチャレンジしていくつもりだ。
2004.01.13
コメント(0)
-
147.もし、あなたが少しも変わらなければ、あなたは決して改善できない(2004-01-12)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】147.もし、あなたが少しも変わらなければ、あなたは決して改善できない《解説》あるアメリカ人の著書にあった言葉だ。1年前に受講したキャリアデザインワークショップで気づいた言葉でもある。人は、変化を相当嫌うものだ(過去の自分もそうだった)。しかし、歴史を見ても分かると思うが、変化(革命)の繰り返しだった。変化しなければ、改善できないのも事実だと思うが、人は皆基本的に保守的になってしまう。今日は、変化を起こすために「必要な仲間」の見分け方について、今日の言葉を引用したアメリカ人の著書から紹介したい。先ず、新しい変化を起こそうとすると、大きく以下の3種類の人間に分類できるそうだ。1.手放しで賛成する2.賛成してもいいが疑問あり(その変化で良くなるのか、など)3.どんな変化も起こさせないこの中で、1と3の人たちは、変化を起こす際の「仲間」にはなりえない、のだそうだ。これらの人は本の中で、「潜在的な敵」という表現をしているほどの存在だ。2の人たちは、時に文句を言ったり、愚痴っぽかったり、するだろうが、彼らを見方につけるのが、最も強力な助っ人になるはずだ。事実、我々の職場でも、業務の見直し(変化)をする際の打ち合わせで、「反対意見」だと思っていたものが、最終的には「改善提案」だったりする。そして、その改善提案を盛り込んで再調整した手続きが、職場の業務として確立してゆくのだ。最終的に、反対意見を発言した担当者の賛成を得ているのだ。現状を改善するために、変化を起こそうとするなら、「人は変化に対して反対するもの」と構えた上で、「その変化に疑問を持っている人を見方にする」と良い。
2004.01.12
コメント(0)
-
146.ソフトウェア開発者が幸せになるようにがんばります(2004-01-11)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】146.ソフトウェア開発者が幸せになるようにがんばります《解説》これは、自分が今の職場に異動になる際、送別会の席上の挨拶で言った言葉だ。異動した当初は、どうしたらこの言葉を実現できるのかを悩んだが、すぐに「品質」に焦点を当てれば、叶えられると思い、契約するプロジェクト1件ごとに、そのプロジェクトの難しさや実際に納品されたプログラム(ソースコード)を自分で実際に見て、取引価格の交渉をしていた。それから5年もすると時代は変わってしまい、契約するプロジェクトの件数が増加してきた。これに伴い、1件ごとに吟味して契約をする事ができなくなってきた。この頃を境に、今日の言葉を忘れかけていた。ところが、ちょうど1年前、キャリアデザインワークショップを受講して知り合ったcsfcw(http://plaza.rakuten.co.jp/csfcw/ )さんに影響され、新しいソフトウェア開発方法が存在することを知ったのだ。それ以来、「ソフトウェア開発者が幸せ」になれるように行動してきたつもりだ。そして、いまは、まだ完全に確立されていない、この新しい開発手法に向けた契約方法を模索している。このために、社外にもコミュニティを広げ始めたところだ。やっと、13年前に立てた誓いを果たせるような気がしている。このためには、ソフトウェア開発手法の先端にいる米国の情報も入手できなければならない。TOEICも目標の点数に向かってさらに前に進んでいくつもりだ。
2004.01.11
コメント(0)
-
番外.やりたい事を始めるにはまずやるべき事から(2004-01-10)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.やりたい事を始めるにはまずやるべき事から《解説》仕事を(きっちり)すすめるために、自分自身で、たまに思い起こす言葉だ。人は(自分を含めて)やりたい事を先にやりたくなってしまう。最近この言葉を思い起こす回数が増えているのだが、これは、やるべき事をやっておかないと、「安心して」やりたい事ができなくなっているのだと最近気づいた。これは、「$25,000のメモ」のおかげで、身についたのだと思う。このパソコンに「$25,000のメモ」のデモ版をインストールしたので、従来の「紙のメモ」も「電子メモ」になって、まさに電子化されている。「PCが無い場所でメモを見られない」という難点はあるが、電子的に保存されているし、後で、メモ一覧を表示したりメモを加工したりできる(今開発のお願い中)「$25,000のメモ」を使っていると、目の前のやるべきことを明確にすることができるので、自分の目標をどのように実現しているかも見えるようになる。目標に向かって、どんな事をどのくらいやっているのかが把握できれば、不足している部分にパワーを投入すればいい。
2004.01.10
コメント(0)
-
番外.朝の任務1周年記念秒読み(2004-01-09)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.朝の任務1周年記念秒読み《解説》悪い癖、自画自賛である。1年前(1/16)から始めた、「朝の任務」いよいよ1周年記念だ。今振り返ってみて、1年間続けられるなんて思っていなかった。というより、割と気楽に始めた部分があったが、いままでに2回ぐらい「サボっちゃえ~~~」という悪魔のささやきがあったが、「自分がやろうと決めたことに例外を作ってはならぬ」とか、「やり遂げさせてくれ!」と言った言葉で、何とか乗り切ってきた。もちろん、この成功の影には、家族の協力もあったわけだが、正直言って、この任務を1年間続けてきたことで、自分自身の中で「結構やるじゃん」と自分自身にエールを送りたい気分になっている。あまり、大きな声では言えないが、1周年記念まであと「7日」、今度の「一周年記念」夕食会は、どこに行こうか.....
2004.01.09
コメント(0)
-
145.事実を正確に正しくつかむ事が重要(2004-01-08)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】145.事実を正確に正しくつかむ事が重要《解説》これは、尊敬するある会社の取締役のKさんと接するたび、講演を聴くたび、に頭に浮かぶ言葉だ。人は、得てして、自分の思い入れなどから「色眼鏡」でものを見てしまう。これでは、事実を正確に正しくつかめなくなってしまう。正確に事実をつかめないと「判断を」誤ってしまう事になる。だから、先ず、現実を正しくつかむ事が重要、ということだ。今、新しいソフトウェアの開発方法を実践し、世の中に広めようとしているのが、尊敬している取締役のKさんなのだ。Kさんは、自分の実践(成功例)をもとに、この新しい開発方法を世の中に広めようとしている。しかし、この新しい開発方法というのが、まだまだ世の中に浸透していない。さらに、新しい開発方法を正しく実践しないことが原因で、その開発方法は「あまりよくない」と評価されてしまっている部分もあるようだ。Kさんを尊敬するのは、Kさんが「この開発方法は万能ではありません」と言い切り、自分の信じる開発方法も「色眼鏡で見ていない」点なのだ。私なら、じぶんがほれ込んだものなら(欠点を隠してでも)勧めてしまうところだ。また、自分の悪い癖で(たまにはいいが....)「自画自賛」がある、このような事態に陥ったときには、Kさんの顔を思い浮かべることにしよう。
2004.01.08
コメント(2)
-
144.目にしたものはすべて信じるしかない(2004-01-07)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】144.目にしたものはすべて信じるしかない《解説》目に入ってくるものは、事実だ。だから信じるしかない。しかし、見たくないものもあるだろうが、見てしまったら、やはり信じるしかないだろう。信じると言うことは、その事実を受け入れる事でもあると思う。今日は、受け入れることで、かえって前向きに行動してしまおう、という話をしたい。実は今日、部内で「ある業務に関わる担当者だけ」の会議をした。そのときのことなので、ほぼノンフィクションだ。紙(の書類)で、社内手続きの依頼をしている業務があるのだが、その手続きを(いまはやりの)「書類の電子化」を進める会議をしたのだが、みんなの意に反して「大反対」する担当者が現れた。みんなのけぞった(これが事実:避けて通りたかった)。ところが、反対の理由を聞いたり、どうすべきと考えているのか、と言ったやり取りをする中で感じたのは、半分以上「書類の電子化」に向け考慮すべき問題点だった。(これも事実)私は、今日の会議を「これが会議だ」と思って参加していたのだ。私が、異動していまのグループに来たときに感じた「コミュニケーション不足」が、今日の会議では、微塵も感じられなくて、大変いい気分だった。また、この会議の中で、その「大反対の人」とも、業務上のプロ意識についても議論できたし、個人的には非常に満足できる会議だった。ただ、少し残念だったのは、「大反対した担当者は会議に参加させるべきでなかった」という意見が出ていたことだ。ここで、今日の言葉が、登場するのだが、「大反対の意見」に一度はのけぞったが、その後の議論で、自分たちがある程度想定していた手続きを「軌道修正するための意見」も手に入れることができた、のだ。この二つの事実を平等に見ることが、自分の未来を少しでも明るく(失敗をできるだけ回避させる)することができるのだと思う。
2004.01.07
コメント(0)
-
143.実際に繰り返しやってみる事で情報を知識にする(2004-01-06)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】143.実際に繰り返しやってみる事で情報を知識にする《解説》年末に受けたセミナーで仕入れた言葉だ。情報を見たり聞いたりしているだけでは、知識になっていかない、実際に体を動かし、体で覚える方が、忘れにくいし知識として蓄積されやすい、ということだ。実際には、ソフトウェアの開発手法を会得するための効果的な方法として、紹介されていたのだが、自分が取り組んでいる「英語力強化」策としても、応用できる方法と思った。というより、体で覚える方法は、忘れにくい。実際、「英語力強化」に向け、「日本人用英文法則」の習得に努めていたが、「テキストを読むだけ」から、「その英文の意味を解釈しつつ書いてみる」方法に変えた途端、自分の記憶への定着が強くなったような気がする。ただ、まだまだ反復していかないと、「忘却の彼方」となる単語、熟語があるので、反復のサイクルを見ながら、適宜復習してゆくつもりだ。今月TOEICを受けるので、馬力をかけて取り組みたい。
2004.01.06
コメント(1)
-
番外.仕事はじめの日に休むべからず(2004-01-05)
!【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.仕事はじめの日に休むべからず《解説》これは、母親の教えだ。会社員になったのなら、仕事始めの日に休んではいけない。その理由は以下のとおり。(1)正月気分を早くぬく →長い休み明けはエンジンがかかるのに時間がかかる1日でも 早く「通常モード」で仕事ができるようになれ!(2)年始の挨拶が大変になる →仕事初めの日に出社しなかったために、職場の全員に挨拶回り これが(暗黙の)義務になってしまうちなみに、今日は「仕事初め」もちろん出社した。そして、職場全員に年始の挨拶をする方法として、ずっとやっている事、それは、「土産配り」。通常は、自分だけ休みを取って休んだ時しか「土産は買わない」が、年始だけは、この目的のために、みんなに配ることにしている。職場の全員に言葉をかけることができる手っ取り早い方法として、自分としても気に入っている。昨年の暮れ、8人の人が異動で増えた。これらの人たちは、仕事柄会話する機会が無いが、今朝かけた一声を足がかりにコミュニティを広げてゆきたい。職場に仲間を増やすことで仕事をよりスムーズに進める事ができる。
2004.01.05
コメント(0)
-
番外.祝!日記開設6ヶ月記念(2004-01-04)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.祝!日記開設6ヶ月記念《解説》今日は、自画自賛の日にしたので、あしからず。朝の任務といい、この日記といい、よく続いたと感心する。(・o・)/何がうまくいった原因なのだろう、と思い起こすと(思い起こさなくても)浮かんでくるのが、「$25000のメモ」の存在だろう。このメモに、その日やる事を(前日に)書いておく方法だ。シンプルながら、なかなかの「優れもののメモ」だと思う。昨年、このメモの存在を教えてくださった、栂野先生に感謝したい。また、このメモの「パソコン版」を開発している栂野先生のワークショップを受講したメンバがいて、そのうち、Vectorにアップロードする計画があるとの情報も入っている。(機能について少しコメントした)毎日、物事を続けられない人にも、このメモは有効で、今日やる事の項目の最後に「明日のメモを書く」を毎日書くことで、メモ同士のリレーができてしまうのだ。あとは、毎日しようと決めた事(何項目でも)を毎日そのメモに書き、やれたらそのメモの欄に「花丸」をつけて、自分自身を(よくやったぞっと)褒める。(三日坊主が得意だった)自分の経験からすると、3ヶ月くらいで慣れてきて、やることに抵抗がなくなってくる。6ヶ月くらいで、ほぼ習慣化してくる。9ヶ月を過ぎてくると、だんだんそれをしないと落ち着かなくなる、というか何かし忘れているような気がしてくる。12ヶ月を越えてくると、まだ未体験ゾーンなので分からない。ただ、これだけは言えると思う。このページを見る事ができる人なら少なくとも「10年以上」人間として生き続けてこられた人たちばかりのはずだ。「これからやり始めよう」という気持ちと行動で、そのことをやり続け、そしてやり遂げる事ができるはずだ。
2004.01.04
コメント(0)
-
番外.物を大事に使うにも限界がある(2004-01-03)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.物を大事に使うにも限界がある《解説》物を長年大事に使っても、所詮限界がある、と言う事だ。ものを大事に使う事は大事なことだが、物を大事にするあまり、別の部分がムダにしているものがあるかも知れない。正月は、いつも帰省している。今日の言葉は、実家の掃除機のことだ、もう30年近く使っている。実家の床(というか畳)をこの掃除機で、大晦日に掃除機をかけたのだが、スイッチを入れたとたん「ゴミ捨てサイン」がでたので、掃除機の中のゴミを捨て、フィルタの清掃を実施して、再度、掃除機のスイッチを入れた。なんと、「ゴミ捨てサイン」が出た。仕方なく、この掃除機で清掃開始。ところが、なかなかホコリをすわないような気持ちのまま、清掃作業を進めたが、いよいよこれが無謀だった事が分かった。掃除機のモータが回る音は立派なのだが、「吸引力」が非常に低かった。掃除機の吸引口を手で押さえても、大して吸い付かないほど、弱い吸引力だったのだ。このとき、物には、(いくら大事にしても)限度、と言うものがあると思った。今日、新しい「掃除機」を実家にプレゼントして、帰宅した。実家では、古い掃除機を修理に修理を重ねて、大事に大事に使ってきたのだろうが、掃除機のモータを回して使う電気に見合わない程度の仕事しかしていなかった。この事に気づかなかったら、消費電力に見合わない掃除しかできなかったろう。これは、仕事にも言えることで、コストパフォーマンスの悪い作業は、やめてしまうか、新しい仕事に取って代わらせるべきものがあるかも知れない。
2004.01.03
コメント(0)
-
142.私は(いつも)経営者のつもりでいるのだ(2004-01-02)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】142.私は(いつも)経営者のつもりでいるのだ《解説》アメリカのある研究部長の言葉だ。社内企業家になれ、ということだ。会社員である以上、基本的に自分の仕事に「損益」が付いて回るだろう、この「損益」をもう少し意識すれば、社内企業家になれるだろうし、経営という立場で、仕事を見つめなおしても、いまの仕事がもっと面白くなるはずだ。自分自身の今の仕事では、(事業部ではないので)直接「損益」に関わる事はできないが、間接的になら、関わる事ができる。今年は、いまの仕事に面白さを見出して、進めて行こうと思う。
2004.01.02
コメント(0)
-
141.やる気のパワーを活用せよ(2004-01-01)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】141.やる気のパワーを活用せよ《解説》正月らしい、勢いのある言葉になった。人の持つ「やる気パワー」がすごいので、これを使わない手はない、と言う事だ。昨年、再放送番組をぼ~っと観ていたのだが、一切お金のかからない「ダイエット法」があると言うのだ。NHKのためしてガッテンでやっていた方法なので、この番組を観た人も多いと思う。この方法が、すごいのは、「人間の潜在能力」を利用して、お金をかけず(特別な薬や器具を使わない)に実施するやり方にある。そもそも、人間が太るのは、「物を食べる」と言う基本的な欲求を満たし過ぎる(ようは食べ過ぎ)のが原因の大半だ。この食べ過ぎを毎日の「体重測定」で抑制してしまう方法なのだから安上がりである。番組の説明では、「物を食べる事による」快感を「体重を減らす事による」快感に摩り替えてしまうことで、ダイエットで一番難しいとされる食事制限を自らの体重測定によって、コントロールしてしまうのだ。これは、仕事や他の事にも使えるのではないか?と疑問が湧いた、というか、思い付いた。普段、やらなければならないのだけれど、「つまらない」と考えている事(仕事の中に多く存在したりする)を見直して、面白そうな部分を探し出して、「つまらない」ことを面白がってやってしまう。これは、結構いけそうな気がする。早速、仕事始めから試してみることにしたい。
2004.01.01
コメント(1)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-
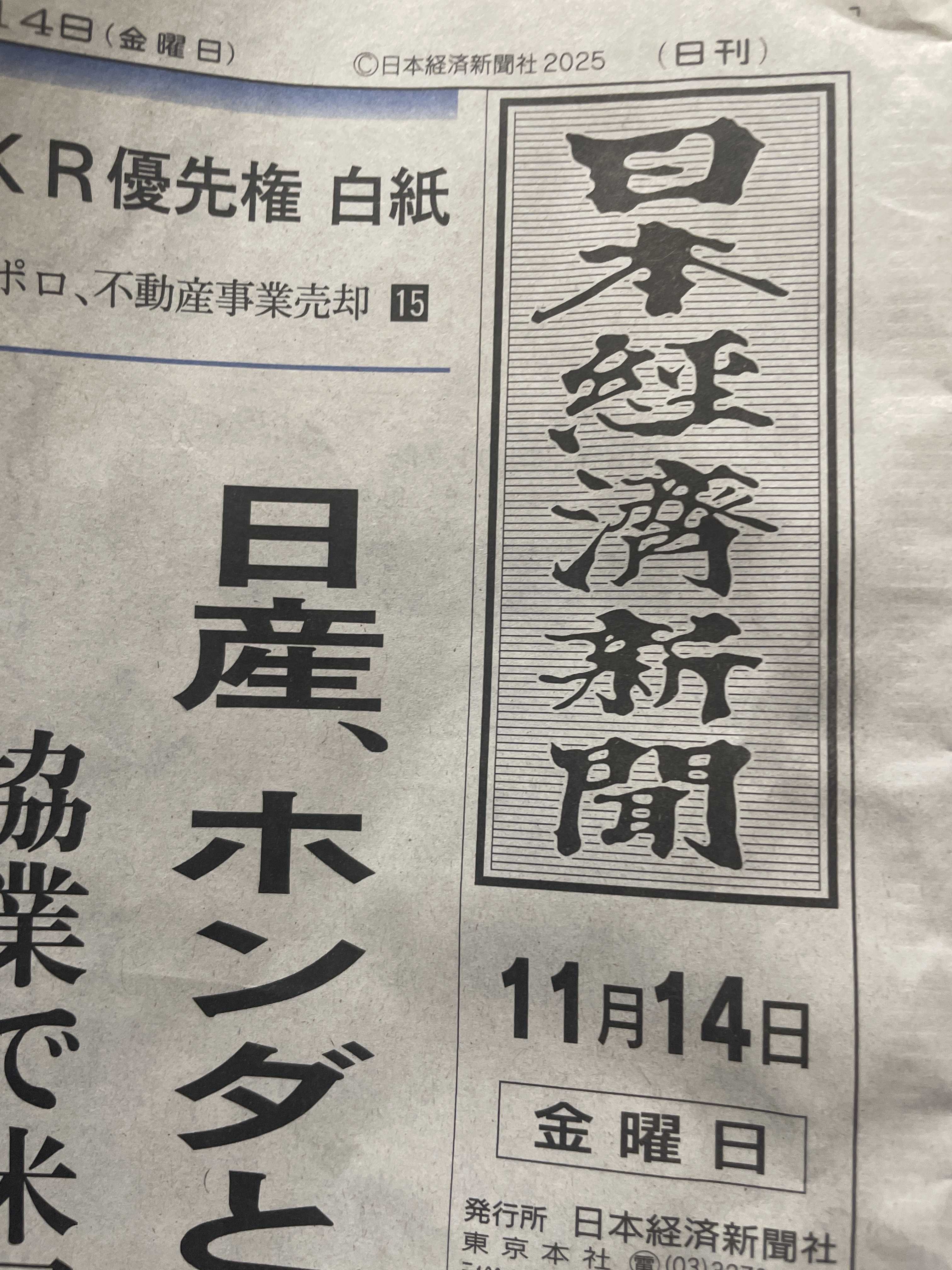
- ★つ・ぶ・や・き★
- 戦争やりたきゃ、てめえがやれ
- (2025-11-15 01:07:19)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 2026年福袋!数量限定🧦選べる 靴下…
- (2025-11-14 21:17:02)
-
-
-

- 楽天写真館
- 辿り着いてできたもの
- (2025-11-15 00:00:10)
-







