この空の下で 9
彩子は、翔が後ろを通っていった気配を背中に感じながら、何となく彼も彩子を認識していたように感じた。
一樹と千鶴を引き合わせた数日後、彩子は翔の顔を初めて見ることになった。
9月1日。彩子のいる研究所に新しく川村翔が配属になった。
朝、9時半過ぎに翔は、所長と部屋に入ってきた。
180センチ近いすらりとした体格で、すっきりとした顔立ちで紺のスーツがよく似合っていた。
他に40代の主任研究員が2人配属になった。
この移動に伴い、研究員や研究員の補助をする女性職員の席が配置換えされた。
彩子は一樹の隣になり、一樹の仕事を手伝うことになった。
『嘘でしょ?』と、彩子は、嫌な気持ちになった。
翔は一樹の後ろだった。
彩子の後ろは正職員の22歳の女性だった。
青木由美子。色白でぽっちゃりした感じでちゃきちゃきした女の子だった。
彼女の趣味は食べ歩きでおいしい所を沢山知っていた。
3時のお茶に出すお菓子にも彼女なりのこだわりがあった。
彼女のこのこだわりのおかげで他の職員たちは珍しいお菓子に巡り会えることができた。
これが官庁の研究所というところなのか、彩子は3時になると椅子を後ろに向け由美子とおしゃべりしながらお茶を楽しんだ。
彩子には翔に視線を向ける勇気さえなかった。
彩子は3歳年上の兄と二人兄弟だった。
子供の頃から両親と兄からかわいがられ、家の中ではちょっとしたアイドルかお姫様扱いだった。
時にそれは彩子にはいつまでも子供扱いされていると感じさせた。
特に母親は彩子をかわいがった。
子供の頃から母親は彩子を連れてよく出掛けた。
二人きりで外食することもあった。
夏になると彩子は母親お手製のワンピースを着るのが楽しみだった。
母親は、女子中、高校に通う彩子にかかってくる男の子からの電話や手紙や遅い帰宅にはうるさかったが、他のことには余り口出しすることはなかった。
彩子の方も両親を怒らせるようなことはなかった。
就職する時もアルバイト程度で、何か習い事でもしたらという感じだった。
そんな両親や兄の態度が返って彩子に経済的にも精神的にも自立したいという気持ちを駆り立てた。
いつも家族から愛され満足していたが、それが自分の手枷足枷になっているのではないかと彩子は感じることもあった。
家族の愛の中で育った純粋な強さと弱さを持った彩子だった。
引き寄せられる二人
翔に出会う前にも何となく好きになった相手はいる。何度となく交際を申し込まれたこともある。
でも、いつも彩子は『いつかこの人と思える人に会えるはず。
そう思える人に会えるまで道草はしない。』と。今では、化石的思考といわれるかもしれないかもしれない。
翔が回覧板をもって一樹の席の前に来た。
「いつ紹介してくれるの?」
「分かっているって。」
隣の席で彩子は資料の整理をしていた。
『私のことかな。』
彩子は、お昼休みに隣の部屋の理彩と一緒に外でランチした。
いつもは社内食堂で昼食をとっているが、時々、外に食べに出掛けた。この日は日比谷公園の松本楼へ行った。
公園はお昼休みを楽しむ人がたくさんいる。9月に入っても残暑が厳しい。レストランの中はクーラーが効いていて涼しい。
「やっぱりカレーかな。」
「そうだよね。あと、アイスコーヒーも。まだまだ昼間は暑いね。」
「そうそう、彩ちゃん、今度、省内のテニス大会があるんだけど出ない?テニス習っているじゃない?」
「習っているけど、大会に出るほどうまくないわ。だって、サーブが入らないもん。試合にならないわよ。」
「多分、川村さんも出ると思うよ。」
「そう。」
「私、彩ちゃんと川村さんってお似合いだと思うんだけど。一緒に出てみたら?」
「うぅん。でも。」
「この間、一緒に食事するの駄目になっちゃったじゃない?あの後何かないの?川村さん何か言ってこないの?」
「うん。別に。」
彩子はさっきの翔と一樹のやりとりについて理彩に話さなかった。
「川村さん、彩ちゃんのこと気になっていると思うよ。テニス大会、出た方がいいよ。私、研究所のとりまとめ役だから、彩ちゃん出ることにしておくからね。」
「えー!私・・・・。」
数日後、いつものように3時のお茶の時彩子が後ろを向くと、
「森川さんテニス大会に出るんだって?多分、一緒にダブルス組むと思うけれど、今度一緒に練習しに行かない?」
一瞬、彩子はどう反応したらいいのかとまどってしまった。
素直に「はい。」と喜んで答えたかったのに周りが気になってぎこちない返事になってしまった。
「えっえぇ。」
翌週の日曜日に調布にあるテニスコートへ行くことになった。
彩子は、後ろの席の由美子を誘った。由美子も翔に心を寄せていることを彩子は知っていた。
何となく自分だけ抜け駆けするような気がして由美子も誘ったのだ。
調布の駅で午後1時に待ち合わせた。翔がコートの予約をした。彩子が調布の駅の改札を出ると翔がもう来ていた。
「こんにちは。待たせてしまいましたか?ごめんなさい。」
「いえ、今来たばかり。電車の乗り継ぎがよくて早く着いたんだ。」
「私、テニス習っているんですけれど、サーブも上手に入れられない程度なんです。なのに大会に出るなんて。」
「大丈夫。今日練習すれば。下からのサーブでいいんですよ。ならできるでしょう?」
「ええ。」
そこに由美子が小走りで改札を出てきた。黄色のワンピースで可愛かった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
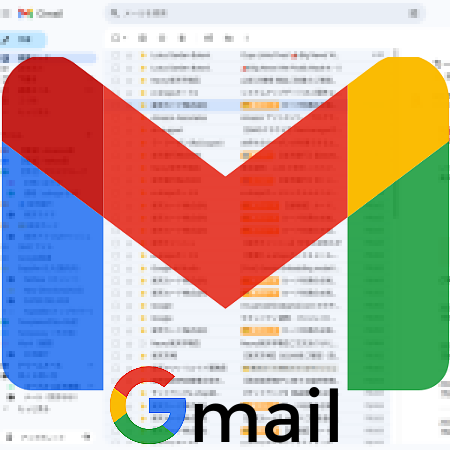
- ニュース
- 2026年1月 Gmail仕様変更! 他ドメイ…
- (2025-11-17 21:04:31)
-
-
-

- つぶやき
- 一回買ってみようかな。
- (2025-11-17 20:09:06)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 元NMB48・本郷柚巴“大人になった”素…
- (2025-11-17 23:00:05)
-
© Rakuten Group, Inc.



