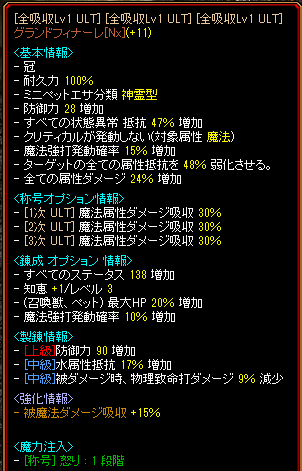ウクバールにて-タコヤキ編
(1) マッギーの葬儀の間、イエローは参拝者ひとりひとりに向かって丁寧に頭を下げていた。 レッドも列に混じって焼香していたが、イエローはそれに気が付かなかったのか、他の人と同様に対応していた。 話しかけるチャンスがないわけではなかったが、オレは特に話はしなかった。 ふと、オレの名前を呼ぶ声が聞こえた。 オレは香典を整理する手伝いの手を止めて、声の主を探した。 見覚えのある顔が、オレの方を見てニヤけていた。 高校の頃、マッギーとウラで『タコヤキ』と呼んでいた、いけ好かないヤツだ。 「久しぶり。遠いところご苦労様だな。」 オレはそう言った。 こいつがやって来るとは意外だった。 遠方で居を構えたと聞いていたし、だいいちそれほど親しくしていたわけでもない。 「遠いけど、こんなことでもないと帰ってくる機会もないんでね。」 (なるほど。。。このあと同窓会でもやるのか。。。) 「そうだな。たまには顔出しておかないと忘れられちまうからな。」 なぜか、あまりにもマトモな返答をしてしまった。。。 コイツが相手だとどうも調子が狂う。 「ところで、後で時間とってくれないか?折り入って頼みたいことがあるんだ。」 タコヤキのくせに、意外なことを言う。。。 生憎だが。。。と言いかけて、ヤツの後ろにいるのはその奥さんと子供らしい、と気が付いた。 「10時以降だったら駅前の『ウクバール』にいるよ。」 とりあえず、オレがいつも飲みに行く場所を教えた。 ヤツもそこは知っているらしく、安心したような表情をした。 (2) ウクバールというのは実際にある地名かもしれないが、マスターの話ではJ.L.ボルヘスの小説に出てくる架空の地名からとったらしい。 エキゾチックな屋号だが、特に変わった酒が置いてあるわけでもない。 いつものバーボンを頼み、音楽に耳を傾けた。 (友人の葬式の後で『Left Alone』は聞きたくねえな。。。) オレは、グラスを明かりにかざして曇りを点検しているマスターに話しかけた。 「なぁ、マスター。思い出ってやつは厄介なもんだなぁ。」 「そうだとも言えるし、そうでないとも言える。 なぜなら、ノスタルジーというのは個人的なものであり、多くの場合感傷的なもので、確かに厄介ではあるし場合によっては非常に気の滅入るものではある。しかし、『時間』というものは常に過ぎ去っていくものであり、過去を振り返る行為というのは、人類が『時間』というものに対して行うささやかな『抵抗』と言えなくもない。」 「・・・・」 いつもの少し早口で、それでいて淡々とした調子でそう答えた。 オレは少し異論を挟みたい部分もあったが、黙って聞いていた。 10時を10分ほど過ぎた頃、タコヤキが店の入り口から顔だけを覗かせた。 「やぁ、盛り上がってたかい?」 オレがいるのを確かめてタコヤキはそう言った。 「お前が来るまではな。。。」 タコヤキは気を悪くした様子もなく隣に座り、オレと同じものを注文した。 「待たせたかな?」 気を使っているつもりなんだろうか。。。 「別にお前が来るのを待ってたわけじゃないさ。 この時間には大抵オレはここでこうしてる。」 オレはそう言って1杯めを飲み干した。。。 人差し指を立ててグラスを置く。おかわりのサインのつもりだが、マスターは見逃すことも多い。。。 (3) 「まさか、オレに用事があって遠いトコはるばるやって来たなんて言うんじゃないだろうね?」 「そのまさかだよ。」 タコヤキは少し照れくさそうにそう言った。 高校生の頃、コイツは何人も彼女をこしらえては、得意気にあちこち連れ歩いていた。 それを見かける度に、オレ達はひがんで、「タコヤキのくせに。。。」といつもコソコソ毒づいていたものだ。 「女性関係でのトラブルならゴメンだぜ。 テメエのケツはテメエで拭くもんだよ。なぁ、マスター。」 マスターは聞いていないような格好で、ビールを片手に持っていた。 「同感だが、それがままならない状況っていうのもよくある。 こんな状況でどうすべきか、そんな時に客観的な意見をきいてみるのも全く無意味とは言えない。ただ、当事者にとっては重大問題であっても、関係のない人物にとっては所詮他人事であって、協力できる部分とできない部分がある、というのは事実であり、問題解決につながるような回答は期待すべきでないのかもしれない。ある程度自分で結論を出しておいて、その正当性を確認するというのが実際のところのように思われる。」 マスターはオレとほとんど同意見のようだった。 「そう言わずに、まぁ聞いてくれよ。」 昔とは打って変わって低姿勢なことに気がついた。オレは話の続きを待つことにした。 「高校生の頃、俺はお前に嫉妬してたよ。。。 お前は自分に気がある女の子の事は見向きもしなかった。 そして、みんなから好かれるように努力するとか、無理するとかってことにはまるで無縁だったのに、お前のことを悪く言うヤツはほとんどいなかった。 俺はそれがずっと気になってたんだ。」 オレに気がある女の子なんて初耳だったし、オレのことを悪く言っていたヤツをオレは何人か知っている。 「そんな話でオレが、この上なくいい気分になって、『これからはどんな事でも協力させてくれ』って言うとでも思ってるのか?」 「ははっ。相変わらずだな。」 タコヤキは笑っているが、どこまで本気なのかつかめなかった。 さっき見かけた奥さんと子供(らしき2人)の表情も気になっていた。 「さっき一緒に居たのは奥さんと子供かい?」 「まぁね。」 ニヤけた表情が少しひきつった笑いに変わったのがわかった。 (4) 「話を聞かせてもらおうか。 お前の頼みっていうのが何なのか、今のところ、おそらく奥さんに関することだろうってことしかわからない。」 タコヤキは軽く1回うなずいた。 いつも絶やすことのない口元のうすら笑いが消えていた。 「実は、ストーカーのターゲットになっているみたいなんだ。 ただ。。。」 タコヤキは少し口ごもった。 どうやらその先はあまり楽しい話ではなさそうに思えた。 オレは気が重くなってきたが、それでもそんなとこ話を切り上げる訳にもいかない。 「ただ? 1日に何十回もイタズラ電話をかけてくるとか、1600ミリの超望遠レンズで遠くから姿を拝んでいるとか。。。 そんなそこいらにいるようなストーカーだったら、わざわざオレに会いに来ておべんちゃら言ったりはしないね。」 タコヤキは、今度は2回ゆっくりとうなずいた。 「誰も信じてくれないだろうと思って、今まで誰にも話してないんだ。 お前だったら、笑わないで聞いてくれると思ってたよ。」 そう言って、さっきから手をつけなかったバーボンを一口すすった。 「1年ほど前から毎晩、妻は夜中に突然起き出して、パジャマのまま靴も履かずに家から出て行こうとするようになった。 妻の話では、誰かに手を引かれているらしい。 後姿だけははっきり見えていて、手を引くのはあまり見覚えのない男の後姿だって言ってた。」 タコヤキはガラにもなく、慎重に言葉を選びながらそこまで話し、また一口すすった。 「夢遊病じゃないのか? 少なくともここまでの話では、ストーカーによって被害にあっていると言えるような状況ではない。。。」 タコヤキは続きを話すべきかどうか少し考え込んでいるようだった。 オレは話を少し変えてみることにした。 「ストーカーといえば。。。マスター、タルコフスキーの映画で『ストーカー』っていうのがあったよな?」 「あれは。。。1979年に制作された映画で当時はまだソ連だった。この映画の中では”ストーカー”と言うのは今使用されているような意味ではなく、”密猟者”の意味のほうで使われていていて、”ゾーン”という謎の場所へ連れて行く”水先案内人”のような人物をあらわしていた。」 「ラストも良くわからなかったが、超能力を持っているような少女が出てきたよな?」 「おそらく主人公のストーカーの娘、ということだと思われるが、一人でテレキパス(念力移動)を使っているシーンがあった。そのシーンの間にはチュッチェフの詩が朗読されていた。確かにその意図はつかみようがない。」 話を聞きながら、オレは2杯目のバーボンを飲み干した。 (5) この店では、棚に並べてあるグラスはいつ見ても光っている。 おそらくマスターのこだわりなんだろう。。。 毎日そいつを、端から順番にひとつひとつ取り出してはじっくり時間をかけて磨き、何度も灯りにかざして点検を繰り返す。 ようやく気に入った状態になるとグラスを棚に戻し、次のグラスにとりかかる。 どうも、ただのグラスに対する扱い方とは思えない。 その動きはまるで。。。 アナログレコードをターンテーブルから丁寧にジャケットに納めて棚に戻し、別のレコードを物色して、とっておきの一枚を取り出して慎重に針を載せる。。。 そんな姿を連想させる動きだった。 最後のグラスを棚に戻すと、マスターはいつもミックスナッツを一皿サービスしてくれる。 自分も同じものをつまみながらビールを飲むためだ。 「おそらく全国紙に載るような事件ではないから、お前が知らないくてもムリはないんだけど。。。 うちの近隣では女性が失踪する事件が、知ってるだけでこの2年で5件発生した。」 オレは、知らないと答えた。 その後タコヤキは詳細を話し始めた。 話をまとめてみると、だいたいこういうことだった。 タコヤキは奥さんの異常に気付き、車で外に連れ出して夜を明かす、という日々を過ごしている。 夜中に自宅にいなければ大丈夫だと考えたらしい。 その知り合いの場合も、奥さんの異常には気付いていた。 奥さんのその行動が始まってから一晩中見張るようにしていた。 ただ、5日目に寝込んでしまって、熟睡している間に出て行ってしまった。。。 翌日捜索願を出したが、残念ながら手がかりもなく、連絡もないまま1カ月が過ぎた。 タコヤキの説では、少なくともこの2人の間には何らかの接点あるいは共通点があり、そのために何者かにターゲットとして選ばれたのだ、ということだった。 「2人の接点あるいは共通点が何なのか俺なりに調べてみようと思う。 その間、妻は実家に預けて置こうと思うんだ。 実家にいれば問題ないとは思うが、ただ、何が起こるかわからない。 だから、君を頼ろうと思ったんだよ。」 オレは少し時間をおいた。 酒をひと口飲み、タバコに火をつけた。 「困ったな。。。 断る口実がみつからない。」 (6) 自分でも、その時どうしてそんな事を言ったのかわからなかった。 後から考えてみると、口実なんかはいくらでもある。 マッギーの葬式を終えたばかりだ、というのもあるし、差し迫って金が必要と言うわけでもない。 しばらく南の島でバカンスなんていうのも悪くない、なんてさっきまで考えていた。 「そうか。助かるよ。ありがとう。 実は、お前が引き受けてくれるとは、正直思ってなかったんだよ。 他に仕事を抱えている、とかそういった意味じゃなくて。。。」 「言っておくが、報酬は受け取らないぜ。 これは仕事じゃない。 オレが1人勝手に気まぐれでやることさ。 今夜、お前はこの『ウクバール』へは来なかった。。。そういうことにしてくれ。それが条件だ。」 報酬ももらわずに誰かを見張ったりするような行為は、ただの物好きだ。 見方によればどっちがストーカーだかわかったもんじゃない。 そんなことは重々承知した上で、オレはそんな条件を出した。 タコヤキは腑に落ちないような表情で酒を飲み干し、オレの方をじっと見た。 顔色をうかがっているらしい。。。 「わかった。 それじゃ、俺はもう帰るけど、今夜はオレのオゴリにさせてくれ。 見ず知らずの客が、飲んでるうちに気分がよくなって他の客の分まで払った。。。そういうことでいいだろ?」 オレは、ヤツのしたいようにさせて帰らせる事にした。 (何言ってやがるんだい、タコヤキのくせに。。。) ただ、内心ではそうつぶやいていた。 タコヤキが帰った後、オレは手元のグラスと棚に並べられたグラスを見比べながらただボンヤリとしていた。 騒々しい酒場で、全身がタコヤキをかたどったカブリモノを着たタコヤキが、その場にいるひとりひとりに車代を配っている様子を想像してみた。。。 「なぁ、マスター。。。オレは、さっきのヤツが相手だとどうも調子が狂うんだ。 どんなもんだろうね。」 「Je est un autre。。。」 「私とは他者である、か。。。ランボーだね。 あんなヤツごときに惑わされるのはオレらしくないってことかな?」 「『自分らしい』とか、『本当の自分』などというものに固執するのは良くない。例えば、今こう思った、ということがあっても、数分後にはそれとは矛盾する考えに支配される事もある。考え方の傾向であれ、行動パターンであれ、所詮は人間のすることは恣意的というか気まぐれというか。。。それならばいっそのこと『他者である』としてしまえばいい。」 いい考えかもしれないが、少し異論を挟みたくなってくる。 マスターが何か言い切ったような時はいつものことみたいだ。。。 そんな事を考えながらも、次第に考えはタコヤキの奥さんに付きまとっているというストーカー(密猟者)のことのほうに移っていった。 |
© Rakuten Group, Inc.