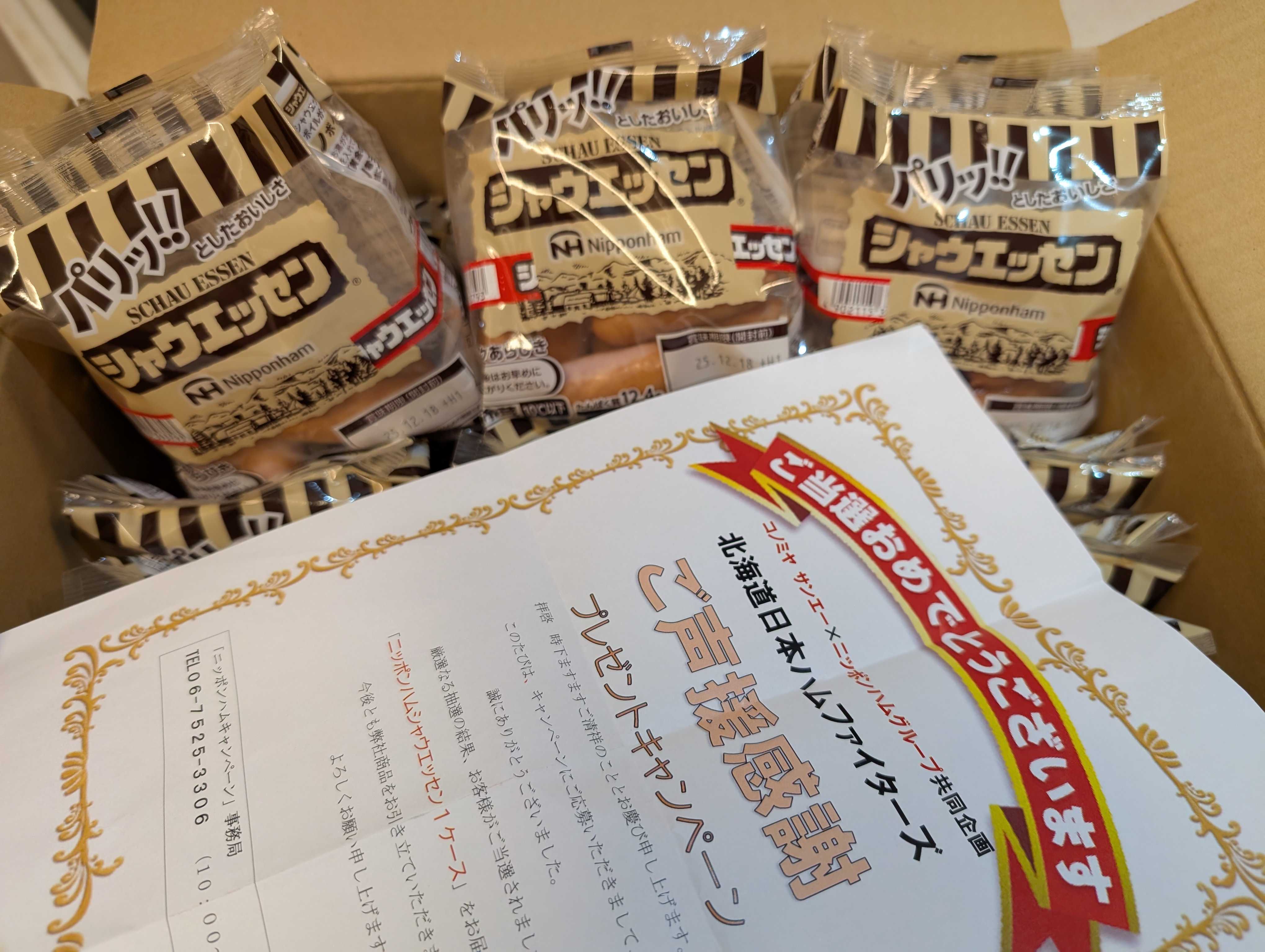政策提案1(風通しの良い組織)
「風通しの良い三重県庁」にするための提案活用制度
【現状と課題】
三重県では、ワークショップ、ベンチマーキング、オフサイトミーティングなどの手法で、職員のアイデア、提案を募り、それを政策、施策に反映させる試みを講じている。
しかし、アイデア、提案に見るべきものが少ないためか、または、アイデア、提案を活かす制度が不十分なためか、中々、職員の発案により実施されたという、政策、施策、事業にお目にかかれない。(産業廃棄物税はその数少ない例か)
これは、一般職員の提案がトップや担当部局長に到達するまでに何らかの形の障害があるためと、考えられる。つまり、提案者の原案が、どこかの段階でセレクションにかけられ、ふるい落とされ、却下されているケースがあるためではないだろうか。
もちろん、それらのアイデアは玉石混交だと思うが、それを判断する権限がある人の目に触れる前に消滅してしまうとしたら、多大な損失といわざるを得ない。
【趣旨又は目的】
ブレーン・ストーミングでは4つの基本ルールがある。(アレックス・F・オズボーン)①批判厳禁 ②自由奔放 ③質より量 ④結合改善の四つであるが、それは他人の意見を批判せず、思いついたことを自由に言い、質や内容よりもまずは多くのアイデアを出し、場合によっては他人のアイデアに便乗したり、アイデアを組み合わせたりしようとするものである。
それはバカバカしいようなアイデアが本当によいアイデアであり、たくさんアイデアが出れば中にはダイヤモンドのように光輝くものが混じっている可能性があり、また、他人のアイデアを聞くことによって結合や改善の発想ができるからである。
このことは庁内でのアイデアや提案の募集制度にも同じことが言える。エントランスの部分ではできるだけ審査を加えずに、まず、生のアイデア、提案をトップ(三役)や担当部局長まであげる。
所属長の段階で適否の判断を加えないことによって職員としてはアイデア、提案を出せばトップの目に触れるという機会を保証をすることで発案のインセンティブが高まる。直接の上司の方としては職員のアイデアに否定的立場をとる場合はなぜ採用できないかということを自ら実証的に説明しなければならないようにすることにより、部下の提案を真剣に聴く態度が養われると思われる。
部下が面白いことを言ったとき、上司が潰すのであればその責任だけはきちんと取るということを制度化する。
【政策の概要】
①上司に部下の提案を却下するときには、挙証責任を負わせる制度
部下の提案に対して「NO」と言うときには、理由をつけなければならないとする。 このことによって、上司としては「ノー」と答えることに対しての実証的な理由が必要となる。そういうものをつけなければならないとなると、まず、部下の意見や考えをよく知ろうとする。と同時に、論理的な言葉にする、すなわち形式知にする訓練が上司に生まれ、自治体経営に緊張感がみなぎるという効果が期待できる。
[参考:3Mの提案制度]
②現場(直接の担当者や地域機関)が提案したらトップが即決する制度
現場が提案したらトップが即決するというプログラムで、アッパー・ミドルの壁を飛ばして自治体革新をしていくという仕組みで、現場のミドルの活性化にもつながる。即決にする理由は、自分の言ったことが二年も三年もたらい回しになったままでは、担当者はやりきれない。それがトップの面前でプレゼンの上、即決となれば大きな達成観が生まれる。
変革の必要性を知っているのは現場の人間であり、その提案に対して中間管理職が判断を下すのではなく、トップが責任をもって即決するようにする。
[参考:GEのワークアウト]
③部下に上司との一対一のミーティングを要求できる権利を与える制度
部下は上司に一対一のミーティングをリクエストし、上司はそれに最優先で応えるようにする。アイデアがたくさん出るには「人と違ったこと」「変わったこと」「バカにされそうなこと」でも自由に発言してよいという雰囲気をつくることが重要であり、それには職員の多様性を重視した自治体風土づくりが欠かせない。それにはまず、直接の上司が応える制度を保証することである。
[参考:インテルのワン・オン・ワンミーティング]
【具体化に当たっての課題】
・新しいことや、前例のないことをやることに対しての漠然とした懸念、危惧という類の組織としての消極姿勢
・ボトムアップでの提案、アイデアに対して中間管理職としての判断を要求される立場
・部下の提案を積極的に上層部へあげていこうとする姿勢に欠ける組織体質
PS)サントリーの佐治社長は、「トップに上がってくるのは、角の取れた丸い氷ばかり」との表現で、尖ったアイデアも上へ上がってくる段階で面白みがなくなると懸念されている。下手に枝葉末節にこだわらず、そのままトップへアイデアを上げることが大事だと思う。
© Rakuten Group, Inc.