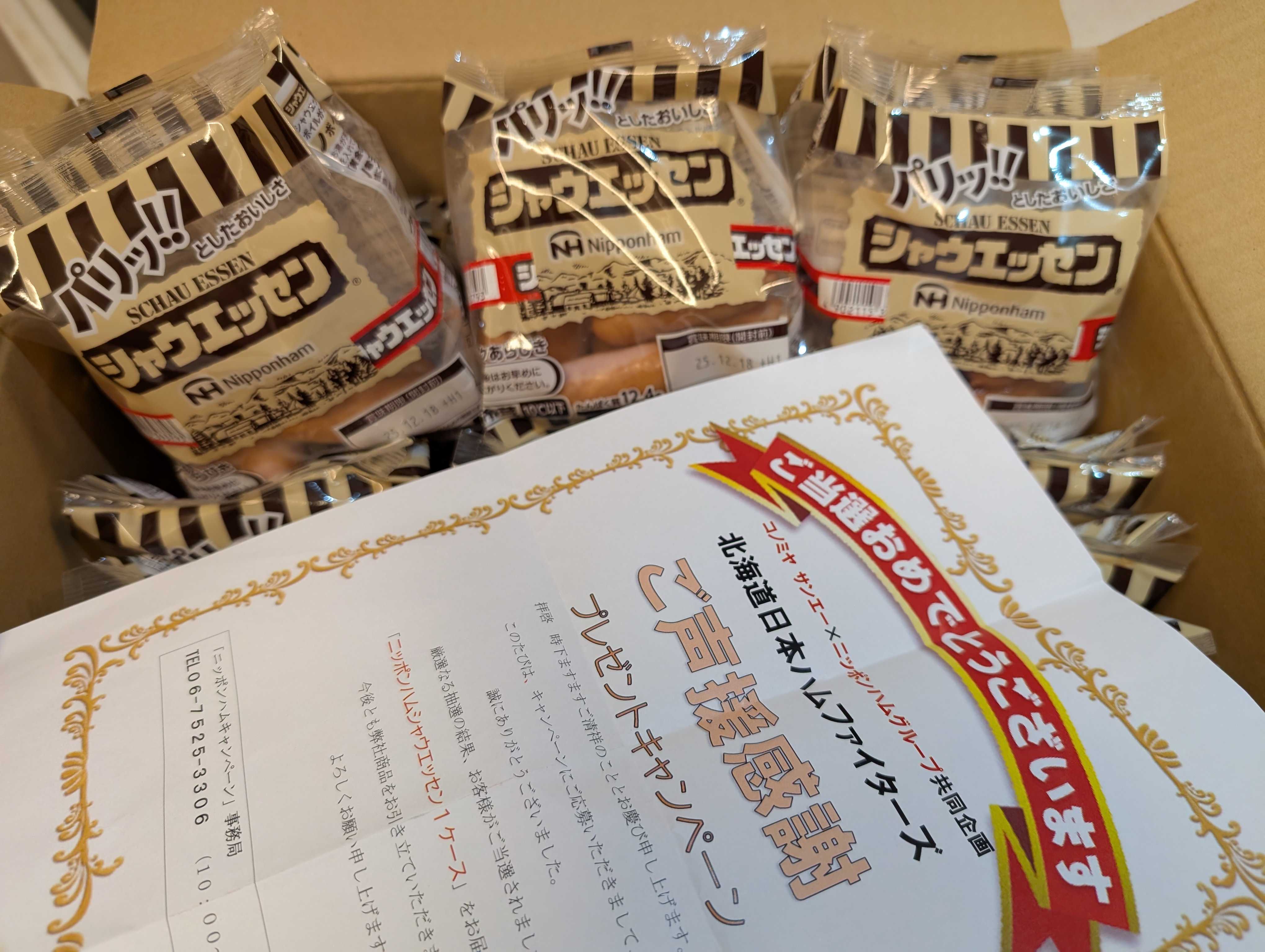CS関係で感動した本
著者名:藤ジニー
出版社:幻冬社
紹介:「来てよかったです」とお客様が喜ぶ一流のサービスについて話します。
感想:以下の点に共感しました。
・コミュニケーションをスムーズにするためのマニュアルなのに、それに忠実になりすぎて、お客さまに不自由な思いをさせては意味がありません。マニュアルはアメリカではじまったものですが、日本ではちょっとまじめに取り組もうとしすぎているのかもしれませんね。
・ルールというのは、お互いが気持ちよく過ごすための約束事であって、一方をただ怒らせるだけでは意味がないように思います。不愉快な思いをしたお客さまは二度とお店に足を運びませんし、「あそこはサービスが悪い」と口コミで広がるかもしれません。もてなす側が決めたルールはときどき見直したほうがいいかもしれませんね。
・見直すとまでいかないまでも、ちょっとしたものの言い方と柔軟な対応で、お客さまの気分を害さずに済む気もします。これは決まりですから、というかたくなな態度でつっぱねては、気持ちよく受け入れていただくことはできません。
・嫌々ながら対応していると、困ったことに、「態度が悪い」「対応がなっていない」などど問題がよけいにこじれてしまうことにもつながります。はじめから非のうちどころない完璧なサービスなどないと思いますから、お客さまによくなるコツを教えていただきながら、成長する努力をすべきではないでしょうか。(以上)
書籍名:超顧客主義
著者名:片平秀貴 古川一郎 阿部誠
出版社:東洋経済新報社
紹介:ヤマト運輸、ホンダ、資生堂、アスクル、スタバといった活気ある企業に共通する経営の極意を説きます。
感想:以下の点に共感しました。
・「私が泊まりたいホテルをつくる」という哲学は、当時も今もフォーシーズンズを支えている。「私はホテル業者としてよりホテルを客としてみてきた」と、シャープ氏は『日本経済新聞』のインタビューに語っている。
・さらに、「最高のサービス品質を維持する秘訣は何か」との質問に、「自分がされたいように顧客にして差し上げる、これに尽きる」と語っている。
・本田技研工業(ホンダ)の創業者、本田宗一郎氏は、徹底的なお客さま第一主義で知られている。このことは「120%の良品」と題する次の文章に如実に表れている。「100%を目指したのでは、人間のすることだから1%程度のミスをする。その1%の製品を買ったお客さんには、100%の不良品をお売りしたことになる。だからミスをなくすために120%を目指さなければならないのだ」
・「われわれの会社はピープルドリブン(人間が引っ張る)だ」と言うホンダの吉野浩行氏は次のように語っている。
「会社からこう言われているが俺たちはこうしよう、という部分が多い。そういう点がホンダの一つの特徴であり、なんでこういうことになるかというと、もともと会社の成り立ちがそういうものに近いからである。創業者である本田宗一郎は自分のやりたいことをやったという感じだった。それが会社の文化・DNAになり、夢を持つ人々を惹きつける。会社のためというより自分のために働けということはわれわれの会社では当たり前のことである。われわれが自分のやりたいようにやる。自分の未来は自分で決めるというのが基本だ」
<ヤマト運輸>
(元会長小倉昌男氏)
・わからないことを一生懸命考えても駄目だ。わからなければやってみればわかる。それ以来、「やってみればわかる、やらなければわからない」が私のモットーになっています。
・社内で標語をつくりました。わかりやすく。「サービスが先、利益は後」という標語です。利益のことは考えてくれるな、と。利益のことを考えると、サービスがほどほどになる。だから利益のことは一切考えない。
・要するに、会議で月の営業成績報告の時に、収支のことは一切言わない。ただ配達のスピードをチェックしていく。翌日配達できたかできないかのチェックは、きっちりとやりました。
・とにかく、いかにサービスを大切にするか。サービスの差別化ということをやかましく言いました。競争だよ、ただしコスト競争ではなく、サービス競争だよ、サービスの差別化。とにかく、サービスが他と違うところを見せなければいけないと口を酸っぱくして言いました。
・売り手と書い手は全然論理が違うのです。売り手がいくら当社のサービスはいいですよと言っても、買い手がいいなと思わない限り絶対駄目です。買い手が本当にいいですね、と言ってくれて初めて良いサービスといえるのです。
・何を大事にするか、そういう優先順位をつける。何でも第一の社長は駄目なのです。売上第一、利益第一、品質第一、従業員第一、その都度その都度第一が変わってくるわけです。それでは駄目なのです。
・第一をはっきりさせるためには、第二を出して、そこはちゃんと説明をつけるようにしなくてはならない。経営者というのは、説明をしなければいけないのです。なぜこういうことなのか、と。なぜサービスが先で、利益が後なのか。「なぜ」を説明する能力がないと、社長は務まらない。それが説明できて初めて社員が納得するわけです。
・みんなが喜んで稼いでくれる会社にするためには、経営理念がしっかりしていて、しかもそれをきちんと説明できなければいけない。コミュニケーションが大切です。
・経営理念というのは、紙に書くものではない。それをよく説明し。社員がみんな体で覚えて実行すること、それが経営理念です。口でうまいことを言い、紙に書いてあることを暗記しようとしてもしようがないのです。お客さまが大事だということは、理屈でとまってもらっては困る。それが日常の動作に出てこないといけないわけです。
・革新には従来の延長線上からの飛躍が必要であり、過去を否定・破壊してこそ新しいものが創造できるのである。
・本田宗一郎氏は「99の失敗の上に1つに成功が生まれる」と言って、自らの失敗(実際売れない製品が倒産の危機を招いたこともあった)だけでなく、若手の失敗にも寛容であったという。
・超顧客主義は決して顧客にこびへつらうことではない。顧客に共感と感動を与える「本物」をつくるためには「開発チーム」に「超顧客」を取り込まなくてはならない。
・「本物」が革新的であるならば、市場調査から得られる情報は、開発者の夢の実現をサポートする役割を果たすことはあっても、開発者の夢をつくり出すことはできないことをこのケースはよく物語っている。
<伊東屋>
(代表伊藤高之氏)
・私はブランドではなくのれんだとか、看板だとか、お客さまの評判だとか、そういうものが商人にとっては命よりも大事なことだと思うが、では何をもってその店のブランドらしきもの、のれんらしきものを具現化するかと言えば、人間と人間の関係であると思う。
・伊東屋には「ないもの帳」というのがある。これは店員がポケットの中に持っている小さなノートのことで、お客さまの要望する商品がなかった時、次は用意しますという意味を込めて「ないもの帳」に書き、そしてそれを仕入れに伝え、それが伊東屋に置くべき商品であれば早速仕入れる。
・伊東屋には「一つからお売りします」というスローガンが掲げてある。一つから売るというのは、たとえば10個入りで1箱、こういう商品の形態が文房具には多い。この一つから売るというのはわれわれが自分でメーカーからもらった商品を全部箱を破りばらばらにして一つずつ売るということ。
・また、ぽち袋も10枚1セットのところをばらして1枚3円から4円くらいで売っている。そうすると銀座の伊東屋で使えるお金の単位は1円玉からある。これはやはりポリシーであって、常にお客さまの立場にたって余計なものをお買いになる必要はないということ。
・「スーパーカスタマー」は上得意ではなく、カスタマーでありながらわれわれが教えられる、あるいはその方が一言言うことによってわれわれの商売に何らかの好影響がある。社会的に知名度が高いとか、この方が言うんだから、と世間が納得するような良識と見識を持った方である。(伊東屋)
・本当に大切なことは言葉で伝えることはできない。それは、現場におけるさまざまな直接体験を通してしか伝えることができない。
・ディズニーランドの「ファイブ・スター・カード」では、幹部社員が現場で良い対応をしているキャストを見かけたら、このカードを渡す。カードをもらったキャストらは。2~3ヶ月ごとに開かれる社内パーティに招かれて、その喜びを分かち合い、経営陣に賞賛されるのである。
・また、「スピリット・オブ・東京ディズニーランド」という制度では。従業員同士でゲスト対応に優れた人を選出し表彰することによって、一体感を醸成している。
・金銭的なインセンティブだけでは、ブランドを愛する気持ちを生み出すことはできない。金銭的なインセンティブに頼ると、給与や待遇の極度な社内格差を顕在化させ、従業員間のねたみ・ひがみを生み出すことになりかねない。
・「理念に基づいて特に努力した従業員に、賞賛で報いる」といった会社への献身を引き出す仕組みを持つと同時に、会社による優秀な従業員の認知は、他の従業員の心の中にロールモデルと憧れを抱かせる。
・組織の中で自分が求められている存在であると感じさせるためには、マニュアルが少なく、従業員自身に十分な裁量権が与えられていることが必要である。
・現場における臨機応変の対応でよく知られた事例は、リッツ・カールトンホテルである。リッツ・カールトンでは客室係に2000ドルの決裁権限が与えられている。リッツのホスピタリティが賞賛の的になるのは、単にそのお金でクレームへの迅速対応・得意客への特別サービスができるからではない。
・お金の使い道はいくらでも工夫の余地がある。客室係に権限を持ってもらうことで、「それを何に使ったらお客さまに一番喜んでいただけるだろうか」と日々工夫しながら仕事をしてもらうための仕組みづくりに寄与しているのである。
・新しいことに挑戦したいと思っていても、実際には失敗を恐れて未知の領域にどんどん踏み入っていく姿勢を保ち続けられる人は少ない。しかし、組織にチャレンジ精神を持った人が少なくなれば、その企業は十分な競争力・活力を維持することはできない。したがって革新し続けるためには、チャレンジする文化を構築しなければならない。
・恐らく10%から20%くらいの人々だけがものすごくハッピーで、残りの80%から90%はアンハッピーというような組織が発揮するパワーと、それに対してほぼ100%の人がそこそこ同じくらいハッピーな組織が発揮するパワーとどちらが強いかといったら、私はやはり後者だろうと思う。それはホンダのもともとのカルチャーのようなものもそうだったということで、そういうようなことを最近力を入れてやっている。
・企業という組織は個人の願望を自己実現してもらう場、そこで働く人たちがそれぞれの夢なり希望なり人生でやりたいことなどをたくさんもつ場である。
・スターバックスのキーワードの一つは、「サードプレイス」という言葉です。これは造語でわれわれの社内の言葉です。米国でもずっとこのコンセプトでやっておいます。
<スターバックス>
(元スターバックスコーヒージャパン代表取締役専務兼 COO好本一郎氏)
・われわれのお店をお客さまにとっての「サードプレイス」にしたい、という夢です。お客さまの住んでいるところ、すなわちわが家が「ファーストプレイス」、出てきて社会とのかかわりのあるところ、多くの方は会社だと思うのですが、これを「セカンドプレイス」とすると、ちょうどその中間に当たります。
・家の外ではあるのだけれど、何かホッとできるところ。自分を取り戻せるところ。都会では時間は早く流れていくのですが、お店の中ではちょっとした自分の空間がもてる。「サードプレイス」、これがわれわれのお店のコンセプトということで共有しています。
・もう一つのキーワード。「One cup at a time,One customer at a time」、すなわち「一杯ずつ、お一人ずつ」という、われわれの呪文のようなものです。どんなに大きくなっても、どんなにいろんな地域にお店を出しても、われわれの価値というのはいっらしゃるお客さまとの一回一回の出会い、その時に出す一杯一杯のコーヒー、その質、その時の笑顔、この積み重ね以外のなにものでもない。このような呪文があるのです。
・ブランドの定義は100種類以上ありますが、ある教授によるとブランドとはお客さまとの信頼関係だとされています。私も同様に、かならず一定以上の質、ある価値あるものがもらえるという信頼関係の確立によりブランドは確立されると思います。
・数値化はできませんが、われわれは他のチェーンと比べてかなりマニュアルが少ないです。20%くらいがマニュアルで規定されていて、残りの80%くらいがお店のパートナーの自主性に任されています。マニュアルが少ないことの利点は、みんなが「これだけは守ろう」と考えることです。
<花王>
(常盤氏)
・「異質を取り込むことである。ボーダレス化とは外と内との壁が低くなる、あるいはなくなるということだ。当然今までと違った仲間が入ってきて、同質というのは許されない。外から入ってくるものは異質の世界だということを認めざるを得ない。われわれ企業は、質と質の競争をしていて、しかもそれは異質な質同士のものである」
・多くの日本企業では、「カラー」をそろえて採用され入社した新卒の新入社員が、入社年次ごとの「先輩・後輩」の厳しい上下関係の中で次第に企業風土になじもうと型にはまっていく。これを見てもわかるように、これまでは異質な人材が組織に入ることを敬遠してきたように思える。
・ホンダの吉野浩行氏はコミュニケーションについて次のように述べている。
「やりたいことをやる、個人尊重、人間尊重、というホンダの人材に関するポリシーを、組織が大規模になってからもうまく浸透させるためには、なるべく頻繁に人と接触することだ。現場に行ったり、対話する場をいろいろなところで設けたり、そういうところで自由に双方向のコミュニケーションをやることだ」
・一橋大学の野中教授によれば、組織がさまざまなアイデアを具現化し、成果を収めるためには、アイデアジェネレーター、コーチ、ポリティクストの三つの役割を担う人材が必要であるという。
・アイデアジェネレーターとはさまざまなアイデアを思い浮かぶクリエイティブな人間であり、コーチはアイデアを具現化するための方法や手順・段取りを教える。そしてポリティクストは、部署を超えた調整を行い、具現化のプロセスを邪魔する社内の障壁を必要に応じて排除する。
・多様性は重要であっても、新陳代謝の域を超えた極度な離職・転職は、組織にとっても個人のキャリアにとっても安定性と一貫性を欠いたものになりかねない。それに、そもそも社員がロイヤルティを持てない企業のブランドに、どれだけ顧客が愛着を感じるのか、極めて疑問である。
・モンゴル帝国のジンギスハンにつかえた宰相の言葉に、「一事を興すは一害を除くにしかず」というのがある。捨てることが前向きの改革には必要であり、改革とは、まず旧来のものを捨てることなのだ。
・自分たちのモノやサービスのよさを主張するには、他のモノやサービスを経験させるべきである。他を経験し自分たちのよさをわかってもらわなければ顧客はついてこない。
・これからは、個性のある質を持って生きることが大切である。それがバイタリティということだろう。米国のシリコンバレーはまさにそうで、お金も規模もなくても新しいアイデアやビジネスモデルを持った人たちが集まり、質と質がせめぎ合い、淘汰されて、良い質のものが残っていく。まさにビジネス・エコシステムである。これからはそんな時代ではなかろうか。
・単なる消費者のニーズに応えていては駄目である。消費者の言うニーズとは過去のニーズであって、メーカーに期待されている未来のニーズは消費者にはわからないものであり、メーカーが自分たちで作り出さなければならない。
・超顧客主義を志向する企業文化は、外へ向かって開く「開放系」でなくてはならない。いわゆる従来の日本型組織における企業文化は、組織構成員の同質性と内部結束力を高める方向に働き、どちらかと言えば「閉鎖系」であった。
<アスクル>
(代表取締役社長 岩田彰一郎氏)
・扱っているのはどこにでもある普通の商品なのですが、新しいサービス、新しい価値創造をしていくことで、お客さまにご指示いただいているのです。「旧商品・新サービス」というのは、まさにセブンーイレブンさんがそうで、牛乳も雑誌も日本一って言ってますけど、全部旧商品です。今まであった商品で、朝七時から夜十一時までやっているだけで、まさに生活の起爆剤といいますか、完璧な産業になっている。
・ノードストロームでのビジョンは、「どうような状況にあっても自分で考え、最善の判断を下すこと」である。従業員は厳しい目標管理と同時に、徹底的にノードストローム・ウェイを叩き込まれ、また現場で常にそのように考え、判断し、行動することが要求される。すなわち従業員は自己判断で顧客に対応するかなりの自由が与えられ、自らの工夫で顧客と交流する中で、非常に高いレベルの顧客満足を達成すると同時に、自分自身の高い満足感をも手にするのである。
・ホンダの吉野浩行氏は、「人間がすべてである。新技術、クリエーションをやるのは結局人間であって、人間がモチベートされていなければ何も出てこない」と述べている。ホンダでは、現場主義とあいまって社員の自主的な動きによって課題をクリアしていく成功事例を、数多く見ることができる。
書籍名:サービス哲学
著者名:窪山哲雄
出版社:オーエス出版
紹介:奇跡の復活をとげた北海道洞爺湖のリゾートホテル「ザ・ウィンザーホテル洞爺」の社長がサービス哲学を語ります。
感想:以下の点に共感しました。
・私は社会におけるサービスの真髄とは、「子どもに対する、親の無条件の愛」だと考えている。言い換えれば、サービスは「母性」だと思うのだ。
・私は正直なところ、「どれだけたくさんの人を集められるか」ということには興味がない。どれだけ集客するかよりも、「どれだけ一人のお客さまに深く愛されるか」ということのほうが大事だと思うからだ。
・最も心に残るサービスとは、期待を超えたサービスを受けた時である。このときお客さまは感動という一歩進んだ次元に入ってこられ、それが結果としてリピート率の向上につながることがある。
サービスには、計算されていない魅力があることが大切で、投資したコストがお客さまにとって楽しいことに使われたのであれば、それは必ず実を結ぶ。
・本当は、「何々がこんなにできる」ということはたいして重要ではないのである。そんな技術や知識は後でいい。サービスに携わる人間は、まず最初にサービスの心、哲学を理解すべきなのである。
・サービスというのは、お客さまがそれに気づかなくてもいいのである。お客さまが気づかないようなサービスはする必要はないというのは大間違いで、気づかれないサービスこそ率先して行うべきなのである。
・さまざまな企業が、いま盛んに顧客満足やサービス強化をうたっているが、それには「心技体」の「心」が必要であるほか、「顧客」を「個客」ととらえることも大切となる。「顧客」は「個客」になりたがっている。自分だけのサービスを求めているのである。
・スコットランドの詩人ロバート・バーンズは、「その国がどんな法律を持っているかよりも、その国がどんな詩や歌を持っているかのほうが私にとっては重大なこと」と言った。
・高い志を持った企業で働いていれば、そこで働く従業員の士気は高まり、人と人との触れ合いの中で人間的な豊かさが生まれてくる。またそこで育った人間が外へ出て行くとき、彼らの人間性は社会に潤いをもたらすことだろう。
書籍名:サービスが感動に変わる時
著者名:渡邉美樹
出版社:中経出版
紹介:タイトルだけ見ると「サービスが伝説になる時」ベッツィ・サンダース ダイヤモンド社の日本版といった感じだが、高杉良の小説「青年社長」のモデルにもなった著者の社員への熱いメッセージが読む者にも感動を与える。
感想:この本を読んで、渡邉美樹社長の外食産業にかける思い、お客さまに対する心情に共感し、手紙を出したところ、ご丁寧な自筆のハガキをいただいた。
やはりすぐれた経営者は、一人ひとりの顧客の声を大事にし、どんなに忙しくても答えていくのだということがわかり、ますます、ワタミのファンになり、大阪へ行った時さっそくチェーン店を利用した。
書籍名:なんとかしてよ店長さん!
著者名:ジャスコ株式会社高橋 晋
出版社:かんき出版
紹介:ジャスコの店長がお客さまの声になんとか応えようとして交わした往復書簡集です。続編に「どう答えるの?店長さん」があります。
感想:著者の「お客さまへの回答を書くときは、決して迎合するのではなく、自分がジャスコのトップであればどのように考え、判断するかという視点で結論を出せば、ほぼ間違いないと思います」という姿勢に共鳴した私は、高橋さんを訪問して「徹底と継続から成果が生まれる」との言葉を添えたサインを著書にいただきました。
書籍名:わたしはコンシェルジュ
著者名:阿部 佳
出版社:講談社
紹介:お客様のどんな疑問・要望・トラブルもホスピタリティで解決するよろず相談係の打ち明け話
感想:お客様の言うことが、正しいかどうかは、とりあえず問題にせず、「それはお引き受けできません」という答えをせず、要望にいかにしたら応えることができるか、とにかくやってみるというコンシェルジュの姿勢は、すべてのサービス産業に従事している方のみならず、住民の要望をお聞きする自治体職員にとっても参考になります。
著者の阿部さんは、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルのヘッドコンシェルジュから現在は研修担当に異動されましたが、本を読んだ感想のメールを出したところ、コンシェルジュの姿勢あふれるご丁寧な返信をいただきました。
ぜひ、一度、阿部さんの勤務されるホテルに宿泊したいものです。
© Rakuten Group, Inc.