<リーダーが発したい言葉>
「リーダーが身につけたい25のこと」鈴木義幸著ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン
■本などからの引用 ○私の意見)
■ホンダの創業者である本田宗一郎さんは「マイルストーンを設定して目指
しても永遠にそこを追い抜くことはできない。そうではなくて、いかに他とは違
うものをつくるかが大切だ」という主旨のことをおっしゃっています。
○他を目標にするのはいいことですが、追い抜いた後、追われる身になった
後の目標を決めておかないとそこから伸びなくなります。
■ビジョンを構築するために最もいい方法は、たくさん話すことです。ふだん
よく話を聞いてくれる同僚や友人をつかまえて、とにかくビジョンを描くことを
目的として話してみる。
○人に話をすることで、漠然とした自分の考えがまとまるし、自分では気づか
ないような意見を聴けるという効果があります。
■「世界一強くて、世界一みんなに好かれるゴルファーになりたい」と石川遼
さんが作文に書いたのは有名です。
○強いだけではなく、「好かれる」という目標がいいですね。
■神戸大学で組織論を研究している金井壽宏教授がおっしゃっているように
「忙しいからビジョンが描けないのではなく、描けないから忙しい」のだとする
と、一度、本気でビジョンを描くための時間をとってみてもいいかもしれません。
○これは木こりと斧、料理人と包丁の関係にも言えますね。道具を研いでいる
暇がないのではなく、道具をしっかり手入れしないから忙しいのです。
■リーダーが身につけるべき行動特性のひとつに、「必要なときに必要な決断
ができる」ということがあります。
部下の側に、「上司に対する不満は何ですか?」と聞くと、非常に多くの人が
「自分の上司は決めてくれない」と答えます。
○決断をしないのであればリーダーである必要はありませんね。
■当然のことながら、決めるときには「責任」が伴います。
自分だけに影響が及ぶことであれば決断できても、他人を巻き込むような
事柄に対しては決めることができないという人がいます。
責任を追及されることを避けたいと考えるからです。
○責任は取りたくないけれど権限は欲しいというのは相容れないことです。
■リーダーの大きな仕事のひとつは「方向を指し示すこと」です。大きなもの
から小さなものまで、他人に影響が及ぶようなジャッジをすることが常に求め
られます。それは、責任を引き受ける覚悟が常に求められるということでもあ
ります。
○英語で言えば、ディレクターでしょうか。方向を指し示すには、大きな責任
が伴います。その責任に耐える覚悟がなければリーダーは務まりません。
■たとえば、「今週1週間、どんな小さなことでも決めるシチュエーションが訪
れたらすぐに決める」と、自分に約束します。
○私はせっかちな性格なので、家族や友人と食事に行ってもさっさとオーダ
ーを決める方なので、いろいろ迷っている人をみるとイライラすることがあり、
むしろそちらの方を改めるべきかなと思っています。
■リーダーはときに、組織の命運を左右する決断に正面から向き合わなけ
ればなりません。「瞬間的にすぐ決める」必要はなくても、検討する時間が無
限にあるわけではない。その時点で考えられうる最善の決断が求められま
す。少ない時間を有効に使い、結論に至らなければなりません。
そこで、次のような自分への質問がシミュレーションするために役に立ちま
す。
・決断するためにはどんな種類の情報が必要か?定量データ?定性データ?
それとも生の声?
・誰から、あるいはどこから情報を集めるか?直属の部下?他部署の部下?
上司?顧客?それとも、他社事例やビジネス書、グーグル?
・何年先までの影響を考慮に入れるか?
・「歴史」にどのように学ぶか?
・最終的にはどんな「軸」で決めるのか?
○どんなにデータを集めても100%間違いない予測ということにはなりません。
そうであればどの時点で決断するか?50%の確率であればリスクが高すぎ、
80%を超えるまで待つと同業他社に先を越される可能性があります。
■かつて私がコーチングをさせていただいた、ある複写機メーカーの営業部
長がいます。どんなに数字が落ち込んでいるところも、彼はV字回復させてし
まう。彼はそんな凄腕の持ち主でした。
V字回復の秘訣はいろいろとあるのでしょうが、あるとき彼はこんなことを話
していました。
「鈴木さん、やっぱり大事なのは、場のエネルギーを高めることです。リーダ
ーは、その場のエネルギーの高低に最も影響を与えるんだと思います。みん
なリーダーを見ていますし、感じていますから」
「だから僕は、調子が悪いときは極力オフィスに顔を出しません。スターバッ
クスで時間をつぶしたり、時には映画を観に行ってしまったり、とにかく自分の
エネルギーが高まるまでは、オフィスに行かないんです。エネルギーが低いと
きオフィスにいても、悪影響を与えるだけですから」
○よく風邪を引いて体調が悪いのに無理して職場に来る人がみえますが、こ
れなどは自己満足で、周りの人間にとっては感染のリスクもあり、たまったも
のではありません。
■人が発するエネルギーを高めるには、心と体の両方に働きかける必要が
あるようです。
未完了とは、「やろうと思っているのにやれていないこと」です。とりわけ、人
とのコミュニケーションにおいて未完了のコミュニケーションが発生したとき、
心のエネルギーは最も奪われます。
言いたいのに、言えない。言おうと思っているけれど、なかなか言うチャンス
がない。こうして自分の中に溜めてしまった状態です。
○「もの言わぬは腹ふくるるわざなり」とは徒然草の吉田兼好の言葉ですが、
かといって何でも自由に、どんな言い方でも言ってしまっては逆効果です。
ダムダム弾は相手の懐に入ってから爆発させるため、ファースト・コンタクトは
ソフトであるべきです。
■どうすればリーダーは「最後まであと少し」の局面を迎えたとき、力強く前を
向いて走り切る意識が持てるのでしょうか。
3つの方法をご紹介しましょう。
1 「ゴールまで」ではなく「ゴールの先」をイメージする
2 ゴール前で失速しないよう対策を考えておく
3 ゴールから逆算して行動を計画し、ゴール間際のアクションをより具体的
にしておく
○ウサギと亀の競争の勝敗を分けたのは見ていた目標の違いです。亀ばか
り見ていたウサギに対し、亀はウサギに関係なくひたすらゴールを見据えて
いたのが勝因です。
■インド哲学によると、この世は、創造、維持、破壊というサイクルで成り立っ
ているそうです。つまり破壊しない限り新しい創造は生まれない。
ところがたいていは、破壊せずにまた新しいものを創造してしまうため混乱
が起きてしまう。「創造に対する創造」は「混乱」であるとインド哲学は教えま
す。いったん破壊しないと真の創造は生まれないということです。
○「スクラップ&ビルド」は「ビルド」より「スクラップ」が先ですね。
■人は基本的に憧れを持ち、その憧れと現実とのギャップが明確になったと
きに変化に向けて動き出す。
○まずは憧れ、目標を定め、それと現実との距離を埋める方法を確認したら
後は努力あるのみです。
■リーダーシップが「実現したいことがあって、協力者を集め、その実現に向か
って人を動かす」ものだとすると、当然リーダーは周りの人の協力を仰ぐという
プロセスを避けて通るわけにはいきません。
○この意味ではリーダーは管理職とはイコールではありません。
■リーダーは、自分が実現したいことを相手に語り、相手にもそれを実現したい
と思わせることが必要です。
○相手をその気にさせるパッション、情熱がないと人は動きません。
■自分の内側で展開する声のことを「セルフトーク」といいますが、逃げるときに
はたくさんのセルフトークがものすごいスピードで沸き起こり、逃げるほうが正し
い選択であることを証明しようとします。つまり、言い訳をつくり上げるわけです。
この言い訳を一掃するため、時にとても有効に機能するものがあります。それ
は「格言」や「マジックワード(魔法の言葉)」と呼ばれるものです。
○プロ野球のピッチャーがピンチになると自分のグラブを見て、何かつぶやいて
いるのを見ることがありますが、あれは多分、自分だけのマジックワードが書い
てあるのでしょう。
■適度な緊張感があってこそ、メンバーには集中力が生まれるでしょうし、目標
達成意識が高まるでしょうし、成長へのドライブもかかるでしょう。「オプティマル・
テンション(最適な緊張感)」が必要なのです。
○ストレスも適度であればバネになります。
■適度な緊張感をつくるためには、抽象的過ぎず、具体的過ぎない、自分が大
事にしたい軸を明確に決めることが肝要です。
○その軸、つまり判断基準は一度決めたらぶれないようにすることも大事です。
■英語には「Cautiously Optimistic(用心深く楽観的)という表現があります。
まさにリーダーが持つべきスタンスではないかと思います。
○「用心深く」と「楽観的」は相反する意識ではありません。最大限注意はするが
悲観的になる必要はなく、希望を持つことが大事です。
■セリグマンは著書の中で、売れる営業マンと売れない営業マンの違いを描き
出しています。その違いは、9件訪問して断られたとき、「次は大丈夫だろう」と
10件目にひょいと向かえるか、「もうだめだ」と9件で断念してしまうかの違いだ
そうです。
○ケンターキーフライドチキンのカーネル・サンダースは63歳のとき、チキンの
セールスで1,009件のレストランから断られたそうです。
■リーダーという地位は、困難に立ち向かい、乗り越えるということを繰り返した
者だけに、本来用意されるべきものなのです。
○自分自身が困難に出会ってない人が部下に向かって「困難を乗り越えろ」と
言っても説得力がありませんね。
■プロゴルファー宮里藍さんの現在のメンタルコーチであるピア・ニールソンは
次のようなことを言っています。
「自分はコントロールできる。スイング、戦術、食べるもの、感情、道具。でも
競技を一緒にする同伴者の振る舞いや、天候や、勝利はコントロールできない。
コントロールできることを最大限コントロールする。これが成長するということで
ある」
○当たり前のことですが、コントロールできることに全力を尽くし、コントロール
できないことでは悩まないことです。しかし、これが中々できないのです。
■リーダーになるということは、最終的には、「すべては自分次第である」という
感覚をもつことだと思います。一切の責任逃れを禁じ、あらゆることを自分に
帰結させ、始まりから終わりまでのすべてを握っていると思える感覚です。
○リーダーには責任をもつこととともに、任せることも求められます。船長には
「唇が血でにじむまで噛む」という我慢が求められるといいます。つまり、一旦
舵を任せたら、口出ししないということです。
■外側の刺激が内側の状態をつくり上げるのではない。外側の刺激はあくまで
もきっかけにすぎず、内側の状態はすべて自分でつくっている。そして、内側の
状態はいつでも自分の好きなようにしておくことができる。
○全ては自分次第。他人や環境は原因ではなく、きっかけの一つに過ぎません。
■「モチベーションが上がらない」ではなく、「モチベーションを上げられない」が
正解です。
○モチベーションを上げるも下げるも自分次第です。
■どんなときでも自分の状態は自分で選ぶことができる。
○「自分の状態は自分で選ぶことができる」人がリーダーの器たる人ですね。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「ボージョレ・ヌーボー飲む?」<回…
- (2025-11-28 08:00:04)
-
-
-
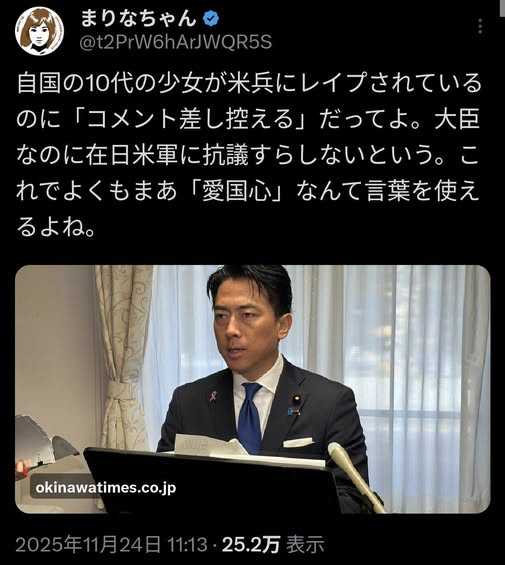
- 政治について
- 今の政権・閣僚は骨の髄まで腐ってい…
- (2025-11-28 07:55:24)
-
© Rakuten Group, Inc.




