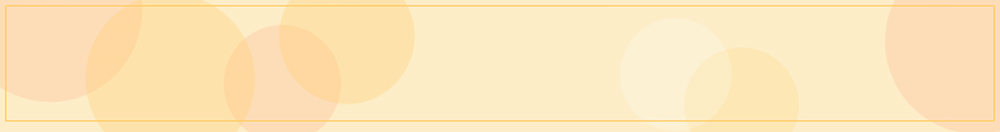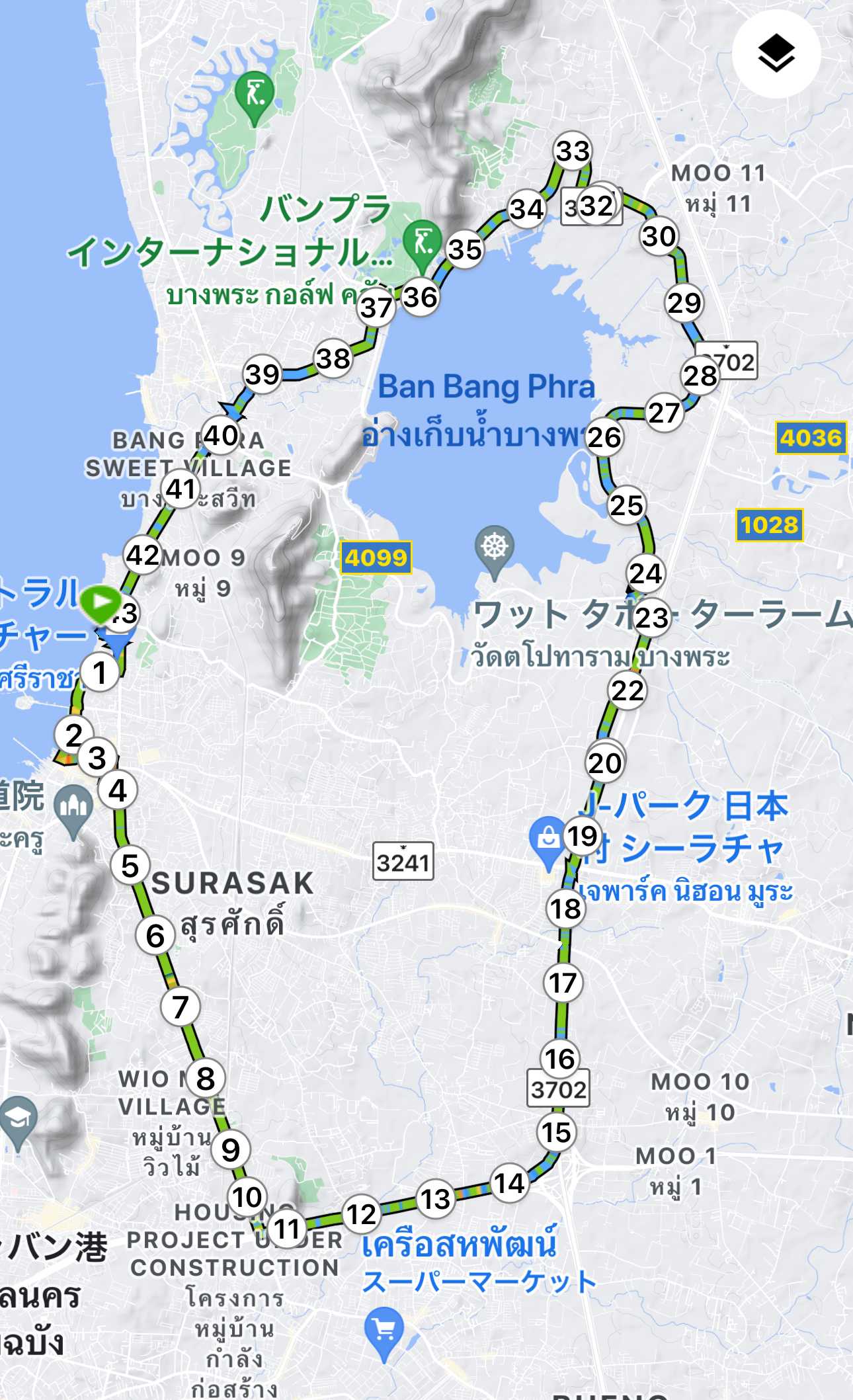悲しみの歌

戦時中、米兵の生体解剖実験に携わった医者と彼をめぐる人たちの物語。「海と毒薬」の続編といわれる。さまざまな人物が登場するが、主な人物はこの医者と、医者のことを記事に書こうとする正義感の強い新聞記者である。
重い過去を背負って複雑な思いを抱えて生きる医者。悪と正義を単純に考え、正義感に燃える若い新聞記者。記者は医者の態度と反応を見て、犯した罪を償う気持ちがないと決め付ける。そのことを日本の政治の腐敗と結び付け、記事を書く。記事は評判がよく、記者は賞を獲得する。結果として医者は周りの住民から糾弾され、居場所を失っていく。
その二人のやり取りの中にさまざまな人物がからむ。特に印象的だったのは、お人よしで、最後まで医者の友達でいようとした外国人のガストンだった。キリスト教的視点というのもあるのだろうけれど、時として外国人には現地の人よりもその国の事情がよくわかる、というか気づくことがあると思う。それがガストンにこのような行動をさせたのではないか、と個人的に思えてならない。
「どんな正しい考えも、限界を超えると悪になる」 。これが、著者のメッセージなのだと思う。著者のメッセージは脇役にセリフに色濃く出ている。
新聞記者の同僚、野口のセリフ。
「絶対的な正義なんかこの社会にないということさ。戦争と戦後のおかげで、ぼくたちは、どんな正しい考えも、限界を超えると悪になるということをたっぷり知らされたじゃないか」
バーテンとしゃべる小説家のセリフ。
「誰だって怒る権利はある、憤る権利はある。だが、他人を裁く資格などどんな人間にも本当はありゃあ、せんのだ…だって裁いてる人だって裁かれた者と同じ状況に置かれたら、同じことをしたかもしれん。俺は絶対そんなことをしなかったと断言できるほど、自信のある人間は…この世にはいないからねえ。しかし、それじゃ社会が成り立たないから人間が人間を裁くんだろうが……」 。
本当に大事なのは、自分が信じることに対しても常に疑問を持ち続けることだと思う。この世の中に絶対的に正しいことなんてなくて、物事はすべて不完全なもの。そのことがわかっていないと、この物語の新聞記者のようなことをしてしまう。この記者のような行動は、誰もが陥りがちで、日常にあふれていることのような気がする。だからこそ、怖い。
例えば、何か問題を解決しようとするとき、絶対的によいと思われる方法をみつけたとしても、その方法を絶対視することだけは避けなくてはいけない。絶対的に正しいものはないけれど、既存のものより「よりよい」何かは存在する。そのよりよいものを見つけ、既存のものにとって代える。しかし、それにも必ず何かしらの欠陥が存在する。一歩ずつその方法を確かめながら、疑いながら、前に進んでいくしかない。この小説を読んで、そんなことを考えた。
「おすすめの本」に戻る
© Rakuten Group, Inc.