2025年02月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
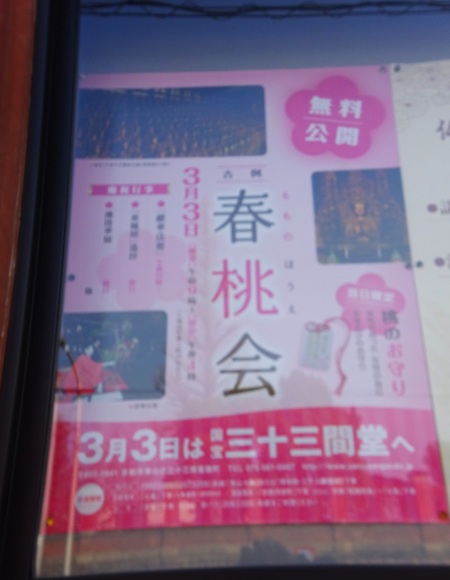
雛祭り 3題
この時期の、当ブログの定番記事ですが・・・三十三間堂の掲示板に春桃会のポスターが掲示されていました。透明版越しの画像、しかもピンボケで見難いですが・・・当日は1001体の千手観音の拝観をはじめ入場無料です。向かいの国立博物館では・・・こちらは70才以上無料です。そして、その向かいの日本赤十字社のビルがすっかり取り壊された前には・・・・法住寺のいつものパターンのユニークな案内板が立ちました。例えば・・・こんな全部無料コースは如何でしょうか?? (一部でも良いですし)三十三間堂を拝観 ~ 向かいの博物館を見学 ~ 豊国神社でお参り ~ 方広寺の国家安康の鐘を見て ~ 京都大仏の跡地で往時を偲び ~妙法院で幕末の七卿落ちの史跡を見て ~ 智積院で観梅半日は十分に遊べます(笑)但し博物館だけ無料は70才以上です。
2025.02.28
コメント(4)
-

毎年恒例の梅の便りです。
ブロともさんのブログを梅の便りが賑わす季節になって来ました。私も負けじと、今日智積院を通った時撮ってきました。紅梅が早くて、白梅が遅いと言う開花状況は例年通りです。金堂へ向かう石畳みの向かって左が主に梅で、向かって右がモミジが主に植えられています。梅は金堂の裏に沢山植えられていますが、そちらの梅はまだチラホラも咲いていません。梅が春の便りと言うならば、冬の終わりを告げているのが菰が外された松の木です。あれだけ沢山松に巻かれていた菰がいつの間にか奇麗に姿を消していました。いよいよ春本番です。
2025.02.27
コメント(4)
-
七草爪って? ?
七草粥は知っていましたが七草爪は知らなかったと言うお話です。最近友達に薦められて読みだした作家・小川糸の小説2冊目の「ツバキ文具店」を読んでいると「七草爪」という記述が出て来ました。「七草爪」なんて私は初めて知ったのです。netで検索すると確かに色々出て来るので、私が知らなかっただけで世の中では広く知られたことなのかも知れませんが・・・・我が家には子供の頃から特に七草粥を食べる習慣が無かったので、今でも踏襲しています(笑)ただ、毎年年初めの1月7日に食べて、無病息災息災を願うことや・・・セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロ は諳んじてはいますが。さて、その小説には・・・「6日の晩から七草を水に浸けつけておき、翌朝、その水に指先き浸して爪を切ることを「七草爪」という。年が明けてから初めて爪を切る日とされており、(主人公の家では) 元旦から6日の夜までは、どんなに爪が伸びても爪を切ることを許されなかった」と言うのです。それでふと思ったのですが世の中広く知られている事なのか、そうでないのか知りませんが、我が家では子供の頃から、「夜に爪を切ってはいけない」と言われたものでした。このことは頭の中に残ってはいるのですが、忙しい現在の生活からして余り遵守はしていないのですが・・・七草爪とは広く良く知られた風習なのでしょうか??そうそうこの小説の舞台は鎌倉なので、ひよっとすると「七草爪」は関東で良く言われることなのかも知れませんが・・・・??
2025.02.26
コメント(12)
-

小塩山(おしおやま) 遠望
我が、智積院は京都東山36峰のほゞ麓に有ります。標高が余り高くないので、市内を見渡し難いのですが、遠く西山連峰の小塩山(642m) などはこの様に見えます。(赤矢印)アップしますと・・・テレビ塔か携帯の電波塔が沢山あり、山頂横には淳和天皇陵もあり、カタクリの自生地もあり人気の山です。何故、改めてこんな写真を撮って来たかと言いますと・・・・カメラのSDカードの画像を整理していると、こんな画像が出て来たのです。一昨年に小塩屋へカタクリを見に行った時撮った写真です。(矢印を付したのは今)その時は、この写真には写っていない比叡山と、清水寺が良く見えるとブログに書きながら・・・・この写真を使わず、智積院も良く見えるなんて書いていなかつたことに今更ながら気が付いたのです。アップしますと・・・・小塩山から智積院が良く見えていたのです。(後ろの建物は京都女子大学の校舎です)・・・・と言う事で、智積院から良く見える小塩山、小塩山から良く見える智積院の紹介でした。因みに赤矢印が小塩山 黄色矢印が智積院直線距離で測りますと・・・赤下線を付した通り13.7kmの距離でした。
2025.02.25
コメント(6)
-
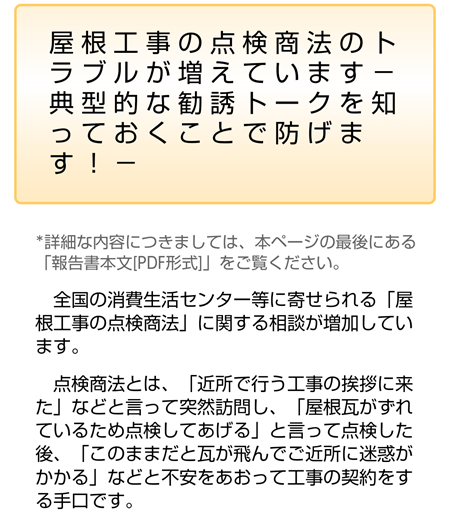
屋根点検商法
この前から屋根の修理の事を書いて来ましたが・・・・今回は「屋根点検商法」のことを。昨日インターホンが鳴って妻が応対に出て、暫し。「うちの屋根がめくれているって」と言いに来ました。代わりに私が出て行くと、手ぬぐいで鉢巻した作業服着た人が曰く「近所で屋根修理の作業しているけど、お宅の大屋根のテレビアンテナが立ってる辺りがめくれている。雨漏りしていませんか? なんならついでだから上って見てあげますよ」下からでも見えるはず見たらと言われ一緒に家の北から、そして南から見ても大屋根の上なんか下から見えません。ひつこく見てあげる直してあげると言ったのですが・・・・頑なに断りました。「まあ一日でも早く直さないと大変なことになりますよ」の捨てセリフ? を残して帰って行きました。それから30分程すると100mほど離れた所に住んでいる姉から電話があり。「屋根がめくれている云々と言って人が来たけど帰って貰った。帰ったあと、何処へ行くか見ていたら〇〇さんの家(7~80m離れている) のチャイムを鳴らしていた」と。ウチも来たよと返事して、元々胡散臭いがしていましたがここで屋根点検商法であることが分かりました。普通の物売りなら隣隣と順番に訪問するところ、さすがこの商法では隣りへは訪問はせずに離れている古い家を訪問するのがマニュアルなのでしょう。多分登って見てもらったら、屋根をめくってスマホで写真撮って、こんなになっていると見せるのでしようね。恐い怖い世の中です。国民生活センターのホームページにはこの様に書かれています。
2025.02.24
コメント(8)
-

鍋の為に又々セイヨウカラシナ採りに・・・。
2/14のブログに土筆と一緒にこの様にセイヨウカラシナを収穫したことを書きました。当然鍋にすると思っていたのですが、先にカシワとこの様に炒め物したら美味しかったので・・・ブタでも食べることに・・・・・・・で、鍋で食べられなかったのでこの前見つけた穴場? に又々採りに行きました。淀川では絶滅危惧種? の様になってしまったセイヨウカラシナですが、この支川にはまだこの様に沢山は生えているのです。今回はもう土筆には目を向けず、これだけのカラシナを収穫しました。・・・で早速鍋に・・・具は鯖缶2缶と豚肉などです。野菜と違い「雑草」は灰汁も強いですが、生命力も強く、冷蔵庫に入れておけば随分長期保管出来るのでまた後日もう一回食べることになりそうです。そして、次はツボミノ時に採りに行こうと思っています。何と言ってもツボミの時が一番美味しいのです。
2025.02.23
コメント(10)
-

仕切り板作りの応用編
久し振りにネクタイを締めました。リタイヤ後ネクタイを締めるのは冠婚葬祭くらい、中でも「葬」に限られていたのですが、コロナ以後殆どが家族葬で行われる為更に機会が無くなっていたのです。思い起こせば4年前に叔母の葬式を取り仕切って以来のお通夜、葬式で超久しぶりにのことでした。長年締めていたネクタイ、締め方は忘れていませんでした(笑)さて、過日、屋根工事の端材で引き出しの仕切り板を作ったことを書きましたが・・・この度、着物着付けの師範免除の看板? を貰った息子嫁からのリクエストでこんなのを作りました。何かと言いますと・・・ ↓ ↓ ↓ ↓でした。早速、応用編まで作る事が出来たのは形の良い自然杉の端材があったからこそ。これからも端材は大事に備蓄しないと・・・です。
2025.02.22
コメント(6)
-

日本最古の京都市電
先日、京都の河原町御池交差点の東南にある幼稚園の前を通りますと・・・園庭に懐かしい日本最古の京都市電車両が置いてあるのに気が付きました。これなのですが・・・何しろ生垣越しなのでこんな写真しか撮れないためプログの記事には出来ないとボツにしていたのですが・・・偶々、今日(2/20) の京都新聞にこんな記事が載りました。この電車は、私がまだ大学生だった頃まで京都駅~西洞院通り~四条通り~堀川通り~中立売通りを経由して北野天満宮まで走っていたのです。運転手席は屋根こそあれ、外で運転しているようなもので、電車の先頭には人を轢かないように地面すれすれのネットが付いていたのを良く憶えています。そんな電車が平安神宮に有ったとは・・・・そして、整備してこれからは無料開放エリアに展示されるらしいです。
2025.02.20
コメント(10)
-

友達の友達はみな友達
私の元趣味の中に自転車も有りました。折り畳み自転車2台、スポーツタイプ自転車2台の計4台乗って来て、今は折り畳み、スポーツタイプ各1台残っているのですが・・・・加齢により先ずスポーツタイプに乗らなくなり、折り畳みも久しく乗らなくなってしまいました。折り畳みはまだ乗る可能性はあるとしても、スポーツタイプの自転車は まずもう乗ることが無いので処分することにしました。誰か欲しい人いませんか?? と声をかけたところ・・・友達から「欲しいと言う友達がいるけど・・・」という話が帰ってきました。要らない自転車を貰って貰うのは誰でも良いので直ぐその話を進めて貰って・・・再整備して、今日配達?? して来ました。こんなのですが・・・乗らずに朽ちるより。乗って貰ってこそのもの、良い嫁入り先が見つかってやれやれです。・・・と言う事で断捨離のことで「友達の友達はみな友達」を実証したことになりました。
2025.02.18
コメント(10)
-

柚子と柚子胡椒とスダチを貰ったので・・・
去年、我が家では柚子が2つしか採れず、スダチに至っては1ヶも採れなかったのです。一昨年は少しは採れたのですが、まだ木が若いからだと思います。そんな消化不良? の思いをしたのですが、偶々相前後して柚子と手作り柚子胡椒を そしてスダチを貰いました。柚子と手作りの柚子胡椒で・・・こちらがスダチです。・・・・で、二つの風味を同時に楽しませてもらう為に、鍋を・・・スダチをビールに絞り・・、大根おろしとポン酢のたれに薬味にはたっぷり柚子胡椒を添えて・・・スダチビールに、柚子胡椒での水炊き・・・相性抜群でした。今年スダチも柚子も沢山生ってくれることを願うのみです。
2025.02.17
コメント(8)
-

廃材利用の大工仕事??
屋根の修理工事で屋根の傾斜に合わせて三角にカットした木材が沢山出たのです。同じく屋根の裏側に使った一枚ものの杉板の端材も・・・これなのですが・・・使用目的が特に無いのに備蓄したいたのですが・・・その各ひとつで、ちょっとお遊び大工をしました。この様にカットして・・・こんな形にネジ釘で組み立てました。さた何に使うかと言いますと・・・私の肌着を入れる引き出しがこの様に仕切りが無いので・・・シャツゃパンツ、靴下は順番に並べて容れてあるのですが、特にシャツとパンツの区別が、し難かったので・・・この様に左右フリーに動かせる仕切り板を作ったのでした。・・・で、こうなりまして・・・これからは迷わず取り出せるようになりました(笑)
2025.02.16
コメント(8)
-

「御周印帳」もらって来ました。
タイトルに「御周印帳」と書きましたが「御朱印帳」の打ち間違いではなく「周」の字なんです。先日から「大和路秀麗八十八面観音巡礼御朱印帳」の事を書いて来ましたが・・・ぶろ友さんの昨日のブログで「日本遺産 御周印帳」なるモノが有って、偶々今日東本願寺前で行われている「日本遺産マルシェin京都」なる催し会場て貰えると教えてもらったので、早速行って来ました(笑) 日本遺産御周印帳について詳しい事はぶろ友さんがブログに詳しく書いて頂いています。ここです。今日は午後3時から配布と言う事で2時半過ぎに現地に行きました。御影堂門(浄土真宗では「ごえいどうもん」)の前が会場でした。104ある現地と言う日本遺産の現地と都道府県とが出店してるようで大変な数のテント村でした。各テントが資料をくれるのでその数たるや・・・後ほど鳥取県の三朝(みささ)温泉は温泉を持ち込んで足湯゜をしていました。舞台が有って次々と各地の日本遺産がPRも・・・私が観た時は大津の三井寺のお坊さんが説明していました。・・・で、調べてみると、三井寺は日本遺産NO8 の「琵琶湖とその水辺景観ー祈りと暮らしの水遺産」に含まれていました。キャラクターも沢山いました。・・・で、「御周印帳」を貰えるテントはここ、配布時間の3時きっかりに配布開始されたのですが・・・・スマホでQRコードを読み取ってアンケートをしないと貰えないのです。これでは2冊貰えないと諦めました。そして帰りは阿弥陀堂門の前から帰りました。・・・・で、苦労?? してもらった「御周印帳」がこれです。まずは、104の日本遺産の既に行ったところ、見たところの消し込みから始めてみようと思っています。そして、各テントでこんなに沢山の資料を貰ったのですが。これでも重くなって貰うのを途中で止めたのでした。
2025.02.15
コメント(6)
-

病院通いのお駄賃
今日は病院の通院日。今回は長時間待ちの日なので、覚悟して本を2冊持って行ったのですが・・・病院の裏は淀川の堤防なのです。ふと、今年は採りに行かなかった土筆、もう遅いだろうけど名残だけでも残っていないかと・・・待ち時間の「読書」を止めて、淀川の堤防へ行ってみました。すると、土筆は沢山残っていたのですが・・・・干からびたものが多く・・・採るのを躊躇したのですが・・・・結局、こんなに沢山の土筆と、私の淀川堤防の畑では殆ど採れなくなったセイヨウカラシナまでこんなに収穫しました。行動する時はいつもリュックなのでこういう時の対応力十分です。・・・・で、帰ってから土筆はハカマ取りをしてバトンタッチ、出来たのがこれです。今年は春の香りの土筆を食べずに終わると思っていたのに思わぬ収穫でした。試食してみると土筆の風味は味わえるのですが、干からびたものが多かったので口の中に筋が残る部分があるのです。・・・で吐き出しながら食べることになりそうですが、例年より沢山採れたし、まあ贅沢は言えません。セイヨウカラシナは後日鍋物に・・・・です。・・・と言う事で病院通いで季節の風味のお駄賃の話でした。
2025.02.14
コメント(8)
-

長谷寺の十一面観音拝観
昨日の続きです。山の中腹の様に高い場所にある近鉄・長谷寺駅を出ると旧街道までは急坂を下り、この街道を歩く事15分余で・・・長谷寺に到着です。この長谷寺は2019.11.19 に訪れて以来5年余ぶりの訪問です。 その時は紅葉の見頃の時でした。記事はここです。「長谷寺」と言えば「牡丹」「牡丹」と言えば「長谷寺」ですが、今回は十一面観音の拝観が目的であるため、冬場の今はこの様に長い登廊のある広い境内が・・・・殺風景な景色を覚悟で行ったのですが・・・仁王門から・・・長い登廊へ進むと、何となんと菰を被った牡丹が左右に並んで迎えてくれたのです。寒牡丹と言うのでしょうか、それはそれは綺麗に咲いていたのです。登廊に沿って満開の牡丹も良いけど、この方が趣きがあって良いではないか・・・と思うほど予想外の光景が見られました。ただ私だけが知らなかっただけで長谷寺の寒牡丹は有名なモノらしいです。左右の寒牡丹を眺めながら更に登廊を登り・・・本堂の前に到達。この舞台の正面に目的の巨大な(10.18m) 十一面観音がおられるのですが、勿論撮影禁止。拝観ののち、持参したこの朱印帳に貼る御朱印を頂きました。撮影禁止の分、この御朱印帳の写真を・・・これで先日拝観したこの西大寺の十一面観音と合わせ・・・88分の22面観音を拝観したことになりました。あとの66面観音は特別公開が3月に始まるとか11月にあるとか、遠隔地であるとか色々制約が有りますが、まあボチボチ回ろうと思っています。
2025.02.13
コメント(6)
-
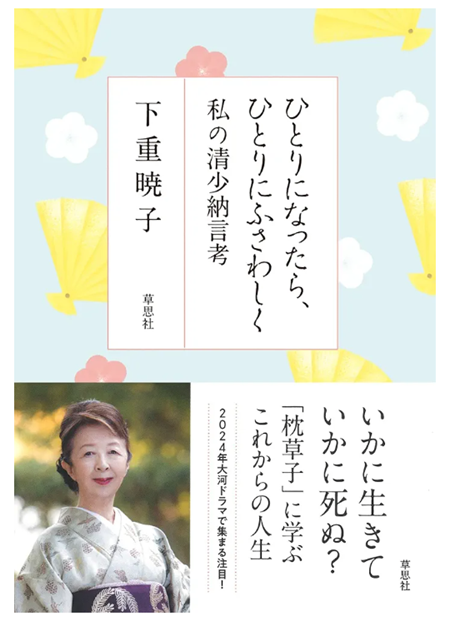
枕草子と八十八面観音巡礼が結びつく。
酒井順子の「女人京都」など読んだのがきっかけだったと思うのですが「枕草子」に興味をもち・・・こんな本を読んだり・・・清少納言が仕えた定子の鳥戸野(とりべの)陵を訪ねたりしてきたのですが・・・こんな本を纏めて借りて来て・・・今、右の「枕草子の楽しみ方」を読んでいます。(左の2冊は読まずに図書館へ返しました)枕草子の本は全て現代文に書き換えられた本が多いのですが、それでは面白くないので、古文と現代文を併記した本を借りて、まず古文を読んで意味の理解をして、分からない部分(ほとんどがそうですが)を 現代文で読むと言う読み方をしているのでなかなか読み進まないのですが・・・・そのことと関係なく片や、先日書きました「奈良路秀麗八十八面観音巡礼」は西大寺の十一面観音の拝観を終わり次は何処へ行くか?? 特別公開の日に行かないといけないのが多いので、どうするかを決めかねていたのですが・・・そんな折、枕草子に初瀬詣でについてこんなくだりが書かれていました。(初瀬と言うのは奈良の長谷寺のこと(地名) なのです)平安時代には和歌山の熊野詣でが盛んであったことは知っていましたが、初瀬詣でも盛んであったこと初めて知ったわけですが・・・古文では現代文ではこうなるのですが・・・赤下線を付した箇所に疑問を持ったのです。奈良の初瀬に行くのに淀から船に乗ったと書かれているのです。まさか大阪へ向かって行くわけじゃなし何故淀から船に???疑問に思って色々調べてこんな昔の地図を発見しました。巨椋(おぐら) 池は確か昭和になって干拓されて今はありませんが当時は木津川とも繋がっていて淀から奈良へ向かうのに木津川を渡ったのはこれでか!! と疑問が解けたのでした。さて、清少納言その木津川を渡って向かった初瀬の長谷寺のご本尊ですが・・・(高さ10.18mもある木造で一番大きな仏像であるらしいのですが・・・)そのご本尊がタイトルに書きました「奈良路秀麗八十八面観音巡礼」の10体の仏像のひとつなのです。・・・で、枕草子を読んでいる今、西大寺の次は長谷寺の十一面観音の拝観に決めたのです。長谷寺には4~5年前に行っているのですが、「奈良路秀麗八十八面観音巡礼」のひとつとして良く眺めて、御朱印も貰わないといけないのです(笑)・・・・と言うのが長い長い前置きで・・・・今からが本論なのですが、昨日長谷寺を目的のウオーキングに行って来たのでした。長くなりますので、そのことは明日に。
2025.02.12
コメント(4)
-

掛け軸リレー
いつも季節季節のフラワーリレーの事を書いていますが、今回は掛け軸リレーです。正月に飾っていたこの掛け軸・松と鶴から・・・ひな人形に・・・・。そして人形も・・・この時期の恒例行事のため毎年書いていますので詳しい事は割愛します。もし関心持って頂ければ去年のブログに詳しく書いていますので、覗いて下さい。 ここです。
2025.02.10
コメント(6)
-

又々燃料補給
屋根の修繕工事で燃料用の廃材が沢山出たのですが、屋根材なので薄い板が主だったのです。薄い板は良く燃えますが直ぐ燃えてしまうので、次から次へと燃やさないといけないので思ったより消費が早いのです。そこで大工さんに「燃料補給」を頼んでおいたところ留守の間にこれだけ届けてくれました。廃材ですのでやたら釘が残っているので、まず釘抜きが必要なんです。普通の釘からネジ釘までこんなに抜きました。あとは長さを合わせて電動丸鋸でひたすらカットするだけです。・・・全部切り終わって備蓄棚に置きますと・・・真ん中辺の白っぽい角材が今回補給出来た「燃料」です。沢山有ったようでもカットするとこれだけの量になりました。これで暫くは心おきなく燃やせますが・・・何しろ暖を取るだけでなく、焼き芋、くん製などに最近ベーコン作りが加わったりして最近とみ燃料消費が多くなっているのです。
2025.02.09
コメント(4)
-

京都と枚方の違い
京都・枚方間の距離は高だか26km程です。その間に山がある訳では無いのですが・・・・今日は大工さんと打ち合わせする為京都に行く予定でいたのですが・・・朝からこんな雪景色の写真が届いたのです。向こうに見えるのは東本願寺の門なので七條烏丸交差点の写真です。そして以下2枚は・・・智積院です。枚方では桜の花びらが舞う程度に少しは雪が舞いましたが、積雪なんか全く無かったのです。自動車でも歩行でも雪道に慣れない身、もし事故を起こしたり、すってんころりんと転んで骨折でもしたら大変と・・・急遽約束をキャンセルして自宅籠りの日となりました。京都と枚方の高が26kmの距離、されど26kmの距離を痛感したのでした。
2025.02.08
コメント(6)
-

京都で2つの景色
今日は午後から雪の予報もある中、同好の友達8人での飲み会にお昼から四条大宮まで出かけました。京阪電車祇園四条駅でエスカレーターで地上に上ると、出雲阿国の像が待っていてくれるのですが、今日はギャーギャーとうるさい声まで聞こえて来ました。何と何と沢山のカラスの群れがいたのです。気が付いた時、阿国像の頭の上にもカラスが止まっていたのですが、カメラを出している間に飛び去ってしまいましたがこんな景色だったのです。冬の鴨川と言えば・・・・ひと昔前までは沢山のユリカモメが乱舞する景色が見られたのですが、その数が段々減って今ではほゞ見られなくなってしまったのですが、その代わりにカラスとは・・・鴨川を渡り、木屋町から再び地下に入り、阪急電車で大宮まで。大宮駅で地上に上ると今度はこんな景色でした。交差点のこう言うスペースは何も無いか、背の低いツツジなどの低木が植えられているのが関の山ですが・・・ここには「庭園?」が出来ていました。角度を変えますと・・・一年程前は多分無かったはずなので最近整備されたものだと思うのですが、殺風景な交差点に一服の清涼剤で有りました。
2025.02.07
コメント(4)
-

南禅寺周辺の別荘所有者の変遷 (盛衰?)
2/5の京都新聞にこんな記事が載っていました。「一般公開始まる」を読んで、ただそうかと思っただけだったのですが・・・・所有者の名前を見てびっくり、対流山荘が今を時めくニトリが所有者になっていたとは・・・南禅寺界隈には超の字が幾つも付く程の名庭のある広大な別荘が沢山有ります。例えば・・・松下幸之助の別荘(真々庵)、元首相の細川護熙家の別荘(怡園) 等など15邸程 超豪邸街を形成しているのですが、それが今誰の所有になっているか詳しく知らなかったのです。各々今の所有者を調べていくとニトリ以外にも、オムロン、ファーストリテイリング ZOZOTOWN 等 今飛ぶ鳥を落とす勢いの会社がずらり・・・各別荘を個別に調べてびっくりでした。
2025.02.06
コメント(8)
-

ず~と気になってはいるのですが・・・。
京都国立博物館でず~と昔から定期的に行われている落語会があるのですが・・・いつもポスターを見てはいるのですが、行ったことが無いのです。拡大しますと・・・凡人には「博物館と落語」はピンと来ないのですが、途絶えず続いていると言う事は人気があるるのでしょうね。東京の国立博物館でも同じようなことが行われているのでしょうかね???前にも書きましたが、京都の博物館は略して「京博」と言われていますが、東京の博物館は「トーハク」と言われているようです。同じ国立でも略称が違う様に、東京では又違った催しが行われているかも??ところで、博物館の東側、東大路に妙法院と向かい合って建っているこのレトロな建物ですが・・・今は博物館の建物(管理棟?) になっていますが・・・昔は京都市の東山区役所の建物だったのです。そんなこと地元の人でも知っているのはそこそこ高齢の方だと思います。因みに今の東山区役所はここから1km程北の同じく東大路の清水道に有るのですが、そこは元ホテルとボーリング場があった場所なのです。そんなことも知っている人も高齢の方に限られると思います。(向こう側に見えている茶色の建物は昨年開業した超高級のシックスセンシズ京都ホテルです)
2025.02.05
コメント(4)
-

三度目のベーコン作り
何しろ桜のチップは沢山作ったし(ここ)、 屋根の工事で廃材は沢山出たし・・・これはやるしかないと又々に、もう一つ又が付く3度目のベーコン作りをしました。今回は多めの3切れ。3切れになると2段使わないといけないのでローテーションが必要になります。・・・で、出来たのはこれだけ。切ってあるのは中の出来具合を確認したのでした。何しろ厚さの違いがあるし、3切れは一段に乗らないので熱の弱い上段も使いローテーションしながらだったので出来具合に自信が無かったのです。結果はやはりまだ赤みが残っているモノが有ったので更に燻製することになりました。それよりも下味の塩が少し効きすぎて少し塩からいベーコンになりました。下味の付け具合が難しいと聞いていましたが,こんなことでそのことが分かった気がしたのでした。
2025.02.04
コメント(10)
-

屋根修理今日完了しました。
2/1のブログでこの様にルーフィングと桟打ちまで書きましたが・・・引き続き沢山の瓦を人力で揚げて・・・瓦葺きが始まりました。腕の見せ所?? はこの鬼瓦の取り付けと・・漆喰を打って・・・平たい瓦は のし瓦と言うらしいのですが・・・棟を作ることの様です。そして、この部分は隅棟(すみむね)と言うらしいのですが、同じく手間のかかる腕の見せ所のようです。・・・で、最上部の半円形の瓦は冠瓦と言うらしいのですが、それを置いて完成です。この手間のかかる部分が真ん中と左右の計 3ヶ所あったので面積の割には手間と時間がかかる仕事でした。瓦葺きが終わると・・・次は翌日の今日 戸樋屋さん出番です。こんな部分の板金も戸樋屋さんの仕事でした。戸樋屋さんの仕事が終わる頃、大工さんが来て足場の解体です。・・・・で、足場が無くなり、スッキリと完成しました。隅棟は右側にしか写っていませんが木の陰の左側にも有ります。アップしますと・・・バッチリ奇麗に仕上がり・・・屋根の修理工事は無事終わりました。そもそも、瓦の下の梁の腐食部分の取り換えののため、瓦には全く問題無かったのに全部新しい瓦になってしまいました(笑)
2025.02.03
コメント(5)
-

智積院の節分会(節分会)に行って来ました。
昨日の続き家の工事の事は明日にして、今日の節分会豆まきの事を書きます。今日は法住寺の節分会のこの案内を横目に見て・・・(後ろに有った日本赤十字社の大きなビルは完全に姿を消しました)智積院に向かいました。智積院の節分会はこの明王殿で行われます。11時開始なので早めの10時半過ぎに行ったのですが・・・・人影は疎ら・・・中に入っても30人程の人が座っているだけで、こんなに少ないのか??? と思って待っていると・・・どんどん来るわ来るわ、11時には200人は超えていたかと思える程ぎっしりの人になりました。程なく紫と緑の法衣をまとった20人余の僧が入場して着席、読経が始まりました。本尊の不動明王像の前では護摩焚きが行われ、凄い炎と煙でした。読経と大きな太鼓がたたかれる中、間もなく参拝者の焼香が始まり私も・・・。何しろ撮影禁止なもので、代わりに智積院のホームページの写真を借りますと・・・読経と説教が終わるとたくさんの僧が主に豆まきです。豆はまず裸の豆が捲かれ、それは持ち帰らない様にと言われ、あとの方で袋入りの豆が捲かれました。確かに「鬼は外」とは言われていませんでした。捲かれた裸の豆は床いっぱいに散らばったまままず僧が退席です。そして、始まってから約45分で終了。帰りはこんな賑わいでした。・・・・で、貰って来たのは捲かれた袋入りの豆とお守りでした。子供にはたくさんの菓子袋が配られていました。初めて行った智積院の節分会でしたが思っていた以上に宗教的で厳かなものでした。・・・で、俄然来年も来ようと言う気になって帰って来ました。それから家に帰って夕食はイワシと恵方巻・・・・ではなく、リクエストしたキンパを食べ易い様に切ったもの。そして捲く豆は・・・節分には関係ない常備食の「でん六」の豆を升に入れて・・・形だけの豆まきを・・・。
2025.02.02
コメント(4)
-

屋根修理工事 3
屋根の修理工事はこの部分の修理のため・・・・瓦を全部めくって・・・新しい木材を入れて・・・ここまで進んだことを書きましたが・・・続いて・・・梁も板も換えてここまで進みました。反対側は板を換えるだけ。中間は元の使える板は使い、新しい板と混ざってこんな仕上がりになりました。ふと割れた陶器の「金継ぎ」の様だと思いました。大工仕事は取り敢えずこれで終わり、次は瓦屋さんの出番です。ルーフィングを貼って・・・・桟を打って・・・次はいよいよ瓦張りです。明日に続きます。
2025.02.01
コメント(4)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- 懸賞フリーク♪
- 八恵堂のおすすめキムチ
- (2025-11-14 14:56:21)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…
- (2025-11-14 14:35:53)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-







