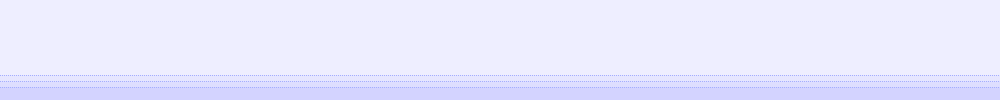るりの創作ノートーー始めて書いた童話
冬の国の王女
冬の国がありました。 そこは北の国の高い山々を北へ北へといくつもこえたところにありました。 その山と山のあいだには指の先も見えないほど雪がしんしんと降りつもっています。 そしてときおり吹く突風が、その降りつもった雪を白いまだらもようのカーテンにして、山をこえようとする人々におおいかぶさるのでした。
そのために北の国の人たちはその山々をこえられず、雪山のむこうには何があるのか、だれも何も知りませんでした。
その山のむこう、だれも知る人のない冬の国に一人の美しい王女がすんでいました。 ガラスのような灰色のひとみに、わずかに色の入った白い髪。 細く通った鼻すじ、かしこく結ばれた口もと。 その姿は人間のようにも見えましたがやはり人間ではありませんでした。
王女はいつもひとりでお城から外をながめてくらしていました。 見上げると灰色がかかったほんのりと青い空に、太陽が色のないいくすじかの光になってさし込んでいます。
それ以外にはこの国には色がなく、ただ新雪の白すぎるほど白い大地にすきとおった氷細工のような木と花が咲きほこっているだけなのでした。 そしてこの、見わたすかぎりの雪の世界が王女の住んでいる世界のすべてだったのです。
王女はふと、思いたって庭に出てみました。 お城の庭はこんもりとした氷の植え込みや、彫刻のような花が咲きみだれ、木が整然とならぶ場所でした。 それらはたいそう美しくあたりをきらめかせていましたが、並木を通りぬける風やさえずる鳥もなく、いつものようにひっそりと静寂につつまれていました。
王女はひざをかがめて、氷の花を取りました。
「お母さまのにおいだわ。」
王女はそう思うとほっとため息をつきました。 王女は冬を治める冬の王さまとお妃のあいだに生まれた、たった一人の娘だったのです。
冬の王さまとお妃はたった一人の娘をたいそうかわいがりました。 けれどもそれはほんの一時で、王さまとお妃は秋の終わりをむかえた国に行き、冬の始まりを告げなければなりませんでした。 それは王さまとお妃にしかできないことだったからです。
出発が近づいて別れがせまると、王女は目にいっぱいの涙をためて言いました。
「お父さま、私もいっしょにつれて行って下さい。」
「いや、それはできない。」
王さまは悲しそうに言いました。 それから王さまは王女の顔をじっと見つめると、王女のほっそりした、小さな体を強くだきしめました。 王女はがっかりしてこんどはお妃のもとに行きました。
「お母さま。 私もいっしょに行ってもいい?」
それを聞くとお妃はひたいを曇らせ、静かに首をふりました。 そうするたびにお妃の豊な、ほとんど白に近い金色のかみがゆれ、かすかに花のにおいが王女の鼻をつきました。
「なぜ? なぜ私はいっしょに行けないの?」
「愛する娘よ。 おまえはまだ小さいのだよ。 そんなに小さくて弱い体では冬の国を出たとたんに暖かさにやられてしまうだろう。 せめて十四になるまで待ちなさい。 そうすればおまえに北の国の秋の終わりを見せてあげよう。」
それから王さまとお妃は王女をなぐさめようとしていろいろな国のめずらしい話を聞かせました。
「王女よ、おまえは空を飛ぶ鳥をまだ見たことがない。 けれども鳥が群れをなして空を飛んでゆくのは、なんとも自由で胸がすくことなんだよ。 その羽ばたきや風をつかむようす、えさを求めて降りたつさまはいくら見ても見飽きることがない。 それに冬を越そうとして南に下る渡り鳥の力強いことといったら…。 それを何にたとえれば良いのかわからないくらいだよ。」
「まったくそのとおりですわ。」
お妃は王女の目をじっとのぞきこんでいましたが、王さまに視線をうつして晴れやかに笑いました。
「しかし、自然のおきてとは厳しいものだ。」
王さまは急に声を落とすと、くんだ指を口元によせ、どこか遠いところを見つめました。 それを見ると王女はごくりとつばを飲みました。
「私は本能にしたがって海を渡る鳥たちが嵐にまきこまれ、海にただようのを見たことがある。 それは激しい嵐だったよ。 海の波は高く激しく波うって、今にも海にうかぶ船を横だおしにしようとしていた。 雨もようしゃなく降りそそぎ、鳥の羽をぬらし、嵐にもてあそばれた体を海の底へと沈めていったんだ。 その日、一つの群れは全て死にたえた。 それはいたいたしくて目をおおいたくなる光景だったよ。 長旅につかれた鳥たちがやせ細った体を海の上に横たえ、それを海の波が散り散りにして群れをひきはなす。 やがて羽の油もすっかり洗われて、鳥たちは一つまた一つと見えなくなった。 海のもくずとなったか、怪物に飲まれてしまったのか…。 知っているかい? 羽は油がなくなると水にぬれてしまうんだよ。 しかし私たちにはどうすることもできなかった。 それが自然というものなのだよ。」
王さまは深いため息をつきました。
「まあ、なんてかわいそうなんでしょう!」
王女は目をうるませました。
「それで、人間たちの乗った船はどうなりましたの?」
王女ははらはらしながら尋ねました。
「おやおや。 おまえはいつも人間がお気に入りだね。 何かというと人間のことを聞きたがるではないか。」
王さまがゆかいそうに体をゆすると、王女はぱっと顔を赤らめました。
「ほほほ。 人間はぶじだったわ。」
お妃は王女の髪をなでつけながら言いました。
「人間は雨でずぶぬれになりながらも帆を降ろし、たくみに船をあやつって嵐を抜けたのよ。 それはとても見事なうでまえでした。
私たちも手をたたいて喜んだものです。 さあ、この話はもう、おしまい。 あとはこの平和な場所で楽しく過ごしなさい。 ここなら嵐は来ませんよ。」
それを聞くと王女は悲しそうに目をふせました。
「もう、お父さまとお母さまは行ってしまわれるんだ。 でも私だけはここに残らなければならないんだわ。」
王さまとお妃が王女をなぐさめようとして外の世界について話せば話すほど、王女はかえって外の世界へのあこがれがつのりました。 そして一人ぼっちの淋しさで身が切られるように感じてしまうのです。
「さようなら、いとしい娘よ。」
王さまは王女のひたいにそっと口づけました。 お妃は涙ぐみながら王女を抱きしめると、悲しみをふりはらうように雲の車に乗りこみました。 もう、出発の時間です。 王さまは閉じられたとびらの窓から王女の顔をながめていましたが、やがて、空の一点を見つめるとさっと車を走らせました。 それを見ると王女の胸はなにかにきゅっと捕まられるようでした。
「ああ、私もいろいろな世界を見てみたい。
冬だけではなく秋や人間や鳥やそれから…ああ、全てのものを見てみたい。 せまい世界からもっと広い世界を訪ねてみたいわ。」
王女は去っていく王さまとお妃を見送りながら、いつまでも窓辺に立ち続けました。やがて二人の姿は遠くの空のかなたに消えていきました。 王女はあきらめて窓辺を離れると白い絹のソファーに座りました。 もうこの城にはだれもいないと思うと、王女の心は寂しさにふるえ宙をただよいます。
王女は王さまとお妃の話を思い出しました。
「いったい、秋に木の葉が赤くなったり黄色くなったりするのはなぜかしら? 土の色や花の色が冬の国と外の世界ではちがっているなんて本当なのかしら?」
王女はそうひとりごちるとテラスから見なれたお城の庭をみまわしました。 庭はいつもとおなじ庭でした。 整然とした林に並木道。 その林には氷の枝に、たわわに実をならせた木々が連なっています。 そしてそれらの木の実はそれぞれに光を受けて、さまざまな角度に光を反射し、冬の国を宝石のようにかがやかせていました。
それを見ながら王女はなんどもかぶりを振りました。
「この国のほかに別な世界があるなんて信じられない。」
そうつぶやくと、王女は目のまえの世界をじっとながめました。
「ほんとに外の世界ってどんなところかしら?」
それから王女はなにか新しいものを見つけられるのではないかと思って、城の外に出てみました。
すると氷の馬が群れをなして、いちもくさんにかけていくのが見えました。
「どうしたのかしら? あの馬たちのいそぎようは…。」
王女はふしぎに思いました。 すると群れから離れた一頭の馬が王女のもとにかけよってきました。 馬は王女のまえに立つとうやうやしく頭を下げました。
「どうしたの? いつも冷静な氷の馬達があんなにあわてているなんて。 それにおまえはどうして私のところにきたの? なにか私に話すことがあるのですか? いったいあの群れはどこへ行ったのです?」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- いつかは死ぬ。それまでにやっておき…
- (2024-12-02 08:37:52)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 「日経ソフトウエア 2025年1月号」
- (2024-12-03 17:18:06)
-
© Rakuten Group, Inc.