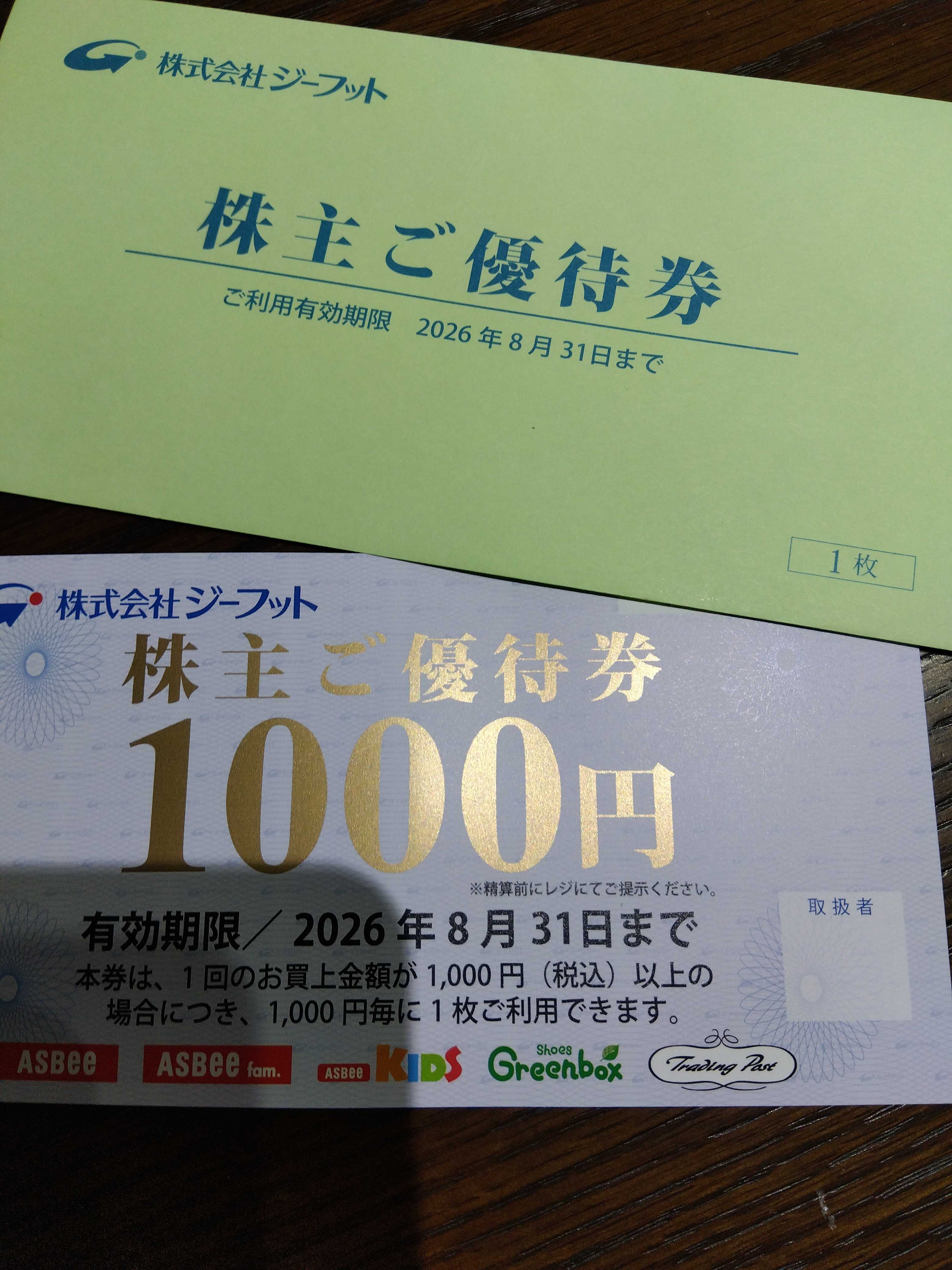2006年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
こんなコンサートに行った~札響第485回定期演奏会
生誕250年にちなむオール・モーツァルト・プログラム。本人を直接知る、指揮者の広上淳一と同業の知人によれば彼は「天才」だそうである。なるほど、彼の指揮からはどういう音楽を作りたいかがはっきりとわかる。交通整理に終わる指揮者が多い中、「この音楽はこう響かなければならない」という自分自身のビジョンを持っている。で、その広上のモーツァルトだが、交響曲第31番「パリ」を聴く限りでは、流行のオリジナル楽器オーケストラのスタイルではなく、大編成の19世紀的なスタイル。ただし甘ったるくもロマンティックでもなく、古典の節度を感じさせるもの。ただ、何というか彼のモーツァルトには優美さとか繊細さとかが不足している。オーケストラも、モーツァルトにしてはややがさつに響く。次のバイオリン協奏曲第3番に登場した米元響子のソロも似たような印象で、日本的にスクエアなところがいまいち。とはいえ、まだ21歳なのに堂々とした演奏ぶりにはすでに大家の風格が漂っている。後半は「戴冠式ミサ曲」。コーラスはガーデンプレイスクワイヤ。どちらかというと若手を集めたソリストといい、若々しい声のこのコーラスといい、祝祭的な気分にあふれたこの曲にはふさわしい共演相手。ソリストの中ではテノールの吉田浩之が日本人には珍しい明るく軽い声質の持ち主で印象に残った。「白鳥」や「アルハンブラの想い出」といった小品ではない曲で「クラシックは何とおもしろい音楽なのだろう」と思った最初の曲はモーツァルトのピアノ協奏曲第26番「戴冠式」だった。その後、生意気盛りになって、音階と和音だけでできているような単純なモーツァルトの音楽からは遠ざかったこともあった。しかし、音響効果のよいホールの、最もいい席で聴くモーツァルトには鳥肌が立つほど素晴らしいと感じる部分がたくさんあった。マンハイム楽派など、一見、モーツァルトと似た音楽を作った作曲家はたくさんいる。モーツァルトがそういう作曲家群と一線を画して素晴らしいのは、すべての声部が、それ自体独立した生き物であるかのように生き生きとしていること、さらに言えばすべての声部が「歌って」いる点にある。器楽曲や宗教曲でも、まるでオペラのように聞こえるときがある。バイオリン協奏曲第3番のラスト近くで突然、オーストリアのノスタルジックな民謡が挿入される部分など、まるでオペラの一場面を観ているようだ。こういうことはやはり生演奏でないとわからないものだ。昼のクラシックコンサート、「昼クラ」がブームなのだそうだ。この日も、リタイアしたシルバー世代が多かった。そのせいか、初演のときはパリ市民が大喜びした「パリ」の第1楽章の転調のしかけにも客席の反応は静かなもの。15年くらい前、クラシック音楽愛好家の新聞記者とクラシック音楽の未来について議論したことがある。彼の主張は、高齢者の割合が多い成熟した社会ではクラシック音楽はブームになる、というもの。そのころはとてもそうは思えなかったが、100万セット売れたという7枚組CDのヒットなどを見ても、あんがい彼の説は正しかったのかもしれない。しかし高齢者にマーラーやブルックナーはきびしい。モーツァルトがもっと聴かれるようになるということかもしれない。
January 30, 2006
コメント(0)
-
ふたたびALWAYS三丁目の夕日(ネタバレ全開)
いい映画は2回観る価値がある。というか、映画というのはそもそも2回観て楽しめるように作られている場合が多い。先日観たときはノスタルジーにふけるあまり気がつかなかったところもあるかと思い、上映最終日にあわててもう一度観てきた。一度観ていると、筋を追う必要はないので主要な登場人物以外の人物や背景などに目が届く。集団就職で上野駅に着いた人たちは、あんなに希望に燃えた明るい顔をしていたのだろうか。希望に燃えて上京したが、小さな個人経営の会社だったので落胆した、というストーリー展開のために明るさが必要だった。そんな気がする。まあ、コメディーのそんな細部に目くじらを立てる必要もないのだが、集団就職で上京した人たちがどんな思いで、どんな表情で上野駅に降りたったのかは強く知りたい。今回、心に残ったのは、テレビが届いて近所の人と大勢でプロレスを観る場面。力道山の空手チョップの場面が、小さなテレビ画面からスクリーンいっぱいに広がる演出が見事だと思った。自分の体がすーっと画面に吸い込まれ、体ごとあの時代にタイムスリップしたかのように感じたのだ。それはそれは心地よい錯覚だった。ほかに大した娯楽もなかった時代、力道山の一挙一投足に、ほんとうに夢中になったものだし、それほどまでに日本人は純朴だった。ショーに過ぎないプロレスに本気で感情移入して観ていた。あのころの、高い教育水準にもかかわらず人を疑うことを知らない日本人の純朴さは、世界史的・人類史的に見てもほんとうに貴重なものだったと思うし、本気でいとおしいと思う。一度観ているがゆえにより深く心に残ったのは、町医者の宅間が帰宅して妻子と過ごす場面。妻子は空襲で死んでおり、この場面は酔った宅間の夢なのだが、それが夢であると知って観るといっそう哀切に感じる。昭和30年代の明るさと暗さは、戦争を抜きにして語ることができない。日本人のほとんどが何らかのかたちで戦争の影をひきずっていた。そして、どんな理由であれ戦争は悪であるという戦後民主主義の根本理念に疑いをはさむ人は、少なくとも庶民にはいなかったと思う。「戦争は悪」は、証明不要の公理だったのだ。金持ちの実父に引き取られていった淳之介が、貧乏作家の茶川の元に帰ってくるラスト近くのシーンには、たぶん多くの人が感涙にむせんだと思う。最初に観たときは、ありきたりの展開に感じてやや白けてしまった。今回は、帰ってくるなと突き放しては結局淳之介を抱きしめる、茶川のアンビバレントな心情に不思議なほど共感できた。淳之介を実父に渡したあと部屋のものをひっくり返す、荒れた茶川の複雑な内面にもストレートに感情移入できた。あらためて、いい映画だったと思う。タイトルロールが流れている間、冒頭に出てきた紙と木の飛行機が背景に飛んでいるのも、最初に観たときは気がつかなかった。神は細部に宿るというが、観ている人が気づかないような細部にどれだけ配慮がされているかが重要なのだ。最初は鼻についた劇画調も、そうと割り切って観れば楽しめた。もっと大げさにやってもいいと思ったくらいだ。登場人物がよく泣く日本映画にありがちな展開なのに、過度に湿っぽくならないのはそうした演出のためだろう。小学校低学年のころの写真を引っ張り出して見てみた。仲がよかったグループのある女の子は、3年間、同じ柄のセーターを着て写っているので驚いた。もう名前もわからなくなっているあの子は、いまどこでどうしているだろうか。そう懐かしく思うのも、みなが貧しく助け合っていた昭和30年代の磁場のせいだ。過去を懐かしんでばかりいてもしかたがないが、懐かしく振り返ることのできる過去のない人生はさびしい。戦後日本人の初心がまだ生命を保っていた昭和30年代が照射するものは何なのかは、いつも考えるようにしたい。
January 27, 2006
コメント(0)
-
こんな映画を観た~Always三丁目の夕日(ネタバレあり)
いま評判になっている映画を観てきた。欠点も多いが、いい映画だ。何十年か後にも心に残る数少ない一本になると思う。冒頭、ゴムで飛ぶ模型飛行機で、すでに「昭和30年代」に引き込まれる。まるでタイムマシンに乗ったかのように、「そうそう、これで遊んだものだ」と40年以上前にタイムスリップしたかのような錯覚、しかし非常に気持ちのよい錯覚に襲われる。そして上野駅とその雑踏。東北・北海道の人間にはとりわけ忘れられない場所であり風景。最初の数分で、涙腺は全開になる。あとは、悲喜こもごもの人情物語に笑い泣き、ノスタルジーに浸るだけ。あっという間の140分。この映画が記憶に残ると思うのは、演技や演出が過剰だったり劇画調だったりという欠点を補ってあまりある、非常に素晴らしい一シーンがあるからだ。貧乏作家の茶川が居酒屋のおかみヒロミにプロポーズするシーンである。ヒロミの指に茶川が見えない指輪をはめるシーン、プロポーズを受諾して見えない指輪を「きれい」と言うヒロミには、昭和30年代の日本人の中にあった最良のものが具現されていると思う。この映画が未来に何かを放射しているとしたら、ひとえにこのシーンの存在ゆえだろうし、もしこのシーンがなかったら、ありきたりの映画で終わっていただろう。おとな役の出演者は全員、演技過剰だ。これは監督の要求であり、喜劇性を追求した結果だと思われる。舞台は東京の下町とはいえ、昭和30年代のおとなはもう少し無知でその分無垢、そして純朴だったと思う。他人の子どもに対しても、自分の子どもに対してと同じように叱ったりしたものだ。それに対して、子どもがいい。子どもとはこういうものだったと懐かしさで胸がいっぱいになる。そして、自分もそのひとりだったことにあらためて気がついて愕然とする。物質的な豊かさと心の豊かさは逆相関にある、つまりトレードオフの関係にあるという「俗説」がある。この映画でも、母親に捨てられた子を引き取りにくる実業家の描き方にそのことは暗示されている。それは明らかに間違っている。しかし、同情心や義侠心は、かなりの程度まで豊かさとトレードオフの関係にあるかもしれないとは思う。おなかをすかしたことのない人に、おなかをすかして辛い思いをしている人の気持ちはわからないからだ。日本人がごう慢さから最も遠かった時代。電話さえまだ普及せず不便で、新興宗教の流行や男尊女卑といったうっとうしいことも多かった昭和30年代。しかし、昭和30年代には、この映画に出てくるような健気さを持った人が、おとなにも子どもにもたくさんいた。それを懐かしみ、それが喪われたことを嘆いて何が悪い?
January 18, 2006
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~ゲルギエフ指揮マリンスキー歌劇場管弦楽団
このコンサートの事前の興味は二つ。ひとつはロシアのオペラのオーケストラはどんな音がするのだろうかというもの。もうひとつは「鬼才」ゲルギエフがどんなマーラーをやるのかという興味。結論から言うと、悪くはないが、ぜひゲルギエフでマーラーを聴きたいというほどの演奏(解釈)ではなかった。むしろ前半に演奏されたチャイコフスキー「くるみ割り人形」からの抜粋が「おそるべき」演奏だった。メルヘンなおとぎ話として軽く扱われるこの曲に、実はとてつもなく深い何か・・・人間が宿命的にもつ悲劇性のようなもの・・・があるということを感じさせられた。音で思考するというか、音楽で哲学し瞑想したようなチャイコフスキーというべきか。ユーリ・バシュメット、ゲルギエフ、そしてロストロポーヴィチ・・・なぜかこうしたロシアの音楽家の演奏には、西洋や日本の音楽家には決してない<瞑想的>な何か、深い地の底へ降りていく感覚に引き込まれることがある。後半のマーラー(交響曲第5番)は、尾高忠明や小澤征爾の白熱と集中、インバルの緻密さに及ばない。もちろん凡庸な指揮者とは比較にならない素晴らしい演奏ではあるのだが、ゲルギエフでなくてはならないという必然性のようなものは全く感じられない。何カ所かはイージーに、ルーティンワークに流れていたところをみると、ゲルギエフの資質とマーラーの音楽には根本的に相性の悪い部分があるのだと思う。オーケストラはすばらしかった。歌っても決して吠えない管楽器。強奏しても柔らかくまろやかで甘い響きの弦楽器。いまでは少なくなったローカルさと現代的なビルティオーゾティが両立している。しかもオペラのオーケストラのためか柔軟で室内楽的な音楽作りは実にヒューマンな温もりがある。ベルリン・フィルはもちろん、ウィーン・フィルよりもこのオーケストラの方が好きだ。このオーケストラをここまで育てたのはゲルギエフの功績だと思うが、本人にはもう少し音楽的な成熟を期待したい。
January 7, 2006
コメント(0)
-
薬が効いた
薬が効いて、母の左股関節の痛みは劇的に緩和されたようだ。それにしても予防や健康作りといったことに関心のある医者というのは少ない。病気を見つけ、治療するのが医者の仕事だと思っている。何と愚かなことか。それでは病人相手にしかビジネスができないではないか。予防や健康作り、アンチエイジングといったことなら、すべての人を相手にビジネスができるというのに。すぐ近くの内科医は、糖尿病になり手足を切断した。あとを継いだ息子も肥満気味だ。その2軒となりにある歯医者は完全に肥満。治療のとき前にかがむと呼吸が苦しくなりゼーゼー言うので気持ち悪く、二度と行かないことにした。300メートルほど離れたところにある内科医は70歳をすぎてからジョギングを始めたようだが、まだタバコを吸っている。そういう姿を、地域住民はよく見ている。
January 5, 2006
コメント(0)
-
背中の夕陽
母は「年末休養」を終えて病院へ戻った。三度の食事を一緒に食べ、夕方にはお風呂を沸かし、テレビやDVDを見ながらおしゃべりする。そんなごく日常的なことの繰り返しが何とかけがえのないことかと思う。母がいないと火が消えて冷たくなった石炭ストーブのように家の中がさびしい。しかし不思議なことに、弟は何も感じていない気がする。母がいる間も、遅く起き出してきてはひとりで食事をとる。ひとりの食事の味気なさを感じない人間というのは、本質的に大切な何か、共感力のようなものを欠落させているような気がする。いろいろ聞きだそうと思っていたことも、家にいると気が散ることが多く何も聞けなかった。戦前生まれの多くの日本人の男がそうであるように、父も家庭を顧みることはほとんどなかった。だから、子どもの頃の楽しかった思い出に父はいない。例外は、家族そろって出かけたハイキングの記憶。年に一度くらいは家族旅行をしていたと思うのだが、バスや列車に長時間乗るのは子どもにとってあまり楽しいことではないし、旅としては受け身だ。むしろ、自分の足で歩いたり、自転車で出かけたりしたことの方が楽しい記憶になって残っている。それにしても家から歩いてハイキングに行けたのだから、昭和30年代は何と豊かな自然に囲まれていたことか。どこまでも広がるジャガイモ畑の中をトノサマバッタを追いかけて走り回り、昼食は草むらの上にお弁当を広げた。たったそれだけのことなのに、あんなに楽しいことはなかった。たしか写真があったはずと探したが見あたらない。夕陽を背に帰ってきた、あの楽しかったハイキングのお礼を母に言っていないことが、心の負担になっている。
January 4, 2006
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1