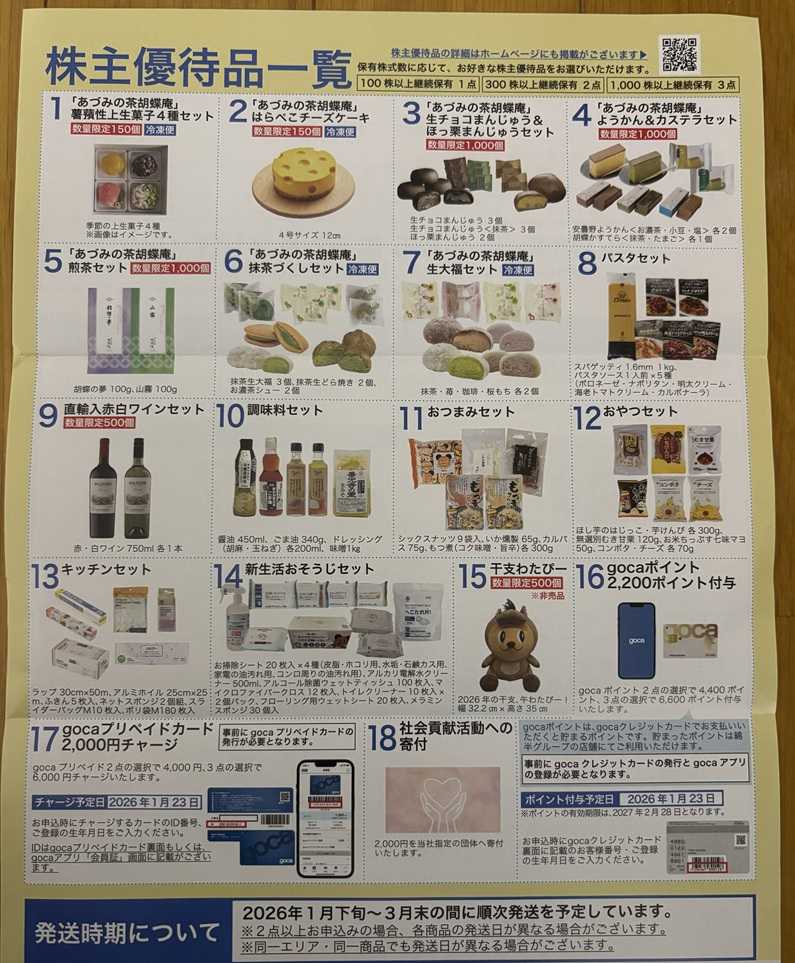学校に提出した手紙の内容(9/2)
諸先生方
平素より、愚息が大変お世話になっております。本当にありがとうございます。
三年 ■■■■の母です。
先生方におかれましては、ますますのご健勝のことと拝察申し上げております。
このたび、このようなお手紙を差し上げる無礼をお許し下さい。
3年生は、一学期の授業を通し、また夏休みの宿題として、「バリアフリーの研究」を頂いているとのことを知りました。
本当にすばらしい授業を考え出して下さったこと、感銘いたしました。ぜひこれからも積極的に継続いただけることを切に望んでおります。
が、しかし、その授業の題が、「やさしさ見つけ」というものであるとか。
大変失礼ですが、その視点に大いなる疑問を持ちました。
「やさしさ」とは、一見大変よい言葉のように感じますが、この場合どうしても、健常者(強者)が障害者やお年寄り等(弱者)に対して、譲っている・・・・という意味が含まれてしまいがちです。
とらえ方によっては、嫌な優越感さえ見え隠れします。
もちろん先生方がそんな意図でないことは十分理解しておりますが、この言葉から違う連想をしてしまう子供たちが生まれる可能性があるとしたら、やはり訂正いただくべきなのではないかと存じます。
社会はどうしても前提条件として、強い者に有利なようにできています。
それをやっと一部の国では、本当の豊かさのために、また少子化社会を迎えるためにも、弱者も同様の権利を持ち、皆が一緒に住みやすい社会を作るために、新しい努力を始めています。
これが「バリアフリー」です。
差別や区別や不便をなくし、等しく利用でき、過ごせるための工夫です。
そこで大事なのは、わざわざ「強者が配慮していやる」のではなく「自然に当たり前のように配慮されている」ことなのだと思います。
以前、公共施設の建設プロジェクトに参画する機会を得たことがあります。
そのとき、複数の障害者の方々に、直接バリアフリーを教えていただき、また議論を尽くしましたが、こうおっしゃった方がおられました。
■「『区別』というのはすでに『差別』が始まっているのです。
変に気を遣うというのは『区別』であり『差別』なのです。
健常者も障害者も、何も気を遣わなくて、すんなり生活できるように配慮することが
バリアフリーなのです。」
■「障害者も『一個の人間』です。多くの権利を持っているのです。
『手助け』とか『やさしくする』とかというのは、相手を見下しているのと同じと
思いませんか?」
■「目が見えないことは、私にとっては、肌の色が黄色いというのと同じことなんです。」
私は今までの考え方を恥じました。それまでの私はバリアフリーであるべき等の主張をしながら、本当のバリアフリーの視点を持っていなかったのです。
今の私は知っている私です。私の息子にもそうあってほしいと願うばかりです。
先生、どうか将来の社会を背負う子供達を育てる学校でも、本当のバリアフリーが理解できるよう、危うい意識を植え付けてしまう可能性を摘んで下さい。
どうか、どうかよろしくお願いいたします。
また、公文書となる通知票にも同様の記述を見つけました。すでに配布されたものですので変更が大変な負担になるであろうことは予想できます。せめて今後だけでも訂正していただけないでしょうか。
障害をもつ人だけでなくその家族も心が傷つけられている可能性があります。
そういう方々はとても配慮があって、口に出さないことが多いのです。どうかご配慮賜りますよう、よろしくお願いいたします。
ちなみに、私は息子に以下のように指導をしました。
■『やさしさ』はおこがましく、優越感が見える可能性があるので、全く同等な目線で捉えた『バリアフリー』という言葉を使うべき。
バリアは、人と人をへだてようとするすべてを言い、フリーはそれを崩して自由になることを言い、社会みんなが等しく普通に暮らせることをいうのだということ。
■例えば、お店に行って、高い椅子しかなくて、子供のあなたが座れずに困っているときに、店員さんが子供用の椅子を持ってきてくれることは、「やさしさ」ではなく「きがつく」ことで、あなたからみたら当然の権利といってもよいこと。
(但し、そのとき感謝の言葉を言えるあなたでいてほしい。たとえ権利であっても、その人は気づいてくれ、行動に移してくれたのだから、感謝できる心の余裕を持ってほしい。)
■例えば、前をとてもゆっくり歩く歩行者がいて、それを追い越そうとする人間が、前の人のじゃまにならないように歩くのは、やはり当然であること。
■彼が調べてきた「エレベータの鏡」は車椅子の人のためだけになっているのではく、私や息子にとっても姿を写したりしてとても便利なこと。それはバリアフリーの工夫であること。
■彼が調べてきた「点字」は目の見えない一部の人にとっては助けとなるが、途中失明等で点字ができない人も多く、点字があれば視覚障害者が困らないのではない。One of Them(複数の選択肢のひとつ)にしかすぎないこと。
■貧しい人が、豊かな人より劣るのではなく、あくまでもお金を使って手が届く範囲が限られているに過ぎないこと。
■肌が黒いことも、白いことも、黄色いことも、自分ではけして選べない。でも、流れている血は同じ赤、骨は白。まったく同じであること。
同様に、目が見えないことも、足が不自由なことも、望んでそうなったわけでなく、そのひとの特徴となっているだけであること。
■人間として恥じ入るべきは、傲慢。優越感というものは傲慢の一種にすぎないこと。
専門職の教育者の皆様におこがましとは存じましたが、敢えてお手紙申し上げました。
なにとぞ、気持ちをくんで下さいませ。 よろしくお願いいたします。
■■■■
平成17年9月1日
© Rakuten Group, Inc.