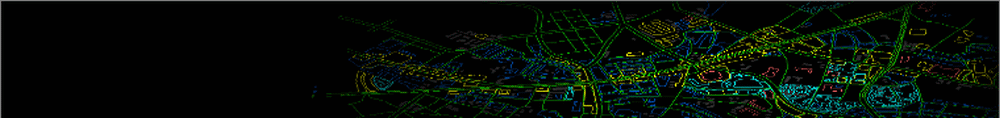月~人類の歴史の傍系5 杉野正誘拐事件~
マンホールの裏、地下水路の中の歩道の上、そして爆破された車。
それらの写真を見るたびに構成員の中の唯一の女性の顔色はどんどん悪くなっていった。
「どうした、メリル、顔色が悪いぞ。」
いつもは冷静沈着なおそらくこの構成員の中では一番有能だろう、この女性にしてはあまりにも珍しいことである。周りの皆の心配をよそにメリルは無言を貫いていた。
「・・・」
この言葉を象徴として扱うのは、イスラム教徒以外にこの世にもう2人しか残っていないだろう。
自分と、杉野だ。
おそらく、兄を殺したのは杉野であるに違いない。
「・・・」
同じぐらいの時刻だったろうか、セリムもメリルと同じく無言にならざるを得なかった。
ロス島の地方紙に、大学教授から聞いた事件らしきものをようやく発見したのだが、
明らかにそれは異常な状況で保存されていた。
老人と少年が強盗に襲われるとの見出しの下にあっただろうと思われる写真が、ない。
きれいにカッターで切りとられているかのように、ない。
7月5日午後11時ごろ、近所の老夫婦が発見したらしい二人の遺体が写っているらしき写真がない。
これはもう、現地へ行くしかないだろう。
セリムは早速出張の手続きに入った。
「ジョーン=アル・ファトフって、誰なんですか?」
無残にへし折られた十字架の下に書かれた名前について少年は杉野に初めての質問をした。
「シュケルだよ。名無し君でも、いまさらわかりきった質問をするんだな。」
「ジョーンというと、欧米人の名前、ですよね。アラブの名前と一緒にするのはかなり無理がありますね。」
「ああ。」
「シュケルは欧米人なんですか?」
「おそらく、半分欧米人だ。父親はイラクに駐留していた米軍の軍人だったらしい。母親は道であるいた所を無理やり強制収容所に入れられたかわいそうな女性だよ。そこで、あってはならないことが起こった、ということだ。」
…少年は眉をひそめた。起こってはならないこと。
「大体、女性たちが“ひどい事”と表現することですか?」
「そうだな、捕虜に対するレイプだ。それによってシュケルは誕生した。だから、母親の名前も父親の名前もわからない。彼らのような子供の処理に困ったアメリカ軍に泣きつかれて最初に育てる事となってしまった孤児院のシスターが最初にそう名付けたようだね。だから、へんてこりんな名前になってしまった。シュケル、との名前が与えられたのはブルネイの富豪に引き取られた後の話だ。」
杉野は事実を簡潔に語った。名無し君には隠すことでもないだろう。シュケルの出生がどうであれ、シュケルがチンギスハンより広大な領土をもった今のところ人類史上最大の英雄であったことには変わりはない。
思い起こせば、チンギスハンも父親の名前が明確ではないといわれている。彼の生まれた時代背景を考えても、おそらくは同じような出生であった可能性も少なくないと杉野は考えている。
ついでに、公にされてある史実では墓もどこにあるかわからないこともこの二人の共通点と言える。
シュケルの遺体はイスラム教徒が最も忌み嫌う火葬にされ、メッカの方向に向けて埋めてほしいという本人の意向など全く無視され、太平洋にばらまかれた。チンギスハンもユーラシア大陸のどこかの森に埋められたそうである。分かっているのは公にされている事実ではどちらの“墓”も今は放射能づけになっている、ということだけだ。
「可哀そうな人だ。」
少年は静かにシュケルの墓に語りかけるように話した。
その青い瞳には同情、というよりも共感の念が浮かんでいるように杉野には思えた。
「名無し君のご両親はご健在なのかね?」
つい、そう聞いてしまった。おそらく礼儀正しく無視される、と思っていた杉野の耳に思ってもいない言葉が飛び込んできた。
「僕は人工授精で生まれました。父は元アメリカ海兵隊の優秀な兵士だと聞きました。生きていれば120歳ぐらいになるんじゃないですか?僕の生まれるずっと前に亡くなったと聞きました。母親はわかりませんが…僕の見かけからでもわかるとおり多分白人ではないかと思います。」
すっきりとした顔立ちの中に東洋的な面影もないわけではなかったが、少年の目は見事なアイスブルーで、髪の毛は金色に輝いていた。この時代には珍しいほど、純粋な白人、といった見かけだった。
「ついでに、僕は名無し君ではありません。3歳の頃に教官に付けてもらった名前で、元から親につけてもらった名前はあったかどうかもわかりませんが、ショーン=マクレガーといいます。この間12歳になったばかりです。はじめまして、ですね、杉野正さん。よろしくお願いいたします。」
「やっぱりな。」
ロス島の放射能値は高い。両親も妹も放射能障害によってこの世を去っている割にはセリムはその点ジャーナリストだった。別に気にする様子ではなく、大きな体の割には小さな手帳にその事実を書きつける。
ロス島には有名な活火山エレバスがある。昨年の今頃、また爆発を起こし、放射能除去装置が2日間機能停止になる騒ぎがあった。
政府の素早い処理によって人間が住めないほど数値が上がることはなかったが、危険な地域であることには変わりはない。
目指す村はその前の大爆発の際に、火砕流に飲み込まれ、今は廃村となっているそうだ。
かなり歩く必要があるらしい。
セリムはエレバス登山の際、必ずと言っていいほど皆が寄るといわれる登山専門店に足を運んだ。
そこである少年とおなじタイミングで、一番人気の同じサイズの登山靴に手を伸ばし、思わずお互いが手を引いた。
「ど、どうぞ。」
「い、いえ、そちらが御先だったようですから。」
少年にしては丁寧な言葉にセリムは店員だと思ったので気楽に語りかけた。
「ベルディ村の方角を教えてほしいのですよ。廃村になってずいぶん経つと聞くのだが、、取材でどうしても行かなくてはならなくてね。」
「ベルディ村ですか?また辺鄙なところに行かれるんですね。」
「ええ、廃村特集を雑誌で組んでましてね。統括政府下のいろんな廃墟へ行って取材するのが、私の仕事なのですよ。」
「そのセリムという名前は聞いたことがあるな。確か統括政府に睨まれてるジャーナリストだ。前大統領の汚職について一番最初に暴露した人間のはずだよ。」
「本人は全国の廃墟を回っているんだと自慢げに語ってましたよ。その割にはかなり太ってましたが。あれじゃぁ、絶対に100キロは超えているかと思います。」
「ふん、おそらくはデスクの上で、情報収集をしながらのジャンクフードの食い過ぎだろう。あの山道を乗り切れるかどうか、見ものだな。後ついて行ってみるか?」
杉野とショーンは目を合わせて笑った。
次の目的地も山だ。とだけ杉野はショーンに伝えてあった。
ただ、もう一度同じ山に登る話はしていない。
「さあ、行こうか。」
杉野は靴をはきなおした。ビジネス用の靴では以外に足跡が目立つ。これで、わざわざ岩の上を飛びながら移動しなくて済む。
「どちらへですか?」
「付いてくんだよ。あの男は必ず“組織”に追い付かれる。そして、墓場の前で殺されるだろう。これ以上、むざむざ無実の人物を殺させるわけにはいかないしね。」
なるほど、登山の予定とは、そういうことか。
杉野の容姿はこの島では目立つ。ということで代わりに自分が買い物に行っていた。
山に登るときも下りる時も足跡を気にして、岩の上を猿のように身軽に飛び回る杉野の靴がついに昨夜、宿に着いた時に悲鳴を上げるように破れてしまった。
仕方なく新しい靴を買うように指示され行った店でセリムという男に出会ったのだ。
ショーンを外に出したのは別の目的もあるが、教官の多くがロス島の出身であるらしいショーンはどこの店のどのサンドイッチがおいしいか、とか、色々情報を知っていた。言わなくても杉野のもう一つの目的を彼は敏感に察知したらしい。あらゆる所に顔を出し、色々なものを買い付けて来ていた。
そのロス島の珍味やら、美味やらを一応腹八分目に食べて、二人はセリムの後を追うことにした。一応、心優しいショーンはセリムには一番難易度のない山道を紹介してやっていた。追いつくのはすぐだろう。
杉野としても、ショーンからある程度のことは聞いているとはいえ、ほぼ初めての“組織”との遭遇である。そういうチャンスでもない限り、アラブ系の太ったジャーナリストなどを守ってやる義理も道理もないのであった。
「カエサルのものはカエサルに、とイエスキリストが言っていただろう、
アル・カーフィルーン、ね。アヤトラ師がその昔にたしか、同じ意味の言葉がある、と教えてくれたことがあったよ。
確か…あなたがたには,あなたがたの宗教があり,わたしには,わたしの宗教があるのである、てな言葉で閉められたものであるはずだ。」
親友の記憶力には脱帽さざるを得ない。アッタードが持ち込んできた写真には見事なアラビア語の白い文字が色々なところに書きつけられていた。
叔父の死後もその命令に従っているのはいかにも彼らしい、とカートはおもう。
「杉野はアラビア語もかけるんだな。それにしてもきれいな字だ。知らなかったよ。」
そういうアッタードにカートはこともなげに言った。
「あの男は20もの言葉を操れるという特技がある。ついでに変装の名人だ。長年の親友であるテン大統領も知らない素顔がたくさんある男だよ。」
「20もの言葉って、一体どれだけの言葉なんだろう。」
「日本語、英語、フランス語、中国語は全部で3種類話せるらしい。アフリカの言葉にも精通している。後、奴の頭の中には月と地球のすべての地図が記憶されている。日々、コンピューター並みに更新もされているようだ。」
やはりあまり近づかなくて良かった。元からあまり気が合いそうではない男ではあるが、ここまで機械的な男であるとは知らなかった。
「おそらく今現存している人類の中でいちばんIQが高いといわれているらしい。」
「よく脳外科に通っている、って言うのはそれでですかね?研究材料とか?」
「いや、それとはまた違う理由だがね。とにかく彼の脳みそは死んだ後、あらゆる学者がほしがる代物となりそうだとのことだ。おれたちの脳みそとは作りが違うらしいな。」
人間の脳みそのシナプスはある年齢に達すると減少に転ずる。どうやら杉野はその減少の度合いが人より10倍は遅いらしい。何らかの障害なのか、遺伝なのかは今のところ不明らしい。
「見た目は老けてるように見えるんだがね。」
という親友の素直な感想に吹き出しそうになりながらカートは本題に入った。
「なぜ、杉野は勝手に統括政府の地下道にもぐりこんだと思う?」
「さぁ。助けた少年兵がお好みだったとか?かわいそうに。今頃、お母さんに助けを求めて泣いているだろうな。」
「そんな下ネタではない。」
とうとう吹き出しながら、カートは新聞から切り取ったらしい一枚の写真をアッダードに見せた。
白人の老人と少年が血だらけで倒れている。
「2047年に起こったこの事件がすべての原因さ。彼はその失敗をいまだに挽回するチャンスをうかがってたんだろうな。」
「そこら辺の爺さんと子供だろう?それが杉野と何の関係が?」
「この爺さんはお前もよく知ってるはずだ。通称をシュケル=ラディンという。この男を助けるためにセディームの命を受け、杉野はロス島へ向かったが・・・とんでもない先客がいたわけだよ。それが横に倒れている少年だ。どうやら人を殺すために育てらてたような少年でね。その少年がシュケルを殺したらしい。」
「しかし、シュケルは2042年に死んだはずじゃぁ…それにこの爺さん、白人だろ?」
「ほとんど誰も知らない事実なのだが、シュケルは白人男性とアラブ人の中でも白人に近い女性のハーフらしい。髪の毛、ひげに至るまでの体毛すべて、も肌の色も染めていたとの話だ。処刑されたシュケルはあれは本当によく訓練された影武者だ。実際はPLOとの駆け引きの道具のためにしばらくロス島の田舎の小屋に軟禁状態で、生かされていたらしい。それが、PLOとシュケルの考えは根本から違っていてね。それがアル・カーフィルーンに代表されるイスラムの教義なのだが、そういう関係上、シュケルを生かす必要がないと統括政府のウチの急進派が判断した、と聞いて、叔父は当時、外交部という名前の中でスパイとして行動していた杉野に命令した、ということさ。」
「しかし、なぜ、シュケルがそんな中途半端な立場で軟禁されていたんだ?一時は地球の半分以上を治めた男だぞ。」
「シュケルは自分が破れたと思ったら、もう、その地位には何の未練もなかったらしい。少しでもたくさんの同胞を救うために道具となる道を選んだ、というところらしいが、残念ながら、無駄に終わったというわけだ。仕方がないので、殺すとなっても騒ぎになっては困るとのことで、アヤトラ師がいる月に移住させたらどうだ、という話が地球から来てな。準備をしているさなかに急進派の穏やかではない噂を聞いて急派されたのが杉野だったわけだが・・・」
「この少年に先にしてやられた、ということか…まぁ、話はわかった。しかし、あのシュケルとはだれも思わない爺さんと少年の遺体が転がっていたとしたら、誰にも気づかれないような、そんな失敗程度だろ、その程度で、杉野がスパイに戻らなければならない理由でもあるのか?」
「その少年の属する“組織”の真の目的はおれたちの抹殺になる。」
「は?」
こんな少年兵など、100人かかってこようが、今の連合政府の兵力には到底及ばないはずだが・・・それにしても、シュケルが白人だったとは。
アラブ人の自分もかなり近くまで接近し、一緒に酒も飲んだこともあるが、全く気付かなかった。確かに眼のあたりの面影は写真の老人とシュケルは似ていないわけではないが・・・
それにしてもなぜ、杉野なのか?
この連合政府内にスパイ、といった前時代的な役職が存在していることも今日初めて知った。
いや、杉野という男は知れば知るほどいろんな事を教えてくれる存在だ。
どちらかというか、アッタードからみると薄気味の悪い事実ばかりではあるが。
それにしてもカートも人が悪い。なんで、このタイミングまで、こんな大事なことを教えてくれなかったのだろうか?
いぶかしがるアッダードのためにカートは用意してある映像を見せる準備を始めていた。
「この事実を知らないのは我らがテン大統領閣下だけですわ。
杉野も、カートも熟知しているはずです。急いでください。杉野がどこに隠れているのか、それを早く探し出さないと。」
メリルの言葉の通りに今のところ“組織”は動いている。しかし、サウザンドから出た彼らの動きがわからない。
「少年兵からの連絡はないの?」
「ああ、いまだに意識が戻ってないのではないのかね」
そんなはずはない。あの子は、あの子なら、絶対に組織を裏切らないだろうし、元気なはずだ…何らかの方法で、無事を知らせるはずだ。
“組織”は必ずロス島のあの墓地へやってくる。それを一番楽しみにしているのは、汗かきのセリムのあとをショーンと失笑しながら静かに尾行する杉野自身だった。
© Rakuten Group, Inc.