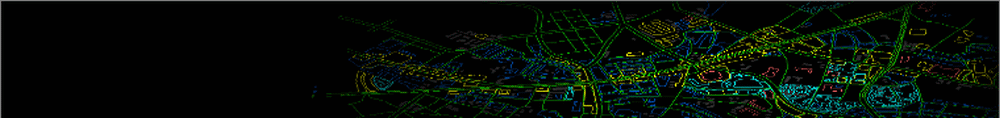月~二人の天才と残り一名 3~
20世紀にはあまり知られていない話だったが、放射能除去装置をつけ、人間が住めるほどに氷が解けた結果、ロス島と呼ばれるエレバス山がある地球時代にヴィクトリア・ランドと呼ばれていたところはほとんど島だらけとなっていた。サウザンドがあるのがウインクスランド地方である。
テンとアクア夫妻とともに命からがら北側のノースイーストがあるクイーンモードランドについた途端、セリムの横に立っていた金髪の青年が柔和な笑顔で近づいてきた。
杉野が知らない顔ではない。統括政府史上最年少の市長さん。ショーンほどの美貌ではないが、それなりの容貌で女性に人気が大変高いらしい。との話は聞いている。
「イーサン=ジュニア=ヨーゼフといいます。ノースイーストの市長をしています。」
「ショーンの同級生だったんだ。こっちで居酒屋を経営していてね。時々こっちに来るたびにお世話になっていたんだ。」
“死の天使たち”はあの杉野事件の後、“組織”が自主的に解散したといわれる。ほとんどの生徒は“組織”側の兵士として地下に潜ったとの話だが、彼をはじめとする数人の生徒たちはセリムの世話で、それぞれに養子に行くことになった。彼を引き受けたのがノースイーストの居酒屋を経営していたそれなりの資産家だったらしい。
「ショーン君とはあまり縁がなかったんですよ。彼はあの通りの優等生で僕は中間以下の成績だったので、彼が僕を覚えているかどうか…」
趣味の料理をしたくてどうやらその道に進ませてくれそうな人を探していたらしいが、結局は経営の腕を見込まれてその資産家の後を継いだ。
その様子を見て商店街の人々から市長としての選挙に出ないか?と誘われたのは去年の話だった。
若い彼が当選するとは当初はだれも思わなかったが、ありがちな市長の汚職問題でもめていたこの市の市民はすったもんだの末に彼を選んだ。こうして24歳の若い市長が誕生した。
ようやく公務になれたばかりの彼の上にいきなり降りかかった困難。
故郷がほとんどなくなったロス島の住民や、サウザンドほどの打撃はないが、それらの難民を受け入れるにはノースイーストには力がなかった。
月に頼るには昨年結んだ“相互不可侵条約”が邪魔になっている。
「しばらくはジャガイモを食べればいいじゃないか、あきればパスタをアンチョビを付けて食べたらいいさ。うまいワインがあれば何とか乗り切れるぞ。」
著名なジャーナリストの発言とはとても思えない気楽なセリムの言うとおり、難民たちが食べられるのはこの地域に山ほどあるジャガイモと小麦だけだった。
ウスマーンがなくなったのは2年前のことだった。
PLOの中の一派に暗殺されたとのことだ。生涯テンとの約束を守り続け、メッカに帰してくれた恩を皆に説教していた男を邪魔に思う勢力がそれ以降かなりの勢いでのしてきている。
統括政府から独立する形で、PLOがメッカに移住したのは2069年のことだった。
それから5年もたたないうちに反ウスマーンの彼らは異常な力を持ち始める。
後ろに“組織”がいるのは明らかな事実と言うことで、杉野も何度かカートに報告していた。
南極にいたときは盤石のはずのウスマーンの影響力はメッカに行った後もかなりのものがあったが、それが必ずしも絶対のものでもなくなってきていることも杉野の心配に輪をかけていた。
そのウスマーンが暗殺され、急進派のアル・ファトフ師が導師として就任したと聞いて悪い予感がより、つのっていた。
彼はイスラムでありながら“組織”の一員であるといわれている。
噂によると例のメリルとも儀式とやらであやしげな行為に耽っていたといわれている。
政治の世界だ。歴史とはこういうものだ、と杉野は思ってはいたが・・・
カートは今のところは月は手は出せない、というスタンスを取っている。去年連合政府と統括政府の間で結ばれた“相互不可侵条約”がその足かせとなっていた。
それを待っていたかのように南極大陸に侵攻してきたイスラム軍と当初テン率いる連合政府軍はよく戦っていたが、多勢に無勢とはまさにこの言葉で、ロス島は破壊され、サウザンドも焦土となった。
彼らの標的は次はノースイーストだろう。
どう戦うか?
テンをはじめとする連合政府軍にも人材はいないわけではないが、杉野の事件以来、専守防衛を表に出しているために軍事教育も制服組は戦術担当が多いらしい。アル・アッタードやアマンダのような戦略までち密に組める人物と言うとかなりの年齢の人物たちとなって来る。テン・イーモウとその戦友たちだ。第3次世界大戦を戦ってきた老兵と呼んでいい人材である。
彼らを中心に戦隊を立て直す必要があった。
陸戦を得意とするのはテン・イーモウとチャン・べリンガーという韓国系アメリカ人だ。彼らは第3次世界大戦の最後には中将まで上り詰めている。
それぞれ、戦略まで組める程度の経験と実績はある。
空戦を得意とするのは68にもなって宇宙空間にも出れる最新戦闘機“シェリー”を乗りこなすジョナサン=カマル。彼は空戦に戦略を持ちこんだ最初の人物として名高い。彼は少将だ。
後、杉野の存在も忘れてはいけない。
一応去年定年を迎えたことになって、連合政府の情報部は退職している形ではある。今回組まれる“義勇軍”に入ることになるだろう。
後一人、いい人材がいる。
アマンダだ。
今頃兄の結婚式で飲んだくれていることだろう。その酒の中には薬が入っていて、情報部の部員とともに明日目覚めたら彼女はノースイーストにいる予定だ。
最近元交際相手とかなり派手な喧嘩をして別れたばかりらしく、父カートとしてはいつまでも3面記事を騒がせる“娘”お灸をすえる意味でも実戦に参加させる必要があった。
理由はどうでもつけることができる。なんならセリムという見事な代弁者もいることだし、一回、彼女もそろそろ実戦を経験しておいて損はない、というのが、彼女の師匠であるアル・アッダードと杉野とテンとカートの共通の認識だった。
後は兵士だ。
白人勢力とアジア人勢力、少数だがアフリカ人勢力もいる。
この3勢力は今までは決して交わることはなかったが、この国家の未曽有の危機の中で団結することになった。どうしてもイスラム教にはなじめない人々もいる。
シュケルならなんとも思わなかったろうが、アル・ファトフはちがうだろう。
アッ・ザーリヤートは焦土と化したサウザンドをみてすっかり満足した。
自分たちイスラムコミュニティーの人間は放射能に汚染されている可能性があるから入ることを許されなかった場所だった。
本当は核爆弾でも落としてやりたかったが、“組織”の手前、それは避けた。
それをしなくても彼は勝てる自信があった。
相手は過去の栄光にすがりついた老兵どもだ。
戦場ほど体力を消耗するところは少ない。彼らの体力で持つかどうか?アッ・ザーリヤートのような若者は嘲笑するのみであった。
彼を途中からだが、育てたのが“組織”の教官たちだった。
ショーンと言う天才を失った彼らがショーンと比肩する、とまで評したアッ・ザーリヤートとショーンの最大の違いは地位への執着、その一言に尽きた。
ショーンは自由を愛する男だが、アッ・ザーリヤートはその逆だった。まさに“組織”向きの男だったのだ。
眠い目をこすってアマンダが見た風景は生まれて初めてみるものだった。
「ここはどこだ?」
「地球のノースイーストですよ。アマンダさん。」
杉野の声には聞き覚えがあった。ショーンが師匠とあがめる男。悪い予感がした。
「昨日、兄の結婚式があって…」
花嫁はそれは美しかった。兄ラフマーンの婚約者として紹介されたジョシュアも担当していた妊婦が難産だったことで来るのが遅れたがいい人だった。父は花嫁に伏し目がちに祝福の言葉を言っていた。ミケーレはそれを見てただほほ笑んでいた…
ショーンはと言えば、プラトン=ナイドゥの孫とやらを連れてきてしきりに自分に紹介しようとしていた。確かに趣味も合うし、いい奴だが、恋愛対象としては考えられない…その男と色々音楽談義をしながら飲んだ酒が変に回るな、とおかしく思った時にすでに意識はなかった。
強烈な二日酔い。
普通ではありえない。
「薬でももったんですか?」
「よくお分かりですね。」
何が“よくお分かり、”だ。ショーンと杉野が肝胆相照らす仲なのは知らないわけではなかった。今回の計画にこの2人が絡んでいるとなると、逃げることは難しそうだ。
軍事大学時代、それとなく生存術を勉強し、師範までは行ったので、ためしにショーンと組んだ時にまた10秒で初めて会った日のような経験をさせてもらった。
そのショーンの師匠さんが今度は監視役だ。もう同じ失敗はしたくない。
また、終身刑だ。ボンド先生のような優しい先生は現れるのだろうか?
杉野から明日の朝には今後の方向を決める軍事の会議が開かれるとのことを聞かされた。うなずくしかないアマンダであった。
月の新聞にはアマンダを良く知る人物が読めば爆笑するようなセリムの代筆のアマンダの手記が載せられていた。
「いい選択だな。」
妹の活躍ぶりに少々心配していた世話好きの兄ラフマーンはほっと胸をなでおろしていた。そんなことは関係ないほど忙しそうにジョシュアは初めて担当した妊婦の状態がおかしいことを心配しながらも、手早く2人分の弁当と、夕食を作り飛び出していこうとした。
「ジョシュア…あ、あの、挨拶の…」
まさか、昨日の新郎新婦のキスを見て思いついたのだろうか?
ジョシュアは絶対にしたくないことをラフマーンはしたがっているようだ。
ラフマーンは目をつぶり、可愛らしく口をつきだしてきた。
仕事に行く前にキスなんて。その上可愛らしい表情が全く似会わないラフマーンの様子が笑いを誘った。
こういうことは趣味ではないジョシュアは困ったようすだったが、ちょうど手が濡れていたので、その口に二本の指を押しあてて満足した様子のラフマーンを残して出て行った。
ラフマーンがその事実を知ったのは入籍して1年ほどたったある日の朝である。
二人が大げんかになったことは言うまでもない。その上、結局ジョシュアの勝ちとなったことも予測通りだった。
「これ以上の治療は難しいってどういうことですか?先生、彼女をこのままあの地球へ返せと言う事なんですか?」
医師の信じられない言葉にジョシュアは激昂した。今日は朝から変な日だ。ラフマーンはへんてこりんなことをしてくるし、医師も非人道的なことを平然と言い放つ。
確かにこの妊婦は中国系の華僑と結婚しているイスラムの女性だ。“相互不可侵条約”によってこれらの人も月に来ることはできるようになったのだが、3年に一度ビザの申請のために地球に帰らないといけない、という条項が含まれていた。政治にはあまり興味のないジョシュアから見ると重病者は別だという印象があったが、先生から奪い取るようにして読んだそのリストの中に「妊婦」という言葉は確かにない。
「だから、妊娠に伴う疾患はこの条項には含まれない、という院長の判断なんだよ。」
…こんな大事なことを忘れるなんて。
おそらく地球側と最後に推敲し折衝に当たったのはラフマーンのはずだ。どうしても今日のアホ面が目にちらつき、余計イライラが募った。確かに妊婦は病人ではない。しかし、病人となる可能性が一番高いリスクのある人たちなのだ。
「彼女は38歳で初産。それも被爆経験者です。相当な難産でしたし、産後の様子も普通の妊婦とは違います。人道的に内戦状態の地球には返せません。私は断固反対します。」
「同じアラブ系だから感情が移入するのはわかるが・・・」
「フランス人でもアメリカ人でも同じです。先生のおっしゃる意味がわかりません」
この男は何を言っているのだろう。
ビザが切れそうでも伸ばせる方法はないのだろうか?
看護婦の集団で院長に抗議した結果、最悪、最後の手段として、不法移民管理局の病院に転院させる、との話し合いに落ち着いた。そこで、今の統括政府にビザの発給を特例として申請させる、という相当めんどくさい話ではあり、この今体の弱っている女性にそれは酷な話だし、これ以上何もしてやれないというジョシュアは複雑な心境だった。それでも涙を流して喜んだこの女性と夫の姿が痛々しかった。こんな幸せな夫婦が、一つのケアレスミスで、別れさせられる可能性があるのだ。これが生まれたときから日の当たる道を歩んできたジョシュアが最初に体験した“社会の不合理”だった。
彼女が政治に興味を持つのはかなりのちの話となるが、この事件が、このかなり先にはなるが彼女の進む道を変えていく起爆剤となる。
「20世紀から21世紀にかけての女性の慈善事業家、反政府指導者には、はかなりの社会的地位のある家の出身者が多い。マザーテレサ、プリンセスダイアナ、アウンサン=スーチー、ベナジル=ブット、アネッサ=ボンド、ジョシュア=シュナイダー。彼女たちはそれぞれ国を代表する家に生まれるか、嫁ぐなどして一見社会とは無関係な生活も送ることができたはずなのにあえて社会と対峙することとなる。」
と後世の歴史書は書いている。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3
- (2025-11-14 13:43:41)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月2日分)
- (2025-11-16 01:19:06)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 『漫画ビジネス』(菊池健)
- (2025-11-16 21:00:05)
-
© Rakuten Group, Inc.