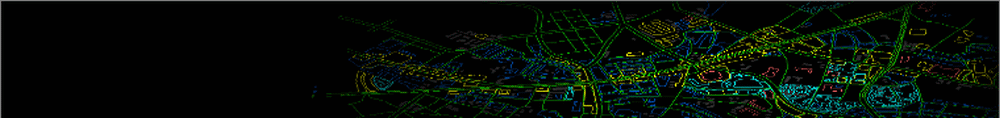アル・ジャズィーラ攻防戦1~
現在はアラビア湾を中心にアフリカ大陸と切り離されているが、今は、その南半分が海面の上昇で姿を消し、(日本列島もよく似たものである。)その間に少々残っていたアラビア湾も、この間のアッ・ザーリヤートの工事で、杉野の言うところの砂場になってしまい、その上には陸軍が30万、周りにはイージス艦が40隻の連隊としてとり囲んでいる。
当時のイージス艦は今と比べて巨大化の一途をたどり、第二次世界大戦時代の戦艦並みの大きさとなっている。理由といえば、第3次世界大戦の際、宇宙空間から攻めてくる空軍の“トムキャット”“アブダルジャラル”といった戦闘機を迎え討つために大気圏外まで届く高射砲を持つ必要があり、その高射砲を支えるためにどうしても巨大化の一途をたどっていた。
アッ・ザーリヤートは、その旗艦のアル・ムルクに乗り込みご満悦の様子である。
それを苦々しく感じているに違いないのが導師アル=ファトフだが、彼は彼で全く別行動をとることにした。彼は彼の一族の戦い方を踏襲することにしたのだ。
大体あのシュケルですら、海戦は不得意だ。
地球政府軍の無名の少将に敗れたこともあるぐらいで、彼はほとんどの場合、陸戦か、空中戦を得意にしていた。どちらかというと戦略の常道ではなく、ゲリラ戦の延長、とよく評される彼の戦法は、20世紀後半からのアラブの伝統でもあった。
その一族の中のエリートと呼ばれるのがあのビン=ラディンであり、彼も、ゲリラ戦を得意とするマスード等とも親交があったことから山岳地帯での戦いを得意としていた。
一応ドバイにも私邸を構えてはいたものの、メッカの後ろにある聖地ヒラー山のふもとに彼は今のところ居を移していた。彼らの言うところのアル・ジャズィーラ(彼らの言うところのアラビア半島の意味)を見渡せる後ろの山岳地帯には導師アル=ファトフの指揮する精鋭部隊が控えており、いざという時に備えている、という表現が穏当だろうが、この2人の司令官はすでにまったく違った戦略のもとで動いていた。
アマンダはアマンダで第一、第三、第五、第七、第九、第十一、第十三の艦隊を率い、ひそかにインド湾に潜伏していた。
第3次世界大戦の影響で、南極からの間の海図が全く変わっており、それらを丹念に調べながらの侵攻だった。
元、ミクロネシアと呼ばれていた地域は南極の氷が解けたためほとんど海底の下にもぐっている。このあたりには最高で20ほどの国があったはずだが今はその国民のほとんどと同じくこの世には存在していない。
第十三艦隊の隊長チェルニー=ラズニニャフは旗艦ドヴォルザークの中で祖父の祖国があったはずのサモアの様子を見ていた。
ビルが海底に沈んでいる。
何かの学校らしき建物も見える。
確かに人間が、ここに住んでいたのだが、海水の上昇と、核爆弾によって彼らの祖国は姿を消してしまった。
同じくたくさんの野生動物も絶滅した。一応連合政府でDNAは保管されているので、しかるべき科学技術が開発されたらマンモスとマレー象が一緒に飼われる日も来るかもしれないが、いまだその噂も聞かないところを見ると、自分が生きている内は祖父が保護に力をつくしたオランウータンも見ることができないかもしれない。
祖父の最後は壮絶だったといわれる。
急な海面の上昇のため、人間の輸送を最優先にしたため、動物はおいていかれることになった。動物園の園長の祖父は抗議の意味も込めて動物たちと最後まで行動を共にしたのだ。
地球政府軍史の中でいまだに汚点とされている事件の一つである。
しかし、孫から見ると、それが祖父の生き方で、天命であるとしたら仕方がない、と思う。おそらく自分の家族より大事にしていたオランウータンと死んだのだから本望だろう、と昔、祖母に聞いたこともあるし、自分もそう思う。
チェルニーから見ると、人間より動物と気が合うようなちょっとした変人、というイメージが祖父には付きまとっていたこともあって、軍人になった時、テン大統領に謝られた時も違和感が付きまとった。
「別にいいんですよ、それが祖父の生き方でしたから。」
というのが精いっぱいだった。
チェルニーの視線の先には旗艦バーンシュタインがいた。
まさか海軍の、いや、統括軍全体の失笑の的となっている、あのシベリウスのようなことはないだろうが…何かものすごい仕掛けでもあるのかな?などと思いながらチェルニーはその艦を見つめる。
初めてアマンダを見たときに感じた衝撃はいまだに彼の脳裏から離れないが、その戦術の鮮やかさも驚くに値した。
「25にして48のカエサルを下す勢い」
と彼はその日記に書いている。
今度はどんな魔術を見せるのか…
それとも今度こそ、正当な方法で、アッ・ザーリヤートを下すのだろうか…
今日の午後にあの旗艦で軍議がある。
そこで何かの発表があるだろう。チェルニーは何となく楽しみですらあった。
黒地に赤の蛍光塗料の炎の絵が真ん中に書かれている。
これが旗艦バーンシュタインの特徴である。統括軍の潜水艇は大きさこそ差があるものの、ほとんど同じ形であるので、それぞれが色々な色でペインティングを施していたが、この旗艦ほど目立つペインティングは珍しかった。
午後一時に始まった円卓の会議は四時には終わった。
会議、というものではなかったかもしれない、面接といった感じで、それぞれの隊長たちは意味不明の指令をそれぞれ与えられて、解散となった。
ただ、皆に与えられた情報は同じであった。
後にまったくの大転換をすることになった話だったが、当初は大体、こんな話だった。
あの砂漠のロングビーチがすでに崩壊を始めている、といった話だった。
その部署にはアッ・ザーリヤートが次から次へとサハラ砂漠から砂を運んでいるらしい。
砂漠の砂がアラビア湾全体に広がりつつあり、遠浅になりつつあるため、つまり近づきすぎることはできない。
で、どうするか。だ。
ということで、それぞれの話をされた。チェルニー率いる第十三艦隊は、とにかくアッ・ザーリヤートの旗艦アル・ムルクのいるあたりを行ったり来たりすればいいらしい。
おそらく問題児のジャン=クローネ率いる第五艦隊が事件を起こすだろうから、それを聞いて大騒ぎをしろ、との指令を受けただけの第九艦隊もいた。艦長はジョルジュ=ラマルク。
第三艦隊はいかにも暇をつぶしているといった風にして、待っていろ。と言われただけらしいし、館長の館 直見はどうラフマニノフの部下に説明するべきか迷ったが、一同には、アマンダから預かった月の夜の女性のメールアドレスを部下たちにばらまいていた。
そのメールアドレスにはいずれ劣らぬ美女たちの立体写真が付いており、隊員たちは狂喜していた。第三艦隊は一番後ろに陣取っている。
一応他の艦隊が明日出発してからそのメールなり電話番号に電話をしていいのらしいが、隊員たちは色めき立っていた。
第七艦隊の隊長のアミル=マリナーズは赤十字並みの傷病兵のための施設を作っておくように、との指令を受けたらしい。
一番難しいのは第五艦隊であのアッ・ザーリヤートを何としてもおびき出せ。
という命令を受けた程度だ。
あの自己顕示欲の塊のようなあの男なら、そう難しくないだろう。
ジャン=クローネは二つ返事で引き受けた。
ショーンはもし、これをアッ・ザーリヤートが自分で考えてやっているのであればアマンダ並みの天才だ、と思いながら、どんどん崩れていく砂の城を見つめていた。
もはや、彼の乗っているアル・ムルクは、あの砂の城から2キロ離れたところにしか繋留できないほどになっている。
他のイージス艦も同じだ。
大きな誤算だったろう。
イージス艦の不自然な動きを見ても(今日は砂に包まれ座礁したものもある)この状況ははじめから想起されているものではないらしい。
その上、不思議なことにアマンダがインド湾に入ったとたんその傾向が強くなり、
日に日に崩れていく砂の城にある法則性をショーンでなくとも感じただろう。
当時、アラビア海を流れている海流はほとんど第三次世界大戦の影響でない状態だった。凪いだ海というイメージがあったが、今は、インド洋を流れるインド海流がものすごい勢いでアラビア海に流れ込んでいた。一応昔はモンスーン海流といわれたくらいの海流で、一応季節ではあったのだが、それにしても不自然だった。
アマンダに聞いてみたところ、インド湾に沈んだ、島だのなんだのを掃除したら水の流れがよくなった、という答えが返ってきた。
こうすることで、ドバイを守るつもりの砂の城はいつもサハラ砂漠から運び込んでいないと一つ間違えたらまた海になってしまう。その上、運び込んだ砂は扇状に反対に広がり、妙な形の遠浅が広がるだけの話だ。
アル・ムルクにいるアッ・ザーリヤートはびっくりしてお抱えの気象予報士を呼びつけたもののその男から、一時的な気象の変化で2週間ほどするとおさまるだろう、といわれ、安心していた。
昨日から、運良く海水から砂をくみ上げる装置も届いたので、わざわざサハラから運ぶ手間が少し減ったこともあり、今のところ、そんなに心配はしていなかった。
しかし、なぜ、彼はこの最後の時までもレーダーを見ることはなかったのだろうか?
あの南極戦線は9割がた彼の勝利のはずだった、それが失敗したのはレーダーを見なかったせいだ。
そのせいで失敗していたものの、彼は今回非常に楽観視していたらしい。
どうやら、アマンダは今度は潜水艇でこちらに来ているらしい。となると、別に意図したことではなかったが、圧倒的な砂の量により遠浅となったこちらの地形にはそぐわない。
というのがその理由だった。
確かに戦争の常道はそうなのだが、相手が相手なのだから、念に念を入れてあらゆることに注意を払えないといい司令官とは言えない。
彼はまた、同じ失敗を犯そうとしていた。
意外に当時のPLO軍には楽勝ムードが漂っていた様子である。
砂に包まれ、座礁したイージス艦を他の艦隊のイージス艦が引っ張って海の上にもう一度引き出してみたり、残っている妻への手紙などにもそんなことを書いている兵士もいる。
アマンダにコテンパンにやられたのは空軍と、陸軍であった。どちらかというとどの国でも海軍と陸軍の仲は悪いこともあるし、空軍はエリート、という感じで、ライバル意識を持たれやすい。あいつらのような馬鹿な失敗はしたくない、となれば気をつけることとなりよいのだが、自分たちはあいつらとは違うからそうでないだろう、といったような期待に似た気分がそこにはあった様子だ。
その心理もアマンダには手に取るように読まれていたことも彼らは知らなかった。
「チャンネル男をどうにかしてやるよ。あの闘牛男のジャン=クローネを使ってね。」
ショーンはまた苦笑した。
ジャン=クローネ。パニック障害で倒れた女性兵士を戦意が足りないと足蹴りにしたり、まさにあのパットン将軍並みの鋼鉄の戦意を持つ男だ。
杉野が一度ジャンに聞いたことがあるらしい。
「あなたの前生は誰だと思います?」
ジャンは即答した。
「俺の前生は闘牛だってよ。だからどこにでも突っ込むのさ。」
戦略的には何の問題のない男だ。ただ、戦場以外で生きていこうとするとかなりの無理があるだろう。DVにより、2回離婚し、2回目の離婚はいまだに係争中らしい。
とにかく酔うと手に負えなくなるらしく、2回目の妻は壁に思いっきり投げつけられたらしい。
確かに闘牛並みの男だ。ということで、ショーンとアマンダの間ではジャンのあだ名は闘牛男と決まった。
しかし、その占い師もよくいったものだ。それを信じ切っているらしいジャンもジャンだが…
アマンダにとって、まずはアッ・ザーリヤートを片づける時が来ていた…
その、はずだった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その4
- (2025-11-20 12:25:59)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 税金・地方交付税から行政法まで!国…
- (2025-11-19 09:04:40)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- マンガハックさん閲覧数総まとめして…
- (2025-11-17 11:55:02)
-
© Rakuten Group, Inc.