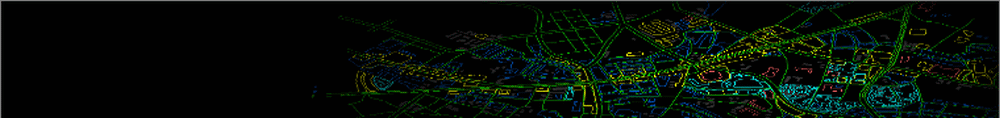アル・ジャズィーラ攻防戦3~
20世紀後半にはこの名前を冠したTV局が創設されたが、今も存続している。
そこのキャスターの一人の日記がある。このシャマシュ=アル=ブルーシュという女性キャスターは最後までアフ=ファトフと行動を共にすることになる。
この人物の日記がPLO側の第一の資料として取り上げられているものもいれば、切れ切れのアル=ファトフの弟の日記を参照するものも多い。
この女性の戦後の人生がこの日記の信ぴょう性を疑問視させても仕方のない面もあるが、克明に描かれている数字や客観的な事実は信ぴょうするに値するためここではこの女性の日記で、PLO側の最後まで描いていくことにする。
「北極へ向かっている潜水艇、ほぼ50隻か…」
目的は何であるか、アル・ムルクの誰もがひとつのことをおもっただろう。
北極の氷をとかして、海面を上昇させるつもりだろう。
そんなことをされたらメッカやドバイなどはひとたまりもない。
プライドの高いアッ・ザーリヤートも初めて部下に尋ねたという。
「どうすればいいと思う?」
誰も即答しなかった。
このまま彼らを追いかけていけばおそらくはアマンダに追尾され、挟み撃ちにあうだろう。
しかし、このままにしておくわけにはいかなかった。
小一時間ほどそれでも話し合ったが、その時間ももったいない上に、まずは知らせておかねばならない人物がいることをアッ・ザーリヤートはようやく思い出した。
導師アル=ファトフへ急使が派遣され、事を知った彼は即、ヒラー山をおり、アル・ムルクへ向かった。
「君が向かうか、私が向かうか…どちらにするか、きめようか?
このシュケル金貨の表が出たら、私が向かう。裏が出たら、君が行けばいい。」
コイントスで決めるのか・・・
導師はあり得ないほど冷静に、とんでもないことを言った。
ショーンがその場にいればさすがは妊婦の身の上で亡命し、その上、とんでもないレベルの医科大学を受験すると言って聞かないビスファラシュの兄だ。と思ったに違いないが、その場にいたほとんどの人間、もちろんその中にはアッ・ザーリヤートもいたが、まさか、この導師がそんなことを言い出すとは思ってもいなかったらしく狼狽した様子だったが、
そんなことを気にする導師ではない。
「では、投げるぞ。」
と、まさにコインは投げられた。
かたずをのんで見守るアッ・ザーリヤートに向かって導師はこう言った。
「残念だ。アッ・ザーリヤート。君は南極戦線の借りを山猫に返すことはできないようだな。私が行くことになった。」
コインは確かに表を向いていた。唖然とするアッ・ザーリヤートを冷然と見つめて、導師はこう言い放った。
「今すぐ、潜水艇10隻、イージス艦5隻、海軍空母15隻を出港させる。その中で旗艦にふさわしい船を一応用意してくれ、旗艦はアル・アーディヤートと名づけることにしよう。では、私も準備がある。後は諸君に任せた。」
と言い残して導師は部屋を出て行った。アル・アーディヤートとは、進撃する馬との意味で、あのシュケルが乗っていた愛馬の名前でもあった。
「?」
カートですら狼狽するうわさだった。
北極行きの潜水艇を追って、なんとあのアル=ファトフがイージス艦5隻と潜水艇10隻、空母15隻で追尾しているとの噂だ。
昨日、北帰行の連中から連絡がアマンダのところにあったというが、その際はまだその艦隊の司令官は誰なのかは不明だった。
「ついに出てきたか。そのコインは裏がなかったんじゃないか?」
というアマンダの言葉が残っているが、おそらくそうではないか、そのアマンダの言葉を聞いたというシャマシュ=アル=ブルーシュも書いている。
彼女は非常にアル=ファトフと仲がよく、男女の噂もあった女性である。その日記にも彼に対する“愛”としか表現できないような記述も多い。
彼女もさすがにビスファラシュの事件は驚いていたようだが、その兄のアル=ファトフならそういうことをやりかねないことを知っていたその頃は数少ない一人だった。
「さてと。私は確かに海の上は初めてだ。
その上、戦争というものも始めてだ。だが、奴らの海軍もお飾り艦隊といわれた程度の艦隊であることを忘れてはならない。
確かに諸君も心細いだろうが、ある程度の自信はある。」
といったきり、アル=ファトフはち密な戦術を語り始めた。
主な戦場はドーバー海峡だ。
今夜出向すれば、ジブラルタル海峡を抜け、明日には元フランスのマルセイユを抜けるだろう。
並いる将軍たちのため息はまさに、賞賛を現していた。
彼らの中にはアッ・ザーリヤートなどに今まで付いて言っていたことを後悔するかのような言葉を吐くような連中もいたと伝えられる。
まるで、一年も前から考えていたような戦略ではあるが、もちろん、ヒラー山からアル・ムルクへ向かう途中に考えたものである。
彼もアマンダを相手に戦う可能性がある以上、少なくとも2重の保険をかけておく必要があった。
まずは退路。
次は一時的に負けたとしても、奴らを北極に行かせなければ戦略的には勝利となる。
その二つを中心に考えると、戦場はドーバー海峡にするしかなかったのだ。
「おそらく、導師はドーバー海峡へ最大戦速で向かっているだろう。ドーバーまで最大戦力で向かえ。すぐに我々も追いつく。」
今までは目立たないように深海をゆっくり進ませていたが、相手の能力をある程度以上買っていたアマンダは先行する60隻の潜水艇にそう命令した。
「明日中に我々はドーバーを超えることはできるだろうが…きみのほうは無理だろう。」
ショーンの冷静な言葉と、アル=ファトフの迅速な行動はアマンダを絶句させるのに十分だった。PLOも統括政府軍と同じく海軍の実力は他の軍隊よりは低いはずだ。
しかし、彼はすでに何年も乗りこなしているかのように平然と旗艦アル・アーディヤートに乗りこんで、一日で旧フランスまで到達している。
つまり、統括政府軍を2分することは十分に可能なところまで艦隊を進めているのだ。
「我々としては、ドーバー海峡で導師を待ち受けることも可能だ。挟み撃ちにするのが一番だろう。」
「…導師がそれだけで済ませると思うか?」
アマンダはかなりの数の陸軍がロシアへ向かっているとの報告も聞いている。衛星写真に写る彼らの中に黒い布に包まれた巨大な物体が10個ほど見受けられる。
(これがイージス艦だったら…)
中に潜水艇も入れることもできる。アル・アーディヤートにいる導師が命令して動かしている軍隊であると聞いている以上、可能性は高い。
これは、先回りされてしまう可能性が高い。
ドーバー海峡をすっ飛ばし、北極に向かう途中の海には第三次世界大戦中に何度も空中戦が行われ、海底の様相が全く変わったといわれている。沈んだ船隻だのが海底にうずたかく積まれ、その後、南極大陸に集合して済むことになったために不要になったこの海域は正式な海図すらなく、その上、海戦は不得意なシュケルがばらまいた地雷のように配置されたミサイルが点在しており、それらのほとんどはいまだに作動するといわれている危険極まりない海域だ。
大事をとって航行する必要があり、10日はかかるとアマンダは考えていた。
となると、地上を移動するほうがはやい、ということになる。
空襲するとしても、イージス艦は上からは核爆弾や宇宙空間からの爆撃にも耐えられるように設計されている。
何故下からの攻撃には弱いかといわれれば、なにかあった時にそこから人が脱出したり、潜水艇の出入り口があるからだ。
かといって、その出入り口を完全に閉じてしまえばなかなか潜水艇でも沈没させることが難しいのがイージス艦なのだ。
「まずは、皆で導師のお手並みを拝見するか。」
結局あせって北極に行ったとしても途中で事故に巻き込まれてしまったら元も子もない。
導師さえいなければもし、先回りされていたとしても恐れる必要などなかった。
ドーバー海峡の北で、まずは偶数の統括政府の潜水艇艦隊が待ち受けることになった。
明日には導師が到着するだろう。
アマンダが到着できるのはその一日後だ。
導師はその一日の間でショーンたち偶数艦隊をせん滅する予定だった。
うまくいけば、の話だが。
少なくとも彼らの間に何らかの方法で、くさびを打ち込むつもりだった。
アッ・ザーリヤートとちがい、情報収集には力を入れている導師だ。意外に戦歴のある隊長たちと、誰よりもあのショーン=マクレガーがいることをすでに把握していた。
簡単に勝てる敵ではないが、まずはあの山猫よりは組みしやすいだろう。
「この時代の一番冷静な楽天家」
と後に評されることになるこの導師は、最後まであきらめることをしない性格らしい。
出来る限りのことをすれば、全能の神でもない以上、導師としても後は相手の出方を見るだけだった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書日記
- 書評【ホットクックお助けレシピ】橋…
- (2025-11-15 00:00:14)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
© Rakuten Group, Inc.